
LTVとは?意味、計算方法、最大化する施策や事例など徹底解説
いうまでもなく、新規で獲得した顧客といかに信頼関係を築き、長期に渡って取引を続けられるかは、ビジネスを行ううえで非常に大事です。継続的な利益なくして、企業経営やマーケティングは成り立ちません。だからこそ、その成否を適切にジャッジする必要があります。そこで挙げられる重要な指標がLTVです。本記事にて徹底解説します。
意味や計算方法をはじめ最大化する施策、成功事例まで幅広くご紹介。ぜひ参考にしてください。
目次
LTVとは?用語の意味

LTVとは「Life Time Value(ライフタイムバリュー)」の頭文字をとったものです。
日本語では「顧客生涯価値」と訳されます。
意味はシンプル。まさしく顧客に対して生涯ベース(顧客ライフサイクル)で与える価値です。転じて、一人または一社の顧客が、特定の企業やブランドと取引を始め、終わるまでの一連の期間内にもたらす利益を算出した数字が該当します。
LTVは1回の購入だけでなく、その後継続して購買行為を追跡することも特徴的です。
数値の高さは、顧客の企業への信頼度、愛着度を示すものといえます。
多くの企業が重用するわかりやすい指標です。
LTVが注目される背景

LTVが注目を集める理由は、そのわかりやすさだけではありません。背景を紐解くと、いくつかの要素が浮かび上がってきます。具体的には以下のとおりです。
新規顧客の獲得難易度が上昇
LTVを考える際、大抵もう一つの引き合いとして出される指標がCAC(Customer Acquisition Cost)です。これは顧客を新規で獲得するために、どれだけの金額を投資したかを表します。
そうしたなか、国内の人口減少に伴い新規顧客の獲得はなかなか困難です。必然的にCACが増えることを見越さなければなりません。また、あらゆる市場に多くの企業が存在する今、類似の商品やサービスはカテゴリー問わずそこかしこで飽和状態です。しからば既存顧客との関係強化に舵を切るのも、容易にうなずけます。
かのフレデリック・F・ライクヘルド氏が提唱した「1:5の法則」にもあるように、新規顧客獲得よりも既存顧客の維持・拡大の方がコストパフォーマンスを考えれば効率的です。そして後者は、時間軸と利益で定量化できるためLTVで測れます。したがって、この指標がいたるところで活用されるようになったわけです。
マスからパーソナライズドマーケティングの時代へ
インターネットの普及はもちろん、顧客の嗜好も顕著なまでに多様化し、購買行動にも大きな変化が見える昨今、従来の不特定多数に向けたマスマーケティングから一人ひとりの顧客に訴求すべくパーソナライズドマーケティングへと移行する企業が増えています。ずばり重視されるのは、個別の顧客と密にコミュニケーションをとり、ロイヤルティを高めてもらうことです。その傾向が強まっていくなかで、長期的な価値を測るLTVがおのずと指標として用いられるようになります。
スムーズなデータ収集が可能
データ収集用ツールの進化や分析手法の発展もまた、LTVの注目度に関わる要素です。
顧客の属性や行動履歴をもとに商品やサービスを改善できれば、リピート率向上やアップセルにつながる期待も持てます。加えてデータから抽出できる項目や見て取れる結果が増えたり、明確になったりすると、LTVの測定もスムーズです。
そのため、データを広く活用するなら特に、この指標を使いたいと考える向きが増えるのは自然な流れといえるでしょう。
LTVを重視するメリット

前述のとおり市場やテクノロジーの変化によってLTVが重視されるようになった趨勢は、とどのつまり、顧客との関係強化につなげやすい指標だと多くのビジネスパーソンが感じていることの証左とも捉えられます。安定的な収益向上につながる羅針盤として機能することを期待しているのでしょう。
一度接点の生まれた顧客を購入まで導けたなら、次はリピートしてもらうことが課題です。厚い信頼を超えた先に築くファンダムの確立まで、顧客一人ひとりを育てられるように手を打たなければなりません。だからこそ、スポット的な商売ではなく、アップセル、クロスセルを自然と促すべく、LTVの数値を気にかけ、改善を図ることが効率的だといえます。
とりわけ、BtoBマーケティングでは購入段階が一筋縄でいかない(客先で複数の部署からアンサーをいただく)ケースも多いため、検討期間が長引くことを想定したうえでの対策が必要です。
既存顧客をいかに維持していくか。そのヒントあるいは分析方法を可視化してくれるLTVは、ビジネス、マーケティングにおいてどうしたって大きなヒントになり得ます。
上記踏まえて、メリットを洗い出すと次のとおりです。
- コストを下げながら経営の安定化が図れる
- 課題別に計算できる
- 優良顧客を可視化できる
それぞれ簡単に説明します。
コストを下げながら経営の安定化が図れる
数多ある新規顧客の獲得手法は、それ自体、有効策である一方で、上述した「1:5の法則」に則ると、過度に固執しいたずらに繰り出すだけではコストが嵩み続け、かえって経営を逼迫することにもつながります。
だからこそ、LTVに目を向けることが大事です。新規顧客の獲得ほど高いコストがかからない既存顧客との関係維持・拡大が進めば、長期的で安定した利益を見込めます。つまり、企業の安定した経営が低コストで可能になるのです。紛うことなくLTVがもたらすメリットだといえます。
課題別に計算できる
LTVは課題別に計算・分析が可能です。
具体的には「売上」「利用頻度」「期間」など定量的な指標が挙げられます。計算方法については後述しますが、各項目それぞれ使い分けて算出し、課題解決の糸口にするわけです。
たとえば、不要なコストを見つけたい場合、通常の計算式から対象額を引いた数値がLTVに当たります。これが芳しくなければ、そのコストは削減する必要が出てくるでしょう。このように活用し、ビジネスの解像度を高めていけるのは、どうしたってメリットです。
また、LTVは解約率(チャーンレート)にも深く関わります。算出した数字と照らし合わせながら、利益の最大化にアプローチすることが可能です。
優良顧客を可視化できる
一口に優良顧客といってもさまざまです。利用サイクルが短い日用品や食料品は週単位、自動車や電化製品は年単位で捉える必要があるなどその定義、目安は商品やサービスで異なります。が、共通していえるのは、企業に対して大きな利益をもたらしてくれることです。
期間別に比較でき、中長期的に追跡していくLTVは、優良顧客を可視化するのにまさにうってつけの指標だといえます。
LTVの計算方法
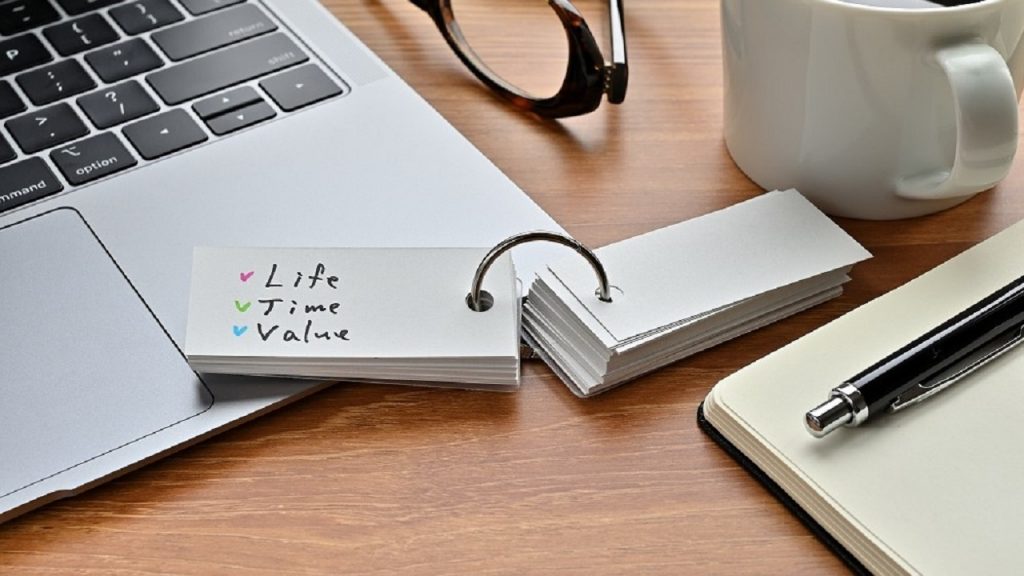
LTVの算出は、一定の期間を抽出し行います。
顧客によって異なるとはいえ、基本的にグループを分けて計算することがほとんどです。
また、「顧客全体」という枠組みもあります。
計算式は次のとおりです。
| 購入金額×購入頻度×継続期間(1÷離脱率) |
たとえば、1件当たりの購入額が平均5,000円、購買頻度は平均で1年間に2回とします。その際、1年間に離脱する顧客についても考慮が必要です。継続期間は1÷離脱率で算出されます。年間20%が離脱すると考えると「1÷0.2」で5年です。
そうなると「5,000円×2回×5年」の計算式が成り立ちます。結果、50,000円が顧客のLTVです。つまり計算上では、顧客1人を獲得するにあたり企業は50,000円の売上を、将来的に見込めることがいえます。
一方で、コストを差し引いた数値を正規に扱うことも少なくありません。
宣伝費や問い合わせ対応の人件費など、獲得や維持にかかるコストが10,000円だったとすると、先の例ではその額を差し引いてLTVは40,000円になります。
LTVを最大化するには?具体的な施策を紹介

売上はもちろん、顧客満足度の向上も含めてLTVの最大化は、企業のミッションのうち最たるものといっても過言ではありません。
いかにサービスを継続的に入手したい、利用したいと思わせられるか。信頼、ファンダムの構築は、長期に渡っての利益増加につながるため、やはり良質なプロダクトの提供と親しみやすさを伴うアプローチが求められます。いずれにしてもLTVの把握は必須。裏を返せばこれができていると、経営の方針などもぶれる心配も少なくなるでしょう。
結果が良好であれば、新商品の開発など躊躇せずに踏み出すことができ、サービスだけでなく組織の活性化にも期待が持てます。
では、具体的にどのような施策が有効なのでしょうか。
以下、いくつか紹介します。
広告・宣伝媒体を活用する
LTVは顧客全体から平均値を出すやり方が一般的ですが、個別にアプローチできる部分も疎かにしてはいけません。人によって購買金額に差があるからです。そこを埋めるのか、それとも愛着度の高いお客様に絞るのか。もちろん、顧客自体の数を増やすことも大事です。
広告・宣伝媒体の活用は、上述した戦略のすべてに当てはまります。
WebサイトやSNSでの発信だけでなく、テレビ広告や配布チラシなども現代とのギャップが多少あるとはいえ、ターゲットによっては有効です。
うまく使い分けることで最適化、そして最大化が図れるでしょう。
商品の魅力を従来と違う観点で伝える
購入する人それぞれの購買単価が増えれば当然LTVは向上します。
手っ取り早い方法としては商品の値上げです。
しかしこれは、従来と比較した際の損失感や、競合会社との価格差といった懸念点が浮かび上がり、実際に既存顧客の離脱が大いに考えられます。そのため、あまりおすすめはできません。が、打ち出し方を変えれば、値上げ分は付加価値として見せることも可能です。
従来とは違った角度でその商品の魅力を謳えば、何かしら新鮮味を与えられる期待も持てます。それらが意外と顧客のニーズにマッチすることも珍しくありません。
なお、そうはいってもやはり顧客離れが不安なら、品薄の状況になってから値上げすることをおすすめします。
メールマーケティングを導入する
LTVを最大化するには購買頻度を上げることも大事です。そのためには定期的に既存顧客との接点を作っていく必要があります。
具体的におすすめしたいのは、メルマガの活用です。リマインドも含めて頻繁にアプローチしましょう。
特に新商品の発表やキャンペーンの実施など、広く宣伝するトピックがある場合はメルマガがあることで機会損失を防げる可能性が高まります。同様に、ダイレクトメールも効果的です。顧客維持率の下落を回避すべく、ぜひ活用してみてください。
顧客管理システムを導入する
顧客獲得や維持にはどうしてもコストがかかるわけですが、それらを減らすこともまた、LTVの最大化につながります。
CRMなどの顧客管理システムは、その課題に対して現状を改善してくれるすぐれものです。
導入によって顧客管理がスムーズになれば、資料請求や問い合わせ、購買履歴などを簡単に把握できます。また、顧客の状況やニーズにあわせて臨機応変にメールを送るなど先述した各種アプローチを効率的に行うことが可能です。
結果、中長期的にはコスト削減の実現が期待できます。
複数のパターンを用意するなど売り方を工夫する
一つの商品を軸とし、パターンを複数用意することで購入者のアップにつながるケースがあります。
たとえば、「松:20,000円」「竹:15,000円」「梅10,000円」といった形で販売するとどうでしょう。消費者心理として、中間価格で購入する人が出てきやすくなります。これはいわば古典的なセオリーですが、いまだ有効に作用することは少なくありません。その他、セット販売なども定番の方法です。
LTVを向上させた成功事例

LTV向上のための施策を講じたからといって必ずしもうまくいくわけではありませんが、それでも一定の成果を出す企業は数多存在します。
今、伸び悩んでいたとしても、それは後につながる布石かもしれません。あるいは他者の実績(型)を真似ることで一気に状況が開けるケースもあるでしょう。
以下、成功事例を紹介します。
メールマーケティングをうまく活用したA社の事例
A社では、LTVを高める戦略、目標として定期購入者を増やすことを掲げ、そのためにメールマーケティングを採用。あわせて購入タイミングを逐一把握できるようにします。
メールは自動送信システムです。フェーズに応じた内容が届きます。
いわゆるカスタマージャーニーに基づいた、ファネルの原理を用いた施策です。
テキストの内容は“商品はどうでしたか?”“不都合や疑問点はありませんか?”など実にシンプルだったといいます。が、どうやれこれが効果的に作用したようです。事実「気にかけてくれている」「丁寧に対応してもらっている」といった印象を持たれる顧客が多かったのだとか。「使用中」「使用終了」などメールを届けるタイミングも顧客との接点を絶やさないよう工夫がなされていたと聞きます。
そうやって商品や企業のことを折に触れ思い出させ、再購入への道筋をしっかり作った結果、多くのリピーターを生みLTV向上にもつながるわけです。
継続的な信頼構築があっての成功例。まさに理想の形ではないでしょうか。
「お試し価格」をきっかけに商品の良さが広まったB社の事例
もう一つの成功事例は、テストサービスがLTV向上につながったエピソードです。
既存顧客の維持・拡大が効率的な攻め方と再三お伝えしましたが、新規顧客の獲得を端から諦める必要はありません。たとえば初回は「お試し価格」を打ち出し安さに訴求することで、使ってもらえる可能性は高まります。実際、購買行動が価格重視のお客様は少なくありません。初めて利用するサービスであれば尚更です。
ただし、この施策は通常価格に戻った際に離脱されやすい傾向にあります。そのため、LTVが低いことがほとんどです。
が、B社は違いました。というのも、実は最初から離脱数を抑えることを見据えていたのです。どうすれば、継続的に購入してもらえるか。磨いたのはプロダクトの質です。
お試し価格はあくまで新規顧客を増やすきっかけに過ぎず、本当の勝負はそれからでした。だからこそ、品質の高さにもっとも自信のあるプロダクトにいわば切り札として「お試し価格」を使ったのだといいます。
購入の決め手をまず用意したうえで、実際に使ってもらいサービスのクオリティを気づかせた結果、離脱防止を図るロジック。うまく機能すれば、B社のようにLTVの最大化につながるわけです。
LTVを理解し、ビジネスのなかでうまく取り入れよう!

LTVの最大化は、多くの企業の課題といえるでしょう。
経営やマーケティングにおいて、意識することは必須です。
仮にこれまで無頓着であった場合、まずは基本をしっかり理解し、いくつかの仮説を立てることからはじめましょう。そのうえで戦略に基づいた施策を実行し、一つの基準を設けてください。検証後は改善点をあぶり出し、徐々に向上させるイメージで取り組んでいくことをおすすめします。
そのなかで拙稿が少しでもお役に立てるのなら幸いです。
おそらく、すぐにはうまくいかないかもしれません。
ぜひ、試行錯誤の末、最適解を導き出してください。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
