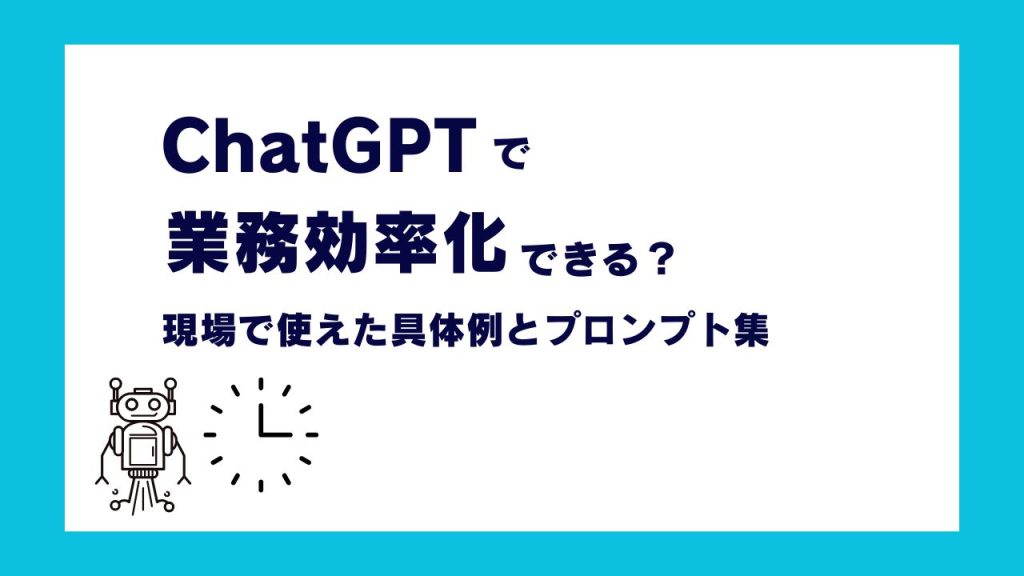
生成AIでビジネス業務を効率化|企業導入の成功ポイントと活用事例、プロンプト集
「生成AIはビジネスにどう使えばいい?」「本当に成果は出るの?」「社員が使いこなせるか不安…」
そんな悩みを抱える企業担当者は少なくありません。
この記事では、生成AIを業務に定着させ、成果につなげるための。導入を成功させるためのポイントやステップ、業務ごとの活用例や成功事例まで、くわしく解説しています。
議事録・FAQ・マニュアル・メール文面などの定型業務から、SNS投稿・企画などのクリエイティブ業務まで、すぐに試せるプロンプト例もご活用ください。
この記事では、生成AIを業務に定着させ、成果につなげるための導入ステップ・成功事例・活用例を実践的に紹介します。
目次
生成AIとは?
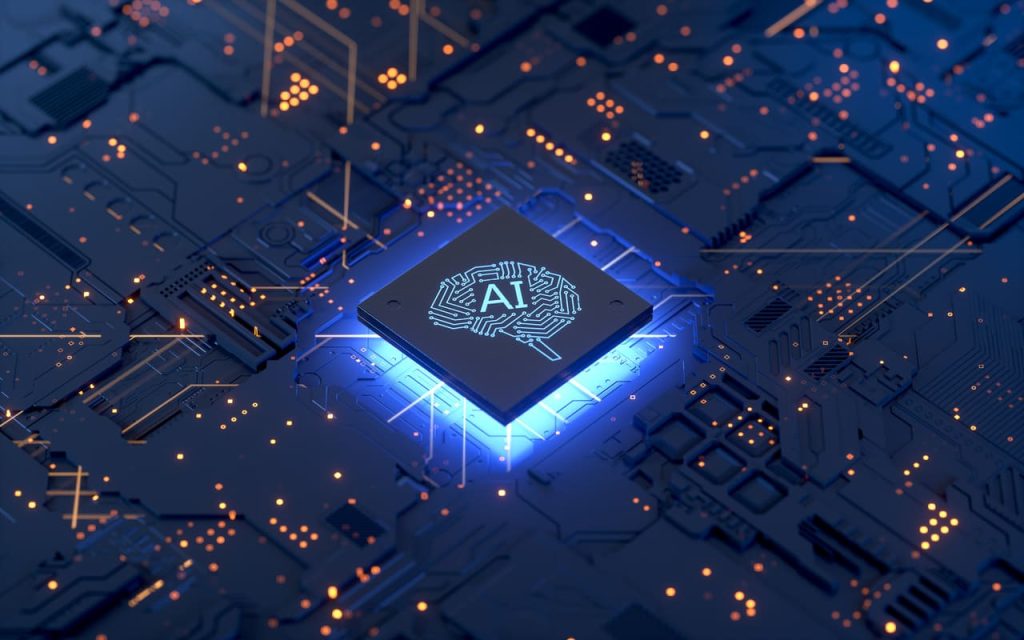
生成AIとは、文章・画像・音声・プログラムコードなど、人間が創作するようなコンテンツを自動で生み出すAI技術のことです。
特に近年注目されているのが、ChatGPTに代表される「対話型AI」です。自然な言語でのやりとりが可能で、企業の業務効率化やアイデア創出に活用される場面が急速に増えています。
なぜ今、生成AIの導入が注目されているのか?

生成AIが多くの企業で注目を集めているのは、「労働力不足」や「業務の属人化」といった、長年抱えてきた課題を見直す手段になりうるからです。
テクノロジーの力で、人手や時間といった制約を超える可能性に、多くの経営者が期待を寄せています。
特に中小企業では、「限られた人員で毎日ぎりぎりの業務を回している」「マニュアル化されておらず、特定の人にしかできない作業が多い」といった悩みが絶えません。
人を増やすにも予算がない。けれど、現場は日々のタスクに追われ、改善に手が回らない。そんな悪循環に陥っている現場も少なくないでしょう。
こうした状況を打破する手段として、生成AIの導入が注目されています。
ChatGPTのような生成AIを活用すれば、議事録の要約、マニュアルのたたき台作成、メール文面のドラフトなど、従来は人が時間をかけていた業務をスムーズにこなせるようになります。
手が足りない現場だからこそ、生成AIにできることを任せてみるといった動きが、企業の現場で少しずつ広がってきています。
企業における生成AIの導入状況

生成AIの注目度は日々高まっていますが、企業における導入状況や具体的な活用実態については、十分に可視化されていません。
この章では、最新の調査データをもとに「どれくらいの企業が生成AIを導入しているのか」「どのような業務に活用されているのか」「どのAIツールが使われているのか」といった現状を、わかりやすく整理してお伝えします。
生成AIを業務で活用している企業は17.3%、うち9割が効果を実感
帝国データバンクの調査(2024年8月)によれば、生成AIを実際に業務で導入・活用している中小企業は17.3%にとどまっています。
一方で、そのうちの約9割の企業が「一定の効果を実感している」と回答しており、すでに成果を上げているケースも少なくありません。
【出典:生成AIの活用状況調査|株式会社 帝国データバンク[TDB]】
「情報整理・文書業務」が活用用途の上位に
同調査によると、生成AIを活用している企業の用途として最も多かったのは「情報収集(59.9%)」でした。
続いて、「文章の要約・校正(53.9%)」「企画立案時のアイデア出し(53.8%)」が上位を占めています。
これらはいずれも、ビジネスパーソンが日常的に行う情報整理や文書関連の定型業務です。指示内容(プロンプト)も比較的シンプルで済むため、導入のハードルが低い領域といえます。
実際、初めて生成AIを導入する企業にとっては、既存の業務フローに自然に組み込みやすく、短期間で成果を感じやすい分野として注目されています。
最も活用されている生成AIは「ChatGPT」
同調査によれば、生成AI導入企業の中で、最も導入率が高いAIツールは「ChatGPT」でした。
ChatGPTは、無料プランが利用可能で、シンプルなUIであることから、導入のハードルが低く、中小企業でも使いやすい生成AIツールとして高い支持を得ています。
「ChatGPT」(84.2%)に次いで、「Copilot for Microsoft 365 」( 26.8 % )「Gemini」(19.6%)などが、使用ツールとして挙げられています。
生成AIのビジネス活用例【定型業務編】文書作成・情報整理を効率化
議事録の要約・マニュアルの整理・FAQ作成・定型メールの文案作成など、定型的な業務は、生成AIの導入効果が非常に高い領域です。
この章では、議事録の要約・マニュアルの整理・FAQ作成・定型メールの文案作成など、繰り返し発生する業務をいかに自動化・効率化できるかを具体的に解説します。
すぐに業務に取り入れられるAIプロンプト例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
議事録や報告書の要点を簡潔に整理する
会議のメモや報告書のドラフトを整理するのに時間がかかる──。そんな悩みを抱える方にとって、生成AIは強力な味方になります。
議事録の全文や手書きメモを入力すれば、重要な決定事項・参加者の意見・次回アクションなどを明確に抜き出し、箇条書きや構造化された形式で要点を整理してくれます。
報告書の初稿作成や、冗長な内容の要約にも対応でき、資料共有の質とスピードが大きく向上します。
【プロンプト例】会議を要約して議事録をつくる
箇条書きでまとめ、可能であればカテゴリごとに分けてください。
【議事録原文】
〇〇〇〇〇〇(←メモをここに貼る)
【プロンプト例】報告書の要点を抽出する
文体は敬語で、1文ずつ簡潔にしてください。
【報告原文】
〇〇〇〇〇〇(←本文をここに貼る)
マニュアルや手順書をわかりやすく整える
業務マニュアルや操作手順書は、どうしても文章が長くなりがちで、「結局どうすればいいのか」が伝わりづらくなることもあります。
そんなとき、生成AIを使えば要点を整理し、誰が読んでも理解しやすい構成に変換できます。
専門用語をかみ砕いたり、長文を箇条書き化したり、手順の流れを明確に整えたりと、ドキュメントの“わかりにくさ”を自動でほぐす支援が可能です。
新人向けマニュアル、社内の引き継ぎ資料、操作ガイドなど、幅広い業務で応用できます。
【プロンプト例】既存マニュアルを簡潔に再整理する
必要に応じて補足説明も入れてください。
【マニュアル原文】
〇〇〇〇〇〇(←元のマニュアルを貼る)
【プロンプト例】手順書をステップ形式に変換する
この内容を「ステップ1 → ステップ2 …」の形式に変換し、各ステップで必要な注意点があれば補足してください。
フォーマルな文体でお願いします。
【手順書原文】
〇〇〇〇〇〇(←手順書をここに貼る)
FAQやQ&Aの初期案を生成する
顧客対応や社内サポートで活躍するFAQやQ&Aですが、「そもそも何を載せるべきか迷う」「文章のトーンが揃わない」など、初期作成の段階で手が止まるケースは少なくありません。
生成AIは、サービスや業務の概要を入力するだけで、よくある質問とその回答例を“たたき台”として提案してくれます。
ベースとなる質問案をもとに加筆・修正することで、時間を大幅に短縮しつつ、表現の統一感も保ったFAQコンテンツを作成できます。
対外的なカスタマーサポートだけでなく、社内ヘルプ・業務引き継ぎ資料・教育用マニュアルなど、幅広く応用可能です。
【プロンプト例】外部向けFAQのたたき台を生成する
この内容に基づいて、想定される顧客からのよくある質問とその回答を5件作成してください。
口調はていねいで、回答は簡潔かつ正確にお願いします。
【サービス概要】
〇〇〇〇〇〇(←製品・サービスの説明などをここに記入)
【プロンプト例】社内用のQ&Aを構成する
この内容に関連して、よくある社内からの質問とその回答を5件分作成してください。
形式は「Q.(質問)/A.(回答)」で、明るくフラットな口調でお願いします。
【業務説明】
〇〇〇〇〇(←業務フローやツール説明などをここに貼る)
定型メールの文面を用途に応じて整える
日々の業務で送る定型的なメール。「どう書き出すべきか迷う」「伝えたい内容はあるのに文章が決まらない」。
そんなとき、生成AIを使えばシーンに合った丁寧で読みやすいメール文面を素早く整えることができます。
たとえば、営業メール・日程調整・依頼文・お詫び・報告・お礼など、目的や相手に応じて文体・語調・構成を調整した定型文のたたき台を、すぐに生成可能。
「口調は丁寧に」「簡潔に」「最後にお願い文を添えて」などの条件を追加することで、より精度の高い出力が得られます。
メールの文案をゼロから考える手間を減らし、伝わる・失礼のない・時短にもなるコミュニケーションが実現可能です。
【プロンプト例】営業メール(初回接触)の文案を作成する
相手は法人の担当者で、丁寧な敬語・簡潔な構成(導入→提案→クロージング)でお願いします。
件名も5案提案してください。
【メールの目的】
〇〇〇〇〇〇(例:サービス紹介・資料送付依頼など)
【プロンプト例】日程調整メールのテンプレートを整える
件名・冒頭・候補日の提示・返信依頼・締めの一文まで含めて、社外向けの丁寧な文面でお願いします。
【状況】
〇〇〇〇〇〇(例:オンライン面談の候補日提示、1週間以内で3候補 など)
社内文書やお知らせのドラフトを自動生成する
社内向けの連絡文やお知らせは、「形式はわかっていても、書き出しに迷う」「表現にムラが出やすい」など、意外と時間を取られる業務のひとつです。
特に全社連絡・チーム通知・総務からのお知らせなどは、要件がシンプルでも“きちんと伝わる”文面づくりが求められます。
生成AIを使えば、文面のベースとなるドラフトを手早く整えることが可能。社内報、勤怠・制度変更の連絡、ちょっとしたお礼やお願いまで、幅広く対応することが可能です。
通知の目的・対象者・要点を伝えるだけで、「件名・あいさつ・本文・締め」まで整った文案が一通り出力されます。
【プロンプト例】全社員向けのお知らせメール文案を作成する
件名・あいさつ・本文・締めの一文を含めて、丁寧でわかりやすい文面にしてください。
【通知の内容】
〇〇〇〇〇〇(例:システムメンテナンスによる一時停止のご案内など)
【プロンプト例】チーム向けのライトな連絡文を作成する
文面は1〜3文程度で簡潔にし、カジュアルだが失礼のない口調にしてください。
【状況】
〇〇〇〇〇〇(例:会議時間変更、ランチのお誘い、備品発注済み報告など)
会議アジェンダを目的に合わせて整える
会議の質は、事前のアジェンダで決まると言っても、過言ではありません。
目的が曖昧なまま始まる会議は、時間が長引いたり、議論が散漫になったりしがちです。
生成AIを活用すれば、「目的に沿った論点設計」や「議題の整理」「時間配分」まで含めたアジェンダ案を瞬時に作成できます。
たとえば、「定例会での報告用」「新規案件の企画検討」「クロージングに向けた意思決定」など、会議の種類や目的を伝えるだけで、実用的なアジェンダのたたき台を用意してくれます。
【プロンプト例】社内定例会のアジェンダ案を作成する
参加者はチームメンバー5名で、議題は週次の進捗報告と課題共有です。 各項目の所要時間も記載してください。
【目的・背景】
〇〇〇〇〇〇(例:リモート下での情報共有を円滑にしたい など)
【プロンプト例】新規プロジェクトのキックオフ会議用アジェンダ
この内容に基づき、初回キックオフ会議で使えるアジェンダを作成してください。
要点整理・目線合わせ・役割分担を中心とした構成にしてください。
【プロジェクト概要】
〇〇〇〇〇〇(←概要や目的などを記入)
報告・連絡・相談のテンプレを素早く整える
いわゆる“ホウレンソウ”と呼ばれる社内コミュニケーションは、
「書き出しに迷う」「結論が伝わりにくい」「言葉選びに時間がかかる」など、案外エネルギーを使う場面です。
生成AIを使えば、状況や目的を入力するだけで、要点を押さえた報告・連絡・相談の文案をスムーズに生成できます。
特にチャットでのやり取りが増えている今、簡潔でわかりやすく、でも失礼のない表現が求められるシーンで重宝します。
【プロンプト例】上司への進捗報告メッセージを作成する
簡潔・明確・丁寧な口調でお願いします。
1〜3文で収めてください。
【報告内容】
〇〇〇〇〇〇(例:作業完了報告・期限延長の相談 など)
【プロンプト例】社内向けの連絡メッセージを整える
要点が一目で伝わるようにしつつ、必要に応じて補足をつけてください。
【連絡内容】
〇〇〇〇〇〇(例:会議場所変更、資料アップロード完了通知など)
生成AIのビジネス活用例【クリエイティブ業務編】企画・構成・表現を支援

「キャッチコピーが思い浮かばない」「記事構成がなかなか決まらない」といった、クリエイティブな業務特有の悩みにも、生成AIは有効です。
生成AIは、人の感性を補いながら、複数のアイデアをスピーディーに提示できるため、企画設計やブレスト、初期案作りといった工程において、強力な支援ツールとなります。
この章では、ブログ構成・タイトル案・広告コピー・SNS投稿文・キャンペーン企画など、ゼロからイチを生み出す業務における生成AIの具体的な活用例をプロンプトとともにご紹介します。
ブログ構成・記事タイトル案を効率よく出す
コンテンツマーケティングにおいて、ブログ記事の構成設計やタイトル案出しは非常に重要な工程です。
しかし、「何から書き始めればいいのか分からない」「タイトルが思いつかない」といった悩みは多くの担当者が抱える課題でもあります。
生成AIを活用すれば、テーマやキーワード、想定読者を指定するだけで、記事構成案やタイトル候補を複数提案してくれます。
SEOを意識した構成や、読者の興味を引く言葉選びにも対応可能で、ゼロから構想する初期段階の負担を大幅に軽減できます。
ライターや編集者にとっての「たたき台」としても、チーム内ブレストの出発点としても有効です。
【プロンプト例】SEOを意識したブログ構成案を生成する
読者は初心者想定で、やさしく理解できるような順番と内容にしてください。
【キーワード・テーマ】
〇〇〇〇〇〇(例:「リスキリングとは」「ChatGPT 使い方」など)
【想定読者】
〇〇〇〇〇〇(例:中小企業の人事担当者 など)
【プロンプト例】魅力的な記事タイトル案を複数出す
タイトルには主語や数字を活用し、自然な日本語で構成してください。
【記事のテーマ】
〇〇〇〇〇〇(例:「副業に向いている仕事とは?」など)
広告コピーやキャッチフレーズのアイデアを広げる
「どう表現すれば響くのか」「同じような言葉しか浮かばない」といった壁にぶつかることも多いのが広告コピー制作です。
生成AIは、商品やサービスの特徴・ターゲット・トーンを伝えるだけで、複数のキャッチコピー案を瞬時に提案してくれます。
LP、バナー、チラシ、営業資料など、媒体や目的に応じて出力パターンを変えることも可能です。
特に“最初の一言”に悩むときのブレスト支援や、複数案から選びたいときの比較材料として、強力なツールになります。
【プロンプト例】ターゲットに刺さる広告コピー案を出す
ターゲットは20代女性、トーンは親しみやすくポジティブにしてください。
【商品・サービス概要】
〇〇〇〇〇〇(例:スキンケア化粧水・成分や特長など)
【掲載媒体】
〇〇〇〇〇〇(例:Instagram広告/LPヘッダー など)
【プロンプト例】LPや資料用に複数タイプの見出しを生成する
それぞれ「ベネフィット型」「問いかけ型」「数字を入れた型」など、タイプを変えて提案してください。
【紹介文】
〇〇〇〇〇〇(←例:サービス内容や特長を簡潔に記載)
SNS投稿文やキャンペーン文をトーンに合わせて生成する
SNSやキャンペーンでの情報発信では、「言葉選び」「テンション感」「媒体ごとのトンマナ調整」が成果を左右します。
とはいえ、「毎回考えるのが大変」「告知文が似たパターンになる」と悩む場面も多いのではないでしょうか。
生成AIを活用すれば、「誰に」「何を」「どの媒体で」伝えるかを指定するだけで、トーンに合った投稿文を即座に出力可能です。
Instagram、X(旧Twitter)、LINE公式アカウント、メールマガジンなど、媒体特性に合わせた口調や長さに変換できるのも大きな利点です。
また、季節イベント・期間限定キャンペーンなど、“毎年発生するけど毎回作るのが面倒”な施策でも強力な味方になります。
【プロンプト例】SNS投稿文を媒体・トーンに合わせて作成
媒体はInstagram、トーンはややカジュアルでポジティブにしてください。
絵文字も2〜3個取り入れてください。
【サービス概要】
〇〇〇〇〇〇(←例:美容サロンの予約キャンペーン)
【キャンペーン内容】
〇〇〇〇〇〇(←例:期間限定割引、来店特典など)
【プロンプト例】キャンペーン文を複数の口調でバリエーション化
それぞれ「フレンドリー」「丁寧」「ワクワク感重視」の口調にしてください。
【キャンペーン内容】
〇〇〇〇〇〇(←例:新商品発売記念のクーポン配布など)
【対象媒体】
〇〇〇〇〇〇(←例:LINE公式/メールマガジン/Instagramなど)
企画書や提案資料の構成案を自動生成する
企画書や提案資料を作成する際、「構成を考えるのに時間がかかる」「何から書き出せばよいかわからない」と感じる方も多いはずです。
生成AIは、目的とターゲット、伝えたい内容を入力するだけで、論理的でわかりやすい構成案を提示してくれます。
0から企画を立ち上げる際のたたき台として非常に有効で、骨子を時短で整えることが可能です。
特に、営業提案・マーケティング企画・社内施策など複数の要素を整理したい業務において、思考の整理+構成支援の効果が大きい分野です。
【プロンプト例】企画書の構成案を目的に合わせて生成
ターゲットに納得感が伝わるよう、論理的な順序にしてください。
【企画の目的】
〇〇〇〇〇〇(←例:社内コミュニケーション改善施策)
【対象者】
〇〇〇〇〇〇(←例:管理職・営業チームなど)
【盛り込みたい要素】
〇〇〇〇〇〇(←例:背景、課題、施策案、メリット、実行体制)
ストーリーや構成のテンプレートをもとに発想を助ける
商品紹介・プレゼン・動画構成などでは、「伝え方の型」が成果に直結します。
ただ、ときには構成が毎回ワンパターンになってしまう・発想が止まってしまうこともあるでしょう。
生成AIは、ストーリーテリングやプレゼン構成の“型”をベースにした構成案を素早く提示してくれます。
既存のテンプレートに沿って複数パターンを出すことで、内容の再構成や伝え方の工夫がしやすくなるのが特徴です。
【プロンプト例】ストーリーテンプレートを活用した構成案の提案
【目的】
〇〇〇〇〇〇(←例:Web動画用のサービス紹介)
【商品概要】
〇〇〇〇〇〇(←例:人材マッチングアプリの特長など)
デザインやビジュアルのラフイメージを言語化する
バナーやLP、チラシなどを制作する際、「デザインの方向性がうまく伝わらない」と感じた経験はありませんか?
とくにデザイナーでない方にとっては「こんな感じにしたい」といったイメージの共有が難しい場面も多いのではないでしょうか。
生成AIは、「ターゲット」「雰囲気」「使用目的」などをもとに、言語でラフイメージを構成してくれるため、デザインの初期共有や生成AI画像ツールへのプロンプト作成にも非常に有効です。
【プロンプト】ビジュアル表現をAIに説明文で描写させる
MidjourneyやCanvaなどの画像生成にも使えるよう、描写要素を詳しく含めてください。
【ターゲット】
〇〇〇〇〇〇(←例:20代女性)
【雰囲気】
〇〇〇〇〇〇(←例:ナチュラル・洗練された・明るい)
【目的】
〇〇〇〇〇〇(←例:春の新生活キャンペーン告知)
ネーミングやタグラインの候補をブレストする
新商品・新サービス・キャンペーン名を考える場面では、「なかなか良い名前が浮かばない」という課題がつきものです。
生成AIを使えば、ブランドコンセプトやターゲット、雰囲気をもとに数十案のネーミングを一括生成できます。
「すぐ使える案」だけでなく、「検討の起点」になるアイデアが出る点も、ブレスト向きです。
【プロンプト例】ネーミングやキャッチ案をブランド軸で出力
【商品・サービスの概要】
〇〇〇〇〇〇(←例:自然派素材を使ったスキンケア商品)
【ブランドコンセプト】
〇〇〇〇〇〇(←例:毎日にやさしさを届ける)
【ターゲット】
〇〇〇〇〇〇(←例:30代女性/敏感肌)
生成AIでビジネス業務を効率化するメリットと注意点
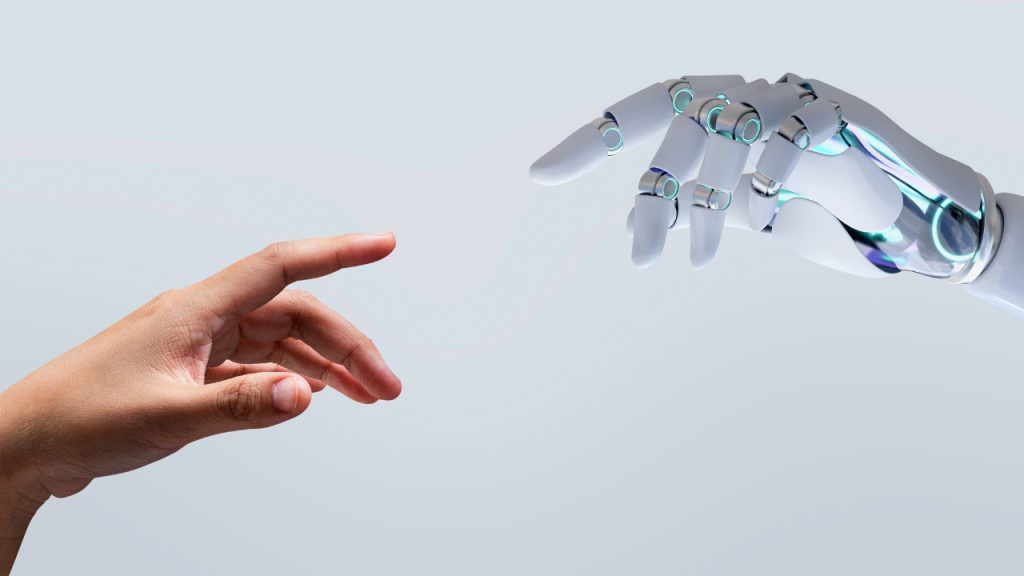
この章では、生成AIを業務に活用するなかで見えてきたメリットと課題を整理します。導入初期では特に、「使い方次第で効率化が図れる一方、注意すべき点もある」ことを実感するケースが多くありました。実際の活用現場でよく挙がりそうなポイントを紹介します。
導入時は、まず一部の業務に絞って効果を検証し、業務との相性を見極めたうえで段階的に拡大していくことが現実的なアプローチといえるでしょう。
メリット①:作業スピードが大幅に向上する
生成AIは、定型的な文書作成や構成案の生成を短時間で行えるため、「考え始める」までの時間を短縮できる点が大きな利点です。
たとえば、メール文案やアジェンダ作成など、これまで毎回ゼロから組み立てていた業務が、数分で初稿を得られるようになることで、全体の処理スピードが大幅に改善されます。
メリット②:業務への着手ハードルが下がる
「何から始めたらよいか迷う」ような業務──たとえば記事構成や社内向け文書の冒頭などでも、生成AIがたたき台を提供することで着手のハードルが下がる効果があります。
思考を助ける“補助的ツール”としての活用により、作業の停滞を防ぎやすくなるという声も多く見られます。
注意点①:出力した文書がそのまま使えるとは限らない
生成AIの出力は一定の品質を保っていますが、文脈理解や語調調整においては人の確認が不可欠です。とくに外部向けの文書では、正確性や表現のニュアンスを細かく確認する必要があります。
あくまで「素材」として捉え、人が仕上げる前提で利用することが基本となります。
注意点②:対応できる業務は限定的
生成AIは、定型文の作成やアイデア出しなどには強みを発揮しますが、高度な判断を伴う業務や、背景理解が求められる領域には不向きです。
経営判断や顧客との交渉といった複雑なタスクについては、人間の判断・対応が必要になります。
したがって、AIの得意な領域に絞って活用する設計が重要です。
企業の生成AI活用例【業種別】
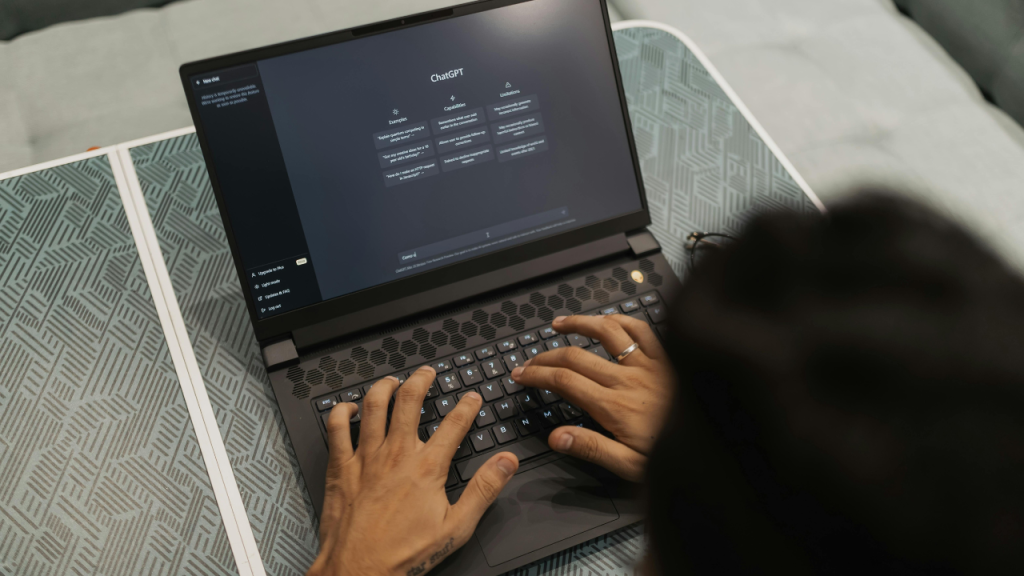
生成AIは、業種を問わず幅広い業務に活用されています。ここでは代表的な5業種における具体的な活用方法と、その効果を紹介します。
製造業|画像認識AIで検査工程を効率化
ある金属加工企業では、熟練検査員による目視検査をAIで補完する目的で、画像認識システムを一部工程に導入。まずは特定部品の検査工程に絞って試験導入し、その効果を検証しながら他工程へ展開しました。
【結果】検査精度が向上し、時間・コストの大幅削減と品質安定に貢献。
小売業|需要予測AIで廃棄ロスを削減
地域密着型スーパーでは、生鮮食品の廃棄ロス削減が喫緊の課題でした。販売データに天候・曜日・地域イベントなどの外部要因を加味したAI需要予測ツールを導入。
【結果】発注精度が向上し、過剰仕入れの抑制と廃棄ロスの削減に成功。
美容室|AIチャットボットで予約業務を自動化
ある美容室チェーンは、電話応対が業務を圧迫していたため、FAQ応答・予約変更に対応するAIチャットボットを導入。
夜間・休日にも自動回答ができるようになり、サポート工数が大幅に削減し、CS改善にもつながった。
【結果】電話件数が約40%減少し、スタッフの負担軽減と顧客満足度向上を実現。
飲食業|SNS運用やメニュー説明をAIで効率化
小規模飲食店では、ChatGPTを活用してメニューの説明文やSNS投稿文の作成を自動化。期間限定メニューの訴求表現やInstagram用の文章を複数案生成。
【結果】SNS運用の工数が約1/3に削減され、集客効果も向上。
士業|問い合わせ対応の一次返信をAI化
ある行政書士事務所では、問い合わせ対応に生成AIを活用。フォームの内容から想定回答をAIが複数作成し、それを修正・送信する方式を導入。
【結果】メール対応時間が約40%削減され、本業に集中できる時間が増加。
教育業(個人塾)|教材作成をAIで効率化
個人塾では、教材づくりの初稿をAI生成し、「中学英語の練習問題10問+解説」といった指示で試作。
【結果】作成時間が1/5に短縮され、授業準備に余裕が生まれた。
物流業|社内文書作成を自動化
中小運送会社では、手書きメモや口頭内容をChatGPTに入力し、通知文や報告書の草案作成を自動化。
【結果】社内文書の作成工数が削減され、日本語に不慣れなスタッフも安心して対応可能に。
アパレルEC|AIレコメンドで売上向上
あるオンラインアパレル企業では、閲覧履歴・購入履歴・検索キーワード・類似顧客の行動データをAIが分析し、パーソナライズされた商品提案エンジンを導入。
【結果】顧客体験が大きく向上し、クロスセル・アップセル効果で売上増加を実現。
AI活用に成功した企業の取り組み実例

この章では、AI活用に成功した企業の取り組み実例を紹介します。導入の際のヒントとして、ご活用ください。
旭鉄鋼|製造現場でのAI活用でコスト削減・生産性向上
旭鉄鋼は、生成AIを「製造現場の相談役」として活用することで、改善提案のスピードと質を大きく向上させ、コスト削減と組織の生産性向上を実現しています。
従来の製造現場では、トラブル対応や業務改善のノウハウがベテランに属人化しやすく、新人や他部門に共有されにくいという課題がありました。
旭鉄鋼はこの状況を打破するために、現場の知見を形式知化し、全員が活用できるAI支援体制を整備しました。
具体的には、チャット型AIツール「dejiren」を導入し、現場スタッフがAIに相談するだけで、過去の改善事例やグラフの分析結果を自然言語で提示できる仕組みを構築。
生成AIが数百件の改善履歴から類似事例を抽出・提案する「カイゼンGAI」、IoTセンサーと連携して機械の異常を自動検知し、AIが自然言語でアラートを出す「AI製造部長」も展開しました。
これにより、改善サイクルの高速化、属人性の排除、電力使用量の26%削減など、定量・定性的な成果を上げています。
旭鉄鋼の取り組みは、生成AIを業務自動化の道具ではなく、「現場のパートナー」として位置づけた点が特長です。現場発のDXを推進したい企業にとって、再現性のある優良モデルといえるでしょう。
【出典】
旭鉄工が旭DXエンジンに「dejiren」を導入し生成AIを活用した迅速な意思決定を支援|ウイングアーク1stコーポレートサイト
パナソニックコネクト|ChatGPT活用で年間44万時間の業務時間を削減
パナソニックのB2Bソリューション事業を担うパナソニックコネクトは、社内業務の効率化と生産性向上を目的に、生成AIを活用した「ConnectAI」というAIアシスタントサービスを導入しました。
このサービスは、社内ルールや業務手順、システム操作方法などに関する従業員からの質問に対し、ChatGPTが即座に回答する仕組みを提供するものです。
ConnectAIの導入により、年間で約44.8万時間の業務時間削減を達成。社内の問い合わせ対応や情報検索にかかっていた時間が大幅に短縮されたことで、従業員は本来の業務に集中できるようになりました。
現在ではこの仕組みがグループ全体へと展開され、国内の全パナソニック社員約9万人を対象とする全社スケールでの導入に拡張。
ChatGPTを軸とした社内AIアシスタントが、全社的な働き方改革と知的生産性の向上に寄与する象徴的な事例となっています。
【出典】
パナソニックが全社へ「社内ChatGPT」を導入、国内9万人の社員が業務利用 | Business Insider Japan
パナソニックコネクト、「聞く」から「頼む」へシフトしたAI活用で年間44.8万時間の削減を達成 | プレスリリース
三菱UFJ銀行|生成AIを“組織変革のエンジン”として全社活用
三菱UFJ銀行は、全社的な業務プロセス改革と新たな事業創出を見据え、ChatGPTをはじめとした生成AIを基盤技術として本格導入しています。単なる業務効率化にとどまらず、AIを「組織変革のエンジン」として位置づけ、全行規模での活用を進めている点が大きな特長です。
AIの活用範囲は非常に広く、融資審査、顧客対応、社内文書作成といった銀行の基幹業務にまで及びます。
生成AIが自然言語で情報を処理・提案することで、判断の質を維持したまま意思決定のスピードを向上させ、月間22万時間相当の労働時間削減効果が試算されるなど、極めて高い業務改善効果を上げています。
このように三菱UFJ銀行は、AIを“支援ツール”ではなく、業務設計そのものを進化させる中核技術として捉えています。
大企業における生成AIの全社導入モデルとして、多くの企業から注目される先進事例となっています。
【参照】
MUFG×Sakana AI ─ 金融グループが描く、生成AI活用の未来像|三菱UFJイノベーション・パートナーズ
ユニクロ|Googleと連携しAIで需要予測と在庫最適化を実現
ユニクロは、アパレル業界におけるサプライチェーン改革の一環として、Googleと共同でAIによる需要予測システムを導入し、在庫管理の高度化とコスト構造の改善を進めています。
このシステムは、天候、販売履歴、地域特性、ファッショントレンドなど多様な要素をAIが解析し、店舗ごとに必要な商品の数量を高精度に予測するものです。
2018年の導入以降、過剰在庫や欠品のリスクを大幅に低減し、在庫最適化とともにコスト削減・機会損失の抑制に成功しています。
このようにユニクロは、AIを単なる販売支援ではなく、グローバルサプライチェーン全体の最適化エンジンとして位置づけており、ビジネスの根幹に深く組み込む形で活用しています。
アパレル業界におけるAI活用の先進事例として、国内外の注目を集める取り組みです。
【出典】
最新サプライチェーン|ユニクロのデジタル変革の中枢|NEWSPICKS
トヨタ自動車×NTT|AI基盤投資で「交通事故ゼロ社会」を目指す
トヨタ自動車とNTTは、「交通事故ゼロ社会」の実現という壮大なビジョンのもと、総額5,000億円規模のAI基盤投資を共同で進めています。
両社はこのプロジェクトを通じて、モビリティ社会の根本的な安全性向上と、次世代の交通・生活インフラの創出を目指しています。
取り組みの中心には、AIを用いた高度なデータ分析・予測技術があります。
これにより、安全運転支援システムや自動運転技術の進化を加速させ、車両単体の制御を超えた「社会全体での安全最適化」に挑戦しています。
この大規模投資は、単なる技術開発にとどまらず、AIを軸としたエコシステムの構築やスマートシティ連携を見据えたものであり、未来のモビリティ社会を支えるインフラ整備の中核として国内外から注目を集めています。
【出典】
NTTとトヨタ自動車、交通事故ゼロ社会の実現に向けた「モビリティ×AI・通信」の共同取り組みに合意 | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト
生成AI活用に成功するためのポイントとアクションプラン

生成AIの導入に成功している企業には、いくつかの共通点があります。ここでは、成功するためのポイントとアクションプランをまとめました。
ポイント①:導入目的を明確に定めて活用範囲を限定する
生成AIを導入する際にまず重要なのは、「何のために使うのか」という目的を明確にすることです。
目的が曖昧なまま活用を広げようとすると、現場で混乱が生じたり、期待値と効果にギャップが出たりする原因になります。
たとえば「企画書のたたき台づくりに活用する」「SNS投稿文を効率化する」など、業務の一部に限定して導入することで、スモールスタートが可能になります。
小さく始めて効果を確認し、徐々に活用範囲を広げていくアプローチが、社内に定着させるうえでも有効です。
アクションプラン
- 経営層・現場リーダーで「解決したい業務課題」を棚卸しする
- 最初の導入対象業務を1〜2領域に絞る(例:マニュアル作成、メール文案作成など)
- 試験導入後に振り返りを実施し、次の導入範囲を検討する
ポイント②:現場メンバーの不安や抵抗を解消する働きかけを行う
「AIに仕事を奪われるのではないか」「使い方がわからない」――こうした不安や抵抗感は、多くの現場で見られるリアルな声です。
導入を成功させる企業は、このような感情に寄り添いながら、丁寧なコミュニケーションを重ねています。
AIを「脅威」ではなく「アシスタント」として捉えてもらうためには、現場の声を拾い上げ、懸念を1つひとつ解消していく姿勢が不可欠です。
また、「あなたの仕事を奪うのではなく、単純作業を任せてあなたの価値を高めるためにAIがいる」というメッセージを浸透させることも大切です。
アクションプラン
- 社内アンケートや1on1で現場の不安・期待をヒアリングする
- 「AIに任せられる仕事」と「人にしかできない仕事」の線引きを示す
- 活用事例や操作デモを交えた勉強会を開催し、心理的ハードルを下げる
ポイント③:AI利用ルールやプロンプト運用のガイドラインを整備する
生成AIは、使い方次第で業務効率を大きく高められる反面、誤った運用による情報漏洩や品質リスクも伴います。
だからこそ、導入前に「誰が、何の目的で、どのように使うか」を明文化し、社内に共有できるルールと運用基準を整備することが不可欠です。
たとえば、AI活用が進んでいる企業では、以下のような体制を構築しています。
- 全社向けのAI利用ルールブックの策定:個人情報・機密情報の取り扱い、AIツールやモデルの選定方針などを明記し、従業員全体に周知徹底。
- プロンプト運用のガイドラインの作成:業務別にテンプレートやNG例を明文化し、現場の自己流運用や属人化を防止。
- 操作マニュアルや研修資料の整備:ツールの使い方、よくある誤用パターン、活用事例などをまとめたドキュメントを用意し、社内教育に活用。
- 活用状況のレビューとルールの継続的アップデート:利用実態や成果を定期的に確認し、ルールやガイドラインを随時見直す体制を整備。
こうした運用基準の整備によって、現場での混乱や誤用リスクを防ぎつつ、再現性のあるAI活用が継続的に実現できるようになります。
アクションプラン
- 各部門にヒアリングを行い課題を洗い出す
- 情報管理方針(機密情報・個人情報・著作権)、業務利用の可否、利用ツール・モデルの指定、禁止事項などをルールブックにまとめる
- プロンプトのテンプレート例や活用時の注意点を、運用ガイドラインにまとめる
- ChatGPTなど主要ツールのログイン・利用方法、便利な拡張機能、頻出ミスとその回避策などをマニュアル化する
- 作成したルールやマニュアルを社内Wikiやポータルに掲載し、必要に応じてチーム単位で研修会を実施。質問受付窓口も設ける
- 定期的に部署ごとの活用成果・課題を収集し、ガイドブックをアップデートする改善サイクルを構築する
ポイント④:ITリテラシーに応じたトレーニング・伴走支援を用意する
生成AIを導入しても、全社員がすぐに使いこなせるとは限りません。社内には「生成AIに慣れている人」もいれば、「使ったことがない人」もおり、こうしたスキルレベルの差が活用の定着を大きく左右します。
だからこそ、ITリテラシーに応じた段階的なトレーニング設計と、日常的な伴走支援が不可欠です。
成功している企業では、初心者向けのeラーニングやチュートリアル、実践形式のワークショップ、使い方相談のための窓口などを整備し、「誰でも安心して使える」環境を用意しています。
特に、現場の不安や疑問に寄り添うサポート体制や、プロンプトの添削・共有文化などを育むことで、継続的なAI活用文化の定着につながります。
アクションプラン
- 初心者向けのeラーニング・基礎チュートリアルを整備する
- 部署別・業務別の活用ワークショップを開く
- プロンプト添削・共有会を定期実施し、ノウハウの横展開を促す
- 利用者が気軽に相談できる社内ヘルプデスク・FAQチャットボットを設ける
- 現場の困りごとに対応する生成AI活用支援チームを設置する
ポイント⑤:ピンポイントでAIを試験導入し、効果を検証しながら広げる
AI導入を成功させている企業の多くは、最初から全社一斉に導入するのではなく、「スモールスタート(小規模導入)」を徹底しています。
はじめに特定の業務・チーム・プロセスに絞ってAIを導入し、効果を検証しながら徐々に展開していくことで、現場の混乱や反発を避けつつ、着実に成果を積み上げることで、失敗のリスクを最小限に抑えられます。
特に業務課題が明確な領域であれば、導入効果を数値で示すことも容易です。現場からのフィードバックも得やすく、改善のサイクルを回しやすくなります。
「とりあえずやってみる」のではなく、「どの業務のどんな課題をAIで解決したいのか」を明確にし、「どれくらい効果が出たのか」を可視化する。
こうした流れを繰り返すことが、社内での信頼構築と活用拡大につながります。
アクションプラン
- 試験導入のテーマを“1業務1課題”で決める(例:営業チームの提案資料作成工数の半減/人事部の求人票作成の自動化など)
- 「作業時間50%削減」「資料の品質スコアを平均○点向上」など、効果を測れる具体的な数値目標を設定する
- 簡単に導入できるツールを選ぶ
- 2~4週間で効果を検証し、「継続」「拡張」「停止」を判断する
- 成功事例(プロンプト例や現場の声、数値)を小分けにして社内に共有する
ポイント⑥:AIを“補助スタッフ”として捉え、人との協働を前提に設計する
生成AI導入の本質は「人間の代替」ではなく「補助」にあります。
AIは定型業務や大量の情報処理に強みを持つ一方、創造性や状況判断といった領域には、人の力が不可欠です。
そのため、AIを単なる自動化ツールとしてではなく、“協働パートナー”として捉える視点が求められます。
実際、多くの成功企業ではAIと人の役割を明確に分担しています。
たとえば、「下書きやアイデア出しはAI」「仕上げや判断は人間」といったように、工程ごとに役割を線引きしておくことで、業務品質のばらつきを防ぎ、生産性向上にもつながります。
中小企業では「人手不足の解消」だけに目が向きがちですが、重要なのは“人とAIが補完し合う業務設計”を育てていくことです。
AI任せにしすぎず、人の判断が必要なポイントを工程の中で明示しておきましょう。
アクションプラン
- AI導入における「人とAIの役割分担表」を作る
- 「AIたたき台→人が仕上げ」フローをテンプレ化する
- 「AIは補助役であり主役ではない」という価値観を社内浸透させる
- AI活用領域ごとのガイドラインを整備する
ポイント⑦:現場主導で課題に向き合い、改善サイクルを自走できる体制へ
生成AIの導入を成功させるには、「現場の困りごと」から活用を始めることが効果的です。
経営主導のトップダウン施策よりも、日々の業務で課題を感じている現場担当者が自らAIを試すことで、実用性や効果を実感しやすくなります。
その結果、現場主導での定着が進みやすくなるほか、成果が見えることで他部門への横展開も促進され、社内全体への波及効果が期待できます。
アクションプラン
- 「現場の困りごと」を拾い上げ、「まず試せそうな業務」にAIを活用していく
- 成功事例を社内で共有し、横展開を促す場をつくる
- 現場で使える「業務別プロンプト例」や「簡易マニュアル」などを用意する
- 現場でのAI活用が“評価・承認される仕組み”をつくる
- 改善サイクルを回せる現場リーダーを育成する
ポイント⑧:現場の成功体験を、全社に広げる仕組みをつくる
生成AIは「誰が・どんな業務で・どう使ったか」によって成果が大きく変わります。
だからこそ、現場での成功体験を社内全体に展開できる仕組みが不可欠です。
たとえば、「このプロンプトで提案書の作成が2時間短縮できた」「この言い回しを使うと精度が上がった」など、実践的な知見を共有することで、他部門でも取り組みやすくなります。
特に、文章生成・資料構成・キャッチコピー・調査要約など“業務別”に分類された活用例は再現性が高く、有効です。
社内ポータル(NotionやConfluence)、Slackチャンネル、ナレッジ共有会など、形式は自由ですが、重要なのは “リアルタイムで使えるナレッジを循環させる”こと。
情報の属人化やサイロ化を防ぎ、生成AIが自然と根づく文化を育てる基盤になります。
アクションプラン
- 成功プロンプト・活用Tipsを日常的に投稿する専用チャンネルを開設する
- NotionやConfluenceなどのナレッジ共有ツールで活用事例を業務別にまとめてアーカイブしておく
- 成果の出た活用事例をプレゼン形式で発表する場を設ける
ビジネス業務をもっと効率化したいなら、プロンプト設計を外部に任せるという選択肢も

生成AIを業務に活用するうえで重要なのが、「どのような指示を与えるか(=プロンプト)」です。
同じ業務内容でも、プロンプトの書き方によって出力結果の品質や実用性には大きな差が生まれます。
そのため、「業務に最適化されたプロンプト設計」自体を外部の支援先に任せるという選択肢も、効率的な導入を進めるうえでは有効です。
社内だけで最適なプロンプトを作るのは難しいケースも
生成AIの出力精度を高めるには、「誰に」「どんな目的で」「どんな情報をもとに」生成させたいのかを明確にし、それに合わせた指示文(プロンプト)を丁寧に設計する必要があります。
しかし、現場の担当者が通常業務の合間にこれを試行錯誤するのは現実的には難しいことも多く、うまく活用できないまま運用が止まってしまうケースも少なくありません。
外部支援を活用すれば“使える状態”から始められる
外部の支援サービスを活用すれば、あらかじめ業務に最適化されたプロンプトの設計や、社内ナレッジ共有の仕組みまでを一括で整備することが可能です。
たとえば、社内報、アジェンダ、議事録、営業メールなど、それぞれの業務特性に合わせたプロンプトテンプレートを用意することで、現場のメンバーがすぐに使える状態からスタートできます。
結果として、プロンプト設計にかかる時間や試行錯誤を減らし、業務効率化の成果が出るまでのスピードも大きく変わってきます。
導入フェーズに応じた支援の活用が有効
外部支援を検討する際は、単なるツール導入ではなく、「自社の業務とどう結びつけるか」まで踏み込んで支援してくれるパートナーを選ぶことがポイントです。
たとえば、「定型文業務から始めたい」「まずは一部チームで試したい」など、導入フェーズや目的に合わせて柔軟に設計できる支援先であれば、段階的な社内展開もスムーズに進みやすくなります。
最初から外部に任せるという判断は、効率的で安全
生成AIの導入は、単に使い方を覚えるだけでなく、活用を社内文化として定着させることが重要です。
もし「どこから手を付けるべきかわからない」「プロンプト設計に時間を割けない」といった状況であれば、最初から外部に任せるという判断も、効率的かつ安全な選択肢といえるでしょう。
生成AIによるビジネス業務の効率化に関するよくある質問
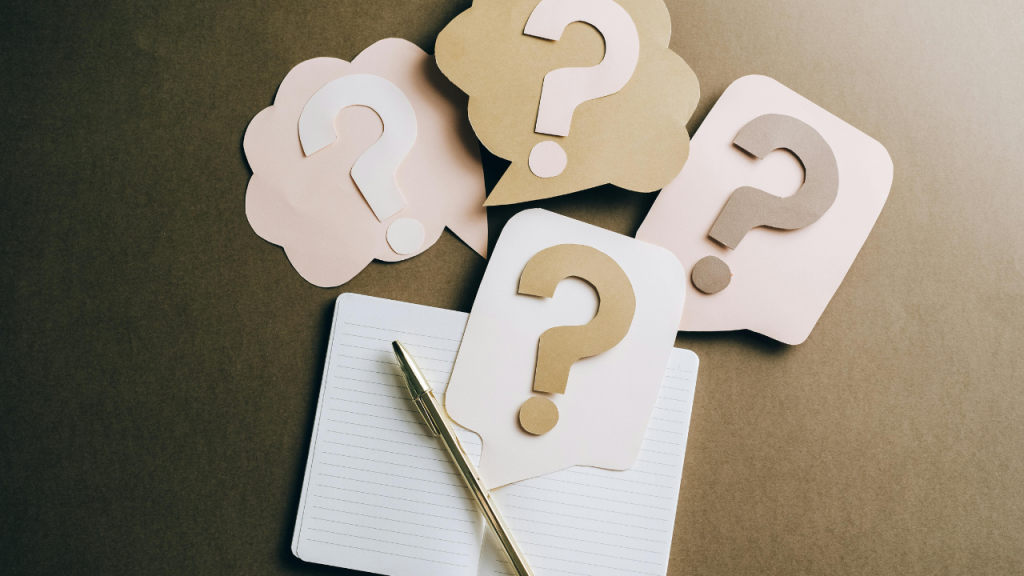
ここからは、生成AIによる業務効率化に関するよくある質問を紹介します。
Q1. 中小企業でも生成AIをビジネスに活用できますか?
はい、十分に活用可能です。むしろ人手や予算が限られる中小企業でこそ、人的リソースや時間の制約を補うために、生成AIの活用が効果的です。
いきなり全社導入するのではなく、1つの業務や1チームから試すことで、無理なく始められます。
Q2.生成AIはどんな業務に活用されていますか?
ビジネス現場では、次のような業務で幅広く活用されています。
- 定型業務:文章作成、議事録の要約、メール返信の下書きなど
- クリエイティブ業務:広告コピー、SNS投稿、ネーミング案の発想支援など
業種によって異なりますが、汎用性が高いため、多くの企業で導入が進んでいます。
Q3. 実際に生成AIを活用している企業は多いのでしょうか?
はい、国内外問わず、さまざまな業種で導入が進んでいます。特に2024年以降は、中小企業やスタートアップを中心に、生成AIをビジネス課題の解決手段として活用する動きが加速しています。
業務効率化だけでなく、競争力の強化を目的とした活用も目立ちます。
Q4. 導入する際に注意すべきことはありますか?
生成AIを企業導入する上で、以下のポイントに注意が必要です。
- 機密情報や個人情報の取り扱いには細心の注意を払う
- 生成された内容は事実確認を行い、鵜呑みにしない
業務で使う場合は、APIの利用、情報管理ルールの整備、ガイドラインの策定、プロンプト設計の工夫によって、リスクを最小限に抑えることができます。
Q5. どの生成AIツールを選べばよいか分かりません。
AIツールはそれぞれ得意分野が異なるため、用途に応じて比較・選定することが重要です。以下の記事では、ChatGPTとほかのAIツールを比較して紹介しています。参考にしていただければ幸いです。
あわせて読みたい記事
Q6. 社員がうまく活用できるか心配です。コツはありますか?
少人数で試行したのち、成果とノウハウを全社に展開するのが効果的です。社内勉強会や、プロンプト集の共有なども活用しましょう。
Q7. 社内にAIやITに詳しい人がいません。専門スキルがないと使いこなせませんか?
専門スキルがなくても十分に活用可能です。基本的なPC操作ができれば問題ありません。
特別な設備も不要で、多くの生成AIツールはクラウド上で動作するため、PCやスマートフォンがあればすぐに利用可能です。ノーコードで使えるツールや、操作支援のある外部サービスも増えています。
もし、どうしても導入が難しい場合は、社外パートナーと連携するのも有効です。
Q8. ChatGPTは、他の生成AIと何が違いますか?
ChatGPTは特に文章生成と対話形式での応答に強みがあります。他の生成AI(例:Notion AI、Claude、Bardなど)と比べても、ユーザーとの対話を通じたタスク遂行力や文体の自然さに定評があります。ただし、用途によっては他のツールのほうが適している場合もあるため、業務ニーズに合わせた選定が重要です。
ChatGPT以外のAIツールにも関心がある方は、以下の記事もぜひご覧ください。
あわせて読みたい記事
Q9.:社内教育や使い方のレクチャーはどうすればいいですか?
まずは、社内向けに「生成AIを使ってよい業務」と「入力してはいけない情報」を整理したガイドラインを作成することが第一歩です。そのうえで、効果的なプロンプトの書き方や活用事例を共有する社内勉強会やマニュアルの整備が有効です。もしリソースが限られている場合は、外部支援サービスを活用することでスムーズに整備できます。
まとめ:自社に合った生成AI活用が企業の成長につながる

生成AIは、もはや一部の先進企業だけが使う技術ではありません。中小企業を含む多くの企業が、業務の見直しや効率化を目的に、ビジネスの現場で本格的に活用し始めています。
特に、定型業務の自動化やクリエイティブ業務のアイデア支援といった領域は、生成AIとの相性が良く、導入効果が出やすい分野です。
本記事で紹介したように、具体的な業務プロセスに合わせたプロンプトを設計すれば、少ないリソースでも成果を得ることができます。
まずは、「自社のどの業務なら生成AIで効率化できるか」を見極めることが第一歩。ツールや導入方法に迷ったら、無料で始められるChatGPTなどから試し、社内の業務課題と照らし合わせて検証してみてください。
生成AIのビジネス活用は、業務改善にとどまらず、社員の時間と創造性を取り戻す手段にもなります。自社に合った形で少しずつ取り入れ、継続的に活用できる仕組みを整えていくことが、企業の成長につながる重要なカギとなるでしょう。
-
NO.1/7
ARTICLE2024/04/04
【おすすめ17選】AIライティングツールとは?無料?使い方や選び方を解説!
-
NO.2/7
ARTICLE2025/06/17
心に響く営業メールのテンプレート25選!業種別例文&ChatGPT(AI)プロンプトを一挙紹介
-
NO.3/7
ARTICLE2025/06/11
ChatGPTで営業メールを効率化!AI活用プロンプト20選&例文・使い方ガイド
-
NO.4/7
ARTICLE2025/06/05
LP制作をAIで効率化するには?ChatGPTプロンプト例や注意点を解説
-
NO.5/7
ARTICLE2025/06/10
ChatGPT音声モードの使い方を解説|無料版の制限・エラー・PC対応も整理
-
NO.6/7
ARTICLE2025/03/18
ChatGPTによるプレゼン資料の作成方法とは?クオリティを上げるコツや効率化のポイント
-
NO.7/7
ARTICLE2025/06/09
Notion AIとChatGPTを徹底比較!中小企業に最適なのはどっち?
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
