
ジョブ理論とは?業務改善に役立つ思考法と注意点を初心者にもわかりやすく解説
商品開発や業務改善において、「ジョブ理論」を活用するビジネスパーソンが増えています。しかし、ジョブ理論とは何か、ベネフィットやニーズ分析とは何が違うのかなど、疑問を抱えている方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、ジョブ理論とは何か、活用方法や注意点を具体例とともに解説します。
ジョブ理論を活かして業務に役立てる際にぜひ参考にしてみてください。
目次
ジョブ理論とは?

ジョブ理論とは「顧客はモノやサービスを買っているのではなく、何かを成し遂げるための手段として製品を雇っている」と考える思考法です。
「成し遂げたいこと」こそがジョブであり、商品開発だけではなく業務改善にも役立ちます。
具体的な例を紹介します。
- 眠気覚ましにコーヒーを買う…「眠気を覚ます」がジョブ、雇うものが「コーヒー」
上記の場合、眠気覚ましというジョブを達成するためには、濃い目のコーヒーを販売すると売り上げが上がるかもしれない、と仮定ができます。
ジョブを明確にすれば、より一層顧客に選ばれる商品やサービスを提供できるようになるのです。
ジョブ理論の提唱者「クレイトン・クリステンセン」とは
ジョブ理論の提唱者であるクレイトン・クリステンセンは、最も影響力のある経営思想家トップ50において、2011年・2013年の両年で1位を獲得した人物です。
ジョブ理論について書かれた名著「ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム」は、ビジネスリーダー1万人が選ぶベストビジネス書トップポイント大賞で2017年下半期第2位を獲得しています。
彼が提唱したジョブ理論は、顧客がなぜ商品やサービスを選ぶのかにフォーカスを当てた考え方です。「ニーズがあるのに売れない」「賢くやったのに失敗した」といった問題を抱える企業の、マーケティング、開発、営業、組織の運営者にまで幅広く広がっていきました。
そして、商品ではなく進歩を売るという新しい視点や、現場で使いやすいフレームワークである点がビジネスパーソンに響き、幅広く使われるようになっていったのです。
クレイトン・クリステンセンの提唱するジョブ理論は、今なお多くのビジネスシーンで使われています。
ジョブ理論とミルクシェイク・ストーリー
「ミルクシェイクはなぜ朝に売れるのか?」という事例は、ジョブ理論の提唱者であるクレイトン・クリステンセン氏が、実際のコンサルティングの場で語ったものです。
あるファーストフード店で、ミルクシェイクの売り上げが伸びないことが問題になっていました。しかし、朝の時間帯は、ミルクシェイクの売り上げが良いという状況でした。
なぜ朝にだけミルクシェイクが売れるのかを探るため、クレイトン・クリステンセン氏は、朝ミルクシェイクを買う人々にインタビューしました。すると、次のような購買理由が明らかになったのです。
- 長時間の運転で退屈を紛らわせたい
- 運転中の空腹をしのぎたい
- 運転中でも飲みやすいものがいい
つまりミルクシェイクは、「朝の通勤時間に、空腹をしのぎ、手持ち無沙汰を解消したい」というジョブに適していることがわかりました。
明らかになったジョブを踏まえ、ファーストフード店では商品の量を増やし、飲み口を細くして、なるべく長い時間退屈をしのげるようミルクシェイクの設計をし直しました。その結果、売り上げが大きく伸びたのです。
表面的な顧客の課題ではなく、その行動の背景にまで注目することが大切だと、多くのビジネスパーソンがジョブ理論によって気付かされています。
ジョブ理論がビジネスで注目されている理由

ジョブ理論は、顧客の行動理由や背景が理解できる便利なフレームワークとして、今もなおビジネスで注目され続けています。
その理由は次の通りです。
- イノベーションの成功確率を高めるため
- プロダクトの機能改善方針が明確になるため
- 顧客への理解が深まるため
それぞれの理由について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
理由①:イノベーションの成功確率を高めるため
ジョブ理論は、イノベーションの成功確率を高められるフレームワークです。
かつて、イノベーションは運任せの部分が多く、「なんとなくニーズに合っていたのかもしれない」と判断してしまったり、なぜ商品やサービスが売れたのかが分からなかったりといったケースが少なくありませんでした。
しかし、ジョブ理論は顧客の無意識の選択を言語化し、商品が売れた理由を明確にしてくれるフレームワークです。
単なるニーズではなく、顧客の背景や目的を深掘りすることで、ヒットの再現性を高め、成功確率が高いイノベーションを生み出すことができます。
理由②:プロダクトの機能改善の方針が明確になるため
ジョブ理論では顧客のジョブを理解して行動できるため、「何を優先して改善すべきか」が明確になります。
たとえば、顧客から「アプリが使いにくい」という要望があった場合、デザインやUIの変更、高度・便利な機能の追加ばかりに目が行ってしまいがちです。
しかし、顧客のジョブである「作業の流れを止めずに使いたい」を理解していれば、起動の速さや操作の簡単さなど、作業の流れを止めないための改善策が最優先であるという判断ができます。
顧客の片付けたいジョブを明確にしつつ実務に役立てられるからこそ、ジョブ理論はビジネスで注目され続けているのです。
理由③:顧客への理解が深まるため
ジョブ理論は、顧客への理解を従来の方法よりも深められるフレームワークでもあります。
これまで、顧客分析には年齢や性別などの属性、満足・不満足といった意識調査、購買データなどの行動ログを元にしていました。
しかし、これらの情報は顧客の表面的な理解しかできず、行動の裏にある意図や文脈まで読み取ることはできません。
一方、ジョブ理論を使えば、顧客が言語化できない「本当の行動の理由」を顕在化できます。ジョブとは顧客が達成したい成果であり、「この人は何に悩み、どのような姿を目指し、何に投資しているのか?」まで見えるようになるのです。
ジョブ理論は顧客の深層理解に優れているため、ビジネスで長く注目され続けているのです。
ジョブ理論のフレームワークとは?6つの視点でみる意思決定の流れ
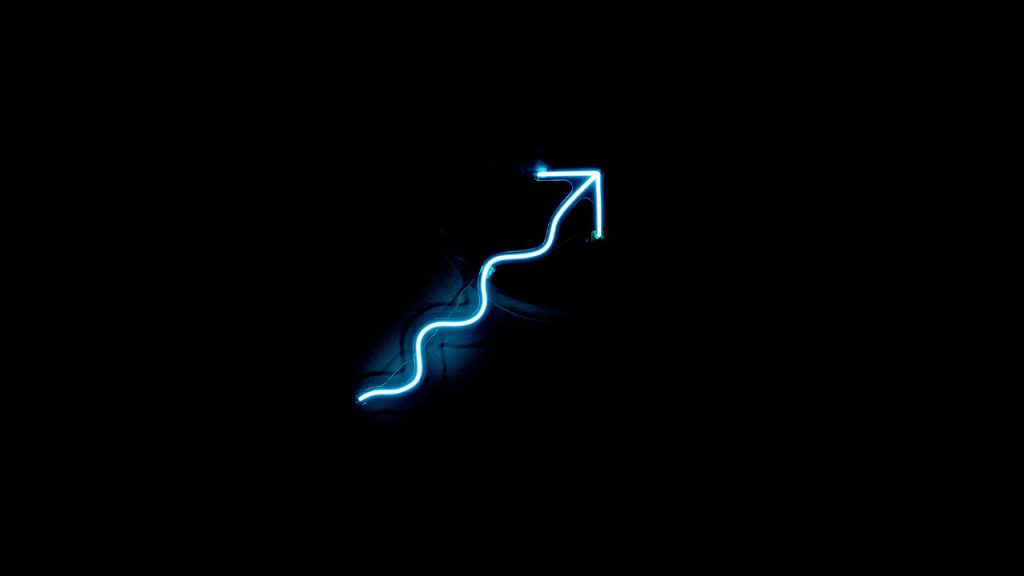
ジョブ理論のフレームワークは、以下の6つの視点で構成されています。
- ジョブ
- 進歩
- 無消費
- 状況
- 雇用
- 解雇
6つの視点を理解することで、より顧客の意思決定の流れがわかり、顧客行動を具体的に捉えられるようになるでしょう。それぞれの視点について、解説します。
①ジョブ
「ジョブ」は、顧客がある特定の状況で成し遂げたい進歩や課題を指します。
家電を例にして考えてみましょう。
| ジョブの例 | 商品 |
| 夕食の準備を時短して、子どもとの時間を増やしたい | 電気圧力鍋 食洗機 |
| 家事にかける時間を減らして、リラックスタイムを増やしたい | お掃除ロボット |
| 家族に「美味しい」と喜んでもらえる料理をつくりたい | 多機能オーブンレンジ 自動調理鍋 |
| 見た目もおしゃれな家電で、毎日の気分を上げたい | デザイン家電 |
ジョブを明確にする際は、以下の質問を繰り返してみましょう。
- 「なぜ、それを買おうと思ったのか?」
- 「その商品を使って、どうなりたかったのか?」
- 「どんなときに、これがあって良かったと感じたのか?」
- 「その商品を選ばなかったらどうしていたのか?」
これらの質問で掘り下げることで、ジョブがより明確になっていきます。明確なジョブを見抜くことで、売れる商品・サービスづくりが進められるようになるでしょう。
②進歩
「進歩」は顧客が求めるゴールにたどり着くことであり、ゴールまでのプロセスも含まれています。
顧客の状況や環境は常に変化しています。そのため企業側は、顧客がジョブを達成できるより良い状態を絶えず作り続けなければいけません。理想的な状態を目指し、常に探求し続けることが「進歩」です。
ゴールまでの進歩は短い場合もあれば、何度も小さな中間地点を設定し、時間をかけていかなければならない場合もあります。中間ゴールを設定しておくようにすれば、ゴールに向けて、ブレない進歩を作ることができるでしょう。
企業は顧客の変化を常に察知し、柔軟に、なおかつゴールを見失わずに進歩していく必要があります。
③無消費
「無消費」は、顧客自体がそもそもニーズや課題に気づいておらず、解決のための行動すらしていない状態を指します。市場すらできあがっていない場合もあります。
そこで顧客のニーズや課題を顕在化させれば、新しい市場の発見につながっていきます。
無消費から新しい市場の発見につながった例を紹介します。
| 隠れていたニーズ・課題 | 結果 |
| ホテルは高い、もっと安く泊まりたい | 民泊サービス「Airbnb」が選ばれるように |
| 読書したいけど時間がない、読書は目が疲れる | 耳で本を聞くサービス「Audible」の登場 |
| 献立を考えるのがつらいけど、自炊はしたい | ミールキットの登場 |
無消費から新しい市場を発見するためには、進歩したいけど、何かに阻まれている人に注目するのがおすすめです。
④状況
ジョブには、常に顧客の「状況」がセットで存在します。状況とは、どんな人が、いつ、どこで何をしており、何に不満を感じているのかなどを示したものです。
ミルクシェイクの例で考えてみましょう。
| 状況 | 朝の通勤ラッシュ。片手がふさがっていて、食べる暇がない。運転中はスマホも読書もできず、退屈 |
| ジョブ | 運転中に片手で摂れる、腹持ちが良くて退屈しのぎになる飲み物がほしい |
| 商品 | ミルクシェイク |
この場合、片手がふさがっており、退屈を感じているという状況から、ミルクシェイクが導き出されます。
もしも状況が異なり「両手は空いている」「友達と一緒で楽しい」という状況であれば、サンドウィッチやチキンなど、他の食べ物が適していたかもしれません。
顧客に選ばれる商品づくりのためにも、状況の明文化が重要です。
⑤雇用
ジョブ理論において、特定の商品を採用することを「雇用する」「雇う」と言います。「この商品があれば、自分の課題・進歩が解決できる」と判断して、顧客が選ぶ行為のことです。
たとえば「朝の通勤が退屈」という課題を解決するために、ミルクシェイクが雇われました。「献立を考えるのがつらいけど、自炊はしたい」という課題に対しては、ミールキットが雇用されます。
なぜ雇われたのかを理解すれば、商品の提供価値はより明確になります。価値が明確になると、今後商品をどのように伸ばすべきか、どのような特徴をさらに強化すればよいかがはっきりするでしょう。
⑥解雇
「解雇」は、顧客がより新しい商品に乗り換えるために、現在雇っている商品を使わなくなる状態を指します。
たとえば、「より便利なアプリが出てきて、これまでのアプリをアンインストールした」とか、「配送の遅いサービスを辞めて、当日配達が可能なサービスに乗り換えた」という状況も「解雇」です。
解雇は、顧客の不満を明らかにできる視点です。解雇された理由によって、商品の弱点や、改善すべき項目がはっきりするからです。
顧客のニーズや課題は日々移り変わり、意思決定に関わる項目なども常に変化していきます。解雇に至った理由がわかれば、顧客の変化に対応した、より新しい商品を生み出すきっかけにもなります。
ジョブ理論とよく混同される言葉との違い

ジョブ理論では、混同されやすい言葉もいくつかあるので注意しなければいけません。言葉の違いを明らかにしないまま使っていると、マーケティングや商品開発の際に、勘違いから大きな間違いを引き起こしてしまう可能性もあります。
ここでは以下の3つの違いについて説明します。
- 積極的ジョブと消極的ジョブの違い
- ジョブとニーズの違い
- ジョブとベネフィットの違い
ジョブ理論を正しく活用するためにも、違いをよく理解しておきましょう。
積極的ジョブと消極的ジョブの違い
ジョブ理論では、積極的ジョブと消極的ジョブという二つの用語が用いられます。積極的ジョブと消極的ジョブの違いは次の通りです。
| 種類 | 解説 | 例 |
| 積極的ジョブ | 顧客が「達成したい進歩」や「前向きな目的」に基づくジョブ | ・早起きして余裕のある朝を過ごしたい ・副業を始めて収入を増やしたい |
| 消極的ジョブ | 顧客が「避けたい事態」や「不安・不満の回避」を目的にするジョブ | ・寝坊して怒られたくない ・収入が不安定で将来が怖い |
成功する商品は、積極的ジョブと消極的ジョブの両方を満たすパターンが多いです。たとえばロボット掃除機は、「帰って来たときに部屋が綺麗で、気分が良くなりたい」という積極的ジョブと、「掃除の時間を取られたくない」という消極的ジョブの2つを満たしています。
ジョブとニーズの違い
ジョブとニーズは、似ている言葉のようで異なる意味をもっています。両者の違いは次の通りです。
| 言葉 | 意味 | 例 |
| ジョブ | 顧客が「達成したい進歩」や「乗り越えたい課題」 | 夜遅くまで働いた後に、手軽に栄養を摂って眠りたい |
| ニーズ | 顧客が「○○がほしい」と望んでいる状態 | 簡単に栄養がとれる食事がほしい |
ニーズは「何が欲しい」に近く、ジョブは「なぜそれが必要なのか」に近いです。また、「ニーズ」は調査結果として表面的に現れやすいのですが、「ジョブ」は観察や分析から見える深層の動機のため、表面的に知るのは難しいです。
ジョブとニーズの違いを正しく理解できるようになると、顧客の本質に寄り添った商品開発ができるようになるでしょう。
ジョブとベネフィットの違い
ジョブとベネフィットの違いは次の通りです。
| 言葉 | 意味 | 例 |
| ジョブ | 顧客の達成したい進歩や課題の解決 | 夜の運転中に眠くなるから、安全に目を覚ましたい |
| ベネフィット | 製品やサービスが提供する価値・利得 | 眠気が冷めて、集中力もアップする |
ベネフィットは商品側からの語りなのに対し、ジョブは顧客側からの語りという大きな違いがあります。顧客のジョブにぴったり合うベネフィットを提供できると、顧客に選ばれやすくなるでしょう。
例のように、運転中の眠気覚ましを探している顧客に、眠気が冷めて集中力が上がるドリンクを売り出せば、選んでもらえる可能性は高くなります。
しかしベネフィットが「リラックスできる」だった場合、選んでもらえる可能性は低いでしょう。
ジョブ理論におけるジョブの種類と事例

ジョブには、目的や性質別に以下のような3つのジョブが存在します。ジョブごとの違いと特徴を理解しておくと、商品開発において何を重視すべきかが明確になります。
- 機能的ジョブ
- 感情的ジョブ
- 社会的ジョブ
それぞれのジョブの特徴や違いについて、具体的な事例を交えながら紹介します。顧客のジョブを導き出す際の参考にしてみてください。
機能的ジョブ
機能的ジョブとは、実用性や効率化、安全性などのキーワードが重視される、顧客が現実的にやりたいことを指すジョブです。
具体的な事例を見ていきましょう。
| 商品 | ジョブ |
| ロボット掃除機 | ・掃除する時間を節約したい ・家にいない間に自動で掃除してほしい |
| GoogleMap(地図アプリ) | ・目的地に最短ルートでたどり着きたい ・渋滞を避けて効率よく移動したい |
| お弁当用冷凍からあげ | ・朝の忙しい時間に手軽に1品用意したい |
機能的ジョブはもっともわかりやすく、企業側が把握しやすいジョブです。しかし、機能的ジョブだけでは、他社との差別化を図りにくいため、状況をしっかり捉え、顧客がほかのジョブを抱えていないかなども意識して調べる必要があります。
感情的ジョブ
感情的ジョブは、顧客が「幸せを感じたい」「不快を避けたい」といった感情面の欲求を満たすために雇うジョブのことです。
具体的な事例を見ていきましょう。
| 商品 | ジョブ |
| アロマ機能付き空気清浄機 | ・部屋をいい香りにしてリラックスしたい |
| 服 | スタイルをよく見せて自信を持ちたい 楽なのにキマる服を着て、人前でも堂々としたい |
| 家事代行サービス | ・自分の自由時間を増やしたい ・忙しいけれど快適な部屋で過ごしたい |
感情的ジョブは数字で測りにくいため、顧客の書いた文章などから判断する必要があります。ジョブを導き出すのに時間はかかりますが、意思決定の軸になりやすいジョブです。
社会的ジョブ
社会的ジョブとは、人からどう見られているか、社会や集団でどう評価されたいかなど、社会的な文脈での動機を指します。具体的な事例を見ていきましょう。
| 商品 | ジョブ |
| デザイン家電 | ・友人を招いたときにセンスが良いと思われたい ・丁寧な暮らしをしている印象を与えたい |
| 高級車 | ・周囲からお金持ちだと思われたい ・都会的でスマートな印象を持たれたい |
社会的ジョブは、顧客本人からも意識されにくいジョブで、購買動機の奥底にあるケースが多いです。
ジョブ理論を業務改善に活かすステップ

ジョブ理論を業務改善に活かすためには、次の5つのステップを踏むとスムーズに進められます。
- 現場が手に入れたい進歩は何かを定義・言語化する
- 状況を正しく把握して片付けるべきジョブを見つける
- 雇用すべきフロー改善案やプロダクトをリストアップする
- 実際に雇用して効果を測定する
- 導入後に生じたジョブがないかを監視する
それぞれ、具体例を交えて紹介します。実際に自社で業務改善を行う際の参考にしてみてください。
STEP①:現場が手に入れたい「進歩」は何かを定義・言語化する
まずは、現場が取り入れたい進歩を具体的に定義・言語化しましょう。ジョブ理論で重要な「進歩」とは、顧客や現場が現状から目指す理想の状態へと変化していく結果・過程です。
ジョブ理論では、顧客が商品やサービスを「雇う」のは、その進歩を叶えるためだと考えます。
進歩を具体的に定義して、何をすればいいのかを明確に言語化しましょう。
進歩を明らかにするためには、以下の質問をしてみましょう。
| 質問 | 回答 |
| どんな作業が苦痛・煩雑なのか? | コピペ作業、複数システムへの同一入力など |
| そのせいで、どんなことができていないのか? | 分析に集中できていない、顧客対応にもっと時間を取って丁寧に対応したい |
| 理想の状態とはどんなものか? | 仕事の質が上がる、定時で帰れる、評価されやすくなる |
この質問によって、顧客にとっての進歩は「単純作業に追われず、価値ある仕事に集中できる状態をつくる」ことだと判明しました。
何のために、どうなりたいかまで含めた言語化を心がけましょう。
STEP②:「状況」を正しく把握して片付けるべきジョブを見つける
ジョブ理論における「状況」とは、どんな人が、いつ、どこで何をしており、何に不満を感じているのかなどを示したものです。状況によって、顧客のジョブは異なります。
たとえば「日々の仕事での入力業務を楽にしたい」という事例で考えてみましょう。
質問を繰り返し、正しい状況を把握していきます。
| 質問 | 回答 |
| どのタイミングで「面倒」と感じる? | ・朝イチに顧客データを全部まとめて入力するとき |
| なぜ、そのタイミングなのか? | ・前日の処理がたまっているから ・午前中に上司のチェックを控えており時間がない |
| どんな感情が湧いている? | 「早くやらないといけない」「焦る」 「ミスをするのがこわい」 |
| どうして今改善したいのか | 他の業務も抱えており業務を効率化したいため |
このように見ていくと、「単に入力業務が面倒」なのではなく、「朝のチェックまでに、大量の入力をミスなく終えたい」というプレッシャーの中にいることがわかります。
そして片付けるべきジョブは、「朝の限られた時間内で、正確かつ素早く入力作業を終え、上司のチェックをクリアしたい」という、時間的制約・心理的焦り・精度要件が組み合わさったものだと判断できます。
STEP③:雇用すべきフロー改善案やプロダクトをリストアップする
進歩(=目指す理想の状態へと変化していく過程)が明確になり、顧客の「状況」が把握され、片付けるべき「ジョブ」が分かったら、次は雇用する対象(フロー改善案やプロダクト)を決める必要があります。
業務改善の8原則を参考にしながら、以下のような流れでリストアップしてみましょう。
- 廃止の原則:この作業はやめられないか?
- 削減の原則:作業の頻度や回数を減らせないか?
- 容易化の原則:手順をもっと簡単にできないか?
- 標準化の原則:やり方を統一できないか?
- 計画化の原則:作業を事前に準備できないか?
- 同期化の原則:他の業務とのタイミングは適切か?
- 分担検討の原則:本当にこの人がやる必要があるか?
- 機械化の原則:PCやツールで自動化できないか?
こうして洗い出した改善案については「その業務改善が本当に進歩や成果につながるか?」を必ず確認しましょう。効果の薄い改善を取り入れると、逆に新しいムダを生んでしまうこともある点にご留意ください。
STEP④:実際に雇用して効果を測定する
雇用候補が見つかったら、次は仮説を実行し、効果を測定する必要があります。
ジョブ理論を使って立てた仮説が現場で通用するかどうかは、実際に試してみないとわかりません。
効果測定を行う際は、改善前後のビフォーアフターを明確に出し、数値で変化を見るようにしましょう。定量評価だけではなく、感覚や満足度の調査を同時に行うのも大切です。
望んだ進歩が得られていた場合は、雇用した手段を本格的に導入します。得られなかった場合は雇用候補の見直し、状況や進歩の再定義を行います。
STEP⑤:導入後に生じたジョブがないかを確認する
導入の前後を比較し、新たに生じてしまったジョブが生まれていないかを確認しましょう。
新たなジョブが生まれていないかを見るためには、1週間~1ヶ月といった期間を決め、定期的なジョブ観察を行うのがおすすめです。
現場のリアルな声から、新たなジョブが生まれていないか判断することが大切です。
ジョブ理論の注意点と課題

ジョブ理論には、押さえておきたい注意点や課題も存在します。特に押さえておきたい注意点と課題は以下の2つです。
- ジョブの特定そのものが難しい
- 解決策までは見つからない
それぞれの対処法もあわせて紹介します。ジョブ理論を使う際の参考にしてみてください。
ジョブの特定そのものが難しい
ジョブは顧客自身でさえも言語化することが難しいものです。
ジョブを特定するには、まず「なぜ売れるのか」に目を向けるようにしましょう。顧客中心の思考に切り替えることが、ジョブを特定する第一歩です。
量的なデータだけではなく、顧客がどのような感情を抱き、どんな状況を抱えているかといった質的なデータも掘り下げることが大切です。
解決策までは見つからない
ジョブ理論は、顧客が「ある状況で進歩するために商品・サービスを雇う」という視点が中心となっています。なぜその商品を選んだのか、どんな状況だったのか、何を達成したいのかは明確にできますが、解決策まで見つけることはできません。
顧客への共感から解決策を探る「デザイン思考」やビジネスの構造を可視化する「ビジネスモデルキャンバス」などを用いながら、ジョブ理論で「誰が、どんな状況で、何を進歩させたいのか」を明確にし、「どのように提供するか」を導き出していきましょう。
ジョブ理論を解説したおすすめの本3選

最後に、ジョブ理論について学べる書籍をご紹介します。
- ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム
- 「ジョブ理論」完全理解読本 ビジネスに活かすクリステンセン最新理論
- 実践「ジョブ理論」
ジョブ理論を体系的に学ぶ際に、ぜひ参考にしてみてください。
ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム
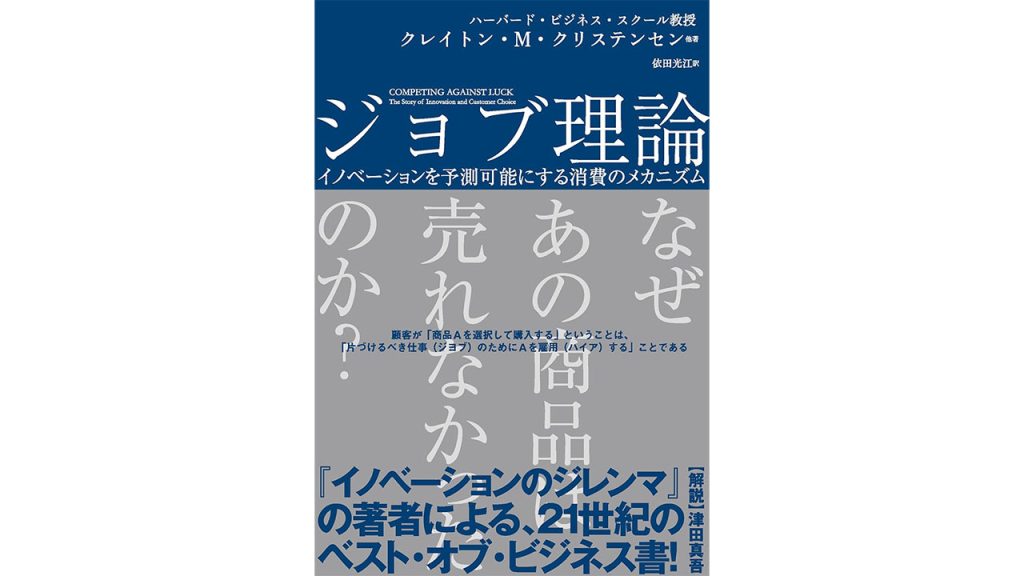
「ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム」は、ジョブ理論の提唱者であるクレイトン・クリステンセン氏が書いた名著のひとつです。
顧客がモノを買うのは、製品が欲しいからではなく、達成したい「進歩(=ジョブ)」を解決するためであると、実践的に解説した一冊となっています。
実際の事例も取り上げられているので、ジョブ理論の本質が理解しやすいでしょう。
雇用や無消費といった視点についても丁寧に触れているので、ジョブ理論を学び始めるのなら、ぜひ一度読んでおきたい本です。
「ジョブ理論」完全理解読本 ビジネスに活かすクリステンセン最新理論
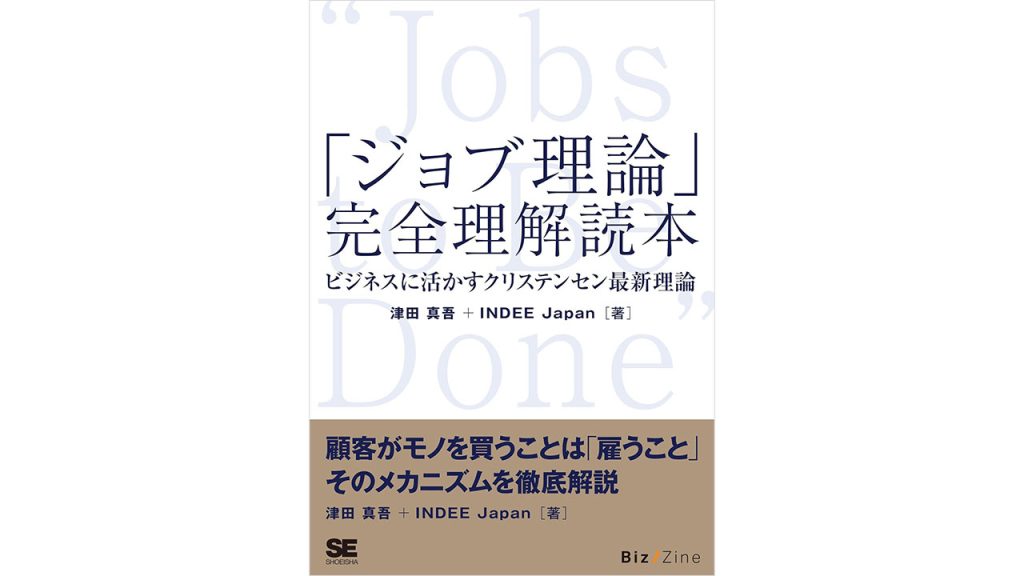
「『ジョブ理論』完全理解読本 ビジネスに活かすクリステンセン最新理論」は、クレイトン・クリステンセン氏の「ジョブ理論」を、さらに実践的でわかりやすい内容にかみ砕いている、津田真吾氏の一冊です。
日本人にとって親しみやすい事例などが交えられており、実際の業務にも取り入れやすくなっています。さらにマーケターや事業開発者など、さまざまな立場の人が理解しやすいように説明されています。
クレイトン・クリステンセン氏の「ジョブ理論」よりも読みやすい本を探している方に向いています。
実践「ジョブ理論」
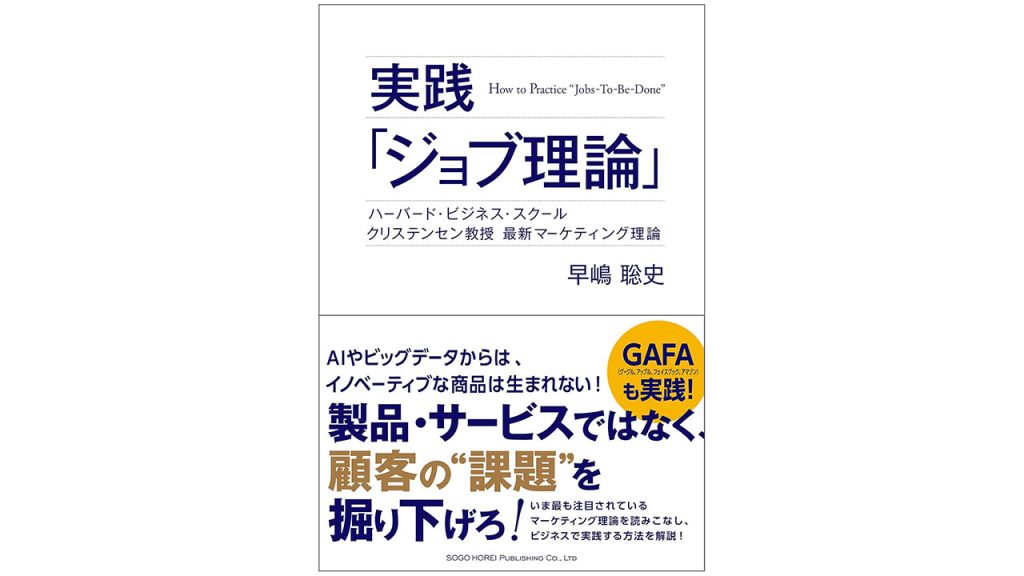
早嶋聡史氏の書いた「実践『ジョブ理論』は、マーケターや商品開発担当者向けにジョブ理論を解説している本です。マーケターだけではなく、営業や起業家などにも役立つ内容です。
理論の説明だけではなく、実践に導入するためのポイントや、ジョブ理論を実践するうえで押さえておきたい視点などについても触れています。
全体像をイメージしてから、段々とジョブ理論への理解の粒度を上げていく構成となっており、読んでいてわかりやすいとの評価も多く寄せられています。
原書のクレイトン・クリステンセン氏の「ジョブ理論」に書かれている内容をさらにかみくだいて説明しているので、原書への理解をさらに深めたいときのサポート役となる一冊です。
ジョブ理論を活用して業務改善や新規事業の創出を実現しよう
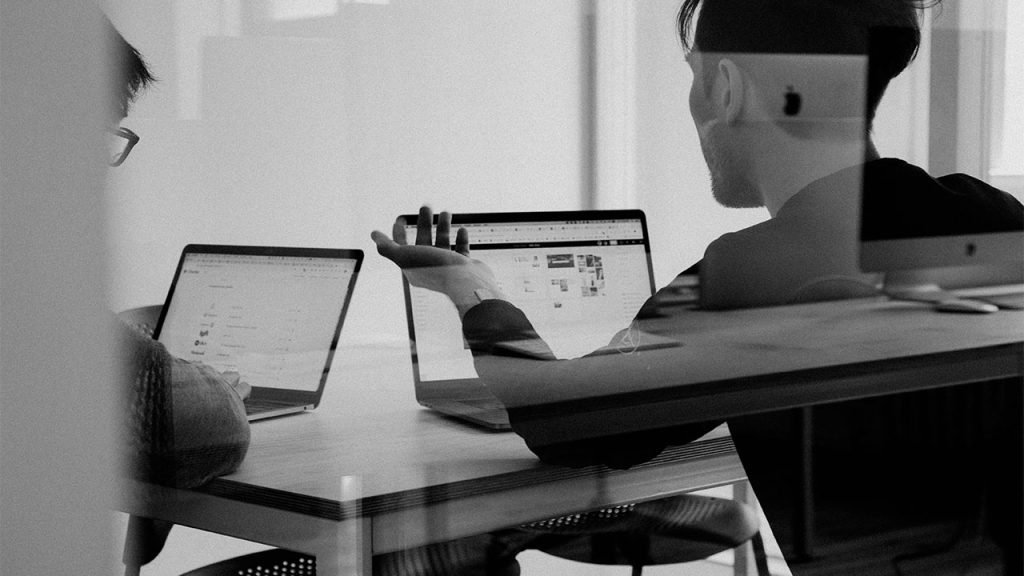
ジョブ理論は、顧客の心理を深く理解し、「なぜその商品やサービスが選ばれるのか」という本質に迫るためのフレームワークです。
商品開発や新規事業に活用することで、表面的なニーズにとどまらず、顧客が本当に“雇いたい”と感じる商品設計が可能になります。
業務改善においても、従業員の行動の背景にあるジョブを捉えることで、単なる効率化ではなく、感情に寄り添った本質的な改善を実現できるでしょう。
本記事で紹介した視点やステップを参考に、日々の業務にジョブ理論を取り入れてみてください。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
