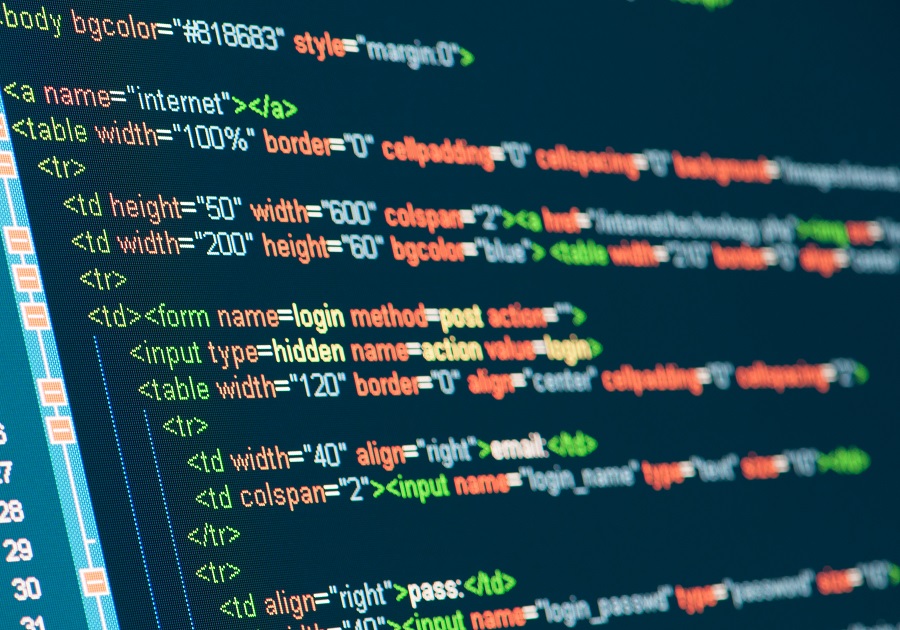
SaaSとは?メリット・デメリットや代表例15選を初心者向けに解説!
最近よく耳にする「SaaS」という言葉。Web企業に配属になったものの、SaaSって一体何なのか、どういう仕組みなのかがよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
SaaSは現代のビジネスにおいて欠かせないサービス形態となっており、理解しておくことで業務効率化や課題解決につながります。
本記事では、初心者向けにSaaSとは何か、導入するメリット・デメリットや代表的なSaaS例についてわかりやすく解説しています。失敗しないSaaS選定ポイントや進め方、そのほか知っておくべき基礎知識についても網羅しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
SaaS(サース)とは?

SaaS(サース)とは「Software as a Service」の略称で、「サービスとしてのソフトウェア」という意味です。従来のようにCDやUSBでソフトウェアを購入してパソコンにインストールするのではなく、インターネット経由でソフトウェアを利用できる仕組みのことを指します。
読み方は「サース」が一般的ですが、「サーズ」と呼ぶ場合もあります。どちらも正しい読み方なので、職場や取引先に合わせて使い分けると良いでしょう。
従来のソフトウェアとSaaSの違い
従来のソフトウェア(パッケージソフト)は、家電量販店でDVDを購入し、自分のパソコンにインストールして使うものでした。一度購入すれば永続的に使えますが、アップデートやメンテナンスは自分で行う必要があります。
SaaSは全く異なるアプローチです。ソフトウェアはクラウド上で動作しており、ユーザーはWebブラウザやアプリを通してアクセスするだけ。月額料金を支払う代わりに、常に最新版が使え、保守管理の手間もかかりません。
SaaSがクラウドサービスと呼ばれる理由
SaaSが「クラウドサービス」と呼ばれる理由は、ソフトウェアがクラウド(雲)のように、どこか遠くのサーバー上で動いているからです。ユーザーは自分のデバイスにソフトウェアを保存する必要がなく、インターネットを通じて「雲の向こう側」にあるソフトウェアを利用しています。
この仕組みにより、オフィス、自宅、外出先など、インターネットがある場所ならどこからでも同じソフトウェアにアクセス可能。スマートフォン、タブレット、パソコンなど、異なるデバイスからも利用できるのが大きな特徴です。
SaaS・PaaS・IaaSの違い

SaaSを理解する上で避けて通れないのが、似たような用語である「PaaS」「IaaS」との違いです。これらは全てクラウドサービスの種類ですが、提供される範囲が大きく異なります。
混乱しやすい用語ですが、「何をどこまで提供してくれるのか」という視点で整理すると、違いがはっきりと見えてきます。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
提供範囲による3つの分類
クラウドサービスは、どこまでの機能を提供するかによって3つに分類されます。下から順に、IaaS(基盤)、PaaS(基盤+開発環境)、SaaS(基盤+開発環境+アプリケーション)という階層構造になっています。
簡単に言えば、IaaSは「土地」、PaaSは「土地+建物の骨組み」、SaaSは「完成した家具付きの家」のようなイメージです。利用者は必要なレベルに応じて、どのサービスを選ぶか決められます。
SaaS:すぐ使える完成品ソフトウェア
SaaSは3つの中で最も完成度が高く、すぐに使い始められるサービスです。Gmail、Microsoft 365、Zoomなどがその代表例で、アカウントを作成すればすぐに利用開始できます。
開発やセットアップの知識は一切不要で、エンドユーザーが直接使うことを想定して作られています。業務効率化を目的とした一般的な企業では、SaaSを選ぶケースがほとんどでしょう。
PaaS:開発環境を提供するプラットフォーム
PaaS(パース)は「Platform as a Service」の略で、アプリケーション開発に必要な環境を提供するサービスです。サーバー、OS、データベースなどの基盤は用意されているため、開発者はアプリケーション開発に集中できます。
代表例にはAWS(Amazon Web Services)、Microsoft Azure、Google Cloud Platformなどがあります。主にシステム開発会社やIT部門が利用し、一般的なビジネスユーザーが直接触ることは少ないサービスです。
IaaS:基盤となるITインフラを提供
IaaS(イアース、アイアース)は「Infrastructure as a Service」の略で、ITインフラの基盤部分のみを提供するサービスです。サーバー、ストレージ、ネットワークなどのハードウェアリソースをクラウド経由で利用できます。
利用者は提供された基盤の上に、OSやミドルウェア、アプリケーションを自由に構築できます。最も自由度が高い反面、専門的な知識と技術が必要なため、主にIT専門家が利用するサービスです。
SaaSを導入する5つのメリット

SaaSが多くの企業で導入される理由は、従来のソフトウェアにはない数多くのメリットがあるからです。とくに初期コストの削減や運用の手軽さは、中小企業にとって大きな魅力となっています。
ここでは、SaaS導入によって得られる主要なメリットを5つに整理しました。
- 初期費用を大幅に削減できる
- 保守・運用の手間が不要
- どこからでもアクセス可能
- 常に最新版が利用できる
- 複数人での同時作業ができる
それぞれがどのような場面で威力を発揮するのか、具体例とともに解説していきます。
初期費用を大幅に削減できる
従来のパッケージソフトは、ソフトウェアライセンス料として数十万円から数百万円の初期投資が必要でした。SaaSは月額制のサブスクリプション型が主流のため、初期費用を大幅に抑えることができます。
例えば、会計ソフトの場合、パッケージ版なら10万円程度の初期費用がかかりますが、SaaS版なら月額数千円から利用可能。スタートアップや中小企業にとって、資金繰りの負担を軽減できる大きなメリットといえるでしょう。
保守・運用の手間が不要
パッケージソフトでは、アップデート作業、セキュリティ対策、サーバー管理などの保守業務が必要でした。SaaSではこれらの作業をすべてサービス提供者が行うため、利用者は本来の業務に集中できます。
IT担当者がいない中小企業や、専門知識を持つスタッフが少ない会社にとって、この手間の削減効果は絶大です。システムトラブルが発生しても、サービス提供者側で対応してもらえる安心感もあります。
どこからでもアクセス可能
SaaSはインターネット環境があれば、場所やデバイスを問わずアクセスできます。オフィス、自宅、外出先、どこからでも同じデータや機能を利用可能。リモートワークや在宅勤務が普及した現在、この柔軟性は必要不可欠な要素となっています。
営業担当者が客先で資料を確認したり、経理担当者が自宅から月次処理を行ったりと、働き方の多様化を支える重要な基盤として機能しています。
常に最新版が利用できる
パッケージソフトでは、新機能を使うために新しいバージョンを購入する必要がありました。SaaSでは、サービス提供者が自動的にアップデートを行うため、利用者は常に最新の機能やセキュリティ対策を享受できます。
法改正に対応した機能追加や、ユーザビリティの改善なども自動的に反映されるため、競合他社に後れを取ることなく最新のツールを活用できるでしょう。
複数人での同時作業ができる
従来のソフトウェアでは、一つのファイルを複数人で同時編集することは困難でした。SaaSではクラウド上でデータが管理されるため、複数のユーザーがリアルタイムで同じファイルを編集可能です。
Google ドキュメントでの共同編集や、プロジェクト管理ツールでのタスク共有など、チームワークを向上させる機能が標準装備されています。情報共有のスピードアップと、作業効率の大幅な向上が期待できます。
SaaS導入前に知っておくべき3つのデメリット

SaaSには多くのメリットがある一方で、導入前に理解しておくべきデメリットも存在します。これらを事前に把握しておくことで、導入後のトラブルを避け、適切な対策を講じることができます。
- カスタマイズの自由度が限られる
- セキュリティリスクの考慮が必要
- サービス停止時の業務影響
デメリットを正しく理解し、自社の状況と照らし合わせて検討することが、SaaS導入成功の重要なポイントです。
カスタマイズの自由度が限られる
SaaSは多くの企業で利用されることを前提として開発されているため、特定の業界や企業に特化した機能は限定的です。自社独自の業務フローに完全に合わせることは難しく、場合によってはSaaSに合わせて業務プロセスを変更する必要があります。
パッケージソフトなら自社仕様にカスタマイズできた機能も、SaaSでは標準機能の範囲内での利用となります。特殊な業務要件がある企業は、導入前に必要な機能が提供されているか十分に確認しましょう。
セキュリティリスクの考慮が必要
SaaSではデータがクラウド上に保存されるため、インターネット経由でのアクセスにはセキュリティリスクが伴います。不正アクセスやデータ漏洩の可能性をゼロにすることはできません。
多くのSaaSベンダーは高度なセキュリティ対策を実施していますが、利用者側でも適切なパスワード管理、アクセス権限の設定、定期的なセキュリティ研修などの対策が必要です。とくに機密性の高い情報を扱う企業は、慎重な検討が求められます。
サービス停止時の業務影響
SaaSはサービス提供者のサーバーに依存するため、システム障害やメンテナンス時にはサービスが利用できなくなります。インターネット回線に問題が発生した場合も同様に、業務が停止するリスクがあります。
重要な業務でSaaSを利用する場合は、サービス停止時の代替手段を用意しておくことが重要です。SLA(サービスレベル合意)で稼働率を確認し、ダウンタイムが業務に与える影響を事前に評価しておきましょう。
業界別SaaSサービス代表例15選

SaaSサービスは業務の種類や目的に応じて、様々なカテゴリーに分類されます。どのような場面でどのSaaSを活用すべきか、代表的なサービスとその特徴を理解しておくことで、自社に最適なツール選択ができます。
ここでは業務に直結する主要な5つのカテゴリーから、とくに利用者数が多く、評価の高いSaaSサービスを厳選してご紹介します。
コミュニケーション系SaaS
チーム内のコミュニケーションを円滑化し、情報共有を効率化するSaaSです。
- Slack:チーム向けメッセージングプラットフォーム
- Microsoft Teams:ビデオ会議とチャット機能を統合
- Zoom:高品質なWeb会議システム
- LINE WORKS:LINEのビジネス版
リモートワークの普及により、従来の電話やメールに代わるコミュニケーション手段として重要性が高まっています。
業務管理系SaaS
プロジェクトの進捗管理やタスク管理を行うSaaSです。
- Backlog:プロジェクト管理とバグ管理を統合
- Trello:カンバン方式のタスク管理
- Asana:チーム向けワークマネジメント
チームメンバーの作業状況を可視化し、効率的なプロジェクト運営を支援します。とくにクリエイティブ業界やIT業界での導入が進んでいます。
営業・マーケティング系SaaS
顧客管理や営業活動の効率化を支援するSaaSです。
- Salesforce:世界最大級のCRM・SFAプラットフォーム
- HubSpot:インバウンドマーケティング支援
- Kintone:業務アプリ作成プラットフォーム
営業プロセスの見える化や、顧客との関係強化に役立ちます。BtoBビジネスを展開する企業にとって欠かせないツールとなっています。
経理・人事系SaaS
経理業務や人事管理を効率化するSaaSです。
法改正への自動対応や、計算ミスの防止など、バックオフィス業務の品質向上に大きく貢献します。中小企業での導入がとくに進んでいる分野です。
- freee:クラウド会計ソフト
- マネーフォワード:経理・人事労務の統合管理
- 弥生オンライン:中小企業向け会計ソフト
- SmartHR:人事労務管理プラットフォーム
オンラインストレージ系SaaS
ファイルの保存・共有を行うSaaSです。
データのバックアップ機能も兼ね備えており、どこからでもファイルにアクセスできる利便性から、あらゆる業界で活用されています。
- Dropbox:個人・チーム向けファイル同期
- Google Drive:Googleアカウントと連携したストレージ
- Box:企業向けセキュアなファイル共有
失敗しないSaaS選定の4つのポイント

数多くのSaaSサービスが提供される中で、自社に最適なツールを選ぶことは容易ではありません。機能面だけでなく、コスト、セキュリティ、将来性など、多角的な検討が必要です。
- 自社の課題と必要な機能を明確化
- 料金体系と将来的なコストを試算
- セキュリティ対策とサポート体制
- 他システムとの連携可能性
SaaS選定で失敗しないためには、事前の準備と評価基準の明確化が重要となります。ポイントを押さえることで、導入後の満足度を高められるでしょう。
自社の課題と必要な機能を明確化
SaaS選定の第一歩は、現在の業務における課題と、解決したい問題を明確に洗い出すことです。単に「便利そうだから」という理由で導入すると、期待した効果が得られない可能性があります。
まず現状の業務フローを整理し、どの部分に無駄や非効率があるのかを特定しましょう。その上で、SaaSに求める機能の優先順位を付け、必須機能と希望機能を区別することが大切です。
料金体系と将来的なコストを試算
SaaSの料金は、ユーザー数や利用機能に応じて変動するケースがほとんどです。導入時のコストだけでなく、事業拡大に伴うユーザー数増加や、追加機能利用時のコスト増加も含めて試算しましょう。
月額料金以外にも、初期設定費用、データ移行費用、研修費用などが発生する場合があります。3年から5年程度の中長期的な運用コストを見積もり、予算と照らし合わせて検討することが重要です。
セキュリティ対策とサポート体制
企業データを扱うSaaSでは、セキュリティ対策の充実度が選定の重要な判断材料となります。データの暗号化、アクセス制御、バックアップ体制など、具体的なセキュリティ仕様を確認しましょう。
サポート体制も同様に重要な要素です。日本語でのサポート対応時間、問い合わせ方法(電話、チャット、メール)、障害時の対応スピードなどを事前に確認しておくと安心です。
他システムとの連携可能性
既存の業務システムやツールとの連携ができるかどうかは、業務効率に大きく影響します。API(システム間の連携機能)の提供状況や、よく使われるツールとの連携実績を確認しましょう。
将来的に他のSaaSツールを追加導入する可能性も考慮し、拡張性の高いサービスを選ぶことをおすすめします。データのエクスポート機能があれば、将来的な移行時にも安心です。
SaaS導入を成功させる実践的な進め方

SaaSの選定が完了しても、導入プロセスを適切に進めなければ期待した効果は得られません。とくに従業員の抵抗感や定着率の問題は、多くの企業で課題となっています。
成功事例から学ぶ実践的なアプローチで、SaaS導入を確実に成功に導きましょう。段階的な導入プロセスを踏むことで、リスクを最小限に抑えながら効果を最大化できます。
導入前の準備と体制づくり
SaaS導入を成功させるためには、事前の準備段階が最も重要です。まず、導入プロジェクトの責任者とチームメンバーを明確にし、役割分担を決めましょう。IT部門だけでなく、実際にツールを使用する現場担当者を巻き込むことが必要です。
現在の業務フローとデータの整理も欠かせません。SaaS移行時にデータクレンジング(不要データの削除・重複データの統合)を行うことで、運用開始後の効率が大幅に向上します。
トライアル期間の効果的な活用法
多くのSaaSサービスは、無料トライアル期間を提供しています。この期間を有効活用するためには、事前にテスト項目と評価基準を設定しておくことが重要です。単に機能を試すだけでなく、実際の業務データを使った検証を行いましょう。
複数のツールを比較検討する場合は、同じ条件でテストを行い、客観的な評価ができるようにします。現場担当者からのフィードバックを収集し、使いやすさや業務への適合性を多角的に評価してください。
社内浸透と運用定着のコツ
新しいツールの導入には、従業員の心理的抵抗が付きものです。導入の目的とメリットを明確に伝え、「なぜこのツールが必要なのか」を理解してもらうことから始めましょう。
段階的な導入も効果的な手法です。まずは一部の部署やプロジェクトで試験運用を行い、成功事例を作ってから全社展開します。初期の成功体験が、全社的な浸透を加速させる重要な要因となるでしょう。
SaaS事業で働く人が押さえるべき基礎知識

SaaS事業に携わる方にとって、業界全体の動向や主要企業、専門用語の理解は必須です。顧客との会話や社内のディスカッションで、これらの知識が前提として扱われることも少なくありません。
ここでは、SaaS業界で働く上で知っておくべき基礎的な業界知識をまとめました。日々の業務に活かせる実践的な情報として活用してください。
SaaS業界の市場動向と成長性
日本のSaaS市場は急速な成長を続けており、2023年時点で約1兆円規模に達しています。デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進、働き方改革、新型コロナウイルスの影響によるリモートワークの普及が主要な成長要因です。
とくに中小企業でのSaaS導入が加速しており、従来は大企業中心だった市場構造が大きく変化しています。今後も年率10-15%程度の成長が見込まれ、2030年には2兆円規模の市場になると予測されているのが現状です。
日本の代表的なSaaS企業
日本のSaaS業界をリードする企業として、まず挙げられるのがSalesforceです。グローバル最大手のCRM・SFAプラットフォームを展開し、多くの日本企業で導入されています。
国内発のSaaS企業では、freee(会計ソフト)、サイボウズ(グループウェア)、マネーフォワード(バックオフィス業務支援)、SmartHR(人事労務管理)などが代表的。これらの企業は各分野でのシェアトップクラスを誇り、日本のSaaS業界の成長を牽引しています。
SaaS営業で使われる専門用語
SaaS業界には、独特の専門用語が数多く存在します。「MRR(Monthly Recurring Revenue:月次継続売上)」「ARR(Annual Recurring Revenue:年次継続売上)」は、SaaS事業の収益性を測る重要な指標です。
「チャーンレート(解約率)」「LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)」「CAC(Customer Acquisition Cost:顧客獲得コスト)」なども頻繁に使われる用語。これらの指標を理解することで、SaaS事業の健全性や成長性を適切に評価できるようになります。
まとめ:SaaSを理解して業務効率化を実現しよう

SaaSは現代のビジネスにおいて欠かせないサービス形態となっており、適切に活用することで大幅な業務効率化とコスト削減を実現できます。初期費用の削減、保守管理の不要、どこからでもアクセス可能といったメリットは、とくに中小企業やスタートアップにとって大きな魅力でしょう。
一方で、カスタマイズの制約やセキュリティリスクなどのデメリットも存在するため、自社の状況と照らし合わせた慎重な検討が必要です。適切な選定プロセスと段階的な導入アプローチを取ることで、これらのリスクを最小限に抑えながら、SaaSの恩恵を最大限に享受できるはずです。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
-
ARTICLE
2026/01/26( 更新)
Googleビジネスプロフィールのビジネス名とは?正しい決め方とNG例を解説
MEO
- Googleビジネスプロフィール
-
ARTICLE
2025/10/29( 更新)
葬儀社の広告はどの媒体がおすすめ?種類別の特徴と成功のポイントを解説
企業経営業種別
- 集客
- 葬儀社
-
ARTICLE
2024/05/10( 更新)
MEO対策とは?集客効果や意味・メリットまで基本を完全網羅!
MEO
-
ARTICLE
2025/06/23( 更新)
Googleビジネスプロフィール管理画面を徹底解説!変更点・機能・よくある疑問まで
MEO
- Googleビジネスプロフィール
