
PREP法とは?文章がわかりやすく伝わる書き方、テンプレート、シーン別例文を紹介
「せっかく文章を書いても、うまく伝わらず成果につながらない…」そんな悩みを抱える方は少なくありません。
そこで役立つのが、結論から伝える「PREP法」です。
シンプルなのに説得力があり、プレゼン・レポート・就活の自己PRまで幅広く活用できます。
本記事では、PREP法の基本構造から具体的なテンプレート、実際の例文、メリット・デメリットまで徹底解説します。
ぜひ参考にしてください。
目次
PREP法とは?

PREP法(読み方:プレップ法)とは、結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→再び結論(Point)の順で文章を構成する手法です。
冒頭で結論を提示するため、読み手は内容の方向性をすぐに把握できます。その後、理由や背景を補足し、具体的な事例で理解と納得を深め、最後に再び結論を示すことで印象を強める構成になっています。
構造がシンプルで覚えやすく、レポート、パワーポイントを使ったプレゼンテーション、就活の面接での自己PRや志望動機まで幅広く活用できます。
とくに限られた時間で説得力を求められる場面では、迷わず文章を組み立てられる点がPREP法の大きな強みといえるでしょう。
PREP法に慣れると、短時間でも質の高い文章を自然に組み立てられるようになり、業務効率の向上にもつながります。
PREP法を使った書き方・テンプレート

PREP法は次の4ステップで文章を組み立てます。
- 結論(Point)
- 理由(Reason)
- 具体例(Example)
- 結論Point
それぞれの役割を理解して適切な文章を作成できれば、読み手が話の全体像を素早くつかめます。各ステップについて、それぞれくわしく解説します。
結論(Point)
PREP法で最初に提供する結論では、文章全体のゴールを明確にします。特に、インターネットが発達して情報が溢れている現代では、「ここには自分が求めている情報はない」と判断されるとすぐに離脱されてしまいます。
だからこそ、冒頭で短く簡潔に結論を伝えるPREP法が大きな効果を発揮します。あれもこれもと盛り込みすぎず、まずはシンプルにまとめると、説得力のある文章を組み立てられるでしょう。
理由(Reason)
理由を述べる段階では、結論を裏づける根拠をはっきり伝えます。特に、実績やデータ、専門的な知見など、客観性のある情報を示せば、読み手は納得しやすくなります。
また、読み手が「本当にそうだろうか」と感じそうなポイントを想像し、その疑問に先回りして応えるのも効果的でしょう。あらかじめ不安や反論に触れておくことで、文章全体の信頼度も高まります。
しかし、伝えたいメッセージを詰め込みすぎると焦点がぼやけてしまうので、結論を強調するために本当に必要な情報に絞って伝える工夫が大切です。
具体例(Example)
理由のパートで解説した内容をよりイメージしやすくするためには、実際の事例やエピソードの紹介が有効です。
ビジネス向けであれば成功事例、個人向けであれば経験談などを紹介すると、読み手は内容を自分自身の状況として捉えやすくなります。
もちろん、事実に基づかない脚色は信頼を失う原因になるため、避けなければなりません。主張の根拠となる理由を、具体例で裏付けると、文章全体の説得力が高まるでしょう。
結論(Point)
最後の結論では、最初の結論で提示した主張をより強調するとともに、クロージングとして機能します。論理と事例で丁寧に説明されても、読み手の中には自分にも当てはまるだろうかという懸念が残る場合があります。
だからこそ、その迷いを断ち切るように次にとるべき行動をはっきりと伝え、実際のアクションへと促すのです。
また、提案よりも力強いメッセージを使う方が効果的です。理由と具体例という客観的な裏付けがあるからこそ、一貫した言葉が強い説得力をともなって読み手の心に響くのです。
PREP法の基本テンプレート
結論(Point): 伝えたい主張を、明確かつ簡潔に述べます。
例:「私は〜と提案します。」「〜が重要です。」
理由(Reason): なぜそう言えるのか、説得力のある根拠を提示します。
例:「なぜなら、〜だからです。」「その理由は、〜にあります。」
具体例(Example):理由を裏付けるための具体的な事例やデータを挙げます。
例:「例えば、〜」「〇〇というデータがあります。」
結論(Point): 再度結論を述べ、聞き手や読み手にとってのメリットを再確認させます。
例:「したがって、〜をすることで、〜が実現できます。」「このことから、〜をすることが必要です。」
このテンプレートを活用することで、どのような場面でも論理的で説得力のある文章や話が組み立てられます。
PREP法を活用した例文(シーン別)

ここでは、PREP法を活用した例文をシーン別にご紹介します。実際にPREP法を使う際の参考にしてみてください。
プレゼンテーション
| 結論 (Point) | 弊社が提供する新サービスは、顧客の業務効率を30%向上させます。 |
|---|---|
| 理由 (Reason) | サービスのA機能がルーティンワークを自動化し、B機能が部門間の情報共有をスムーズにするからです。 |
| 具体例 (Example) | 実際に試験導入いただいたC社様では、これまで手作業で行っていたデータ入力が自動化され、担当者の作業時間が週に10時間削減されました。 |
| 結論 (Point) | このサービスを導入することで、生産性向上とコスト削減を同時に実現できます。ぜひ、ご検討ください。 |
就職活動(自己PR)
| 結論 (Point) | 私の強みは、課題解決に向けて粘り強く行動し、成果を出すことです。 |
|---|---|
| 理由 (Reason) | 大学のサークル活動では、イベントの集客率を大きく改善した経験があります。 |
| 具体例 (Example) | 所属していた〇〇サークルでは、イベントの集客率が伸び悩んでいました。過去の参加者アンケートを分析し、SNSでの情報発信を強化した結果、集客率を前年比150%に改善することができました。 |
| 結論 (Point) | この経験で培った課題解決能力と実行力は、貴社が求める営業職で必ず活かせると確信しています。 |
就職活動(志望動機)
| 結論 (Point) | 貴社の「〇〇を通じて人々の生活を豊かにする」という企業理念に深く共感し、志望いたしました。 |
|---|---|
| 理由 (Reason) | 私は以前から、〇〇に興味があり、その分野で人々の役に立ちたいと考えているからです。 |
| 具体例 (Example) | 学生時代、貴社が開発した〇〇(製品名)を利用し、その便利さとクオリティの高さに感銘を受けました。将来、私も貴社の一員として、社会に貢献できるような製品づくりに携わりたいと強く思うようになりました。 |
| 結論 (Point) | 貴社でなら、自分のスキルと情熱を最大限に活かし、社会に貢献できると確信しています。 |
レポートや論文
| 結論 (Point) | 本研究では、地球温暖化が〇〇に与える影響について、新たな知見を提示します。 |
|---|---|
| 理由 (Reason) | 従来の先行研究では見落とされていた、〇〇という要因に焦点を当てて分析したからです。 |
| 具体例 (Example) | 〇〇年に実施したフィールドワークでは、〇〇が〇〇に影響を与えていることを示すデータが複数確認されました。これは従来の説を覆すものです。 |
| 結論 (Point) | 以上のことから、地球温暖化対策には、〇〇という視点を取り入れることが不可欠であると結論付けられます。 |
会議や商談での提案
| 結論 (Point) | 新しい業務管理ツールを導入すべきです。 |
|---|---|
| 理由 (Reason) | 現在のタスク管理が属人化しており、進捗の把握に時間がかかっているためです。 |
| 具体例 (Example) | 先月のプロジェクトでは、タスクの重複が原因で納期が遅れそうになりました。このツールを導入すれば、リアルタイムで進捗を共有でき、コストを削減できます。 |
| 結論 (Point) | 業務効率と生産性を向上させるために、ツールの導入を希望します。 |
日常のビジネスメール
| 結論 (Point) | 添付資料をご確認いただき、明日までにご意見をいただけますでしょうか。 |
|---|---|
| 理由 (Reason) | 月曜日の企画会議で最終案を提出するため、スケジュールの都合上、週末に修正作業を行う必要があるためです。 |
| 具体例 (Example) | 過去にも同様の資料でフィードバックが遅れ、修正が間に合わないことがありました。今回は事前に共有することで、スムーズに会議に臨めると考えております。 |
| 結論 (Point) | お忙しいところ恐縮ですが、円滑な進行のため、明日中のご返信をお願いいたします。 |
チームへの報告・共有
| 結論 (Point) | 来週のA社との定例会議は、オンライン形式に変更します。 |
|---|---|
| 理由 (Reason) | A社の担当者の方が急な出張になったためです。 |
| 具体例 (Example) | 今朝、先方のご担当者から直接連絡があり、Web会議システムでの実施を提案されました。すでにURLは共有済みです。 |
| 結論 (Point) | 皆さんにはご迷惑をおかけしますが、当日は各自オンラインで参加をお願いいたします。 |
PREP法はマーケティングにも活用できる?

PREP法は、説得力のある文章を効率的に組み立てられる型として、マーケティング分野でも幅広く活用されています。
活用シーンを具体的に見ていきましょう。
セールスレターで活かせるPREP法
セールスレターは、できるだけシンプルな構成で読み手に商品やサービスの魅力を伝え、最終的に購入や申込みへと導く必要があります。そのため、最初に結論から入るPREP法を活用すると、訴求力が明確で読み手の行動を促しやすい文章となります。
英会話教材のセールスレターを例にしてPREP法を活用してみると、次のようになります。
| 結論(Point) | この英会話教材を使えば、わずか1か月で実践的な英会話力を身につけられます。 |
|---|---|
| 理由(Reason) | 1日15分の学習で、ネイティブの発音や会話パターンを繰り返し身につけるカリキュラムが組まれているからです。 |
| 具体例(Example) | 実際に、英語が苦手だった営業職のAさんは、毎日出勤前に15分学習を続けた結果、海外の取引先とのやりとりを一人でこなせるようになりました。 |
| 結論(Point) | 短期間で成果を実感できる英会話教材として、忙しいビジネスパーソンにも最適です。 |
このようにPREP法を用いることで主張と根拠が明確になり、読み手は安心して購入や申込みといった次の行動へ進むことができるのです。
ランディングページ(LP)で活かせるPREP法
ランディングページやブログ、SEO記事といったコンテンツにおいても、PREP法は非常に有効です。ユーザーは限られた時間で情報を取捨選択しており、必要性を感じなければすぐにページを離れてしまいます。
だからこそ、最初に結論を示し、読むべき理由と納得感を短時間で伝える構成が求められます。
たとえば、業務効率化ツールを紹介するランディングページなら、PREP法で次のように展開できます。
| 結論 (Point) | この業務管理ツールを導入すれば、日々の作業時間を大幅に短縮できます。 |
|---|---|
| 理由 (Reason) | ツールには業務の進行状況を一括で可視化できる機能があり、各メンバーの進捗確認やタスクの重複チェックにかかる時間を削減できます。 |
| 具体例 (Example) | 実際に導入した企業では、週単位で10時間以上の業務時間を削減できたという報告もあり、社員の満足度や集中度も向上しています。 |
| 結論 (Point) | 時間と労力をムダにしない働き方を実現するためにも、今すぐこのツールを取り入れるべきです。 |
ランディングページでも、PREP法を活用すれば訪問直後にメインテーマを伝えられるため、離脱を防ぎながら行動を促す構成に仕上げられます。
とくに、論理的で整理された分かりやすい構成であれば読者の記憶に残りやすく、コンバージョンの向上にもつながります。
PREP法のメリット・デメリットまとめ

ここでは、PREP法のメリットとデメリットをまとめて紹介します。PREP法は文章構成の型として多くの場面で役立ちますが、万能ではありません。
状況や目的に合わせて使い分けるためにも、メリット、デメリット両面を理解しておくことが大切です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 要点が伝わりやすい | 共感や熱意を重視した内容には適さない |
| 伝えたい内容が記憶に残りやすい | 交渉やブレインストーミングには適さない |
| 自身の思考を整理できる | 使いすぎると単調で型通りすぎる印象を与える |
PREP法を活用するメリット

PREP法を活用するメリットについて、それぞれくわしく解説します。
メリット①:要点が伝わりやすい
PREP法の活用する大きなメリットは、ユーザーに要点が伝わりやすい点にあります。
伝えたい内容を最初に発信するため、読み手は「この話は何についてのものか」をすぐに理解でき、内容について誤解したり混乱したりする可能性が少なくなります。
さらに、「結論→理由→具体例→再び結論」という構成は、自然と論理の筋道が整いやすく、読みやすさにもつながるため、途中で話がぶれることが減り、全体のまとまりもよくなるでしょう。
結論を先に伝えると読み手が早い段階で判断を下しやすくなり、結果として時間の効率化にも繋がります。
メリット②:伝えたいことが記憶に残りやすい
PREP法は、文章の冒頭と締めくくりで結論を繰り返す構成となっているため、読み手の記憶に内容が残りやすいというメリットもあります。
最初に提示する結論により、読み手は常に結論を念頭においたまま内容を読み進められます。そして、理由や具体例のフェーズでも結論が補完され、最後に再び提供される結論により、印象がより強く残るのです。
特にPREP法の構成は、プレゼンテーションや営業トークなど短い時間でメッセージを届けたい場面で効果的と言えるでしょう。
メリット③:自身の思考を整理できる
PREP法は文章の構成が明確に決まっているため、書き手にとっても思考の整理がしやすくなるというメリットがあります。
情報をPREP法の流れに沿って並べていくと、伝えたい内容の中から何を残し、何を削るべきかを判断しやすくなります。
論理的な流れを構成する過程で、「この理由は弱いかもしれない」「例が足りない」といった論理の穴にも気づきやすく、文章を書きながら自然と精度を高められます。
また、PREP法を意識した制作自体が、考えを整理するトレーニングにもなります。思いついた順に書き並べるのではなく、伝える順序を意識して書くため、発信する力そのものが強化されていくのです。
PREP法を活用する際のデメリット・注意点
PREP法は説得力や構成の分かりやすさに優れた文章術ですが、次のようなデメリットや注意点には気をつける必要があります。
デメリットや注意点を理解しておけば、PREP法の効果を保ちながらより柔軟で伝わる文章づくりができます。
デメリット①:共感や熱意を重視した内容には適さない
PREP法は論理的な説明に適していますが、共感や感情の動きを重視する文章でPREP法を使用すると、読み手に硬さを感じさせてしまう可能性があります。
感動的な体験やストーリーを描く場合には、背景や感情を丁寧に伝えながら徐々にクライマックスへと向かう構成が理想的です。そのため、冒頭で結論を述べるPREP法では読者が感情移入しにくくなるおそれがあるのです。
感情を優先する文章と、論理を重視する構成とでは、表現に向き不向きがあります。場面や目的に応じて柔軟に使い分けるようにしましょう。
デメリット②:交渉やブレインストーミングには適さない
交渉やブレインストーミングのように、相手の反応やアイデアを活かしながら話を進めていくような場面では、PREP法は活用しにくいといえるでしょう。
交渉では、相手の立場や価値観に応じて柔軟に論点を調整する必要がありますが、PREP法は進行の構造がある程度固定されているため、自由なやり取りには向きづらいのです。
また、ブレインストーミングでは、自由な発想のやり取りが重要になります。最初から結論に縛られると、参加者のアイデアが広がらず、創造的な空気も生まれにくくなってしまいます。
デメリット③:使い方によっては単調で型通りすぎる印象を与える
PREP法は論理的でわかりやすい構造ですが、同じ型を繰り返し使うと文章が単調になりやすいという欠点があります。とくにブログやニュースレターのように、定期的に発信を続ける媒体では、毎回似たような展開に読者が飽きてしまうおそれもあります。
構成のパターンが読まれるたびに予測できてしまうと、内容そのものに関心があっても、途中で離脱されやすくなるかもしれません。
文章全体のトーンやリズムに変化を持たせたり、章ごとに視点や語り口を少し変えるといった工夫が、読者の集中力を保つうえで効果的です。
PREP法に似た手法と使い分け方

文章構成法には、SDS法やDESC法のように、PREP法と似た流れをもつ手法があります。それぞれに特徴や活用しやすいシーンがあり、目的や伝えたい内容に合わせて使い分けが大切です。
ここでは、PREP法とSDS法、PREP法とDESC法の違いと使い分け方について紹介します。
構造の違いや活用しやすい場面を理解しておけば、自分の目的に合った文章が組み立てやすくなります。ぜひ情報の発信や資料づくりに役立ててみてください。
PREP法とSDS法との使い分け方

SDS法は以下の順で構成される文章手法です。
| 概要(Summary) | 最初に結論や要点を簡潔に伝える |
|---|---|
| 詳細(Details) | 結論の根拠や補足情報を簡潔に説明する |
| まとめ(Summary) | 内容を再確認し、主張を印象づけて締めくくる |
SDS法の構成に沿って文章を作ると次のようになります。
| Summary(概要) | テレワークの導入をおすすめします。 |
|---|---|
| Details(詳細) | 出社にかかる移動時間や交通費を削減でき、生産性も向上する傾向があります。また、社員のワークライフバランスにも好影響が見込まれます。 |
| Summary(まとめ) | 業務効率と働きやすさの両面から、テレワークの導入は効果的です。 |
PREP法と同じく結論から始めて最後にまとめる点は共通していますが、PREP法が「理由」と「具体例」を明確に分けて展開するのに対し、SDS法では詳細部分にそれらを含めて簡潔に伝えるのが特徴です。
短時間で要点を伝えたい場面では、PREP法よりもSDS法のほうが適しています。
PREP法とSDS法は次のように使い分けるとよいでしょう。
| PREP法 | 相手に納得してもらいたいときや、しっかり説明したいとき |
|---|---|
| SDS法 | 短く伝えたいときや、情報の要点だけをサクッとまとめたいとき |
似た構造を持つ両者ですが、それぞれの特性を踏まえて、場面に応じて使い分けてみてください。
PREP法とDESC法の違いと使い分け方

DESC法は次の構成で展開します。
| 事実の描写(Describe) | 状況や出来事を客観的に伝える |
|---|---|
| 感情の表現(Express) | その状況に対する自分の感情 |
| 望む行動の明示(Specify) | 相手にしてほしい具体的な行動 |
| 行動の結果(Consequences) | その行動がもたらす結果 |
このDESC法の構成に沿って「資料作成に関する連携改善」を伝える例文を紹介します。
| 事実の描写(Describe) | 今回のクライアント向け資料について、要望の変更点が事前に共有されていなかったようです。 |
|---|---|
| 感情の表現(Express) | 結果的に求められていた内容とズレた資料を作ってしまい、申し訳なく感じましたし、少し戸惑いました。 |
| 望む行動の明示(Specify) | 次回からは、内容に変更や追加があった場合は、簡単でもよいので一報をもらえると助かります。 |
| 行動の結果(Consequences) | そうすれば、こちらでも正確な資料を準備しやすくなり、全体の進行もスムーズになると思います。 |
PREP法は「結論→理由→具体例→結論」で構成され、論理的な順序で提案や主張の説得力を高める手法です。一方のDESC法は、自分の感情を交えながら相手に配慮した伝え方ができるため、関係を損なわずに改善を求めたい場面に向いています。
同じテーマや要望でも、PREP法なら改善の必要性を根拠づけて提案し、DESC法なら感情と要望を丁寧に伝えることで、相手の受け止め方が変わります。
PREP法とDESC法は次のような使い分け方をするとよいでしょう。
| PREP法 |
|
|---|---|
| DESC法 |
|
PREP法に関するよくある質問

PREP法を学んで実践しようとすると、使い方や構成に関して疑問が浮かぶ方もいるかもしれません。とくに使いはじめのうちは、どのように型を使い分けるべきか、型をどう応用すればよいのか迷いやすいものです。
ここでは、PREP法について寄せられることが多い質問に回答します。
質問①:PREP法の読み方は?
PREP法の読み方は「プレップ法」です。
質問②:PREP法を使っても伝わらないのはなぜですか?
PREP法を使ってもうまく伝わらないと感じるときは、内容や言葉の選び方に原因があることが多いです。たとえば、最初の結論がぼんやりしていたり、具体性に欠けていたりすると、いくら順序立てて書いても、読み手にはうまく伝わりません。
また、理由の部分が抽象的すぎると、「それって本当にそうなの?」と納得してもらいにくくなります。さらに、具体例が相手の立場とかけ離れていると、「自分には関係なさそうだな」と思われてしまうかもしれません。
PREP法はあくまでも構成の型であり、大事なのは中身です。伝えたい相手の状況や興味を意識しながら、わかりやすく、身近に感じられる言葉で表現すれば、内容もしっかり届きやすくなります。
質問③:最初と最後のPはどう書き分けるべきですか?
PREP法の最初と最後にくるP(結論)の部分は、同じ言葉を使っていますが、それぞれの役割は少し違います。
冒頭の結論は、これから伝えたい内容に向かって進むための指針です。読み手が「どんな話なのか」を最初に把握できるような、シンプルで明確な表現が重要です。
一方で、最後に書く結論はそれまでに示した理由や具体例をもとに、内容の納得感を深めてクロージングに繋げるパートです。視点や言葉の選び方を少し変え、行動を促すようなメッセージになります。
それぞれの書き分けを意識してみると、結論が単なるくり返しで終わらず、読み手の心に残る伝え方へと変わっていくでしょう。
質問④:理由(Reason)が複数ある場合は全て紹介すべきですか?
理由が複数ある場合、すべてを理由(Reason)に詰め込もうとする必要はありません。情報量が増えすぎて、伝えたいポイントがぼやけてしまう可能性があるためです。
大切なのは、相手の関心が高いものや伝えたいテーマと深く関わるものを優先して取り上げることです。内容に優先順位をつけて、整理したうえで伝えることがポイントです。
本文では主要な理由に絞り、補足的な情報は別の段落やコラム、あるいは付録の資料として紹介する形でも十分伝わります。
PREP法の良さは、簡潔で筋の通った構成にあります。その特性を活かすためにも、情報の取捨選択を意識してみましょう。
PREP法で説得力ある文章を作ってみましょう!
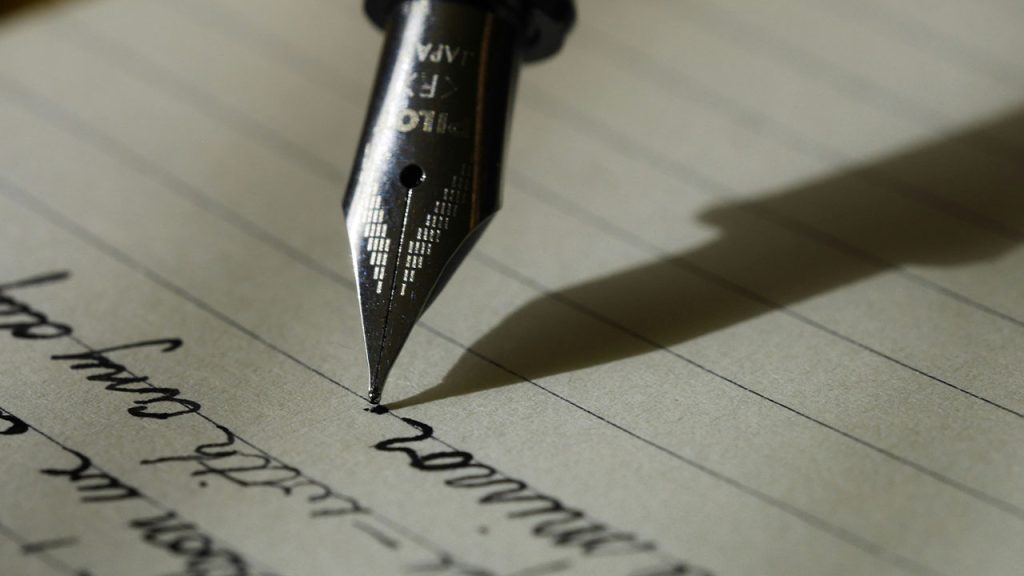
PREP法は、結論を先に提示し、その理由と具体例で裏付け、最後に再び結論で締めることで、明確かつ説得力のある文章を作る手法です。
PREP法を活用すると、情報を効率的に届けられるだけでなく、読み手の理解を助けて記憶にも深く残せます。ただし、場面によっては型の硬さがデメリットになるため、適切な使い分けが重要です。
本記事で解説した内容を元に、まずはPREP法を使った文章を作成してみましょう。日常の報告やプレゼン資料など、さまざまな場面でその効果を実感できるはずです。
PREP法を味方につけて、伝わる文章のクオリティを高めていきましょう。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
