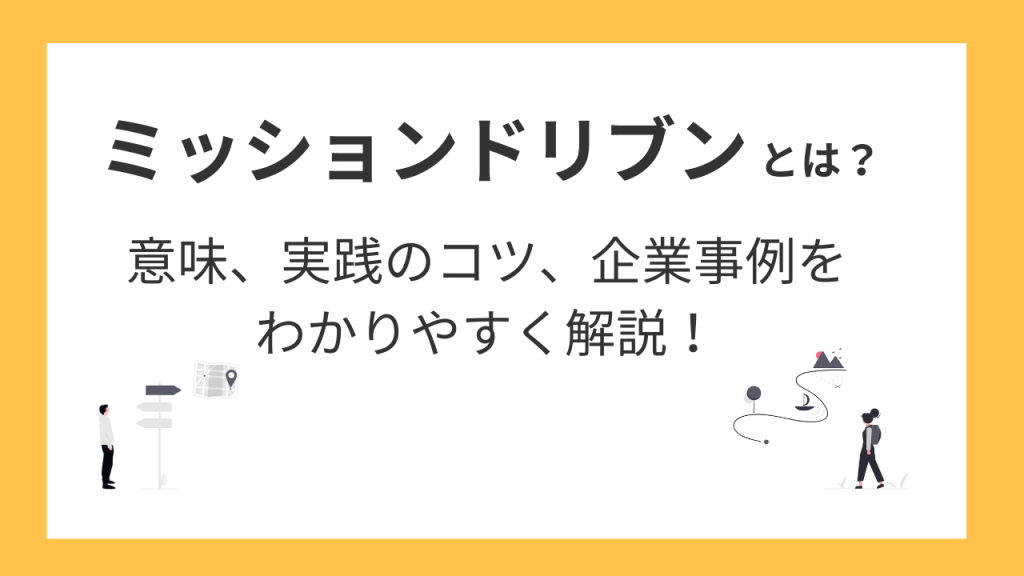
ミッションドリブンとは?意味、実践のコツ、企業事例、導入による組織の変化まで徹底解説
ミッションドリブンとは、企業や個人が掲げる使命(ミッション)を軸に、意思決定や行動を進める経営手法です。
この手法を取り入れることで、社員の行動指針が明確になり、組織全体の一体感や文化形成につながります。
この記事では、ミッションドリブンの意味、取り入れることで組織に起こる変化、実践のコツ、企業事例まで解説します。
「ミッションドリブン」の考え方を理解したい方、理念を行動に変える方法を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
ミッションドリブンとは?
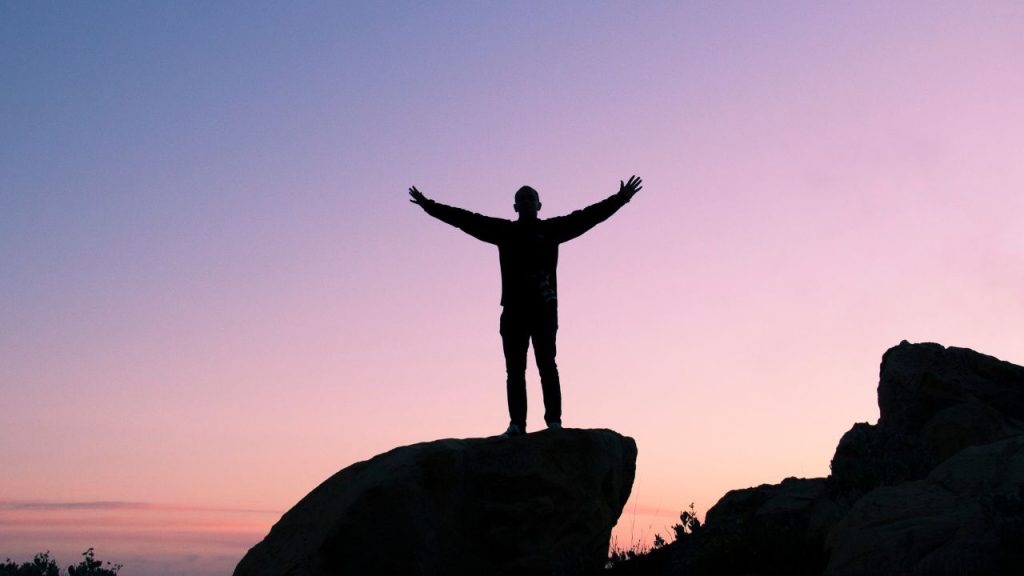
「ミッションドリブン」とは、企業や組織が 「なぜ存在するのか」という根本的な問いに基づいて策定した ミッション(使命) を原動力に、経営や日々の行動を進めていく考え方です。
理念や使命を起点に意思決定を行うことで、社員の行動指針が明確になり、組織全体の一体感や文化の形成にもつながります。
「ミッション」と「ドリブン」の意味
ミッション(mission)には「使命・存在意義」、ドリブン(driven)には「〜によって突き動かされる」「原動力となる」という意味があります。
英語表記のmission drivenという言葉は「強い使命に突き動かされて行動する」という力強いニュアンスを持ちます。
ミッションドリブン・バリュードリブン・ビジョンドリブンの違い
「ミッションドリブン」と混同されがちな表現として「バリュードリブン」「ビジョンドリブン」がありますが、これらの意味合いは異なります。
主な違いは以下の通りです。
| ドリブンの種類 | 軸になるもの | 問い | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ミッションドリブン | 存在意義 | 「私たちは何のために存在しているのか?」 | 長期的に変わりにくい“核”である理念や使命を起点に行動 |
| ビジョンドリブン | 未来像 | 「私たちはどんな未来をつくりたいか?」 | 将来像やゴールを描き、そこから逆算して行動 |
| バリュードリブン | 価値観 | 「どんな価値観で意思決定するか?」 | 日常的な判断基準や文化の形成 |
イシュードリブンとの違い
「なぜやるのか?」という目的から始まるミッションドリブンに対して、「何を解決するのか?」という課題から始まるのがイシュードリブンです。
主な違いは以下の通りです。
| 項目 | ミッションドリブン (Mission Driven) |
イシュードリブン (Issue Driven) |
|---|---|---|
| 出発点 | 理想、ビジョン、成し遂げたい夢 | 現状の課題、問題 |
| 問い | 「何のためにこれをやるのか?」「どんな世界をつくりたいのか?」 | 「何が問題なのか?」「どうすれば課題を解決できるか?」 |
| 時間軸 | 長期的、中長期的な視点 | 短期的、目の前の課題解決に焦点を当てる |
| 原動力 | 内発的動機(理想への共感、目的意識) | 外的要因(問題への不満、緊急性) |
| 主な役割 | 全体の方向性を決定し、活動に意味を与える | 具体的な行動やタスクを生み出し、効率を上げる |
| 向いている場面 | 事業の立ち上げ、新規プロジェクトの開始、チームの方向性共有 | 既存サービスの改善、日々の業務効率化、トラブルシューティング |
この2つは組み合わせることで、大きな効果を発揮します。
たとえば、「地球環境に優しい持続可能な社会を創る」というミッションを持つ企業があるとします。ミッションドリブンなアプローチでは、「地球環境を守る」という大きな理想から逆算し、どのような事業をすべきか考えます。
その過程で、「プラスチックごみが増えている」という社会的な課題(イシュー)に気づきます。
次にイシュードリブンなアプローチで、「ブラスチックごみの増加」という課題を深掘りします。
このように、ミッションが示す「理想」とイシューが示す「現実の課題」を組み合わせることで、具体的な行動につながります。
ミッションドリブン経営が価値を持つようになった背景

近年、経営や組織づくりの現場で「ミッションドリブン」という考え方が急速に広がっています。
この章では、ミッションドリブンという経営手法が価値を持つようになった背景について解説します。
背景①:消費者が「共感」で商品を選ぶようになった
気候変動、少子高齢化、格差拡大など、社会課題が複雑化する中で、価格や品質だけでなく「この会社の理念に共感できるか」が、購買の動機として、重視されつつあるといわれています。
たとえば、環境配慮や地域貢献をミッションに掲げる企業は、その姿勢に共感した顧客から強く支持されることもあるのです。
消費者も「この会社の製品を買うことで社会に貢献できるか」という視点を重視する傾向が強まっており、明確なミッションを持つ企業の価値が高まっています。
背景②:働く人の価値観が変わってきた
ミレニアル世代やZ世代の若手人材を中心に、「どんな会社で働くか」よりも「なぜこの仕事をするのか」を重視する傾向が強まっています。
「給料がいいから」「有名だから」という理由だけでは人材が集まりにくくなっているのです。
採用の現場でも「ミッションに共感したから応募した」という人は増えており、ミッションは人材獲得・定着の鍵となっています。
ミッションドリブン経営の実践で組織に起こる変化

企業がミッションドリブン経営を実践すると、組織や社員の行動にさまざまな変化が現れます。この章では、主な4つの変化を解説します。
変化①:指示待ちから、自律的に動くチームへ
会社のミッションを羅針盤として、社員一人ひとりが自分の頭で考え、判断して行動できる組織に変わります。
「この行動は会社のミッションに貢献しているか?」という問いが意思決定の基準となるため、上司の指示を待つことなく、自ら最適な行動を選べるようになります。
その結果、社員の主体性が自然に育まれ、個人も組織も成長する好循環が生まれます。
変化②:結束力が高まり、組織全体のパフォーマンスが最大化される
ミッションを共有することで、社員全員が目指すゴールを明確に理解し、価値観を共有して行動する組織に近づきます。
「何のために働き、どのような成果が求められるのか」の共通認識が生まれるため、部署や職種の壁を越えた円滑なコミュニケーションや協業が可能になります。
全員が同じ方向を向くことでチームの結束力が高まり、組織全体のパフォーマンスが最大化されます。
変化③:顧客や社会から、信頼される存在に
ミッションが社会貢献や顧客価値に直結している場合、日々のビジネス活動そのものが顧客や社会からの信頼につながります。
一貫性のある行動は企業のブランド力を高め、競合他社との差別化にも寄与します。その結果、顧客との長期的な関係性を築き、持続的な成長を実現する組織へと進化します。
変化④:変化に強くしなやかな組織になる
市場や技術が絶えず変化する現代において、ミッションは組織の根幹を支える揺るぎない軸となります。
具体的な戦略や施策が変わっても、ミッションという大方針がぶれることはありません。
これにより、外部環境の激しい変化にも柔軟に対応しながら、組織としてのアイデンティティを保つ、強靭でしなやかな組織が築かれます。
強い組織をつくるためのミッションドリブン実践のコツ

この章では、ミッションドリブンを実践するための具体的なコツを解説します。
経営・採用・評価・日常業務・社内外コミュニケーションのすべてに組み込むことで、組織全体がミッションに基づいて動けるようになります。
コツ①:現場の声も取り入れ、わかりやすいミッションを定める
ミッションを定める段階では、「私たちの会社はなぜ存在しているのか?」を経営者や幹部だけでなく現場の社員も交えて議論することが大切です。
抽象的な言葉ではなく、「誰のために」「どのような価値を提供するのか」を明確にしましょう。
以下のポイントを押さえてミッションを策定を行うのがおすすめです。
- 難しい表現は避け、社員や顧客が直感的に理解できる言葉を使う
- 社員が日常業務の中で使えるような言葉に落とし込む
- 社員インタビューやワークショップを通じて、リアルな体験や価値観を反映する
また、耳障りの良いキャッチフレーズではなく、社員が「これは自分たちのことだ」と感じられる表現にすることが重要です。リアルな言葉こそが、日々の行動につながる原動力になります。
コツ②:日々の業務にミッションを組み込む
ミッションは「作って終わり」にしないことも重要です。日々の業務に理念を根付かせることが、成功の秘訣となります。
以下のポイントを意識して、日常業務に取り入れてみましょう。
実践する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
- ミッションを「朝礼」「営業資料」「顧客対応のチェックリスト」に組み込む
- 定例会やプロジェクトの振り返りの場で「この活動がミッションにどうつながったか」「誰の課題を解決し、社会に貢献するのか」を明確にする
コツ③:採用・評価・開発指針にミッションを反映させる
ミッションを人事評価や採用基準に反映させることで、組織全体が一体感を持ちやすくなります。
実践する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 採用面接では「自社のミッションに共感している人材か」を重視する
- 人事評価は数値だけでなく「ミッションに沿った行動・成果」を基準にする
- 新しいサービス開発の際も「ミッションに合致しているか?」を指針とする
こうした仕組みがあると、ミッションが日々の意思決定を支える基盤になります。
コツ④:顧客や社会にミッションを発信する
社内にとどまらず、顧客やパートナーにもミッションを発信することで、共感が広がります。実践する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
- ホームページ・SNS・会社案内などでミッションを明示する
- 顧客体験にミッションを落とし込み、「この会社らしい」と感じてもらえる瞬間を設計する
コツ⑤:ミッションを定期的にアップデートする
社会や市場の変化に合わせて、ミッションは柔軟に見直していく必要があります。
その際に意識しておきたいのが、以下のようなポイントです。
- 半年〜1年に一度「ミッションと事業の方向性がズレていないか」を確認する
- 小さな改善を継続的にしていくことで、鮮度を保つ
- 不変の「核」と、時代に合わせる「柔軟性」をバランスよく持つ
コツ⑥:ミッションを浸透させるための取り組みを行う
せっかく定めたミッションも、「掲げているだけ」では浸透しません。社員一人ひとりが自分ごととして捉え、行動につなげる仕掛けをつくることが大切です。
ミッションを広げていくには、以下のような取り組みが有効となります。
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| 社内イベントやワークショップを実施する | ミッションをテーマにしたワークショップや社員発表の場を設けると、社員が自分の言葉で語れるようになります。 |
| 社内報や朝会など、社内コミュニケーションで事例をシェアする | 社内報や朝会、Slackなどのコミュニケーションツールに「ミッションに沿った行動事例」を紹介する仕組みを取り入れる。 |
| リーダーが率先して発信する | マネジメント層が日々の意思決定や発言でミッションを繰り返し示すことで、社員にとっての「行動モデル」になります。 |
このように、ミッションを“語り・共有し・称賛する”文化をつくることで、社員の行動指針として、ミッションが機能するようになります。
ミッションドリブン企業の取り組み事例
ミッションは単なるスローガンではなく、企業が行う活動を方向づける重要な道しるべです。
この章では、有名企業の事例を上げ、どのようなミッションをどのような取り組みで体現していたのかを、解説します。
ファーストリテイリング
安価で機能性の高いファッションアイテムを提供し続けるアパレルブランド「UNIQLO(ユニクロ)」を展開するファーストリテイリング。
ファーストリテイリングのミッションは、以下のとおりです。
ファーストリテイリンググループは─
本当に良い服、今までにない新しい価値を持つ服を創造し、世界中のあらゆる人々に、良い服を着る喜び、幸せ、満足を提供します
独自の企業活動を通じて人々の暮らしの充実に貢献し、社会との調和ある発展を目指します
(出典:ファーストリテイリング公式サイト)
さらにこの文に続けて、「本当に良い服」「今までにない新しい価値を持つ服」「世界中のあらゆる人々に、良い服を着る喜び、幸せ、満足を提供」「独自の企業活動を通じて人々の暮らしの充実に貢献」「社会との調和ある発展を目指す」という各要素について、意味・意義を細かく定義しています。
本文だけでは人によって解釈が分かれてしまいそうな表現に具体的な注釈を入れることで、意識の統一を図っているようです。
実際の取り組み
ファーストリテイリングは自社のミッションを、商品開発や店舗運営、社会貢献活動を通じて、具体的に体現しています。
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| ミッションに沿った商品開発 | ユニクロは、シンプルで高品質な商品を提供しています。例えばヒートテックなどの機能性素材を使用した製品は、同社のミッションに沿った商品開発の一例です。 |
| 現場主導の改善 | 店舗スタッフが接客データや販売状況をもとに、商品配置や販売戦略を主体的に提案しています。これにより、現場の裁量を重視し、ミッションに沿った改善が実践されています。 |
| 社会課題への対応 | ユニクロは難民支援や災害支援のための衣料提供も行っており、服を通じて生活をより良くするという使命を社会貢献に反映しています。 |
トヨタ
日本を代表する自動車メーカー・トヨタ。2021年には実験都市「ウーブン・シティ」の建設に着手し、日本のモビリティテクノロジーを牽引する企業としてますます存在感が高まっています。
トヨタは社員の行動規範として「トヨタウェイ」「トヨタ行動指針」という2種類のルールを設けています。
トヨタウェイの内容は以下のとおりです。
トヨタは、
「だれか」のために
誠実に行動する
好奇心で動く
ものをよく観る
技能を磨く
改善を続ける
余力を創り出す
競争を楽しむ
仲間を信じる
「ありがとう」を声に出す
(出典:トヨタ公式サイト)
また、トヨタ行動指針は冊子にまとめられています。
冊子内ではトヨタ行動指針を次のように定義しています。
「トヨタ行動指針」(1998年策定、2005年改訂)は、実際の会社生活(含.日常業務)・社会生活で、具体的に行動する上で、私たちひとり一人が規範・羅針盤とすべき基本的な指針および具体的な留意点をまとめたものです。
(出典:トヨタ行動指針)
よりくわしい内容を確認したい方は公式サイトを参照してください。
トヨタウェイ、トヨタ行動指針はどちらも単に業務上のルールであるだけではなく、仕事・プライベートの垣根なく社員の日常生活全般において「トヨタ社員としてどう行動するか」を示したものです。
理念や精神論といった曖昧なものではなく、「こう動く」と行動ベースで書かれているのが特徴です。
実際の取り組み
トヨタはミッションを明確に定め、現場の改善活動や安全技術の開発など、具体的な取り組みで実現しています。
| 取り組み | 内容 |
|---|---|
| カイゼン活動(現場改善) | トヨタは「カイゼン(改善)」を企業文化として根付かせ、現場の社員が自律的に改善提案を行う仕組みを構築しています。これにより、品質向上や効率化が実現されています。 |
| 安全技術の開発 | トヨタは自動ブレーキや衝突回避システムなど、先進的な安全技術を開発・導入しています。これらの技術は、同社の「社会に幸福を届ける」という指針に基づいています。 |
| 社会貢献活動 | 交通安全教育や地域社会支援など、社会貢献活動を積極的に展開しています。これらの活動は、企業の社会的責任を果たすとともに、ミッションの実現に寄与しています。 |
ミッションドリブンを学べる本
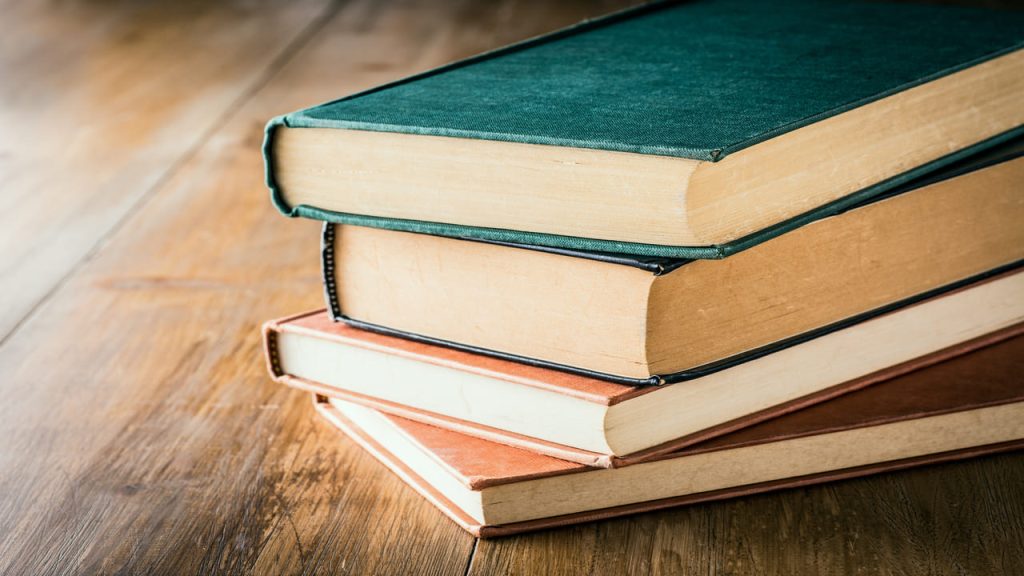
この章では、ミッションドリブンを学ぶのに役立つ書籍を紹介します。
『ミッションドリブン・マネジメント ~「なんのため?」から人を活かす~』
『ミッションドリブン・マネジメント ~「なんのため?」から人を活かす~』(鳶本 真章 著)採用・人事制度・組織文化にミッションを反映させ、スローガンで終わらせない仕組みづくりを行うための実践書です。
「丸亀製麺」などの外食ブランドを展開するトリドールホールディングスで、組織開発に携わった著者が、日本企業の事例をもとに組織開発のノウハウを解説しています。
『WHYから始めよ! インスパイア型リーダーはここが違う』
『WHYから始めよ! インスパイア型リーダーはここが違う』(サイモン・シネック 著)では、「ゴールデンサークル理論(Why → How → What)」をもとに、「なぜ存在するのか(Why)=ミッション」を起点とする組織運営の考え方を学ぶことができます。
ミッションドリブンという言葉自体は出てきませんが、その核心を学ぶのに役立つ一冊です。
なお、TED動画「優秀なリーダーはどうやって行動を起こすか」もミッションドリブンのエッセンスを学ぶのに、おすすめです。
まとめ:「ミッションドリブン」を実践しよう

ミッションドリブンとは、「私たちはなぜ存在するのか?」という根本的な問いを出発点に、経営や日々の行動を進める考え方です。
ミッションを軸に意思決定を行うことで、社員の行動指針が明確になり、組織の一体感や文化の形成につながります。
まだミッションが定まっていない場合は、まずは「私たちは何のために存在しているのか?」を、社内ワークショップ等で言葉にするところから始めてみましょう。
すでにミッションがある場合は、日常業務、採用基準・評価制度に組み込み、理念を浸透させていきましょう。
未来の企業成長を支えるのは、数字や戦略だけではありません。企業が掲げるミッションこそが、社員を動かし、組織を成長へ導く原動力になります。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
