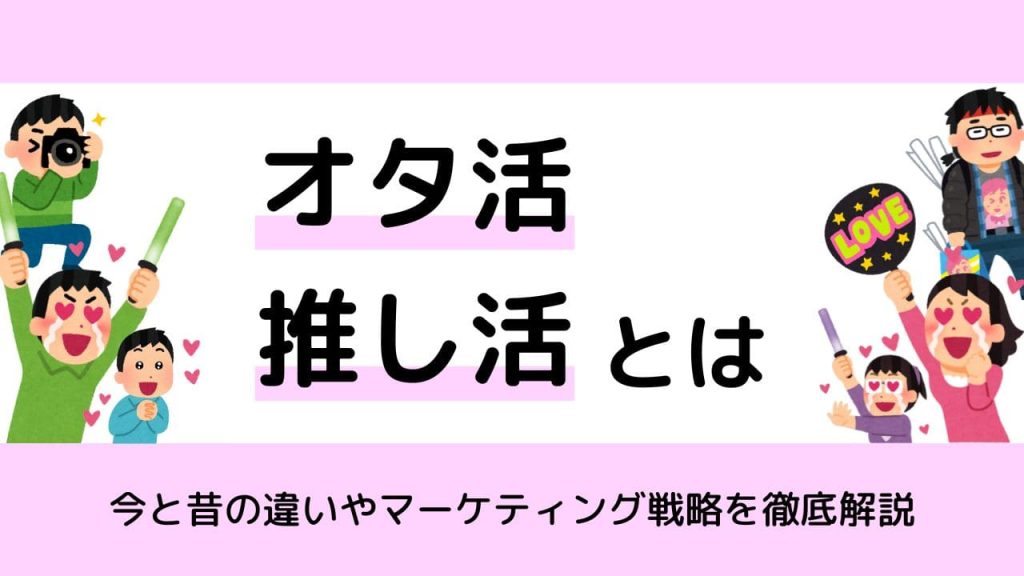
オタ活・推し活とは?広がるオタク市場の経済効果と企業の実例を解説
オタ活・推し活とは、自分の好きな作品や人物を応援し、楽しむことで日常に喜びや生きがいを見出す活動のことです。
近年、アニメやアイドル、ゲーム、VTuberなどを応援するオタ活・推し活が、単なる趣味の枠を超えて、強い経済効果と社会的影響力を持つ存在へと進化。今ではオタク文化は堂々と語られる時代となり、企業もその熱量と拡散力に注目しています。
この記事では、オタ活・推し活の定義や今と昔の違い、経済にもたらしている効果、企業が行うマーケティング事例までを詳しく解説します。オタ活・推し活により人々の価値観や消費行動が大きく変化しているので、その魅力と社会的な影響についてみていきましょう。
目次
オタ活・推し活とは?違いはある?

オタ活・推し活とは、自分の好きな作品や人物を応援し、楽しむ活動のことです。
一見すると「オタ活」と「推し活」は似ているように見えますが、実は異なる背景や価値観から成り立っています。たとえば、「オタ活」はアニメやゲーム、マンガといったコンテンツへの深い愛情や知識の追求が中心であるのに対し、「推し活」はアイドルや俳優、VTuberなど“推し”と呼ばれる対象を感情的・精神的に支える行動が軸となっています。
どちらも「好き」を原動力にしたライフスタイルの一部となっており、特に若者を中心に日本の文化として根付いています。
オタ活とは
オタ活とは、アニメ、漫画、ゲーム、フィギュア、ライトノベル、声優などの特定のコンテンツに対して強い愛情と関心を持ち、趣味として積極的に楽しむ活動全般を指します。「オタク」という言葉から派生したこの概念は、1980年代から徐々に形成され、現在では幅広い年齢層で使われる言葉として認識されています。
主な楽しみ方としては、作品への愛情を表現するためのグッズ収集、設定や制作背景への深い追求、二次創作やコスプレといった創作参加、共通の趣味を持つ人々との交流が行われます。
これらの活動は、単なる消費活動ではなく、対象となるコンテンツに対する深い理解と愛情の現れなのです。オタ活の広がりは、新たな価値を生み出す場にもなるため、コンテンツ産業の発展や日本のサブカルチャーの国際的な認知にも大きく貢献しています。
推し活とは
推し活とは、特定の人物、キャラクター、グループ(アイドル、VTuber、YouTuber、俳優、声優など)を「推し」として応援し、支援する活動全般を指します。「推薦する」の略語である「推し」から派生したこの言葉は、2010年代以降のSNSの普及とともに急速に発展しました。
推し活の主な行動としては、ライブ参加やグッズ購入を通した応援、推しに関する情報発信、同じ推しを持つファン同士との交流が挙げられます。
また、「推す」という行為を通じて対象への愛情を表現すると同時に、自分らしさや価値観を示す自己表現の手段にもなっています。現代においては、推しの成功が自分の喜びとなり、応援を通じて充実感を得る文化として定着していることが特徴です。
オタ活・推し活の今と昔はどう変化した?

オタ活・推し活の文化は、時代とともに大きく変化してきました。特に、社会の価値観の変化やSNSの発展は、オタ活・推し活の在り方を大きく変えるきっかけとなっています。
オタ活・推し活の価値観の変化
かつてのオタク文化は、「内向的で隠すべきもの」というイメージが強く、趣味を周囲に打ち明けることに抵抗を感じる人が多くいました。特に、オタク趣味は「恥ずかしいもの」とされ、活動は限られたコミュニティの中だけで行われることが一般的であり、社会的な理解も乏しく閉じた文化と見られていました。
しかし現在では、推しを公言することが一つのステータスとなり、SNSで積極的にオタ活・推し活について発信する人が増えています。変化の背景には、インターネットとSNSの普及、「個人の好みや表現を尊重する」社会の広がりがあります。今では、オタ活・推し活は「個性的で魅力的な趣味」として、多くの人からポジティブに捉えられているのです。
SNS時代のオタ活・推し活の広がり
SNSの普及は、オタ活・推し活の在り方を大きく変化させました。Instagram、X(旧Twitter)、TikTokなどのプラットフォームにより、オタ活は「見せる・共有する」活動として発展し、多くの人と楽しみを分かち合えるようになったのです。
リアルタイムで推しの最新情報を発信・共有できるようになったことで、ファン同士のつながりは世界中に広がり、ファンアートや動画制作などの創作活動も活発化しています。また、グッズの購入報告などを通じて、経済的な応援のかたちも明確に見えるようになりました。
また、推しへの愛を伝えるSNS投稿は「推し活投稿」と呼ばれ、企業も注目するマーケティング資源となっており、オタ活・推し活の新たな魅力を生み出しています。
「推し=ブランド」化現象
現代の推し活で注目すべきポイントは、「推し」が個人のブランディングツールとして機能していることです。どの推しを応援しているかが、その人の価値観や美意識を表す手段となり、自分らしさの象徴にもなっています。
たとえば、推しの担当カラーを取り入れたファッション(推し色コーデ)や、グッズを飾ってインテリアとして楽しむディスプレイ、推し専用のSNSアカウントの運営、ライブやイベントへの積極的な参加などが代表例です。
このような活動は、推し活が単なる「応援」にとどまらず、自己表現の一部として進化していることを示しています。推しを通じて自分の好みやスタイルを発信し、共感する仲間とつながることで新たな価値が生み出されているのです。
オタ活・推し活の経済効果

オタ活・推し活は、現代日本において無視できない経済効果を生み出しています。以下では、具体的な市場規模と消費行動や広告効果に与える影響について詳しく解説します。
オタク市場は2兆円超
2023年度の国内オタク市場は主要16分野のうち14分野が拡大し、総額はついに2兆円を突破しました。特に同人誌は即売会の復調やデジタル販売の普及、海外需要の増加により前年比37.9%増と急成長。音声合成や2.5次元ミュージカルもチケット・グッズ販売が好調で市場をけん引しています。
この背景にあるのは、推し活を中心とした体験型消費とSNSによる拡散です。さらに、音声合成や2.5次元ミュージカルのように、テクノロジーを融合させた新しいジャンルも登場し、幅広いファンの心をつかんでいます。今後も推し活・オタ活をきっかけにした参加型のコンテンツが広がることで、オタク市場のさらなる成長が期待されています。
参照:株式会社矢野研究所|「オタク」市場に関する調査を実施(2024年)
オタ活・推し活が動かす「熱量経済」の仕組み
熱量経済とは、ファンの感情的な熱量がそのまま経済活動につながる仕組みのことです。オタ活・推し活においては、商品やサービスの購入が「推しへの投資」として捉えられ、高額であっても購入されやすく、継続的な消費が発生するという特徴があります。
また、イベントへの参加意欲も高く、ファン同士によるSNSでの情報共有がさらなる消費を促進しています。こうした現象は、体験やつながりに価値を見出す消費行動として、ライブチケット、特典付き商品などの形で現代の市場を大きく動かしているのです。
オタ活・推し活が生み出す広告効果と購買行動
企業が発信する広告よりも、ファン自身が発信する体験談や感想の方が信頼されやすく、多くの人に自然と広がっていきます。こうした投稿はUGC(ユーザー生成コンテンツ)と呼ばれ、SNS上での開封動画、使用レビュー、コーディネート写真などを通じて高い宣伝効果を生み出します。
推しに関連するアイテムは、「推しが使っている」「推しカラーである」といった理由だけで購入されることも多く、ファンの投稿が他のファンの購買意欲を刺激する事例も多いです。このように、オタ活・推し活による情報共有は広告としての役割を果たすだけでなく、購買行動そのものを生み出す強力な仕組みとなっています。
オタ活・推し活施策を行う企業事例

多くの企業が、オタ活・推し活文化を活用したマーケティング施策を展開しています。ここでは、オタ活・推し活施策がバズった企業事例をご紹介します。
WEGO「メンカラコーデ」
WEGOは、推しのメンバーカラーをファッションに取り入れる「メンカラコーデ」という企画を打ち出しました。公式オンラインストアでは、カラー別のコーディネート例を豊富に掲載し、ファンが自分の“推し色”を取り入れた着こなしをすぐに真似できる工夫がされています。
購入したアイテムを着用してSNSに投稿するユーザーが続出し、「#メンカラコーデ」や「#WEGO推し活」といったハッシュタグが広まりました。ただ商品を売るだけでなく、推し活という感情に寄り添うことで、ファッションの新たな価値提案を行っています。
サンリオ「推しのいる生活」
サンリオは、自社キャラクターだけでなく、すべての“推し”を大切にするファンの気持ちに寄り添う「推しのいる生活」というプロジェクトを展開しています。企画では、アクスタケースやペンライトポーチなど、推し活に欠かせないグッズを種類豊富に取り揃え、推しのジャンルを問わず誰でも活用できるよう工夫されています。
注目すべきは、商品開発担当者自身も推し活に精通していることです。ファンのリアルな課題やこだわりを理解したうえでの商品設計が、深い共感を生んでいます。SNSではユーザー同士がハッシュタグを通じて活用法を共有し合い、ブランドとファンとのつながりが形成されています。
参照:マイナビニュース|企画担当者も”推し活”中 – サンリオが推し活するひとたちを全力で応援するワケを聞いた
カラオケビックエコー「推し色ルーム」
大手カラオケチェーンのビッグエコーでは、11色の「推し色ルーム」を導入することで、推し活とエンタメを融合させる試みを行っています。推し色ルームでは、内装のカラーや照明、インテリアまで徹底的に“推し色”に染め上げ、まるでライブ会場にいるかのような空間が体験できます。
オフ会や誕生日会の場として利用される機会も多く、SNSでは「#推し色ルーム」を使った写真や動画が投稿され、ユーザーの自発的な発信からさらなる集客につながっているのです。利用者の感情を盛り上げる仕掛けが、サービスの新たな価値を創出しており、日常のカラオケに特別な思い出という意味を加えることに成功しています。
くら寿司×ちいかわのコラボ企画
くら寿司は、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーションを通じて、ファン心理を巧みに活かしたマーケティングを展開しました。店内ではコラボメニューが提供されるだけでなく、「ビッくらポン!」で限定グッズが当たる仕組みを導入し、食事の楽しさと収集欲を同時に刺激しています。
さらに、ちいかわ仕様の装飾で店舗の雰囲気も盛り上げ、来店自体がイベント化しました。ファンは「#ちいかわくら寿司」などのタグを付けて写真を投稿し、口コミ的に情報が広まっています。人気キャラクターとのコラボによって、食事にエンタメ要素が加わり、新規客とリピーターの来店を同時に増やすことに成功した事例です。
参照:MAY Planning|「ちいかわ経済圏」から見た、ビジネスにおける「推し活」と「コラボ」の力
エスビー食品株式会社×INI「推しスパ投稿キャンペーン」
エスビー食品は、人気ボーイズグループINIとのタイアップで「推しスパ投稿キャンペーン」を実施しました。キャンペーンでは、各メンバーが監修したスパゲッティソースのアレンジレシピを公開。SNSでは、「#INIの推しスパ」やメンバー名のハッシュタグが活発に使われ、料理写真や感想が次々に投稿されました。
投稿者の中から抽選でオリジナルグッズが当たる仕組みも用意され、参加の動機づけとして効果を発揮しています。日常の食事に推し活の楽しさを取り入れることで、商品の知名度向上と購買意欲を促進させ、さらに企業への親しみも深めるという3つの効果を生んでいます。
参照:エスビー食品株式会社|S&Bまぜるだけのスパゲッティソース×INI「キミの推しスパは!?」プロモーションスタート
JR東日本×名探偵コナン「スタンプラリー企画」
JR東日本は、人気アニメ「名探偵コナン」とコラボし、各地の駅を巡ってスタンプを集めるスタンプラリーイベントを展開しました。各駅にはコナンキャラクターのスタンプ台を設置し、謎解きやストーリー要素を楽しみながら移動するという仕掛けを施しています。
参加者はスマホでスタンプの収集状況を記録し、「#コナンスタンプラリー」などのハッシュタグを使ってSNSに投稿。リアルな聖地巡礼体験がファンの気持ちをさらに盛り上げ、鉄道を利用するきっかけにもなっています。また、各駅の魅力がイベントを通じて可視化され、沿線エリアの観光促進にもつながっている事例です。
森永製菓×あんさんぶるスターズ!!「共創型プロモーション」
森永製菓は、スマホゲーム「あんさんぶるスターズ!!」のユニット「fine」とコラボし、共創をテーマにしたプロモーションを打ち出しました。企画では、メンバーがそれぞれ考案したフレーバーのチョコボールを商品化し、ファンは「推しが作った商品を手に取る」感覚を楽しめるようになっています。
最大の特徴は、世界観やキャラクター性が細かく反映された仕掛けにより、物語と商品がひとつになっている点です。SNSでは「#fineと森永製菓」を使った購入報告や感想投稿が行われ、ファンは商品購入を通じて作品の世界に参加しているような気持ちを味わえる仕組みとなっています。
オタ活・推し活への敬意を大切にし、ファンの気持ちに寄り添った企画が、多くの共感と支持を集める結果につながっています。
参照:宣伝会議|企業が推しを消費してはならない 森永製菓が『fine』とのコラボに込めた思い
オタ活・推し活が変える消費とマーケティングの未来
かつて「隠す趣味」とされていたオタ活・推し活は、SNSの普及により「見せる・共有する」文化へと変化し、2兆円を超える大きな経済圏を築くまでに成長しています。現在では、自分らしさを表現する手段として社会に広く受け入れられる存在となりました。
オタ活・推し活に対する価値観の変化により、ファンの熱い思いがそのまま消費につながる「熱量経済」という新しい経済の形が生まれています。企業もこの流れを重視し、ファンの気持ちに寄り添った取り組みを行うことで、新しい顧客を取り込みつつ、既存のユーザーとの絆を深めています。
将来的には、音声合成やAR・VRなどの最新テクノロジーが加わることで、推しとのつながりをよりリアルに感じられるようになり、楽しみ方の幅も広がっていくでしょう。こうした体験型消費と技術の進化によって、オタ活・推し活の市場は今後さらに拡大していくと考えられます。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
