
AIが抱える著作権問題と文化庁が考える3つの段階|業界の反応や事例も紹介
AIによるコンテンツ生成が広がりを見せる中、AI生成物が抱える著作権に関する課題が注目されています。
AIが生成した作品に著作権はあるのでしょうか。また、AIが生成した作品の利用や権利についてはどのように取り扱うべきなのでしょうか。AI生成物が抱える著作権の課題については、クリエイターや業界団体からの反応、具体的な事例も多く報告されています。
そこで本記事では、AI著作権に関する基礎知識から、文化庁の見解、クリエイター業界からの反応、これからのAIとの付き合い方までを詳しく解説します。AIの活用を検討する方にとって、今後の議論の参考になる内容をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。
※本記事は文化庁の令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」及び「AI と著作権に関する考え方について」の資料を基に作成しています。
目次
AI生成物が抱える著作権の課題とは
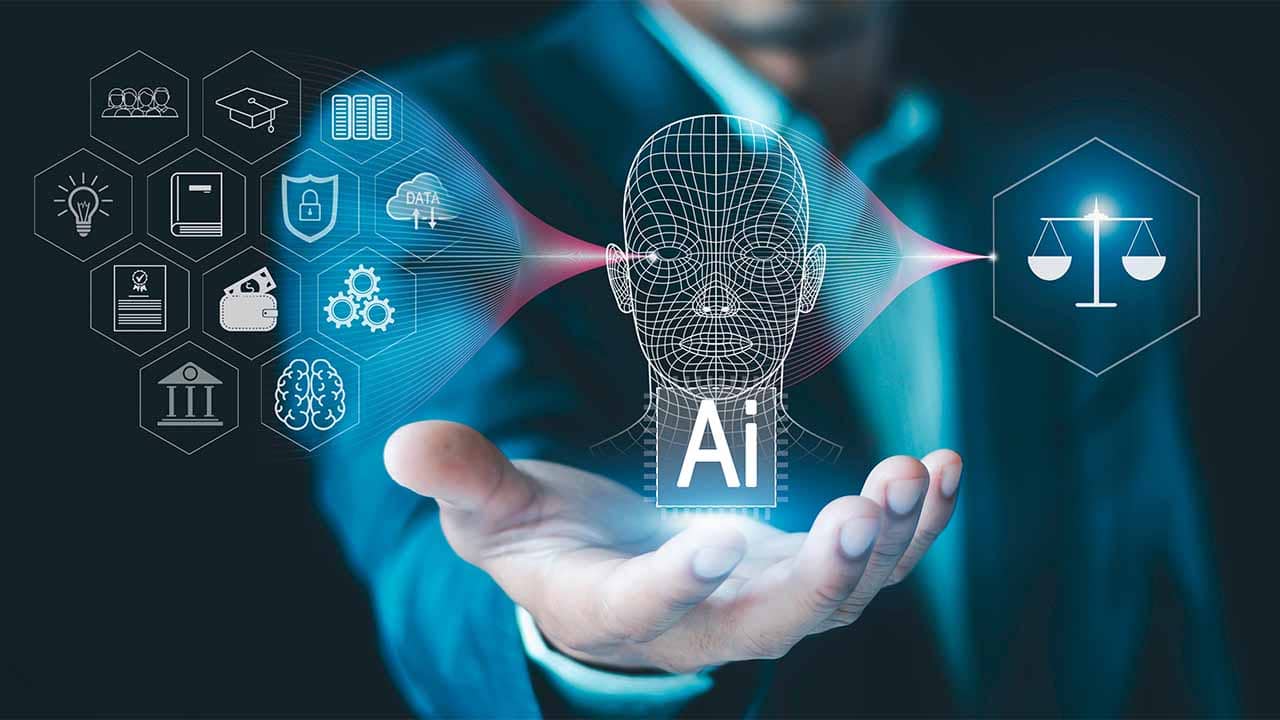
AI生成物の著作権に関する課題は数多く存在しています。
AIが生成した作品に対して、誰がその著作権を持つべきかという点が不明瞭であり、法律上の判断が非常に難しいことがその背景にあります。著作権法は基本的に「人間の創作性」を基準としているため、文化庁の発表でもAIが生成した作品が創作性を持たない場合は著作権上の保護対象にならないと考えられています。
また、AIを使う過程で既存の著作物を学習させた場合、その利用が著作権侵害になる可能性も議論されています。このような状況は、AI技術の急速な発展によりさらに複雑化しており、法整備の遅れが問題を深刻化させているわけです。
これらの課題に対処するためには、法整備の見直しや、新たな指針の作成が急務とされています。AI生成物と著作権に関する議論は、今後も社会的な注目を集め続けると考えられます。
文化庁が公表するAIと著作権の見解と3つの段階
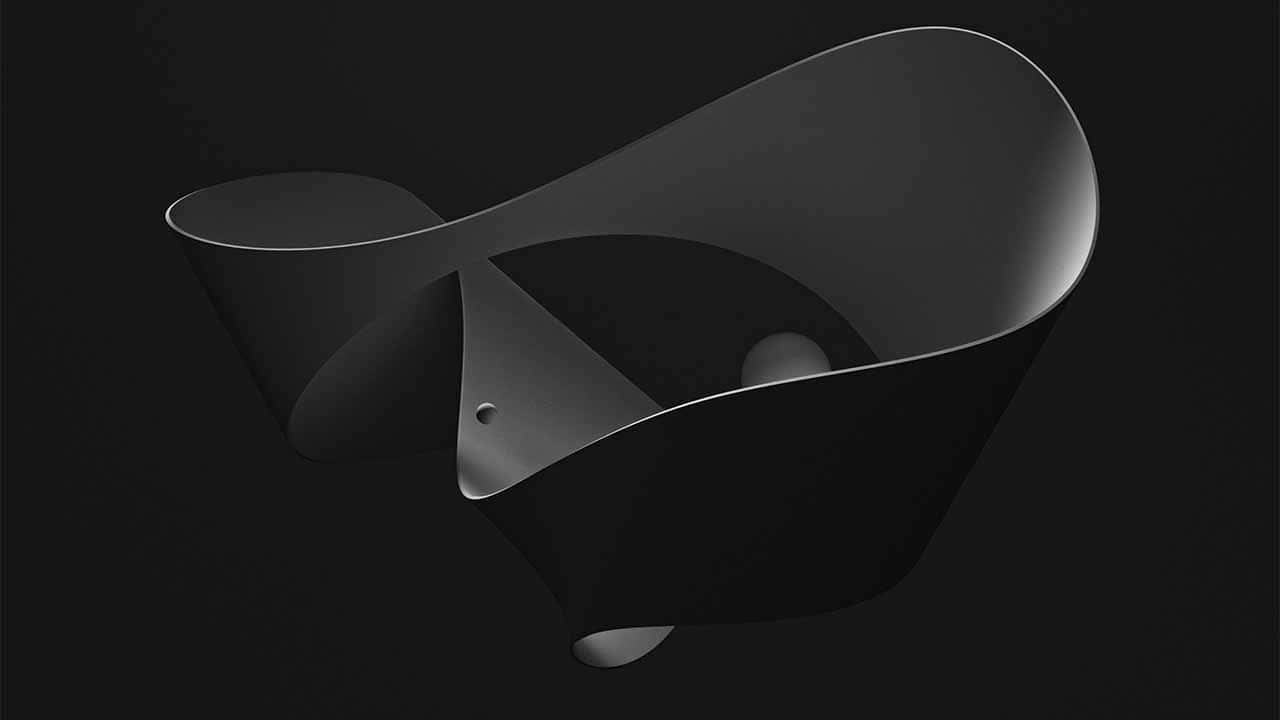
文化庁は、AI技術の発展に伴う著作権問題について、明確な指針を提示しています。この指針は、AIの利用における著作権の適用や対応を「3つの段階」に分けて整理し、それぞれの段階で考慮すべきポイントを示したものです。
これにより、AIの研究者や開発者、利用者が、著作権に関する適切な理解と対応を行えるよう支援しています。具体的には、以下の3つの段階に分かれています。
- AI開発・学習段階
- 生成・利用段階
- 生成物の取り扱い
この3段階は、AIの成長過程や利用プロセスに沿って構成されており、それぞれの段階で異なる法的課題や注意点が存在します。ここからは、それぞれの段階について詳しく解説を進めていきましょう。
【AI開発・学習段階】AI学習への使用は問題ないことが多い
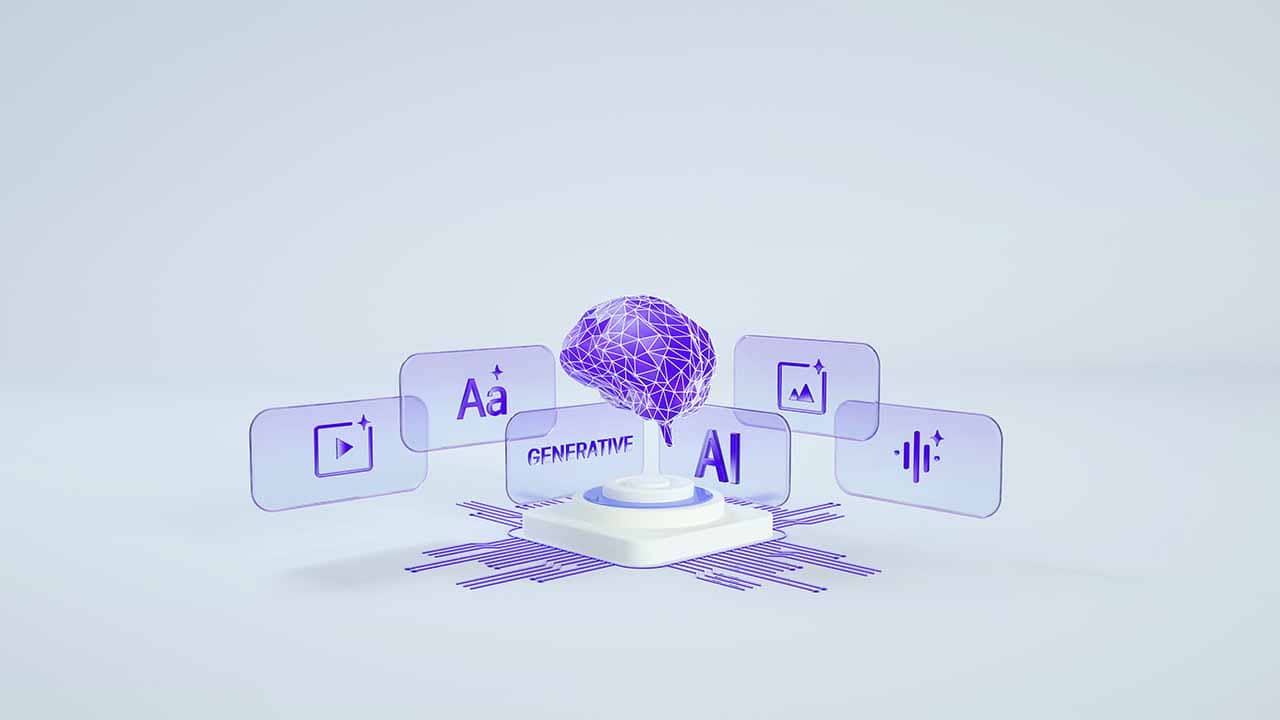
AI開発・学習段階では、著作権法第30条の4の規定により、既存の著作物を分析・学習目的で使用することは基本的に認められています。
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
引用元:著作権法
この規定は、技術革新を促進する目的で2019年に導入されました。
具体的には、AIが膨大なデータを学習する過程で著作物を非商業的に活用する場合、著作権侵害に当たらないとされています。ただし、学習結果を商業利用する際には注意が必要です。
このような枠組みが、AI開発を支える重要な法的基盤となっています。
著作権法第30条の4が導入された経緯
著作権法第30条の4は、AIやビッグデータ技術の進展に対応するために新たに設けられました。この条項は、著作物を無断で分析・利用する行為を特例として合法化し、技術革新を促進することを目的としています。
この規定が導入された背景には、データ活用の重要性が高まる中で、著作権者の権利を保護しつつも、技術開発を妨げない仕組みが求められていたことがあります。
従来は、著作物を利用する際には原則として著作者の許諾が必要でした。しかし、AIが膨大な既存の著作物を学習する際、すべての権利者の許可を得るのは非現実的であり、この手間がイノベーションの進展を遅らせる懸念があったのです。
この条項の導入によって、学習目的での著作物利用が広がりました。
【生成・利用段階】類似性と依拠性が焦点

生成・利用段階において、AIにより生成される作品が他者の著作権を侵害しているかを判断する場合、重要なポイントは「類似性」と「依拠性」の2点です。これらは、AIを用いた場合でも、従来の著作権侵害の基準と同様に適用されます。
類似性が高い場合、生成物が既存の著作物をもとに作られたと認識される可能性があります。例えば、「単なる事実の記載」や「ありふれた表現」、「表現でないアイデア」が含まれる場合は類似性が高いとは言えません。一方、依拠性は、生成物が既存の著作物に依拠して作られたかどうかが問われます。
これらの要素が両方とも満たされ、かつ権利者の許諾を得ていない場合や、著作権法で認められる例外規定が適用されない場合、著作権侵害が成立する可能性が高くなります。
依拠性とは
AIの生成・利用段階において重要視されるポイントのうち、「依拠性」について詳しく知っておきましょう。
依拠性とは、AIが生成物を作成する際に特定の著作物を参照したかどうかを判断する基準を指します。この基準は、著作権侵害の成立において大きな役割を果たしているのです。
具体的には、生成物が偶然似ている場合ではなく、元の著作物に依存していることが確認された場合に依拠性が認められます。例えば、AIが学習データとして使用した素材に基づいて、酷似した作品を生成した場合、依拠性があると判断される可能性があります。
依拠性の有無は、著作権問題をめぐる裁判においても重要な焦点となり、AIの利用における法的リスクを評価する際のポイントとなっているわけです。
【生成物が著作物となるか】個別の判断が必要
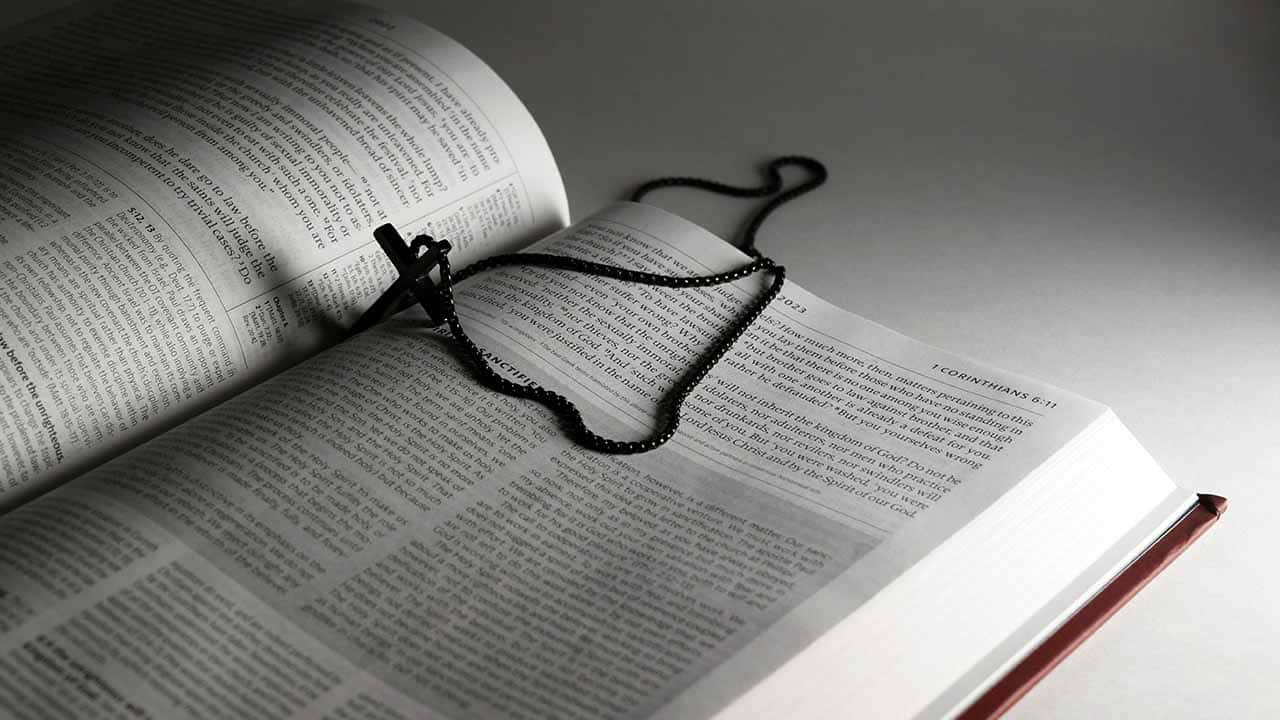
AIが生成した作品が著作物として認められるかどうかは、個別に判断する必要があります。
著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされ、「人間による創作性」が求められます。しかし、AI生成物には人間の関与が少ない場合があり、創作性が認められないことがあるのです。
その一方で、クリエイターが思想や感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用し、生成された作品に手を加えた場合は、著作物として認定される可能性もあります。このため、生成物の性質や生成過程を明確にすることが重要です。法律や裁判例の蓄積により、今後さらに具体的な基準が示されることが期待されています。
AIを活用した小説が文学賞を受賞したケースもある
AIを活用して制作された小説が文学賞を受賞した事例があります。具体的には、以下が挙げられます。
- 2022年にAIを使って執筆した小説が「星新一賞」一般部門優秀賞を受賞
- 2024年にChatGPTの力を借りて執筆した小説が「芥川賞」を受賞
このようなケースでは、AI生成物にクリエイターの意図や編集が加わっている点が評価されました。例えば、AIがプロットや文章を生成し、それを人間が選択・修正することで完成度を高めた場合、その作品は人間の創作性が認められる可能性が高いのです。
このような事例は、AIがクリエイティブな分野で新たな可能性を切り開いている一方で、著作権のあり方について議論を深める契機にもなっています。
AIを利用する人も注意が必要

AIを利用する際には、ユーザー側も著作権に関して注意を払う必要があります。
AIが生成した作品が他者の著作権を侵害している可能性があるため、利用者はそのリスクを十分に理解しておく必要があるのです。
具体的には、私的な利用や教育目的での複製のように「権利制限規定」に該当する場合は著作権侵害の問題はありません。しかし商用利用する際に、類似性や依拠性が認められる場合は注意が必要となります。
また、AIを学習させるために使用されたデータが著作権で保護されている場合、そのデータを無断で利用することは著作権侵害に該当する可能性があります。利用者は、AIの使用目的や生成物の性質に応じて適切な利用方法を選び、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
AIと著作権に対するクリエイターの反応と事例

AIによる生成物と著作権の課題をめぐって、クリエイター業界からさまざまな反応が寄せられています。特に、AIが既存の作品やパフォーマンスを模倣・利用するケースが増える中で、業界全体で著作権の保護や適切な利用に対する懸念が高まっているのです。
ここでは、注目すべき2つの事例を取り上げます。
- 声優や俳優の業界団体は声明を発表
- 音楽レーベルが音楽生成AIに著作権侵害を申出
これらの事例を通じて、AI利用が生み出す法的・倫理的な課題について、それぞれ詳しく解説していきましょう。
声優や俳優の業界団体は声明を発表
声優や俳優の業界団体は、AIが生成した音声や映像が著作権を侵害する可能性について懸念を示しています。特に、自分たちの声や映像が無断でAIに学習させられるケースが問題視されているのです。
2024年11月、声優などが加入する「日本俳優連合」と「日本芸能マネージメント事業者協会」、「日本声優事業者協議会」が声明を発表しました。その内容は、権利者の許可を得ずにAIを活用することの是非を明確にするよう求めるものです。
この動きは、AI技術が広がる中で、クリエイターの権利を守るための重要な一歩となっています。
音楽レーベルが音楽生成AIに著作権侵害を申出
2024年6月、音楽レーベルの「ユニバーサル ミュージック グループ」や「ワーナーミュージック・グループ」などからなる業界団体が、AIによる音楽生成が会社やアーティストの著作権を侵害しているとして訴状を提出しました。AIが既存の楽曲をもとに似たような作品を生成した場合、その作品が依拠性を持つとみなされる可能性があるためです。
これにより、AI開発企業と著作権者の間で訴訟に発展するケースも増えています。この事例はAI技術と著作権者の関係性を改めて考えるきっかけとなっており、業界全体でのルールづくりが急務となっています。
AIと著作権は今後も検討が進められる

AIと著作権をめぐる議論は、技術の進化に伴い今後も継続的に進められるべき重要な課題です。現行の著作権法は人間の創作物を前提にしているため、AI生成物を適切に扱うための新たなルールが求められています。
特に、AIが生成する作品が著作物として認定される基準や、AIが学習に利用するデータの取り扱いに関する明確な指針が必要とされています。また、技術の進歩が極めて速いため、法律やガイドラインの見直しが頻繁に行われる可能性もあるのです。
こうした課題の解決には、法律だけではなく、社会全体での理解や議論が不可欠となります。AIと著作権に関するルールの整備は、技術革新と権利保護のバランスを図る上で重要なステップとなるでしょう。
AIと著作権は何が問題なのかを理解して活用することが大切

AIと著作権の問題を正しく理解することは、AIを適切に活用する上で重要です。AI生成物が他者の著作権を侵害するリスクがあるため、その取り扱いには慎重な対応が求められます。
例えば、AIを利用する際に学習データの出所や生成物の権利帰属を明確にすることは、法的トラブルを防ぐためにも不可欠です。加えて、AIの活用が社会にどのような影響を与えるかを考慮し、倫理的な観点からも適切な対応が必要となります。
AIと著作権をめぐって、文化庁では「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」が公開されています。「AI開発者」「AI提供者」「AI利用者」「業務外利用者」それぞれに向けた構成となっているので、一読しておくことをおすすめします。
AIと著作権への正しい理解が、AI活用の未来を切り開く鍵となるでしょう。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
