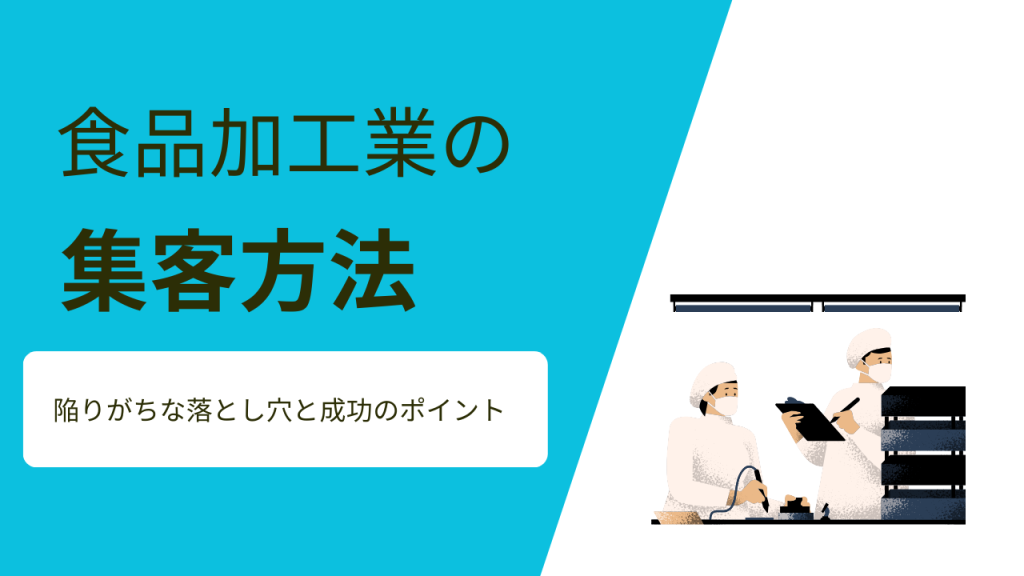
食品製造の集客方法6選!取引先依存を脱して利益率を改善するWeb施策
「良い製品をつくり、誠実に向き合っているはずなのに、なぜかWeb上での反応が芳しくない……」
食品製造の現場では、こうした違和感を覚える場面が増えているのではないでしょうか。
BtoB(卸・OEM)とBtoC(自社販売)の両輪を回すことが多いこの業界では、ターゲットごとに求められる情報が異なり、発信の軸が分散しやすい構造があります。
日々の製造や品質管理に追われるなかで、Web施策まで十分に手が回らない状況も、決して珍しくありません。
本記事では、食品製造業のWeb活用において直面しやすい「共通の課題」を整理し、限られたリソースのなかで、どのように信頼を積み上げ、検討の場に残り続けるかという視点から解説します。
今の体制に合わせて、無理なく取り組める施策を見極めるための判断材料として、お役立てください。
集客が伸びない原因の多くは、施策の数ではなく、「何を優先すべきか」という設計が整理されていないことにあります。
以下のガイドでは、業種や規模を問わず、限られた時間とリソースの中で集客を自社でコントロールしていくための判断基準と全体像を整理しました。
新しい施策を増やす前に、いまの取り組みを見直すための土台として、一度目を通してみてください。
集客に困っている中小企業の方へ
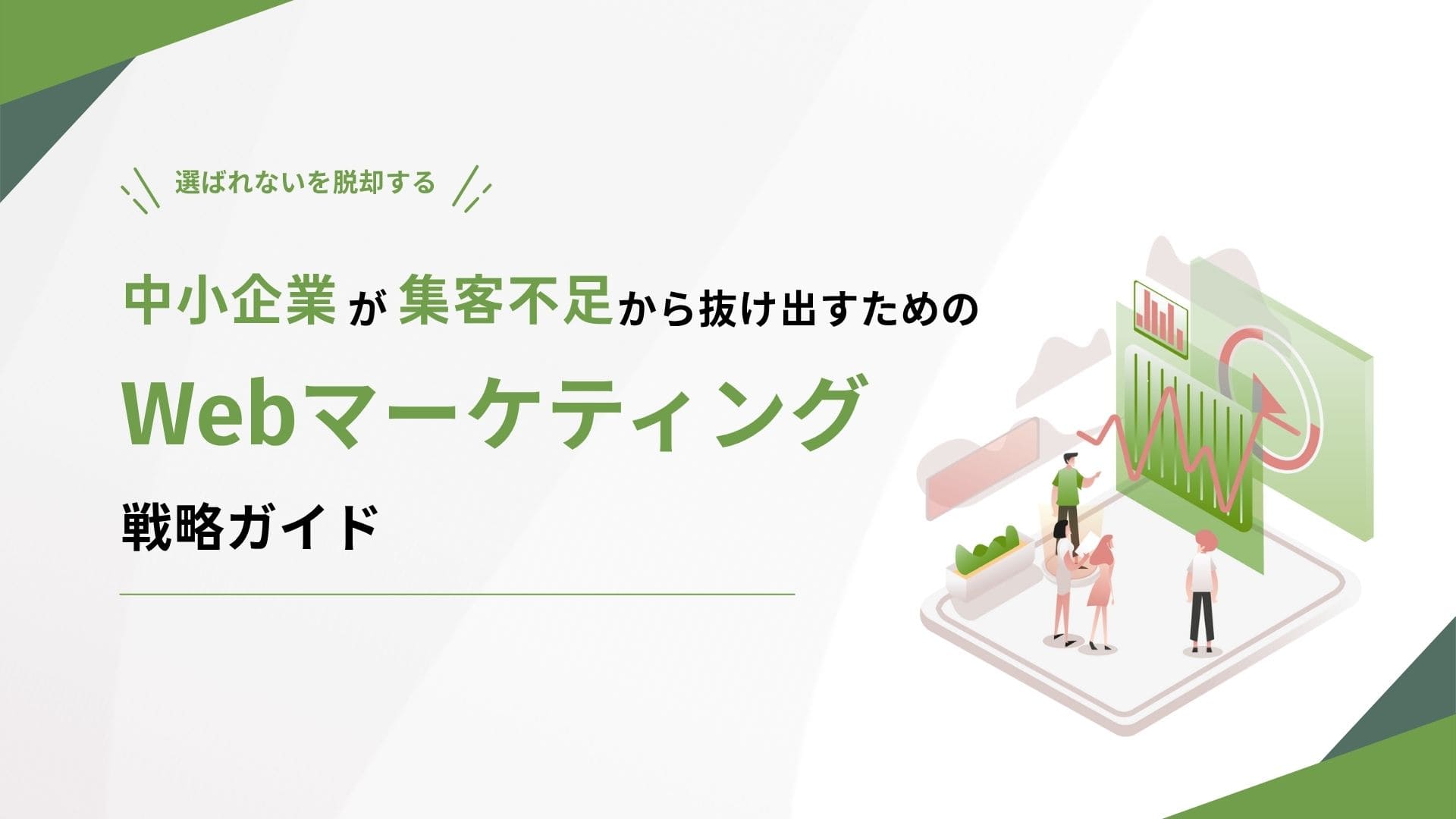
Web集客の施策案や改善で
困っていませんか?
本資料では、中小企業が最短で集客不足から抜け出すためのWebマーケティング戦略をまとめています。限られた予算で効果的な施策を打ちたい、具体的な集客方法を知りたいという方は、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。少しでも経営の手助けになれば幸いです。
目次
食品製造業の集客でよくある失敗

どれだけ品質に自信があっても、集客の仕組みが整っていなければ売上は伸びません。ここでは、多くの食品製造業がつまずきやすいポイントを整理します。
① WebサイトやSNSが機能していない
WebやSNSは企業の顔となる重要な集客チャネルです。しかし実際には次のような状態のまま放置され、問い合わせにつながる情報発信になっていないケースが多く見られます。
- 掲載情報が古く、加工対応範囲や実績が最新ではない
- スマートフォン表示に最適化されていない
- SNSでの発信が不定期、もしくは完全に止まっている
このような状態では技術力や設備の魅力が伝わらず、見込み客の信頼を得ることができません。
まずは、最新情報の更新、スマホ対応、継続的な発信という基本の土台から整えることが重要です。
② 販路拡大の動きが遅れている
長年の取引先に依存し続けると、市場変化に対応できず売上が頭打ちになるリスクがあります。
特に食品製造業は価格競争や需要変動の影響を受けやすく、販路の多様化が必須です。
近年は、以下のような新たな販売チャネルも広がっています。
- ふるさと納税や地場EC
- 自社EC
- BtoBマッチングサイト
- SNSを活用した認知獲得
複数のチャネルを持つことで、既存取引の減少や価格競争に左右されにくい事業構造をつくることができます。
③ 魅力の言語化が不足している
「良いものを作れば自然と売れる」という考えが集客においては、大きな落とし穴となります。
どれほど品質に自信があっても、その価値を言語化しなければ顧客には届きません。
特にネット検索では、文章・写真・実績のわかりやすさが、そのまま問い合わせ率に直結します。
まずは、以下のような要素を丁寧に整理し、言語化することが大切です。
- 技術力・加工対応範囲
- 工場規模・主要設備
- 衛生管理体制(HACCP・ISO等)
- 他社との差別化ポイント(USP)
魅力が明確に言語化されていると、「何ができる会社なのか」が一目で伝わり、選ばれやすくなります。
【参考】HACCPによる衛生管理とは|公益社団法人日本食品衛生協会
【参考】概要 | ISO 22000(食品安全) | ISO認証 | 日本品質保証機構(JQA)
【参考】概要 | ISO 9001(品質) | ISO認証 | 日本品質保証機構(JQA)
④人手不足で施策が続かない
食品製造業は工場の稼働が最優先となるため、マーケティングに人員を割きにくいケースが多く見られます。
その結果、
- EC・SNSの更新が止まる
- 実績紹介や事例公開が滞る
- 問い合わせ対応が後回しになる
といった状況が起こり、集客効果が積み上がらないままになってしまいます。
そこで重要になるのが、少人数でも回せる「仕組み化」です。
- ECで定期的に新着情報を公開
- 製造事例・技術紹介を四半期に1つ追加
- SNSは週一投稿をテンプレート化して運用
無理なく続けられる仕組みをつくることで、顧客からの信頼が着実に積み上がり、自然と問い合わせが増える体制が整います。
これらの4つを解消すると、見込み客からの問い合わせが安定し、一時的な波に左右されない集客基盤が整います。
食品製造業の集客方法6選

この章では、食品製造業者が実務で取り入れやすい6つの集客方法をわかりやすく整理します。
①自社ホームページを整える
食品製造業の多くは、
- ホームページが古い
- 情報が不十分
- 更新されていない
などの課題を抱え、見込み客に魅力が伝わりきっていないことが少なくありません。
ホームページは集客の基盤となるものです。まずは、顧客視点で必要な情報を網羅し、信頼を得る構成に整えることが重要です。
ホームページに掲載したい必須項目は次のとおりです。
(1)会社の信頼性が伝わる情報
- 会社概要(所在地・設立年・代表・従業員数)
- 工場の規模・敷地面積
- 主な設備と特徴
- HACCP/ISO22000/FSSC22000 の取得状況
- 衛生管理体制
(2)加工可能な品目・ロット条件
- 加工できる原料・品目一覧
- 対応できる加工方法(カット・加熱・冷凍・乾燥・味付け など)
- 最小ロット・最大ロット
- PB/OEM商品の製造フロー
(3)製造実績
- 主な取引業種(飲食チェーン・スーパー・ECなど)
- 商品化例
- 製造事例
(4)工場の写真・動画
製造ライン、ゾーニング、衛生対策などの視覚情報は強い信頼要素になります。これらを丁寧に整えるだけで、顧客を安心させられるホームページになります。
以上の必須項目を明確に打ち出すことで、検索ユーザーの信頼を得られ、問い合わせ率が大きく改善するでしょう。
※指名検索とは:特定の企業名・ブランド名・商品名・サービス名を名指しで検索すること
②MEO対策でGoogle検索上位を目指す
食品製造業の場合、近隣の飲食店や地元スーパー、地域の事業者からの検索が多いため、MEO(マップ上で上位表示を目指す施策)は非常に相性が良い集客手法です。
MEO対策とは、Googleマップ上で自社の表示順位を高め、地域の見込み客に見つけてもらいやすくする施策のことです。
このMEOの中心となるのが、Googleビジネスプロフィールの整備です。
※Googleビジネスプロフィールとは:Google検索やGoogleマップに企業情報を無料で表示できるツールのことです。
たとえば「食品製造 〇〇(地名)」といった地域性の強いキーワードで検索した際、地図と会社情報が上位に表示されると、問い合わせや訪問の追加につながります。
MEOで整備すべき主なポイント
- 会社名・住所・電話番号など基本情報は正確な基本情報
- 営業時間や定休日
- 自社サイトや資料請求ページへのリンク
- 工場・設備・商品の写真や動画
- 口コミの管理と返信
これらが充実しているほど、検索ユーザーから「信頼できる会社」として認知されやすくなります。
また、地域内での露出が高まることで、少量ロットの依頼や急ぎの案件など、近隣企業からの問い合わせが増えやすくなる点もメリットです。
MEOは地域ビジネスとの相性が良く、費用もかからないため、食品製造業者にとって非常に取り組みやすい施策といえるでしょう。
ー 店舗集客を強化したい方へ ー
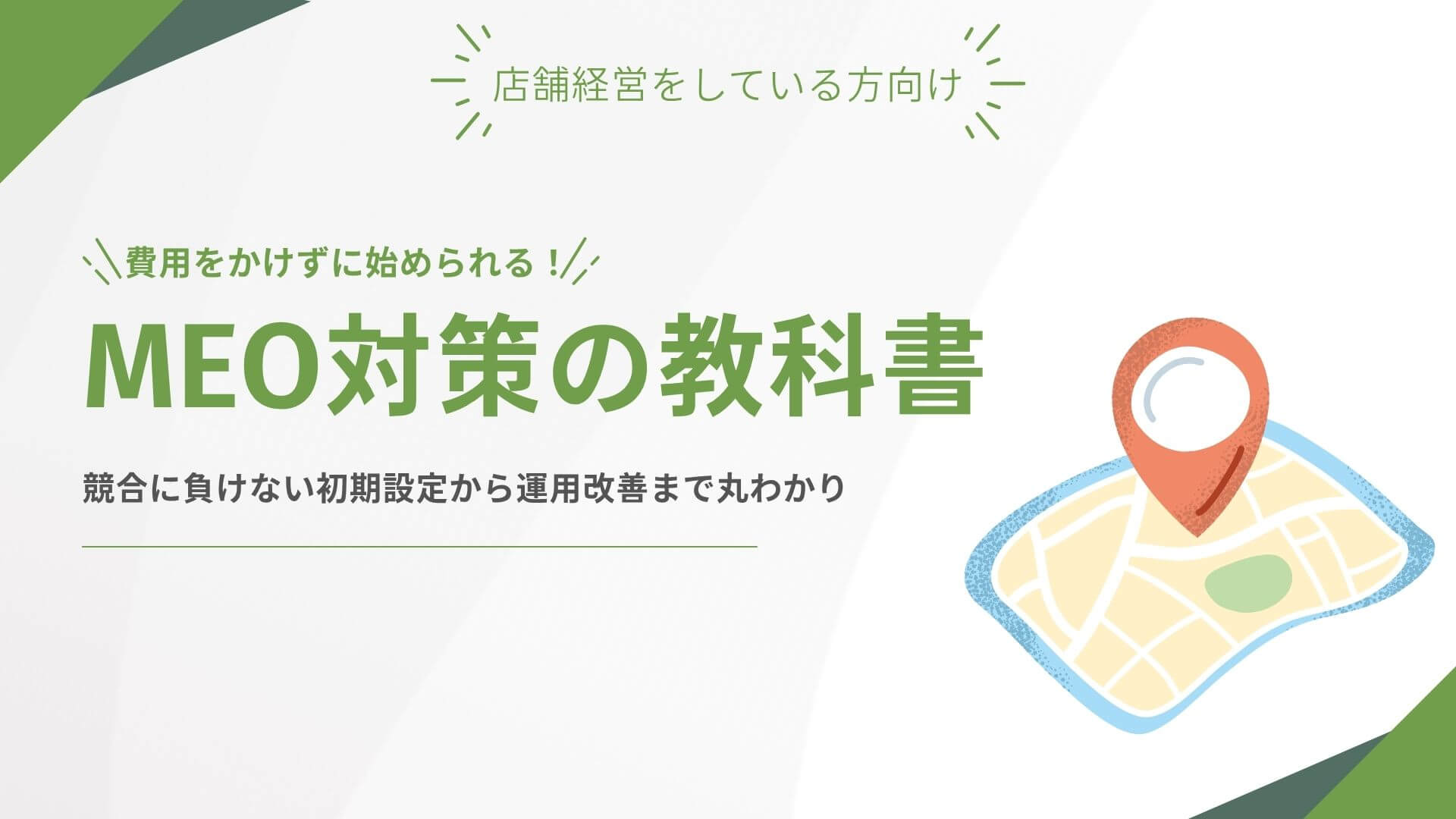
あなたの店舗、
地図検索で見つかっていますか?
Googleマップで上位表示されない=来店機会を逃しているかもしれません。今すぐできるMEO対策の始め方と、成果につなげる運用方法を徹底解説!競合に埋もれる前に、今すぐチェックしてください!
③Web広告を出稿する
Web広告は、短期間で成果を出しやすい集客施策です。
BtoBの場合(OEM・業務用)
BtoBの場合(OEM・業務用)は、課題解決型のリスティング広告が効果的です。
例:「食品 OEM」「業務用 ●●」「プライベートブランド 委託」
これらを検索するユーザーはすでに発注意欲が高く、成約に結びつきやすい傾向があります。
BtoC(自社商品)の場合
BtoC(自社商品)の場合は、InstagramやTikTokなどのSNS広告で、写真や動画を用いて、魅力を直感的に訴求する方法が有効です。
例:「●● 通販」「ギフト」「お取り寄せ」
こういったキーワードを狙うことで、即効性が高まります。
特にOEMや業務用領域では、悩みが明確な顧客に直接リーチできるため、効率的な集客が実現できます。
④SEO対策で自然検索を増やす
広告費に依存せず、長期的に集客したい場合はSEO対策が有効です。
「検索される言葉=顧客が知りたい情報」に合わせてコンテンツをつくることが重要です。
食品製造業で狙いやすいキーワード例は次の通りです。
- ○○ 加工 OEM(例:惣菜、漬物、スイーツ、冷凍食品 など)
- PB 商品 製造
- 食品 乾燥 加工
- 小ロット 食品 加工
- HACCP対応 工場
- ○○市 食品製造業
- ○○県 惣菜加工
一度上位表示が定着すれば、広告費をかけずに継続的にリードを獲得でき、食品製造業にとって安定した集客資産になります。
⑤メールマーケティングで関係性を育てる
メールマーケティングは、少人数でも取り組みやすく、効率よく複数の見込み客にアプローチできる施策です。
配信内容の例:
- 製造ライン増設・新設備導入のお知らせ
- 製造事例紹介
- 衛生・品質管理に関する取り組み
- 展示会・商談会の案内
定期的な情報配信がそのまま問い合わせのフックとなり、引き合いを取りこぼさなくなります。
⑥SNSで信頼と認知を拡大する
SNSは、食品製造業の「目に見えにくい価値」を視覚的に伝えるのに向いています。
工場の清潔さや品質管理、こだわりなどを写真や動画で発信することで、信頼構築と認知拡大の両方が期待できます。
食品製造業での運用テーマ例:
- 工場の衛生管理ルールの紹介
- 製造ラインの様子
- 過去の製造事例
- こだわり原料の紹介
- 社員紹介 など
SNSの活用を通じて「信頼できそう」という印象が積み重なることで、顧客からの信頼形成とブランド力向上に大きく寄与します。
集客状況を一度整理してみませんか?
無料で今の悩みを相談してみる
食品製造業者が集客に成功するためのポイント

前章の「食品製造業が陥りやすい失敗」を踏まえると、集客で成果を出すためのポイントは次の3つに集約できます。
- 「信頼」を軸にした情報設計を行う
- 販路を分散してリスクヘッジする
- 無理なく続けられる発信体制を整える
「信頼」を軸にした情報設計を行う
食品製造業の集客では、まず「安心して任せられる企業かどうか」を相手に明確に伝える仕組みづくりが欠かせません。
特にBtoBのバイヤーは、品質管理や製造体制を最優先で判断するため、次のような情報があるだけで問い合わせ率が大きく変わるでしょう。
- 衛生管理体制(HACCP・ISOなど)
- 工場規模・対応範囲
- 最低・最大ロット数や生産能力
- 過去の製造実績
安心材料になる情報をどれだけ整理して載せられているかが、集客成果に直結します。
販路を分散してリスクヘッジする
OEMや既存取引先からの紹介だけに依存すると、どうしても新規リードの獲得が不安定になります。
集客の観点では、以下のように複数のチャネルから問い合わせを得る仕組みを整えることが重要です。
- 自社ホームページ(SEO/指名検索対策)
- BtoBマッチングサイト(即需要のある層へ)
- SNS(商品や技術の可視化による認知獲得)
- 地域向け情報サイトや行政の販路支援施策
複数の流入経路を持つことで、外部環境に左右されにくくなり、新規リードの獲得が安定します。
無理なく続けられる発信体制を整える
食品製造の現場は忙しく、マーケティングに割ける時間はどうしても限られます。
最初から大規模な運用を目指す必要はありません。重要なのは「小さく始めて、淡々と続けられる仕組み」をつくることです。
例として以下のような発信体制が考えられます。
- 月1回のブログ更新
- Instagramに週一回の投稿
- メールマガジンを月一回配信
こうした最小単位の運用でも、半年~1年続けるだけで問い合わせ数に変化が出るでしょう。
無理なく続けられる体制づくりこそが最も重要な成功条件といえるでしょう。
自社が成果を出す条件を満たしているかチェックしてみましょう。
☐顧客の信頼感につながる情報を明確に発信できている
☐複数のチャネルからリードを獲得できている
☐SNSやブログなど、無理なく続けられる発信体制を構築できている
食品製造業の集客で大切なのは「信頼の積み上げ」と「継続」!

食品製造業の集客は、単に「良いものを作る」だけでは成果につながりません。
本記事で紹介した通り、WebサイトやSNS、Googleビジネスプロフィールなどの土台を整え、自社の魅力を言語化して発信することが最も重要です。
集客で成果を出すために押さえるべきポイントは次の3つです。
- 顧客に信頼感を与える情報を整理・発信する(衛生管理体制、実績、設備、加工対応など)
- 複数チャネルから問い合わせを得られる設計をつくる(ホームページ、広告、マッチングサイト、SNSなど)
- 無理なく続けられる情報発信体制を整える
これらを着実に実行することで、見込み客からの問い合わせが安定し、既存取引に依存しない強固な経営基盤が築けます。
まずは小さく始め、確実に続ける仕組みを作ることが、食品製造業における集客成功の近道です。
弊社では、Webマーケティングを活用し、「集客導線の設計」から「運用・改善」まで一貫してサポートしています。
自社の集客状況を一度整理してみませんか?
無料で今の悩みを相談してみる
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
-
ARTICLE
2025/10/30( 更新)
AIツール議事録ツールtl;dvとは?法人導入前に知るべきセキュリティ体制や料金、注意点を解説
AI
-
NEW ARTICLE
2026/02/20
リスティング広告の品質スコアとは?スコアの確認方法や上げ方をわかりやすく解説
広告広告運用
- リスティング広告
-
ARTICLE
2025/10/30( 更新)
Google広告の品質スコアを改善する方法を徹底解説!評価を高める要因と具体的な取り組み
広告Google広告
-
NEW ARTICLE
2026/02/19( 更新)
リスティング広告の文字数まとめ|Google広告・Yahoo!広告のルールを解説
広告広告運用
- リスティング広告


