
SNSのトラブル事例|企業が知っておくべき5つのリスクと対策方法
企業のSNS運用において、トラブルは避けて通れないリスクです。個人SNSとは異なり、企業アカウントでの失敗は会社全体の信頼失墜につながる可能性があります。
本記事では、企業SNS運営担当者が知っておくべきトラブル事例と対策を、運用マニュアル作成に活用できる形で解説します。初めて企業SNSを担当する方でも、安心して運用できる知識を身につけられるはずなので、ぜひ参考にしてください。
目次
企業SNSで起こりやすい5つのトラブル事例
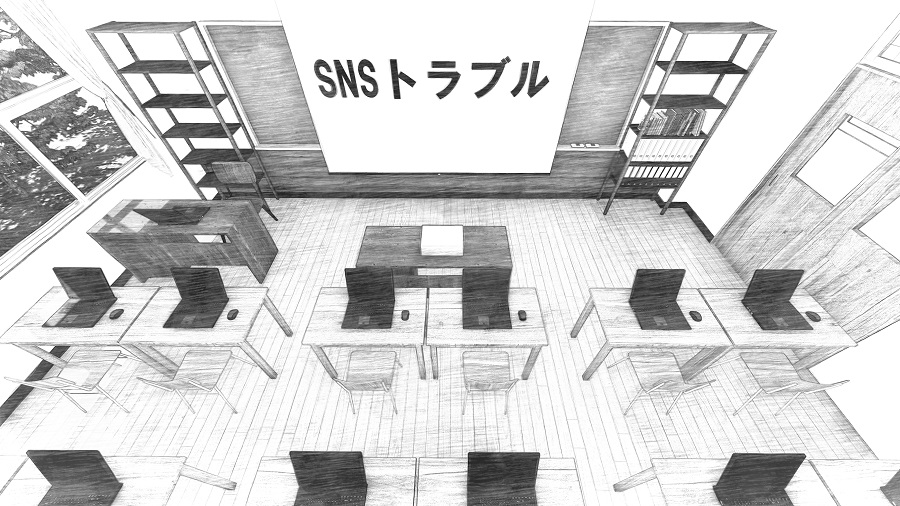
企業SNS運用では、個人アカウントでは起こりえない深刻なトラブルが発生します。実際の事例を知ることで、自社での予防策を立てやすくなるでしょう。
以下の5つのトラブルパターンは、どの企業でも起こりうるリスクです。事例を通じて、企業SNS特有の注意点を理解していきましょう。
情報漏洩によるトラブル【最重要リスク】
2023年、ある食品メーカーの公式アカウントで、新商品発表前の企画資料が写り込んだ写真が投稿されました。資料には競合他社との比較データや価格戦略が記載されており、瞬く間に拡散されて大きな問題となりました。
企業SNSでの情報漏洩は、意図しない形で発生することがほとんどです。背景に写り込んだモニター画面や書類、社内の様子から重要情報が漏れてしまうケースが後を絶ちません。個人情報保護法違反や営業秘密の漏洩は、法的責任を問われる可能性もあります。
炎上を招く不適切投稿【拡散リスク】
2024年、某アパレル企業が「働く女性応援キャンペーン」と称して、スタイルの良い女性社員のみを起用した投稿を行いました。「女性らしさ」を強調する表現が時代に逆行していると批判され、24時間で3万件を超える否定的なコメントが殺到しました。
企業の価値観や社会認識が問われる時代において、無自覚な偏見や配慮不足は一瞬で炎上につながります。ジェンダー、年齢、職業などに関する表現はとくに注意が必要で、多様性への配慮を欠いた投稿は企業イメージを大きく損なうリスクがあります。
著作権・肖像権侵害【法的リスク】
2023年、ある中小IT企業がInstagramで著名なイラストレーターの作品を無断使用し、権利者から損害賠償を求められた事例がありました。「ネットで見つけた画像だから大丈夫」という認識の甘さが、法的トラブルに発展したケースです。もちろん、AI生成画像も要注意です。元となる画像の著作権を問われることもあります。
フリー素材サイトの画像でも、商用利用が禁止されている場合があります。また、社員の写真を投稿する際も本人の同意が必要で、退職後の肖像権使用についても事前に取り決めが必要です。著作権・肖像権侵害は民事だけでなく刑事責任を問われる可能性もある重大なリスクです。
ステマ疑惑による信頼失墜【規制強化】
2023年10月のステマ規制強化後、「社員が自主的に自社商品を絶賛」という投稿スタイルが問題視されるようになりました。ある化粧品会社では、社員の個人アカウントでの商品紹介が「広告表示を隠したステマ」として批判を浴び、謝罪に追い込まれました。
現在のステマ規制では、社員や関係者による商品紹介も「広告」として明示する必要があります。インフルエンサーとのタイアップ投稿も同様で、「PR」「広告」「提供」などの表示が必須です。違反すると景品表示法に基づく措置命令の対象となり、企業の信頼性が大きく損なわれます。
アカウント乗っ取り・なりすまし【セキュリティリスク】
2024年、中堅商社の公式Xアカウントが乗っ取られ、仮想通貨詐欺の投稿が大量に発信される事件が発生しました。パスワードの使い回しが原因で、復旧まで3日間を要し、その間に1万人以上のフォロワーを失いました。
企業アカウントの乗っ取りは、詐欺の踏み台として利用されることが多く、フォロワーに被害を与える可能性があります。二段階認証の未設定や弱いパスワード、複数人での同一アカウント共有は格好の標的となります。セキュリティ対策の不備は、企業の管理能力そのものを疑われる要因にもなりかねません。
企業SNSトラブルが起こる3つの根本原因

企業SNSトラブルの多くは、偶発的な事故ではなく構造的な問題から発生します。根本原因を理解することで、効果的な予防策を講じることができるでしょう。
以下の3つの原因は、多くの企業で共通して見られる課題です。
- 運用ルールの未整備が招く無自覚な違反
- 複数人運用での責任の所在不明確化
- 最新トレンドへの理解不足
自社の現状と照らし合わせながら確認してみてください。
運用ルールの未整備が招く無自覚な違反
多くの企業では「SNSは簡単」という認識から、明確な運用ルールを設けずに開始してしまいます。個人SNSの延長感覚で投稿した結果、企業として不適切な内容を発信してしまうケースが頻発しています。
運用ルールが未整備だと、投稿者は「何が問題なのか」を判断できません。情報漏洩の境界線や、炎上しやすい表現、法的リスクのある行為について明確な基準がないため、善意の投稿が思わぬトラブルを招いてしまいます。
複数人運用での責任の所在不明確化
企業SNSは複数の担当者で運用することが一般的ですが、責任の所在が曖昧になりがちです。「誰が最終確認するのか」「問題発生時の対応者は誰か」が不明確だと、チェック機能が働かずトラブルが発生しやすくなります。
投稿権限の管理も重要な課題です。アルバイトや新入社員にも投稿権限を与えている企業では、経験不足による失敗や、企業の方針を理解していない投稿が問題となることがあります。
最新トレンドへの理解不足
SNSのトレンドや規制は急速に変化しますが、企業の対応が追いついていないケースが多く見られます。ステマ規制の強化や、各プラットフォームの利用規約変更への対応遅れが、思わぬトラブルを招いています。
炎上しやすいトピックも時代とともに変化しており、以前は問題視されなかった表現が現在では批判の対象となることもあります。最新の社会情勢やSNSの動向を把握していないと、知らないうちに「時代遅れ」な投稿をしてしまうリスクがあります。
トラブル回避のための企業SNS運用対策

企業SNSでのトラブル回避には、体系的な対策が必要です。個人の注意力だけに頼るのではなく、仕組みとして安全性を確保することが重要でしょう。
以下の対策を実践することで、リスクを大幅に軽減できます。運用マニュアル作成時の参考としても活用してください。
投稿前の必須チェックリスト【5項目】
投稿前のチェックは、トラブル防止の最重要ポイントです。以下の5項目を毎回確認することで、重大なミスを防げます。
- 機密情報や個人情報が含まれていないか
- 差別的表現や配慮を欠いた内容がないか
- 使用画像・動画の著作権・肖像権に問題がないか
- 広告・PR投稿の場合、適切な表示がされているか
- 誤字脱字や事実誤認がないか
このチェックリストは印刷して投稿担当者全員で共有し、投稿画面のそばに貼っておくことをおすすめします。急いでいる時ほど確認を怠りがちになるため、物理的にチェックを促す環境作りが効果的です。
炎上リスクを下げる投稿作成のコツ
炎上しにくい投稿を作るには、表現方法と投稿タイミングに配慮が必要です。「断定的な表現」ではなく「提案型の表現」を心がけることで、読み手に押し付けがましい印象を与えずに済みます。
社会的に敏感なトピックについては、投稿を避けるか、十分な検討時間を設けましょう。政治・宗教・ジェンダー・社会問題などは、企業として明確なスタンスがない限り言及しないのが賢明です。投稿タイミングも重要で、社会情勢が不安定な時期や競合他社でトラブルが発生している時期は、より慎重な姿勢が求められます。
複数人運用時の責任体制の構築方法
複数人でSNSを運用する場合、明確な役割分担と承認フローの設定が不可欠です。投稿担当者・確認者・最終承認者を明確に分け、必ず2名以上の目を通してから投稿する体制を構築しましょう。
緊急時の連絡体制も事前に整備しておく必要があります。休日や夜間にトラブルが発生した場合の対応者、エスカレーション先、判断権限の所在を明文化しておくことで、迅速な対応が可能になります。投稿権限の管理も定期的に見直し、退職者のアクセス権削除や権限レベルの調整を行ってください。
企業SNS運用マニュアルに必須の項目

運用マニュアルは、属人化を防ぎ継続的に安全なSNS運用を行うための重要なツールです。マニュアルがあることで、担当者が変わっても一定水準の運用品質を保てます。
効果的なマニュアル作成には、実務に即した具体的な内容が必要です。以下のポイントを参考に、自社の状況に合わせたマニュアルを作成してみてください。
投稿ガイドライン作成のポイント
投稿ガイドラインでは、「何を投稿すべきか」と「何を投稿してはいけないか」を明確に定義します。自社の業界特性や顧客層を考慮し、具体的な判断基準を設けることが重要です。
禁止事項については、グレーゾーンを残さず具体例を挙げて説明しましょう。「政治的発言は控える」ではなく「選挙に関する投稿、特定政党への支持表明、政治家の個人的な言動への言及は禁止」といった具合に、誤解の余地がない表現で記載してください。投稿のトーン&マナーについても、企業の価値観を反映した具体的な例文を用意しておくと効果的です。
緊急時対応フローの策定方法
SNSトラブル発生時の対応スピードは、被害の拡大を左右する重要な要素です。発見から1時間以内、24時間以内、1週間以内など、時間軸ごとの対応手順を明確にしておきましょう。
対応フローには、判断基準も含めて記載することが大切です。「どの程度の批判で謝罪投稿を行うか」「投稿削除の判断基準は何か」「外部機関への相談が必要なケースは何か」など、現場担当者が迷わずに判断できる基準を設けてください。関係者の連絡先リストも併せて整備し、緊急時に素早く連携できる体制を作りましょう。
定期的な運用見直しの仕組み作り
SNSの環境は常に変化するため、運用方針も定期的な見直しが必要です。月1回の振り返りミーティングや、四半期ごとのガイドライン更新など、継続的な改善サイクルを設計しましょう。
見直しの際は、投稿のエンゲージメント分析だけでなく、リスク管理の観点からも評価することが大切です。「炎上しそうになった投稿はなかったか」「情報漏洩の可能性があった場面はなかったか」など、トラブルの芽を早期に発見し、予防策を強化していく姿勢が重要です。
SNSトラブル発生時の初動対応手順

SNSトラブルが発生した場合、初動対応の質が最終的な被害の大きさを決定します。事前に対応手順を決めておくことで、パニック状態でも適切な判断ができるでしょう。
以下の手順は、どのようなトラブルにも応用できる基本的な流れです。自社の体制に合わせてカスタマイズし、緊急時にすぐ参照できるよう準備しておいてください。
24時間以内に行うべき4つの対応
SNSトラブルの初動24時間は、被害拡大を防ぐ最重要期間です。以下の4つの対応を迅速に実行することで、適切な危機管理ができます。
- 問題投稿のスクリーンショット保存と事実関係の確認
- 社内関係者への報告と対応方針の決定
- 必要に応じた投稿の削除または修正
- 公式見解の準備と、必要であれば謝罪投稿の実施
まず証拠保全を行い、感情的にならず冷静に事実関係を整理することが重要です。投稿削除は「隠蔽」と受け取られるリスクもあるため、慎重に判断しましょう。謝罪が必要な場合は、責任の所在を明確にし、再発防止策も併せて発表することで誠意を示せます。
謝罪投稿で避けるべきNG表現
謝罪投稿では、言葉選びが二次炎上を防ぐカギとなります。「ご指摘をいただき」「誤解を招く表現」など、責任転嫁と受け取られる表現は絶対に避けてください。
「心からお詫び申し上げます」「深く反省しております」など、真摯な姿勢を示す表現を使いましょう。具体的な改善策や再発防止策も併せて示すことで、単なる謝罪ではなく前向きな姿勢をアピールできます。謝罪文は複数人で内容を確認し、法務担当者がいる場合は事前にチェックを受けることをおすすめします。
再発防止策の立案と社内共有
トラブル解決後は、同様の問題を二度と起こさないための再発防止策を策定します。原因分析を徹底的に行い、個人の注意不足だけでなくシステムや体制の問題点も洗い出しましょう。
再発防止策は全社で共有し、SNS担当者以外にも周知することが大切です。類似部署での横展開や、新入社員研修への組み込みなど、組織全体でリスク意識を高める取り組みが必要です。また、防止策の効果検証も定期的に行い、必要に応じて見直しを行ってください。
まとめ|安全な企業SNS運用で信頼できるブランドを築こう

企業SNS運用におけるトラブルは、適切な知識と準備があれば十分に防止できます。重要なのは、個人SNSとは異なる企業特有のリスクを理解し、体系的な対策を講じることです。
本記事で紹介した事例と対策を参考に、自社に適した運用マニュアルを作成してください。トラブルを恐れるあまりSNSの可能性を活かせないのではなく、安全な運用基盤を築いた上で積極的に情報発信を行うことで、信頼できるブランドを構築できるでしょう。SNS運用の成功は、リスク管理から始まります。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
