
ディープフェイクとは?偽情報による危険性や見分け方を解説
ディープフェイクとは、AIにおけるディープラーニングを利用したフェイク動画や画像などのことを指します。日本では2020年に起きた、合成動画の事件で名前が知られるようになりました。
もともとは映画などの映像に関するAI合成技術でしたが、簡単に作成できることからSNSなどで悪用されるようになってしまいました。なりすましによる被害が多発しており、危険性があるフェイク動画と認識されてしまっています。
本記事では、そんなディープフェイクの危険性や見分け方、個人・企業の対策方法や法律に関する事柄をわかりやすく解説しています。ビジネスに有効活用できる例も紹介しているので、興味本位にでも本記事を読んでいただけると幸いです。
目次
ディープフェイクとは

ディープフェイクとは、AI(人工知能)技術を使って作成された偽の動画や音声のことです。「ディープラーニング(深層学習)」と「フェイク(偽物)」を組み合わせた造語で、本物と見分けがつかないほど精巧な合成コンテンツを指します。
従来の画像加工ソフトでは不可能だった、人物の表情や声を自然に再現できる点が特徴です。Webマーケティング業界でも、この技術による影響が拡大しており、正しい知識を持つことが重要になっています。
ディープフェイクの定義と仕組み
ディープフェイクは、大量の画像や動画データをAIに学習させ、人物の顔や声を別の人に置き換える技術です。機械学習の一種である「GAN(敵対的生成ネットワーク)」という手法が使われており、偽造者と検出者が競い合うことで精度が向上します。
作成に必要なのは、対象人物の顔が映った複数の画像や動画データです。SNSに投稿された写真だけでも、十分な学習データとして利用可能なため、誰でも被害に遭う可能性があります。現在では、スマートフォンアプリでも簡単にディープフェイク動画を作成できるまで技術が普及しました。
従来の画像・動画加工との決定的な違い
従来の画像加工では、PhotoshopやAfter Effectsなどのソフトで手作業により合成していました。しかし、ディープフェイクはAIが自動で学習・生成するため、専門技術がなくても高品質な偽造コンテンツを作成できます。
最も大きな違いは「動的な表現力」です。静止画の加工では実現困難だった、自然な表情の変化や口の動きまで再現できます。音声についても、数分間の録音データがあれば、まったく異なる内容を本人の声で話させることが可能です。
ディープフェイク技術が急速に普及した背景
ディープフェイク技術の普及には、AI技術の民主化が大きく影響しています。2017年頃から、GitHub上で無料のディープフェイク作成ツールが公開され、技術的な知識がなくても利用できる環境が整いました。
スマートフォンの処理能力向上により、高度な画像処理がモバイル端末でも可能になったことも要因の一つです。「FaceApp」や「Reface」といったアプリが数億回ダウンロードされ、エンターテイメント目的での利用が一般化しています。一方で、悪意のある利用も増加し、社会問題となっているのが現状です。
Webマーケターが知るべきディープフェイクの危険性

Webマーケティング業界では、ディープフェイクによる被害が急速に拡大しています。企業のブランドイメージ毀損や詐欺被害など、ビジネスに直接的な影響を与えるケースが増加中です。
とくに、SNSマーケティングやインフルエンサー施策を展開する企業にとって、偽コンテンツの見極めは必須スキルとなりつつあります。適切な対策を講じなければ、企業の信頼性や売上に深刻な損害をもたらす恐れがあります。
企業ブランドを狙った偽広告・なりすまし
有名企業の経営者や広報担当者になりすました偽動画が、投資詐欺や商品販売に悪用されるケースが頻発しています。実在する企業ロゴや公式サイトのデザインと組み合わせることで、消費者を騙す精巧な詐欺広告が作成されているのです。
2023年以降、日本国内でも大手企業の社長を装った仮想通貨投資の偽広告が問題となりました。被害企業は緊急声明を発表し、法的措置を検討するなど対応に追われています。一度拡散された偽コンテンツの完全削除は困難で、長期間にわたってブランドイメージに悪影響を与え続けます。
インフルエンサーマーケティングでの悪用リスク
インフルエンサーマーケティングでは、偽のレビュー動画や商品紹介コンテンツが作成されるリスクがあります。人気インフルエンサーの顔や声を無断使用し、実際には関与していない商品を推薦する動画が制作される事例が報告されています。
企業側は、契約していないインフルエンサーが自社商品を紹介している偽動画に気づかず、そのまま拡散してしまう危険性もあります。法的責任の所在が不明確になりやすく、トラブル発生時の対応が複雑化する傾向があります。事前の契約書面での取り決めや、定期的なモニタリング体制の構築が重要です。
ビジネスメール詐欺での音声偽装手口
CEO詐欺と呼ばれるビジネスメール詐欺では、経営陣の音声を偽装した電話による指示が新たな手口として登場しています。2019年にイギリスのエネルギー企業で発生した事件では、CEOの声を模倣した音声により約2,600万円の被害が発生しました。
日本企業でも、取締役や部長クラスの音声を偽装し、緊急の送金指示を行う詐欺が確認されています。とくに、リモートワークが普及した現在、音声通話での本人確認に依存する企業が標的となりやすい状況です。複数の確認手段を組み合わせた認証システムの導入が急務となっています。
ディープフェイクの見分け方|実践的な判断基準5選
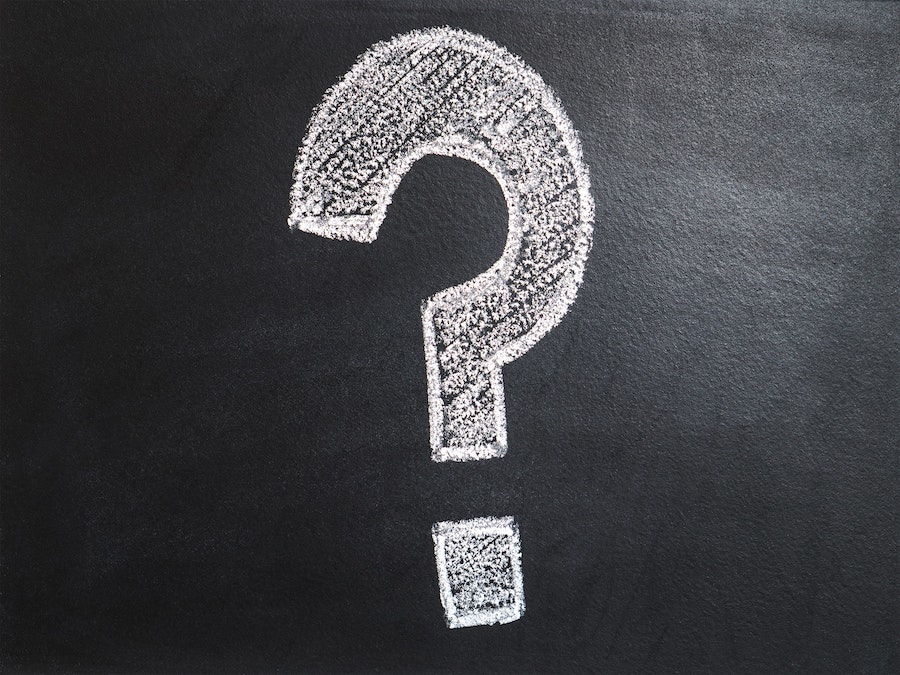
ディープフェイクの精度は年々向上していますが、注意深く観察すれば不自然な箇所を発見できます。Webマーケティング業務では、コンテンツの真偽を素早く判断する能力が求められるため、実践的な見分け方を身につけることが重要です。
以下の5つの判断基準を組み合わせることで、多くのディープフェイクコンテンツを識別できます。ただし、技術の進歩により、これらの特徴が目立たなくなる可能性もあるため、常に最新の情報をアップデートする姿勢が必要です。
目元・口元の動きから見抜くポイント
ディープフェイクで最も不自然になりやすいのが、目元と口元の動作です。瞬きの頻度が異常に少ない、または多すぎる場合は偽造の可能性があります。自然な瞬きは1分間に15〜20回程度ですが、ディープフェイクでは0回や40回以上になることがあります。
口元では、話している内容と唇の動きが微妙にずれる現象が見られます。とくに「ま行」「ば行」「ぱ行」の発音時に唇がしっかり閉じない、歯の見え方が不自然などの特徴があります。動画を一時停止しながら、コマ送りで確認すると判別しやすくなります。
音声の不自然さを聞き分ける方法
音声ディープフェイクでは、イントネーションや息継ぎのタイミングに違和感が生じることがあります。普段その人の話し方を知っている場合、口癖や話すリズムの違いから偽造を見抜けます。
機械的に生成された音声は、感情の起伏が平坦になりがちです。重要な発言や感情的な場面でも、声のトーンが一定に保たれている場合は注意が必要です。また、背景ノイズの品質が音声部分と異なる、音声の品質が映像と不釣り合いに良い場合も疑うべき要素となります。
情報源・配信元の信頼性をチェック
ディープフェイクコンテンツは、信頼性の低いアカウントや匿名のソースから拡散されることが多いです。公式アカウントからの発信でない限り、慎重に検証する必要があります。
同じ内容が複数の信頼できるメディアで報じられているかを確認しましょう。公式サイトやテレビ・新聞などの既存メディアで取り上げられていない「独占映像」は、偽造の可能性が高いです。また、投稿日時や位置情報などのメタデータも、真偽判定の重要な手がかりとなります。
ディープフェイクによる具体的な事件・被害事例
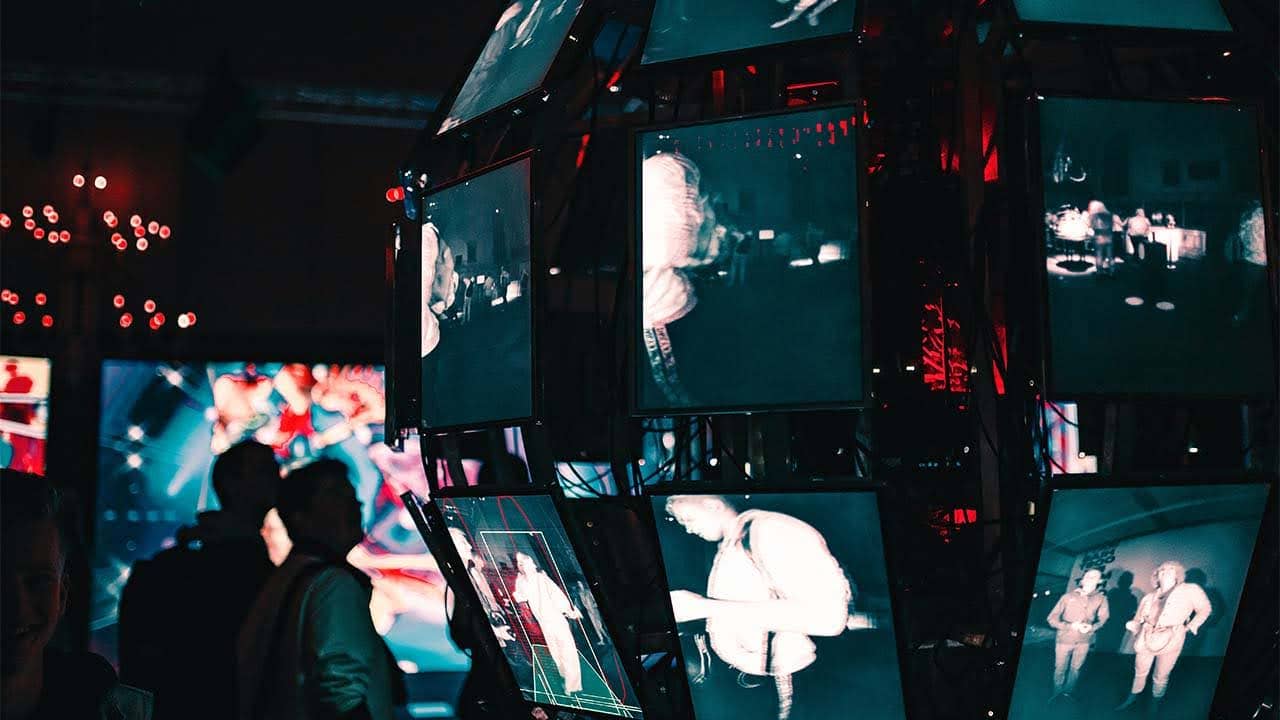
ディープフェイク技術による被害は、世界各地で深刻化しています。詐欺や名誉毀損、選挙干渉まで、その影響範囲は多岐にわたります。
実際の被害事例を知ることで、どのようなリスクがあるかを具体的に理解できます。企業のリスク管理担当者やWebマーケターにとって、これらの事例は対策立案の重要な参考資料となるでしょう。
海外で発生した大規模詐欺事件
2019年にイギリスで発生したエネルギー企業への詐欺事件は、ディープフェイク音声を使った初の大規模被害として注目されました。ドイツ本社のCEOの声を模倣した犯人が、イギリス支社の責任者に電話をかけ、緊急の資金移動を指示しました。結果として22万ユーロ(約2,600万円)が騙し取られています。
2020年には、香港の銀行でディープフェイク動画を使った詐欺事件が発生しました。取引先企業の取締役になりすましたビデオ通話により、3,500万ドル(約38億円)の融資契約が結ばれそうになりました。幸い、銀行側が詳細な本人確認を行ったため被害を回避できましたが、一歩間違えば史上最大規模の詐欺となっていた可能性があります。
日本国内でのディープフェイク犯罪事例
日本では2020年に、アダルト動画に女性タレントの顔を合成した映像を作成・販売した男性2人が逮捕されました。著作権法違反とわいせつ電磁的記録等頒布の罪で起訴され、ディープフェイクを使った犯罪の摘発事例として大きな注目を集めました。
2023年には、大手企業の経営者を装った仮想通貨投資の広告がSNS上で拡散されました。ソフトバンクグループやファーストリテイリングなど複数の有名企業が被害を受け、公式サイトで注意喚起を行う事態となっています。これらの偽広告は主に海外のサーバーから配信されており、完全な削除や犯人の特定が困難な状況が続いています。
企業が実際に受けた風評被害の実態
ディープフェイクによる風評被害は、金銭的損失以上に企業の信頼性に長期的な悪影響を与えます。偽造コンテンツが一度拡散されると、削除や訂正が困難で、ブランドイメージの回復に時間とコストがかかります。
アメリカでは、政治家のディープフェイク動画により支持率が大幅に下落した事例があります。後に偽造と判明しても、初期の印象が有権者の記憶に残り続けました。企業においても同様で、偽造された不祥事動画により株価が下落し、取引先との関係に悪影響が生じたケースが報告されています。迅速な対応と継続的な情報発信により、被害を最小限に抑える努力が重要です。
ディープフェイク対策|企業・個人ができる予防法

ディープフェイクの脅威から身を守るためには、技術的な対策と人的な対策を組み合わせた包括的なアプローチが必要です。企業では組織的な取り組みが、個人では日常的な注意が重要となります。
予防策を適切に実施することで、被害リスクを大幅に軽減できます。とくにWebマーケティング業務では、コンテンツの真偽判定が日常的に求められるため、実用的な対策知識を身につけることが重要です。
無料で使えるディープフェイク検出ツール
Microsoft社が開発した「Video Authenticator」は、動画のディープフェイク判定を行える無料ツールです。動画をアップロードすると、偽造の可能性を0〜100%のスコアで表示します。ただし、現在は限定的な提供となっており、一般利用には制限があります。
個人でも使いやすいのがDeepbrain AI社の「ディープフェイク検出器」です。アカウント登録により無料で利用でき、画像や短い動画の真偽判定が可能です。日本ラッド社の「SeekFakeβ」も企業向けサービスとして提供されており、より高精度な検出を実現しています。これらのツールは完璧ではありませんが、第一次判定として有効活用できます。
社内教育で徹底すべきチェック体制
企業では、全社員がディープフェイクの基本知識を身につける教育プログラムが必要です。広報・マーケティング・経理部門など、外部とのコミュニケーションが多い部署では、重点的な教育が求められます。
実際のディープフェイク事例を使った研修や、見分け方の実習を定期的に実施しましょう。また、緊急時の報告・対応手順を明文化し、全社員が迷わず行動できる体制を整備することも重要です。外部からの怪しい依頼や情報については、必ず複数の手段で本人確認を行うルールを徹底する必要があります。
SNS・広告運用時の注意点
SNSマーケティングでは、インフルエンサーやユーザー生成コンテンツの真偽確認が重要です。契約外のインフルエンサーが自社商品を紹介している動画を発見した場合、まず本人への確認を行いましょう。
広告配信では、競合他社による偽装広告の可能性も考慮する必要があります。自社ブランドや経営陣の画像が無断使用されていないか、定期的にモニタリングを実施してください。また、ユーザーからの問い合わせで偽広告の存在を知るケースもあるため、カスタマーサポート担当者への教育も欠かせません。
世界中で取り組んでいるディープフェイクの対策
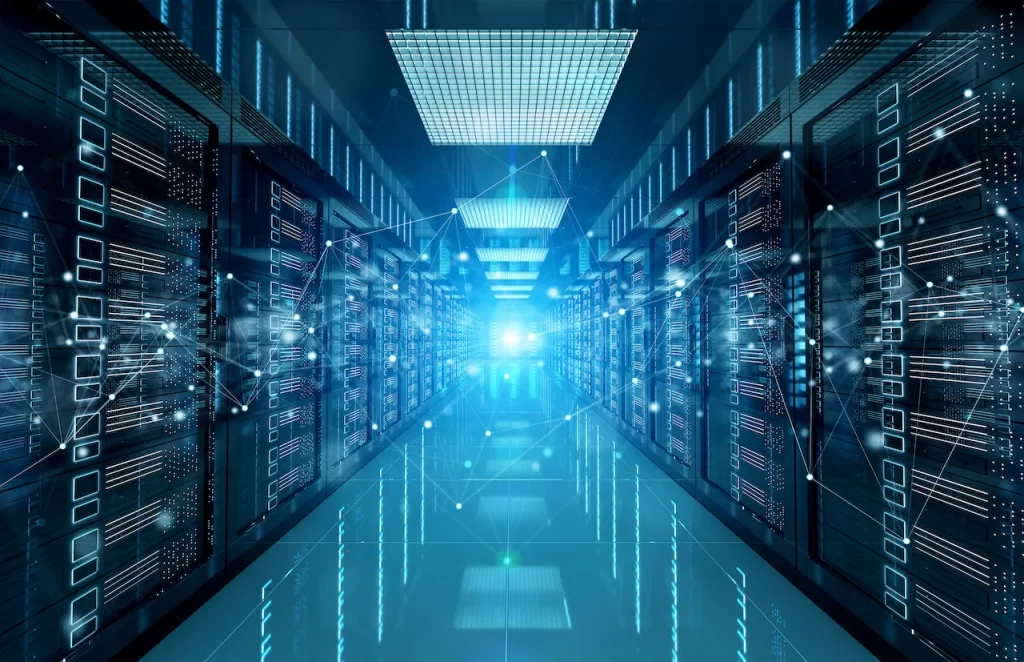
ディープフェイクを利用した事件が増加している中、どこで被害に合うかわかりません。そこで、ディープフェイク対策に取り組んでいる研究機関とその例を紹介します。
DeepFake Detection Challenge
「DeepFake Detection Challenge」とは、2019年9月にFacebook社をはじめとした大手企業や研究機関が立ち上げた「ディープフェイク動画の検知技術」を競うコンテストです。検知率が高いものこそ、優秀として賞金100万ドル用意され、2,000チーム以上からの応募がありました。
結果として、コンテスト用に公開していたディープフェイク動画の検知率は80%を超えたものの、その技術を識別を困難にする加工をした別のディープフェイクに応用したところ65%ほどに留まってしまいました。
このコンテストの検証のおかげで、未知のデータに関しては検知難易度が上がる証明になりました。結果としては検知技術の敗北ではありますが、問題点が浮き彫りになったからこそ次の研究に活かせているようです。
参照:Deepfake Detection Challenge | Kaggle
Spot the Deepfake
「Spot the Deepfake」は、Microsoftをはじめとした3つの機関によって制作された、ディープフェイクについて学習できるツールです。
10問形式のクイズになっており、どうやってディープフェイクを見分けるかを学べます。内容は初心者向けになっているので、一般の人でも気軽に利用できます。
Microsoft Video Authenticator
「Microsoft Video Authenticator」は、Microsoftが2020年9月に公開した「虚偽情報対策に向けた新たな取り組みについて」において発表された、ディープフェイク検知ツールです。
画像や動画に、微妙な色あせやグレースケールといった違和感がないかどうか分析し、ディープフェイク動画の確率や信頼度スコアをリアルタイムで表示してくれるという仕組みです。
参照:虚偽情報対策に向けた新たな取り組みについて|News Center Japan
インフォデミックを克服するソーシャル情報基盤技術
インフォデミックを克服するソーシャル情報基盤技術は、ディープフェイクに対抗するための技術を研究している日本団体です。
この研究は、「AIにより生成されたFM(フェイクメディア)がもたらす潜在的な脅威に適切に対処すると同時に、多様なコミュニケーションと意思決定を支援するソーシャル情報基盤技術を確立すること」が目的です。
Security(SEC)領域(国立情報学研究所 越前グループ)、Multimedia(MM)領域(大阪大学 馬場口グループ)、Computational Social Science(CSS)領域(東京工業大学 笹原グループ)という3領域の専門知識を結集させ、悪意あるディープフェイク対策の研究に取り組んでいます。
参照:研究概要 | インフォデミックを克服するソーシャル情報基盤技術
ディープフェイクを規制する法律と最新動向
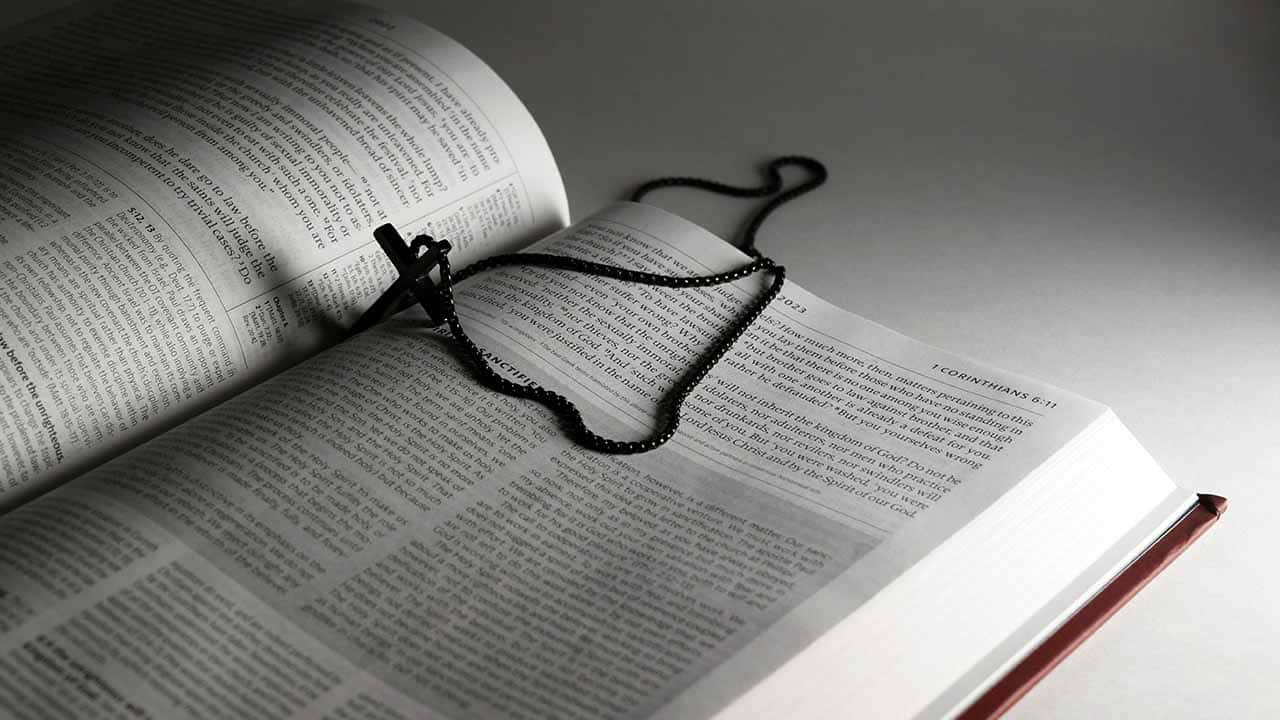
ディープフェイク技術の普及に伴い、世界各国で法規制の整備が急速に進んでいます。技術の進歩に法律が追いつかない状況もありますが、既存の法律を適用した摘発事例も増加中です。
Webマーケティング業務では、法的リスクを理解した上でコンテンツを取り扱う必要があります。とくに、海外展開を行う企業では、各国の法規制の違いを把握することが重要となります。
日本の法規制|名誉毀損・著作権法の適用
現在の日本では、ディープフェイクに特化した法律は存在しません。しかし、既存の法律を適用することで処罰が可能です。他人の顔を無断使用した場合は肖像権侵害、虚偽の内容で名誉を傷つけた場合は名誉毀損罪が適用されます。
著作権法違反も重要な適用事例です。2020年の摘発事例では、タレントの画像を無断使用したことが著作権法違反とされました。また、わいせつな内容のディープフェイク動画は、わいせつ物頒布等罪にも該当する可能性があります。企業の場合、取引先や顧客を騙す目的でディープフェイクを使用すれば、詐欺罪に問われるリスクもあります。
アメリカ・EU諸国の規制事例
アメリカでは州レベルでの規制が進んでいます。カリフォルニア州では2019年から、選挙期間中のディープフェイク動画配布を禁止する法律が施行されました。テキサス州やニューヨーク州でも、類似の規制が導入されています。
EU諸国では、2024年3月に「AI法」が可決され、ディープフェイクを含む生成AIコンテンツへの明示義務が課せられました。作成されたコンテンツがAI生成であることを明確に表示する必要があります。イギリスでも、Online Safety Actにより、ディープフェイクによる被害防止策の導入が義務化されています。これらの規制は、EU域外の企業にも適用される可能性があるため、グローバル展開する企業は注意が必要です。
2024年以降の法整備の方向性
日本政府は、AI戦略会議においてディープフェイク規制の検討を開始しています。2024年中に基本方針を策定し、2025年以降に具体的な法整備に着手する予定です。規制の方向性としては、悪意ある利用の処罰強化と、技術の健全な発展の両立が検討されています。
国際的な協力体制の構築も重要な課題です。ディープフェイクは国境を越えて拡散されるため、各国間での情報共有や捜査協力の仕組み作りが急務となっています。G7やOECDなどの国際機関でも、ディープフェイク対策のガイドライン策定が議論されています。企業は、これらの動向を注視し、コンプライアンス体制を適切に整備する必要があります。
ディープフェイクの正しい活用事例とビジネス応用

ディープフェイク技術は悪用が注目されがちですが、適切に活用すれば多くのビジネス価値を生み出せます。映像制作コストの削減や、新しい表現方法の創出など、クリエイティブ業界での可能性は無限大です。
重要なのは、倫理的なガイドラインを遵守し、関係者の同意を得た上で利用することです。透明性を保ち、視聴者に技術使用を明示することで、信頼性を維持しながら革新的なコンテンツを制作できます。
映画・CM制作での合法的な利用方法
ハリウッド映画では、故人の俳優を蘇らせたり、年齢の異なる演技を実現するためにディープフェイク技術が活用されています。「スター・ウォーズ」シリーズでは、CGとディープフェイクを組み合わせて若い頃のマーク・ハミルを再現しました。
CM制作では、多言語展開時の口パク調整に利用されています。BBCでは、英語を話すニュースキャスターが、スペイン語や中国語を自然に話しているように見える映像を制作しました。
この技術により、各言語圏向けに別々の撮影を行う必要がなくなり、制作費用の大幅削減を実現しています。ただし、利用時は必ず視聴者への技術使用の明示が必要です。
多言語対応・バーチャルキャスターでの活用
グローバル企業では、CEO による多言語メッセージ動画の制作にディープフェイク技術が使われています。日本語で収録したスピーチを、英語や中国語の口の動きに自動調整することで、自然な多言語コンテンツを効率的に制作できます。
バーチャルインフルエンサーやVTuberの分野でも活用が進んでいます。リアルタイムで表情や口の動きを生成することで、より自然なキャラクター表現が可能になりました。韓国では、AIニュースキャスターが24時間体制でニュース配信を行うサービスも開始されています。これらの取り組みは、人件費削減と品質向上を両立させる革新的な活用例です。
マーケティングでの倫理的な使い方
パーソナライゼーション広告では、個人の好みに合わせた商品説明動画を自動生成する技術が研究されています。ただし、プライバシー保護と明確な同意取得が前提となります。
教育・研修コンテンツでは、歴史上の人物による講義動画を制作することも可能です。企業研修では、創業者や著名な経営者による講話を再現し、社員教育に活用している事例があります。重要なのは、教育目的であることを明確にし、誤解を招かない配慮を行うことです。また、使用許可や肖像権の適切な処理も欠かせません。
まとめ|ディープフェイクの脅威に備える心構え

ディープフェイク技術は、Webマーケティング業界に大きな変革をもたらしています。偽造コンテンツによる被害リスクが増大する一方で、適切に活用すれば新しいビジネス価値を創出できる可能性も秘めています。
重要なのは、技術の本質を理解し、リスクと機会の両面を適切に評価することです。見分け方の習得、法規制への対応、社内体制の整備など、総合的な対策を講じることで、ディープフェイクの脅威から企業とブランドを守れます。技術の進歩に合わせて、常に最新の情報をアップデートし、柔軟に対応していく姿勢が、これからのWebマーケターには求められるでしょう。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
-
NEW ARTICLE
2026/02/12
リスティング広告の平均クリック率はどのくらい?目安やCTRを上げる方法を解説
広告広告運用
- リスティング広告
-
NEW ARTICLE
2026/02/10( 更新)
リスティング広告はキーワード選定が重要!洗い出し方や業種別の掛け合わせ例を解説
広告広告運用
- リスティング広告
-
NEW ARTICLE
2026/02/05( 更新)
SEOとリスティング広告の違いは?使い分けや併用による相乗効果についてを解説
広告
- リスティング広告
-
NEW ARTICLE
2026/02/04( 更新)
リスティング広告運用代行会社の選び方!確認すべきポイントや代行費用相場を解説
広告広告運用
- リスティング広告
