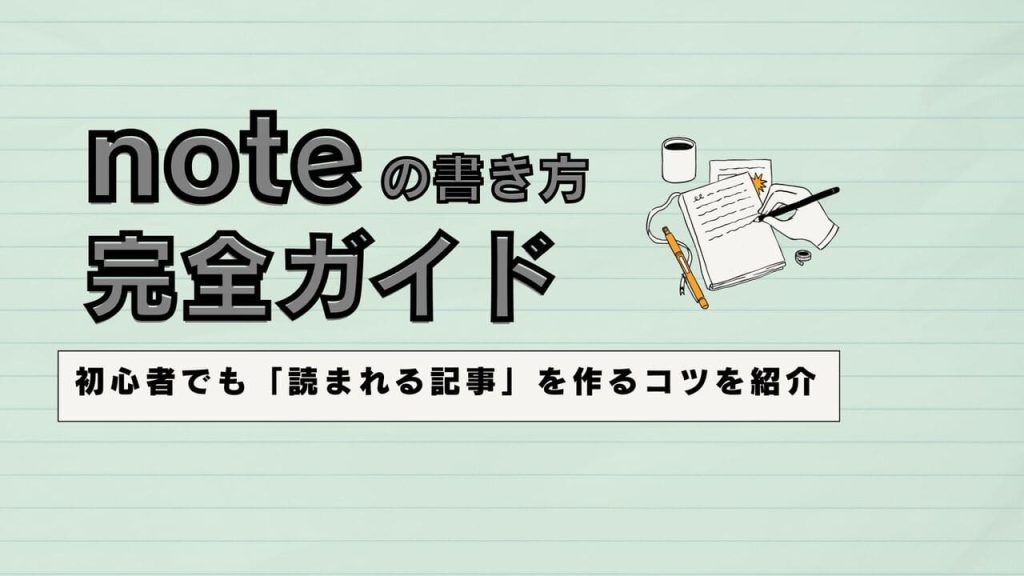
noteの書き方完全ガイド!テンプレ&コツで初心者でも読まれる記事へ【2025年最新】
「noteを始めてみたけれど、書き方がわからない」「せっかく投稿したのに、誰にも読まれない」「“スキ”やコメント、フォローが全然こない」――そんな悩みやモヤモヤを感じていませんか?
note初心者がまず目指すゴールは、「誰かに読まれる」「反応がもらえる」「自分の経験や思いが共感につながる」こと。そして、書くこと自体が楽しくなり、続けられるようになることです。
この記事では、
- noteで読まれる記事を作るための基本構成テンプレート(タイトル、リード、本文、目次)
- タイトルやリード文、自己紹介の書き方
- “スキ”やコメントなど、反応がもらえる記事づくりのコツ
- 読まれないnoteにありがちな特徴とその改善策
- PVを伸ばすための工夫
などを、初心者でもすぐ実践できるように、くわしく解説します。
自分の発信を誰かに届けたい、noteで共感やつながりを作りたい方にぜひ読んでいただきたいガイド記事です。
目次
noteとは?

noteは、誰でも簡単に文章・画像・音声・動画など、さまざまなコンテンツを発信できるメディアプラットフォームです。
「ブログとSNSのいいとこ取り」とも言われ、気軽に自分の考えや体験を発信したい人に多く選ばれています。
noteの主な特徴は次のとおりです。
- 登録・投稿がとても簡単:スマートフォンやパソコンからすぐにアカウントを作り、記事を投稿できます。
- 幅広いコンテンツに対応:テキストだけでなく、写真・音声・動画・PDFなどもアップロード可能です。
- 読者やクリエイター同士のつながりが生まれやすい:「スキ」やコメントでの応援や共感をきっかけにコミュニティが広がります。
- 収益化の仕組みがある:有料記事の販売やサポート機能を使って、自分の作品で収入を得ることも可能です。
また、noteはドメインパワーが高いため、Google検索でも上位に表示されやすいという強みがあります。記事を書くだけで検索からのアクセスが期待でき、多くの人に読まれるチャンスが広がります。
アカウント作成や記事投稿はすべて無料。初心者でも気軽に「自分だけのメディア」として発信を始められる、今注目のサービスです。
※ドメインパワーとは:サイトの信頼性や評価の高さを示す指標。この数値が高いほど、検索結果で上位表示されやすくなります。
初心者向けの始め方・使い方・機能などについて、詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
個人・企業・クリエイターの活用例
noteは、ユーザーの立場や目的に応じて柔軟に活用できるプラットフォームです。たとえば、個人ユーザーにとっては、日常の出来事や感情を綴る日記や、趣味や特技を記録・発信する場として利用されています。
料理や旅行、ライフスタイルに関する記事など、テーマは多岐にわたります。自分の言葉で自由に書けることから、気軽に始めやすい点が支持されています。
一方、フリーランス・副業をしている人やクリエイターにとっては、noteは作品公開の場やポートフォリオ代わりのメディアとしての側面も強くなります。
自身の体験やノウハウを記事として発信したり、有料noteとして販売したりすることで、収益化にもつなげやすく、ファンとの接点を作るためのツールにもなっています。
また、企業や団体による活用も広がっており、自社の理念やサービスの裏側を語る記事、社員インタビュー、採用広報の一環としてのコンテンツ発信などがよく見られます。
広告的な要素を抑え、「人となり」や「想い」を語る形式の記事が多く、読み手との共感を生みやすいのもnoteならではの特徴です。
このように、noteは「個人の自由な発信」から「企業のブランディング」まで、さまざまな目的に応じた使い方ができるプラットフォームとして、多くの人に選ばれています。
無料と有料記事の違い
noteでは、記事を無料で公開することも、有料で販売することも可能です。大きな違いは「読者がアクセスできる範囲」にあります。
| 無料記事 | 有料記事 | |
| 読者がアクセスできる範囲 | すべて閲覧可能 | 購入者のみ全文閲覧可能 |
| 目的 | 認知拡大・交流・ファンづくり | 収益化・プレミアムな情報提供 |
| 公開形式 | 全文公開 | 冒頭のみ無料、残りは有料などを選択可能 |
有料記事は「実体験から得たノウハウ」「専門的な知識」「マーケティング事例」など、読者に価値を感じてもらえる内容が向いています。
“読まれるnote”を増やしていくことが収益化にもつながる
noteには、有料記事の販売や月額制サブスクリプションの作成など、クリエイターが収益を得られる機能が備わっています。noteの収益には上限がないため、作品が話題になれば、その分だけ売上や収益も大きく伸ばすことが可能です。
ただし、「読まれるnote」を作るには、読者の信頼と満足度を高めることが何より大切です。
いきなり有料コンテンツだけを増やすのではなく、まずは無料記事で役立つ情報や体験談を丁寧に発信し、「無料でも価値がある」と感じてもらえる読まれるnoteを積み重ねていくことが、信頼関係を築く一番の近道です。
無理な煽りや「今だけ!」といった強いセールスは避け、読者の満足度を意識した“読まれるnote”を増やしていくことで、自然とファンも増えていきます。
有料noteを作るタイミングの目安としては、無料の記事を読んだ方から「もっと詳しく知りたい」「続きがあれば読みたい」といった声が届いたときです。
まずは、読まれるnote=信頼されるnoteを無料でしっかりと発信し、その上で有料記事を検討してみてください。
noteで収益化する方法や、収益化を成功させるコツについては、下記の記事で詳しく解説しています。興味のある方はぜひご覧ください。
はじめてnoteの記事を書く前に押さえておきたいポイント

ここでは、noteを書く前に考えておきたい3つのポイントをご紹介します。記事の構成や内容をスムーズに決めるための土台づくりとして、ぜひ押さえておきましょう。
ポイント①:誰に向けて書くのかを考える
noteを書く前に押さえておきたいポイントの一つ目は「誰に向けて書くのかを考える」ことです。
まず大切なのは「このnoteは誰に向けたものか?」を具体的にイメージすることです。たとえば、「同じ悩みを持つ社会人1年目」「副業に興味のある主婦」「自分と似た趣味を持つ人」といったように、読者像をできるだけ具体的に設定することで、読み手との距離感が縮まり、共感も得やすくなります。
読者像が明確になると、使う言葉・エピソード・構成も自然と決まりやすくなり、記事全体に一貫性が生まれます。
ポイント②:書く目的を明確にする
noteを書く前に押さえておきたいポイントの二つ目は「書く目的を明確にする」ことです。
何のために書くのかがはっきりしていないと、焦点がぼやけて伝えたいことが伝わりにくくなります。
たとえば「自分の考えを整理したい」「フォロワーを増やしたい」「読者に役立つ情報を届けたい」など、目的をあらかじめ整理することで、noteの方向性がはっきりして読みやすい記事になります。
また、目的によって記事のトーンも変わってきます。共感を求めるのか、ノウハウを提供するのか、記録として残すのか――自分がどんな価値を届けたいのかを考えることが大切です。
ポイント③:どんなジャンル・テーマで書くかを決める
noteを書く前に押さえておきたいポイントの三つ目は「どんなジャンル・テーマで書くかを決める」ことです。noteは自由度が高いため、何でも書ける反面、テーマ選びに悩む人も多いです。
まずは、自分が「書きたいこと」よりも「読者が知りたいこと」「共感してくれそうなこと」に注目してテーマを選ぶと、反応が得やすくなります。
たとえば、
- 自分の経験から得た学び
- 失敗談からの気づき
- 趣味や日常の中で感じたこと
など、等身大のテーマも十分に価値があります。自分の体験や視点を交えて書くことで、オリジナリティのあるnoteに仕上がります。
なお、以下の記事では、note初心者におすすめのジャンル例をまとめています。読まれるnoteをつくりたい、有料記事での収益化に関心がある方はぜひお読みください。
noteの書き方テンプレート【初心者必見】

「何から書けばいいかわからない」と悩むnote初心者の方は、とても多いのではないでしょうか。
そこでこの項では、noteを書くのが初めてでもすぐに実践できる「基本構成の型」をご紹介します。このテンプレートに沿って書けば、自然とnote記事が書けるようになります。
タイトルの付け方
noteが読まれるかどうかは、まずタイトルで決まると言っても過言ではありません。タイトルは記事の「顔」であり、読者が最初に目にするものだからです。
noteで効果的なタイトルをつけるには、次のポイントを意識しましょう。
- 内容が具体的に伝わること
- 数字や疑問形を使って興味を引くこと
- 感情やストーリー性が伝わること
内容が具体的に伝わること
noteに限らず、Web上の記事タイトルでは「この記事には何が書いてあるのか?」が一目でわかることが非常に重要です。
読者はまず、「自分に関係がある内容か?」「読むことでどんなメリットが得られるか」を瞬時に判断しようとします。その際、タイトルがあいまいだったり内容が想像しにくかったりすると、なかなかクリックされません。
明確なタイトルをつけることで、読者は記事の内容をすぐに把握でき、「自分に必要だ」と感じやすくなります。そうすると「読んでみたい」という気持ちが自然と生まれやすくなります。
数字や疑問形を使って興味を引くこと
タイトルに数字を使うことで、読者に興味を持ってもらうのも有効な方法です。数字は読み手の目を引きやすく、「どれくらいの情報量があるのか」「具体的な内容かどうか」を直感的に伝えられます。
例:使いやすい数字タイトルのパターン
- 「◯つのコツ」「◯ステップでできる」
- 「たった◯分で書ける」「◯日で身についたこと」
- 「◯年前の私に教えたい●●の話」
また、タイトルに疑問形を使うことで、読者の関心を引きやすくなります。
疑問文をタイトルに使うと、読者は「その答えが気になる」と自然に感じてくれます。
特に自分に関係がありそうな問いかけは、読者の共感を引き出しつつ、文章の続きが読みたくなる気持ちを強くします。
感情やストーリー性が伝わること
感情やストーリー性を含んだタイトルをつけることで、その記事が単なるハウツーではなく、「人の体験や心の動きが込められているもの」だと伝えることができます。
例:取り入れやすい感情キーワードの具体例
- 嬉しい/苦しい/悔しい/楽しかった/救われた/後悔/焦り
- 「本音」「知らなかった」「正直に言うと」など
ストーリー性を出すには、時系列・変化・結果をタイトルに含めるのがよいでしょう。
例:「noteを100本書いて得た”意外な成果”」「初noteがバズった話とその後」
リード文の書き方
リード文とは、本文に入る前の導入部分のことです。ここで読者の興味をつかめると、その先の記事を読み進めてもらうことができます。
書き方のポイントは以下の通りです。
- なぜこの記事を書いたのか(記事を書くことになった動機や背景)
- この記事で何が得られるのか(読者のメリット)
- 誰に向けて書いているのか(ターゲットを明確に示す)
たとえば、
「これは、note初心者だった私が、1記事目を書くまでに悩んだことと、実際に書けるようになった方法をまとめたものです」
このように「読者が読み続けるとプラスになる理由」を最初に伝えることが、読了率アップのカギになります。
構成の型を使った本文の書き方
noteで「何を書けばいいのか分からない」「話がまとまらない」などの原因の多くは、「構成=文章の設計図」ができていないことにあります。
このパートでは、note初心者でもスムーズに記事を書き進められるようになる3つの構成テンプレートをご紹介します。
- 体験談ベース型(自分の経験を参考にしてほしい場合)
- 問題解決・ノウハウ型(読者の悩みを解決したい場合)
- ストーリー+学び型(感情に訴え、印象に残る記事にしたい場合)
記事の目的に沿って、ご自身に合いそうな型を選んでみてください。
体験談ベース型
体験談ベース型は、リアルな経験を軸に構成する記事です。この型の最大の特徴は、「事実に基づいたストーリー」であるため、説得力と信頼感が自然に生まれる点にあります。
成功体験・失敗談・葛藤・成長など、感情の動きが含まれることで、読者の共感を得やすくなります。
以下のような順番でまとめるのがおすすめです。
- いつ・どこで・どんな体験をしたか(導入)
- なぜそれをやったのか(動機・背景)
- 何をどうやったか(具体的な行動)
- どうなったか(結果・学び)
- 読者への一言(気づき・メッセージ)
具体的には、「印象に残っている経験」を10個ほど書き出す
→その中から1つを選び、上記のテンプレートに当てはめて章立てを作る
→各パートに300~500文字ずつ書く といった手順で進めるとスムーズです。
問題解決・ノウハウ型
問題解決・ノウハウ型は、「読者が抱えている悩み」に対して、答えやヒントを提供する記事です。構成がロジカルで明快なため、検索からの流入をねらうSEO記事との相性が良いのが特徴だと言われています。
たとえば、「ブログ 始め方」「副業 ネタ」など検索ニーズが明確なテーマとの相性が良好です。
以下のような順番でまとめるのがおすすめです。
- よくある悩み・問題の提示(読者と同じ目線で)
- なぜそれが起きるのか(原因の分析)
- 解決策や考え方の提案
- 具体的な事例や方法(ツールや実践例を紹介)
- まとめと行動を促す言葉
具体的には、自分が過去に困ったこと・調べたこと・工夫したことを思い出す
→それを「同じ悩みを持つ読者に教えるつもり」でテンプレートに沿って構成する
といった流れで進めるとスムーズです。
ストーリー+学び型
ストーリー+学び型は、印象的なエピソードを軸に、最後に“気づき”や“学び”を届ける構成です。文章全体に物語性があり、読者の感情を動かしやすいため、記憶に残るnoteを作ることができます。
また、出来事を通して得た内面的な成長や人生観を描けるため、執筆者自身の「人間的な魅力」が最も伝わる型でもあります。読者との信頼関係を深めたい、長期的なファンを増やしたい場合に非常に効果的です。
以下のような順番でまとめるのがおすすめです。
- 印象的な出来事や一言(興味を引く導入)
- 当時の自分の心情や状況(背景)
- 転機になる出来事(変化の瞬間)
- 得られた教訓や気づき(学び)
- 読者へのメッセージや問いかけ(読後の余韻)
具体的には、
自分の「人生が変わった瞬間」や「今の考え方に影響を与えた出来事」を思い出す。
→上記のテンプレートに沿って、時間軸でストーリーを展開していく
といった流れで進めるとスムーズです。
感情の揺れや迷いを丁寧に描写すると、より読者の心を動かすことができます。
目次の作り方
noteの記事が長くなったときや、複数の見出しを使うときは、記事冒頭に目次をつけるのがおすすめです。
目次があることで、読者が記事全体の流れを把握しやすくなり、気になるセクションから読み始めることもできます。
目次作成の基本手順
noteには、記事内に自動で目次を生成できる機能が実装されています。
手順は以下の通りです。
- 記事作成画面でH2・H3などの見出しを設定する
- 目次を挿入したい位置で「+」マークをクリックし、「目次」を選択する
- 自動的に見出しリスト(目次)が生成される
作成された目次の各項目をクリックすると、目的のセクションにジャンプできます。 記事の全体像をつかみやすくなり、離脱防止や読了率アップにも効果的です。
この機能はPC・スマホ(アプリ・Web)どちらでも利用でき、無料記事・有料記事問わず利用可能です。
なお、目次を作成する手順については、noteの公式ヘルプセンターで詳しく紹介されています。
目次例
・noteとは?
・noteの書き方テンプレート
・プロフィール・自己紹介の書き方
・読まれるnoteを書くコツ
・よくある質問
目次づくりのポイント
見やすい目次を作成するために意識しておきたいポイントは、以下の通りです。
- 見やすくするために、目次項目は5〜7個程度にまとめる
- 記事内の見出しと同じ言葉を使うと、読者に親切
- 箇条書きや太字などで、情報を整理する
noteのプロフィール・自己紹介の書き方

noteでは、記事本文だけでなく「プロフィール」や「自己紹介」もとても重要です。読者は、これらをきっかけに「他の記事も読んでみよう」と思うきっかけになることがあるため、丁寧に書いておくのがおすすめです。
プロフィール欄向けテンプレート&例文
ここでは、noteのプロフィール欄(アカウント情報・マイページ)に使う短め・簡潔な自己紹介のテンプレートと例文をご紹介します。
【STEP1】名前(ニックネームでもOK)
【STEP2】居住地・職業・主な活動
【STEP3】noteで発信するテーマやジャンル
【STEP4】一言メッセージ(「よろしくお願いします」「お気軽にどうぞ」など)
日々の経験や小さな気づきをnoteで綴っています。自分のストーリーが誰かのヒントや励ましになれば嬉しいです。
普段は会社員/(主婦・学生などご自身に合わせて)をしながら、仕事や暮らしで感じたことを発信中。
どうぞよろしくお願いします!
※ご自身の属性や発信テーマに合わせてアレンジしてご利用ください。
自己紹介記事の冒頭用テンプレート&例文
次に、初めてのnote投稿や、「自己紹介note」を書くときに使える少し長めのテンプレートと例文を紹介します。
【STEP1】あいさつ・名前(ニックネームでもOK)
例:「はじめまして、○○(ニックネーム)です。」
【STEP2】自分の属性や活動内容(仕事・趣味・住んでいる地域など)
例:「普段は企画職ですが、休日はカフェ巡りや読書を楽しんでいます。」
【STEP3】noteを始めたきっかけや発信テーマ
例:自分の感じたことや、日々の小さな変化を言葉にしてみたくてnoteを始めました。
仕事やキャリアのこと、日常での気づき、たまには趣味や考えごとも交えながら発信していきます。
【STEP4】読者への一言・リアクションのお願い
例:「共感したら“スキ”やフォローしていただけると励みになります。これからどうぞよろしくお願いします!」
はじめまして。大阪在住の○○(ニックネーム)です。
主婦業のかたわら、週末は趣味でイラスト制作をしています。
自分の経験や気づきが誰かのためになればいいなと思い、始めました。
日々の暮らしや、小さな気づき、イラスト制作の過程や感じたことを、noteで発信していく予定です。
もし似たような経験や思いを持つ方がいれば、共感やヒントをお届けできたら嬉しいです。
コメントや“スキ”をいただけると、とても励みになります。これからよろしくお願いします!
※ご自身の属性や発信テーマに合わせてアレンジしてご利用ください。
「自分らしい」自己紹介文を作るコツ
noteで読者に覚えてもらい、ファンや共感の輪を広げていくには、「あなた自身の言葉」でプロフィールや自己紹介を書くことが重要です。ここでは、他の誰にも真似できない“自分らしさ”を表現するコツを紹介します。
コツ①:“じぶんだけ”の体験やストーリーを必ず盛り込む
自分がどんな人生を歩んできたか、これまでの体験やストーリーは、他の誰とも違う“自分だけの強み”です。
たとえば仕事や転職、学生時代の体験、家庭や趣味での挑戦など、どんな小さなことでもOKです。
自分の人生を一言で切り取ることで、誰にも真似できないプロフィールが生まれます。
コツ②:日常の習慣・価値観・こだわりを具体化する
毎日欠かさずやっていること、大切にしている信条や譲れない好きなことが、他の人との違いを生みます。ふだん何気なく続けていることや、「自分にとって大事な価値観」を言語化して、プロフィールに盛り込んでみましょう。
コツ③:“現在地”や“これから”をプロフィールに盛り込む
「今の自分が感じていること」「今後どんな記事を書いていきたいか」など、“現在地”や“これから”をプロフィールに盛り込むことで、読者の“共感”や“応援したい”気持ちも生まれやすくなります。
noteが読まれない理由と注意点

noteをせっかく書いたのに「なかなか読まれない」「反応が少ない」と感じることはありませんか?
実は、noteであまり読まれない記事には、共通する特徴があります。
この章では、noteが読まれない主な理由と、注意点を解説し、注目記事に近づくための小技もご紹介します。
noteで書いてはいけないこと・NG例
noteは自由に発信できる場所ですが、読者に不快感を与える内容や、運営ルールに違反する投稿は避ける必要があります。特に初心者のうちは、以下のような点には注意しましょう。
誹謗中傷や攻撃的な表現は避ける
特定の個人や団体を傷つける内容、悪口や暴言は、読んだ人を不快にさせるだけでなく、思わぬトラブルやアカウント凍結の原因にもなります。
「読み手がどう感じるか」を意識し、ネガティブな感情は日記など自分だけのメモにとどめるか、どうしても伝えたい場合は表現をやわらかく工夫しましょう。
【参照:心身の健康を守ってインターネットと付き合うために – noteヘルプセンター】
著作権侵害に注意する
他人の文章・写真・イラストなどを無断で転載すると、法律違反となり、noteのアカウント停止や損害賠償につながることもあります。
引用する場合は、出典を必ず明記し、自分の言葉で解説を加えましょう。画像や文章を使いたい場合は、著作者の許可をとるのが基本です。
【参照:創作を後押しする著作権の考え方 – noteヘルプセンター】
個人情報の流出に注意する
自分や他人の住所、電話番号、メールアドレス、勤務先など、個人が特定できる情報を書くと、思わぬトラブルや犯罪に巻き込まれるリスクがあります。
体験談を書くときも「誰が」「どこで」といった個人情報が特定されないような表現にしましょう。他者の情報は絶対に公開しないように注意してください。
【参照:アカウントの安全性を守るために – noteヘルプセンター】
広告・宣伝ばかりにならないようにする
自分の商品やサービスの宣伝だけの記事は、読者の信頼を失いやすく、すぐに離脱されてしまいます。note内では“役立つ体験談”や“気づき”が歓迎される傾向にあります。
宣伝要素が必要な場合でも、自分の体験や学び、役立つ情報もあわせて必ず盛り込み、「読者にとってどんなメリットがあるか?」を意識して記事を書きましょう。
不適切な画像や過激な内容は避ける
暴力的な表現、倫理的に問題のある内容は、読者を驚かせたり不快にさせるだけでなく、noteの規約違反で記事削除やアカウント停止となります。
「これを家族や友人が読んでも大丈夫か?」と一度立ち止まってチェックしましょう。不安な場合は投稿せず、運営ガイドラインも確認してください。
(参照)コミュニティガイドライン – noteヘルプセンター
読まれないnoteにありがちな特徴と改善策
noteをせっかく書いたのに「なかなか読まれない」「反応が少ない」と感じる方は少なくありません。ここでは、読まれにくいnoteにありがちな特徴と、それぞれの改善策を具体的に紹介します。
特徴①:タイトルが曖昧/興味をひかない
記事の内容が想像できないタイトルや、漠然とした表現では、そもそも読者にクリックしてもらえません。たとえば「日常のひとコマ」や「つぶやき日記」などは、何について書かれているのかが伝わりにくいです。
タイトルには、記事の主題や読者のメリットを明確に入れましょう。
特徴②:自己満足・ただの日記になっている
自分だけが分かる話や、日々の記録をそのまま綴っているだけでは、読者が共感したり参考にしたりするポイントが少なくなります。
同じ悩みを持つ読者を想定して、「この経験からどんな気づきを得たか」「読者にどんなヒントを届けたいか」を1~2行でもいいので意識して加えてみましょう。
特徴③:文章が長すぎて読みづらい
改行が少なく、文章が詰まっている/1文が長すぎる/段落ごとの切れ目がない記事は、スマホユーザーを中心に途中離脱の原因になります。
1文はなるべく60字以内を目安にまとめ、3〜4行ごとにこまめに改行しましょう。長くなりそうな場合は、見出しや箇条書きで分割するのも有効です。余白を意識した記事設計を心がけましょう。
特徴④:見た目が単調で情報整理されていない
ずっと同じ太さ・同じ大きさの文字が並ぶだけのnoteは、どこが大事なのか、どこで話題が切り替わるのかが分かりづらく、読む気が起きにくくなります。
大きめの見出しや箇条書きを活用し、重要な言葉は太字・下線で目立たせるのがおすすめです。画像やイラスト、区切り線(――など)を入れるのも効果的です。
「記事を3分の1読んでも、どんな話だったか思い出せる」くらい整理されているのが理想です。
特徴⑤:体験談や感情がなく、共感できない
情報やノウハウだけが並び、書き手の個人的な気持ちや失敗談・成功談が全くない記事は、他のnoteと差別化しづらく、読み手も感情移入しにくくなります。自分がそのとき何を感じたのか、少しだけ本音を交えてみてください。
「正直、最初は不安だった」「実は悔しい思いもした」など、一言添えるだけで、グッと親しみや共感が生まれます。
読者へのメッセージや問いかけがない
記事が一方通行で終わっていると、読者がリアクションしにくく、スキやコメントが集まりにくくなります。
記事の最後や途中で「もし同じ経験がある方がいれば、ぜひコメントで教えてください」「この記事が役立ったら“スキ”を押してもらえると嬉しいです」など、読者に呼びかける一言を添えてみましょう。
読まれるnoteを書くには?“スキ”やコメントがもらえる記事づくりのコツ

noteで「たくさんの人に読まれる記事」を書くためには、内容そのものだけでなく、伝え方や見せ方にも工夫が必要です。
これから紹介する5つのポイントを意識してnoteを書き上げることで、読者に共感されやすくなり、“スキ”やコメントなどの反応が増え、ファン化につながりやすい記事に仕上がります。
コツ①:書き終えた後に「読者の目」で見直してみる
読まれるnoteを書くコツの一つ目は、「書き終えた後に『読者の目』で見直してみる」ことです。
noteを書き終えたら、まずは自分で読み返してみましょう。その時、“書いた自分”の視点で読むのではなく、初めて読む読者の気持ちになってチェックするのがポイントです。
以下のような視点を意識すると、記事の質が上がります。
- 最初の数行で「面白そう」「読んでみたい」と感じられるか
- 話の流れが自然で、読みながら迷子にならないか
- 読み終えた後に、何か心に残る内容になっているか
「自分の目」から「読者の目」に切り替えるだけで、記事の完成度は大きく変わります。
コツ②:「自分の話」を「読者へのメッセージ」に変える
読まれるnoteを書くコツのニつ目は、「『自分の話』を『読者へのメッセージ』に変える」ことです。
noteでは、自分自身の経験を書く場面が多くありますが、ただ出来事を並べるだけでは、日記のようになってしまいがちです。大切なのは「この話が誰かの役に立つかもしれない」という視点を持って書くことです。
例:「転職して大変だった」→「転職で悩んでいる人へ。私の失敗から伝えたいこと」
少し読者を意識した言葉にするだけで、体験談が”読者へのメッセージ”に変わります。
コツ③:読みやすい見た目を意識する
読まれるnoteを書くコツの三つ目は、「読みやすい見た目を意識する」ことです。
noteはスマートフォンで読む人が多いため、「文章の内容」だけでなく、「見た目の読みやすさ」も大切な要素です。
以下のポイントを意識すると読みやすいnoteになります。
- 一文を短めにする(60字以内を目安に)
- 3~5行ごとに改行し、余白をつくる
- 箇条書きや太字を活用し、情報を整理する
読みやすさを整えることで、読んでもらえる確率が格段に上がります。
コツ④:文章の中に少しだけ感情をにじませる
読まれるnoteを書くコツの四つ目は、「文章の中に少しだけ感情をにじませる」ことです。
ノウハウ系の記事であっても、書き手の感情が少し見えるだけで、親しみやすさが生まれます。
たとえば次のような一言を添えてみてください。
- 「実は、この方法を試すときは少し不安もありました」
- 「今振り返ると、あの経験が自分を変える大きな転機だったと思います」
読者は情報そのものだけでなく、書き手の人柄にも自然と惹かれるものです。感情表現を適度に織り交ぜることで、文章にあたたかみが加わります。
コツ⑤:行動につながる一言を添える
読まれるnoteを書くコツの五つ目は、「次のアクションを促す一言を添える」ことです。
記事の締めくくりでは、読後に気持ちが動くような一言を添えることで、読者が次のアクション(感想のシェア、コメント・スキなど)を起こせるような後押しをしてみるのもおすすめです。
例:
- 「もし共感していただけたら、”スキ”やシェアで応援してもらえると励みになります!」
- 「似たような経験がある方は、ぜひコメントで教えてください!」
- 「このテーマについてX(旧Twitter)でも発信しています」
記事の内容が心に残った直後にそっと声をかけることで、読者との自然なつながりが生まれます。
読まれるnoteにするためのPVアップ術

noteのアクセスを伸ばすためには、中身の質と同じくらい「届け方の工夫」が重要です。読まれるnoteを目指すために、初心者でも今すぐ実践できるPV,アクセス数向上施策を紹介します。
施策①:検索されやすいタイトルを意識する
Googleなどの検索からnoteに人を集めたいなら、タイトルに「検索されやすい言葉」を入れることが大切です。
たとえば、「noteを始めたいけど、どう書けばいいんだろう」と思って調べるとしたら、Googleにどんな言葉を入れて検索するでしょうか。
おそらくこんな感じになるはずです。
- 「note 書き方」
- 「note 初心者」
- 「note 構成 例」
こうした「読者が実際に使う言葉=検索キーワード」をそのままタイトルに自然に入れておくことで、Google検索に表示されやすくなります。“読まれるnote”にするための戦略として、タイトル設計はとても重要です。
note内検索の特徴
note内の検索結果は、必ずしも「人気順」で表示されるわけではありません。「新着順」や、ユーザーの興味関心に合わせた表示が多いのが特徴です。
そのため、noteの記事はGoogleやYahoo!などの外部検索から見に来る人がとても多くなっています。
検索されやすいタイトルや、記事冒頭で「どんな内容か」をしっかり明示することが、より多くの読者に見つけてもらうコツです。
施策②:SNSで積極的にシェアする
noteは”書いて終わり”ではなく、SNSで紹介することでより多くの人に読まれるチャンスが広がります。実際に読まれるnoteの多くは、SNSでも積極的にシェアされています。
特にnoteは、X(旧Twitter)との相性が良いと言われており、ハッシュタグを使って投稿することで、多くの人の目に触れやすくなります。
具体的な投稿例:
- 「note書きました!初心者が1記事目を書くまでにやった3つのこと」
- 「note更新|自分の失敗体験から学んだことをまとめました」
施策③:note内に回遊導線を作る
「読まれるnote」には、他の記事への回遊導線が用意されていることが多いです。1本読んでくれた読者が、「この人の他のnoteも読んでみたい」と思ってくれるような仕掛けづくりも、アクセスアップには有効です。
そのための方法として、以下のような工夫があります。
たとえば、
- 記事末に関連noteへのリンクを掲載する
- マガジン機能でテーマ別にnoteをまとめる
- プロフィールに代表作やテーマ別記事のURLを設置する
例:「▼初心者向けnoteシリーズはこちら」「▼このnoteの前編はこちら」「プロフィールでは他のnoteもご紹介しています」
note内で、もう一本記事を読んでもらう導線を用意しておくことで、自然とアクセス数が伸び、ファンの獲得にもつながっていきます。
noteの書き方に関するよくある質問

この章では、noteを書き始めたばかりの方から寄せられる、よくある質問にお答えします。
質問①:noteは毎日書いた方がいい?
必ずしも毎日書く必要はありません。
noteは「継続して書くこと」が大切ですが、「毎日更新しなければ」と自分に負荷をかけすぎてしまうと、逆に続けにくくなってしまいます。
初心者の方であれば、まずは週1回、月2回など、自分のペースで無理なく始めるのがおすすめです。
継続して書く中で少しずつ文章力がつき、noteを書く習慣も自然と身についていきます。
質問②:PV(閲覧数)を増やすにはどうすればいいですか?
PVを増やすには「書き方の工夫」と「届け方の工夫」の両方が必要です。
- 読者に伝わりやすい構成や見出しを使う(本文中でテンプレートも紹介しています)
- タイトルに「検索されやすいキーワード」を入れる
- SNS(特にX)で積極的にシェアする
- 関連note同士をリンクでつなげ、シリーズ化する
- 読者とのコミュニケーション(スキ・コメント)も大切にする
どれもすぐに実践できる方法ですので、ぜひ試してみてください。
質問③:途中で書くのが止まってしまいます。どうしたらいいですか?
執筆中にふと手が止まる瞬間は、誰にでもあるものです。そんな時の対処法として、以下のような方法を参考にしてみてください。
- 完璧な文章にしようとせず、とりあえず書き出してみる
- 構成テンプレートを活用して、章立てだけ先に用意する
- 書きたいテーマをメモアプリなどに小分けでストックしておく
- 他の人のnoteを読んで、表現や構成を参考にする
noteは「途中保存」や「下書き管理」もできるため、自分のペースで進めていけば問題ありません。
質問④:noteで書いた記事は外部にシェアしても大丈夫ですか?
はい、noteに投稿した記事は自由に外部へシェアしても大丈夫です。
noteの各記事ページには、X(旧Twitter)・FacebookなどのSNSシェアボタンが用意されており、ワンクリックで投稿できます。
また、記事のURLをコピーして、LINEやブログなどに貼り付けても問題ありません。
特に初心者のうちは、SNSからの流入を得ることが、多くの人に記事を届けるきっかけになります。
質問⑤:アプリでもウェブ版でもnoteを書くことができますか?
はい、noteはアプリ版(スマホアプリ)でもウェブ版(ブラウザ)でも記事を書くことができます。どちらも基本的な投稿・編集機能は同じですが、それぞれ特徴や操作感に違いがあります。
アプリ版の特徴は以下の通りです。
- スマートフォンから手軽に執筆・投稿が可能
- 写真や動画のアップロードが簡単
- 通知機能が充実していてコメント・スキもリアルタイムで受け取れる
- 外出先やスキマ時間でも編集できる
ウェブ版の特徴は以下の通りです。
- パソコンの大きな画面でじっくり記事作成・編集ができる
- 文章の装飾やレイアウトがしやすい
- 画像やPDFファイルのアップロード、目次機能など拡張性が高い
日記感覚でサッと書くならアプリ、しっかり構成を作りこみたいときはウェブ版、と使い分けるのが、おすすめです。
質問⑥: 会員登録なしで、noteを書くことができますか?
いいえ、noteで記事を書くためには会員登録(アカウント作成)が必要です。
noteは「見るだけ」であれば会員登録なしでも可能ですが、投稿やコメント、スキ・有料記事の購入などアクションを行う場合は、無料の会員登録が必須となります。
なお、「noteを見るだけで使いたい場合」のメリットや注意点については、下記の記事で詳しくまとめています。
「会員登録せずにどこまでできる?」「見るだけ利用の制限や活用法が知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
質問⑦:noteを書きたいのですが、始め方がわかりません。
noteの始め方はとても簡単です。以下の手順で、初心者でもすぐに記事を書き始められます。
(1)会員登録を行う:公式サイトまたはアプリで「新規登録」を選び、メールアドレスやSNSアカウントでアカウントを作成します。
(2)プロフィールを設定する:自己紹介やアイコン画像を登録しましょう(後から編集することも可能です)。
(3)記事作成画面を開く:マイページの「投稿」ボタンをクリック(またはタップ)すると、記事エディターが立ち上がります。
(4)タイトル・本文を入力して公開:タイトル、本文、画像やリンクなどを自由に入力。プレビューで確認し、「公開」ボタンで記事がネットに公開されます。
なお、noteの登録方法、始め方については、以下の記事でくわしく解説しています。ぜひご活用ください。
note初心者でも読まれる記事は書ける!まずは1記事書いてみよう

noteは、誰でも自由に発信できる魅力的なプラットフォームです。けれど、「どう書き始めればいいのかわからない」と感じる初心者の方も多いかもしれません。
この記事では、noteの基本から読まれる記事を作るためのコツ、構成テンプレート、PV数を伸ばす工夫まで、初心者の方がすぐに実践できる情報をまとめました。
完璧を目指す必要はありません。どんな小さな気づきや体験も、自分の言葉で表現することに意味があります。 書き続けるうちに、あなたなりの伝え方や魅力がきっと見つかるはずです。
「自分には何も書けないかも…」と感じるときほど、まずは1記事投稿してみてください。
その一歩が、きっと新たな共感やつながりを生み出してくれるはずです。
-
NO.1/5
ARTICLE2020/09/08
note(ノート)とは?初心者向けの始め方・使い方・メリットを徹底解説
-
NO.2/5
ARTICLE2020/08/24
note(ノート)で収益化するには?有料記事で稼ぐ方法を紹介!
-
NO.3/5
ARTICLE2025/05/09
noteは「見るだけ」で足跡が残る?閲覧履歴や通知の仕組み、ログインなしで無料でできること
-
NO.4/5
ARTICLE2025/05/21
【2025年最新】noteで売れる人気ジャンル7選|初心者でも稼げる選び方を解説
-
NO.5/5
ARTICLE2024/04/26
SNSとは?利用するメリット・デメリットや代表的なSNSを一覧で紹介
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
