
α世代の消費行動5つの特徴|Z世代との違いと最新マーケティング戦略
2010年以降に生まれたα世代(アルファ世代)が、今後のマーケティング業界に与える影響をご存知でしょうか。現在0歳から15歳のα世代は、2025年に世界人口25億人に達し、2030年代には主要な消費者層となる注目の世代です。しかし、従来の子ども向けマーケティング手法では通用しない、独特な消費行動パターンを持っています。
本記事では、α世代の基本知識やZ世代との違いはもちろん、α世代の消費行動の特徴をわかりやすく解説しています。α世代をターゲットにした具体的なマーケティング戦略や、成功事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
α世代とは?2010年以降生まれの新世代の基本知識

α世代(アルファ世代)とは、2010年から2024年頃に生まれた世代を指します。2025年時点で0歳から15歳にあたる世代で、世界人口は約25億人に達すると予測されています。この世代は、生まれた時からスマートフォンやタブレット、AI技術が身近にある環境で育っているのが大きな特徴です。
α世代の命名者は、オーストラリアの世代研究者マーク・マクリンドル氏です。アルファベットのX世代、Y世代(ミレニアル世代)、Z世代の次にくる世代として「α(アルファ)世代」と名付けられました。この世代の多くは、ミレニアル世代を親に持つため、デジタル技術に対してオープンな家庭環境で育っています。
α世代の定義と年齢層:Z世代との明確な違い
α世代とZ世代(1997年~2009年生まれ)には、生まれた時代背景による明確な違いがあります。Z世代が「デジタル移行期」に幼少期を過ごしたのに対し、α世代は「完全デジタル社会」で育った世代です。
具体的な違いとして、Z世代はガラケーからスマートフォンへの移行を体験していますが、α世代は生まれた時からスマートフォンが存在していました。また、Z世代がSNSの普及を目撃したのに対し、α世代にとってSNSやオンラインコミュニケーションは「当たり前の日常」となっています。
α世代が育つデジタル環境の特殊性
α世代が育つデジタル環境には、これまでの世代にはない特殊性があります。生後1~3歳という早い段階でスマートフォンやタブレットに触れ、幼稚園や小学校でプログラミング教育を受ける世代です。
さらに重要なのは、コロナ禍による「ニューノーマル」を幼少期に体験していることでしょう。オンライン授業やリモートコミュニケーションが日常となり、物理的な距離に関係なく人とつながる体験を積んでいます。この体験により、α世代にとってオンラインとオフラインの境界は曖昧で、両方を自然に使い分ける能力を身につけています。
α世代の消費行動に見る5つの特徴

α世代の消費行動は、これまでの世代とは根本的に異なる特徴を持っています。まず重要なのは、現在の彼らの消費は「直接的な消費」ではなく「影響を与える消費」だという点です。実際の購買決定権は親世代が握っているものの、商品選択に強い影響力を持っています。
5つの特徴を理解することで、Webマーケターは効果的な施策を立案できるようになるでしょう。これらの特徴は相互に関連し合い、α世代独特の消費パターンを形成しています。
親世代が購買決定権を握る「代理消費」の実態
α世代の消費において最も重要なのが「代理消費」の構造です。実際にお金を支払うのは親世代(主にミレニアル世代)ですが、何を購入するかの選択には子どもであるα世代が強く関与しています。
この代理消費の特徴は、α世代が「欲しいもの」を親に伝え、親が「購入の可否」を判断する点にあります。そのため、マーケティング施策では「α世代の関心を引く」ことと「親世代の納得を得る」ことの両方が必要です。例えば、教育的価値のあるゲームや、親子で楽しめるコンテンツが選ばれやすい傾向があります。
デジタル体験を最優先する消費スタイル
α世代にとって、商品やサービスの「デジタル体験」は購買決定の重要な要素です。物理的な商品であっても、アプリ連携や拡張現実(AR)機能があるかどうかで魅力度が大きく変わります。
実店舗での買い物においても、QRコードでの情報取得やデジタルポイント機能など、デジタル要素が組み込まれた体験を好みます。純粋にアナログな商品よりも、何らかのデジタル要素が加わった「ハイブリッド商品」への関心が高いのが特徴的です。
ゲーム・エンタメ課金への積極的姿勢
α世代は、オンラインゲームやデジタルコンテンツへの課金に対して、これまでの世代よりも積極的です。ゲーム内アイテムや限定コンテンツを「価値あるもの」として認識しており、親に購入を依頼することに抵抗感がありません。
注目すべきは、α世代がゲームを単なる娯楽ではなく「友達とのコミュニケーション手段」として捉えていることです。友達と同じゲーム内アイテムを持つことで仲間意識を共有し、オンライン上での社会的地位を構築しています。この社交的価値により、課金への心理的ハードルが低くなっています。
サブスク・定額制サービスへの親和性
α世代は生まれた時からNetflixやSpotifyなどのサブスクリプションサービスが存在する環境で育っています。そのため、「月額料金を払って継続利用する」という消費モデルに違和感がありません。
この親和性は、親世代の消費行動にも影響を与えています。α世代が興味を示したサブスクサービスに対し、親も「毎月定額なら管理しやすい」として承諾するケースが多く見られます。とくに教育系やクリエイティブ系のサブスクサービスは、親の理解も得やすいため市場拡大が期待されます。
環境・社会問題への早期関心と消費判断
α世代は小学校でSDGs教育を受けており、環境や社会問題への関心が非常に高い世代です。商品を選ぶ際にも「環境に優しいか」「社会的に意味があるか」という視点で判断する傾向があります。
例えば、プラスチック包装の商品よりも紙パッケージの商品を好んだり、フェアトレード商品に興味を示したりします。親世代も子どもの価値観を尊重し、多少価格が高くても「意味のある消費」を選択するケースが増えています。この傾向により、企業の社会的責任(CSR)や環境配慮が、α世代向けマーケティングの重要な要素となっています。
α世代の興味関心とトレンド分析
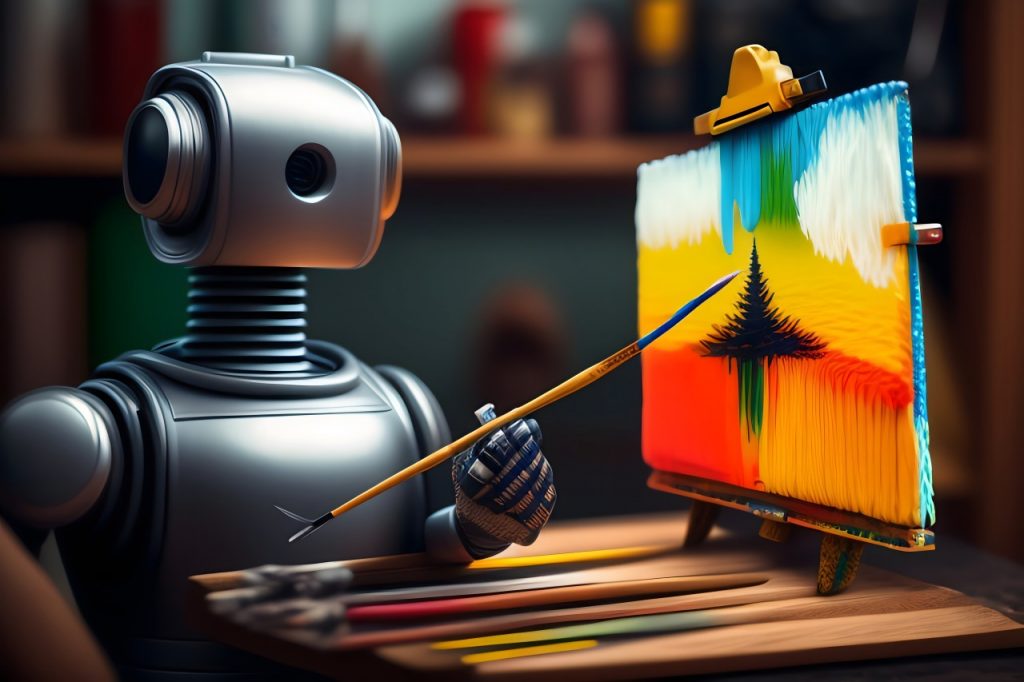
α世代の興味関心を理解することは、効果的なマーケティング施策立案の基盤となります。彼らの関心事は、従来の子ども向けコンテンツの枠を超え、大人顔負けの多様性と深さを持っています。
トレンド分析から見えてくるのは、α世代が「受動的な消費者」ではなく「能動的な参加者」であるという事実です。単に商品を購入するだけでなく、コンテンツ制作や情報発信にも積極的に関わっています。
ゲーム・メタバース空間での社交活動
α世代にとって、ゲームやメタバース空間は単なる娯楽ではなく「第二の生活空間」です。マインクラフトやRobloxなどのプラットフォームで、友達と一緒に建築をしたり、オリジナルゲームを制作したりしています。
この社交活動の特徴は、現実世界の友達関係とオンライン上の関係が密接に連動していることです。学校で話し合った内容をゲーム内で実現したり、ゲームで協力して作った作品を現実で自慢したりと、オンラインとオフラインが自然に融合しています。企業がα世代にアプローチする際には、この「社交機能」を重視したコンテンツ設計が重要になります。
TikTok・YouTube中心の情報収集スタイル
α世代の情報収集は、TikTokやYouTubeの動画コンテンツが中心です。文字情報よりも視覚的で直感的に理解できる動画を好み、短時間で多くの情報を取得する能力に長けています。
重要なのは、彼らが「受動的な視聴者」ではないという点です。気になった商品やサービスについて、複数のクリエイターの動画をチェックし、コメント欄で質問や意見交換を行います。さらに、自分でも商品レビュー動画を制作し、友達や家族に共有することも珍しくありません。この行動パターンから、α世代向けマーケティングでは「参加型コンテンツ」の重要性が浮き彫りになります。
AIツール・最新テクノロジーへの順応性
α世代は、ChatGPTや画像生成AIなどの新しいテクノロジーツールを「便利な道具」として自然に受け入れています。学習や創作活動でAIを活用することに抵抗感がなく、むしろ積極的に取り入れています。
この順応性は消費行動にも影響しており、AI機能が搭載された商品やサービスに対する期待値が高いのが特徴です。例えば、AI搭載の学習アプリや、音声認識機能付きのおもちゃなどへの関心が高く、従来の商品よりもテクノロジー要素のある商品を「より価値が高い」と判断する傾向があります。
α世代とZ世代の消費行動比較

α世代とZ世代の消費行動には、世代間の明確な違いが存在します。両世代ともデジタルネイティブという共通点がありながら、育った時代背景や価値観の違いにより、消費パターンが大きく異なっています。
この比較理解は、Webマーケターにとって施策の方向性を決める重要な指針となるでしょう。Z世代向けのマーケティング手法をそのまま適用するのではなく、α世代特有の特徴に合わせた調整が必要です。
購買決定プロセスの違い
Z世代は自分で稼いだお金で購買決定を行いますが、α世代は親世代を通じた「代理購買」が中心です。この構造的違いにより、購買決定プロセスが根本的に異なります。
Z世代の場合、「興味→調査→比較→購入」という個人完結型のプロセスですが、α世代は「興味→親への相談→親子での調査→親の承認→購入」という多段階プロセスになります。そのため、α世代向けマーケティングでは、子どもの興味を引くだけでなく、親の理解と納得を得られる情報提供が不可欠です。商品の教育的価値や安全性、コストパフォーマンスなど、親が重視する要素も同時に訴求する必要があります。
情報収集チャネルの変化
情報収集において、Z世代はInstagramやTwitterなどのテキストベースSNSも活用しますが、α世代は圧倒的に動画コンテンツ中心です。TikTokやYouTube Shortsでの短時間動画から情報を取得し、詳細が知りたい場合に長尺のYouTube動画を視聴します。
また、α世代は「友達からの情報」を非常に重視します。学校やオンラインゲームで友達が紹介した商品への信頼度が高く、インフルエンサーよりも身近な人の推薦を参考にする傾向があります。この特徴を活かすには、「友達同士でシェアしたくなる」要素を商品やコンテンツに組み込むことが重要です。
ブランドに対する価値観の相違
Z世代は「個性」や「自己表現」を重視してブランドを選びますが、α世代は「体験」や「機能性」を重視する傾向があります。ブランドの歴史やストーリーよりも、「何ができるか」「どんな体験が得られるか」に関心を持ちます。
さらに、α世代はブランドに対する忠誠心よりも「その時のベスト」を選ぶ合理性を持っています。同じカテゴリーでも、用途や状況に応じて異なるブランドを使い分けることに抵抗がありません。この価値観により、継続的な顧客獲得には、常に価値を提供し続ける努力が必要になります。
α世代をターゲットにしたマーケティング戦略

α世代向けマーケティングには、従来の子ども向けマーケティングとは異なるアプローチが必要です。彼らの高いデジタルリテラシーと独特の価値観を理解した戦略立案が成功の鍵となります。
効果的な戦略実行には、α世代の「今」と「将来」の両方を見据えた長期的視点が重要です。現在は親世代経由の消費ですが、将来的には自立した消費者になることを念頭に置いた関係構築が必要になるでしょう。
親世代(ミレニアル世代)へのアプローチが必須
α世代向けマーケティングにおいて、親世代であるミレニアル世代へのアプローチは避けて通れません。実際の購買決定権を持つ親世代の理解と支持を得ることが、成功の前提条件となります。
効果的なアプローチ方法は、「子どもの成長につながる価値」を明確に伝えることです。ミレニアル世代の親は、単なる娯楽よりも教育的意義や創造性育成につながる商品を好みます。また、親子で一緒に楽しめる要素や、子どもの安全性に配慮した設計も重要な訴求ポイントになります。情報提供の際には、子ども向けの楽しいコンテンツと、親向けの詳細な商品説明を並行して展開することが効果的でしょう。
デジタルネイティブに響くコンテンツ制作
α世代に響くコンテンツは、従来の一方通行型の広告ではなく、参加型・体験型の要素を持つ必要があります。彼らは受動的に情報を受け取るのではなく、能動的に関わりたがる世代です。
具体的なコンテンツ制作のポイントとして、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)技術の活用、ユーザー生成コンテンツ(UGC)の促進、インタラクティブな要素の組み込みなどが挙げられます。また、短時間で魅力を伝える動画コンテンツや、友達と共有したくなるビジュアル要素も重要です。コンテンツの更新頻度も高く保ち、常に新鮮な体験を提供することで継続的な関心を維持できるでしょう。
ゲーミフィケーション要素の活用方法
α世代にとってゲームは日常の一部であり、ゲーム的な要素を組み込んだマーケティング手法(ゲーミフィケーション)は高い効果が期待できます。ポイント獲得、レベルアップ、コレクション要素などを商品やサービスに組み込むことで、継続的な関心を維持できます。
重要なのは、単純にゲーム要素を追加するのではなく、α世代が求める「達成感」や「成長実感」を提供することです。例えば、学習アプリであれば進捗に応じたバッジシステム、商品購入であれば限定アイテムの獲得など、努力や継続に対する報酬システムを設計します。また、友達との協力や競争要素を加えることで、社交性も満たせるゲーミフィケーションが構築できるでしょう。
α世代向けマーケティングの成功事例

α世代向けマーケティングの成功事例を分析することで、効果的な施策のヒントを得ることができます。成功している企業やブランドは、α世代の特性を深く理解し、従来のマーケティング手法にとらわれない革新的なアプローチを実践しています。
これらの事例から学べるのは、α世代へのアプローチには「体験価値」と「参加性」が重要だという点です。単なる商品販売ではなく、α世代が主体的に関われるプラットフォームやコミュニティの提供が成功の鍵となっています。
ゲーム業界の先進的な取り組み
ゲーム業界は、α世代向けマーケティングの最先端を走っています。とくに注目すべきは、MinecraftやRobloxなどのプラットフォーム型ゲームが展開する教育連携の取り組みです。これらのゲームは単なる娯楽を超え、学習ツールとしての価値も提供しています。
Minecraftの「Minecraft Education Edition」では、歴史的建造物の再現や科学実験のシミュレーションなど、教育現場での活用を推進しています。この戦略により、親世代からの理解と支持を得ながら、子どもたちの継続的な利用を促進しています。また、ユーザー生成コンテンツ(UGC)を奨励し、α世代が「消費者」から「創造者」になれる環境を提供している点も成功要因の一つです。
教育×エンターテイメントの融合事例
教育とエンターテイメントを融合した「エドテック」分野では、α世代のニーズに応える革新的なサービスが次々と登場しています。例えば、プログラミング学習アプリの多くは、ゲーム感覚でコーディングを学べる仕組みを採用しています。
成功している教育系サービスの共通点は、「学習の成果が目に見える形で現れる」設計です。作成したプログラムで実際にキャラクターが動いたり、3Dモデルが完成したりと、学習成果が具体的な形で表現されます。また、作品を友達や家族とシェアできる機能も重要で、α世代の「承認欲求」と「社交性」を同時に満たしています。これらの要素により、継続学習率の向上と親世代からの高い評価を獲得しています。
α世代の消費行動を踏まえた今後の展望

α世代が本格的な消費者として市場に参入するのは2030年代以降と言われていますが、その影響力は既に現在から始まっています。彼らの価値観や行動パターンは、今後の消費市場全体を大きく変革する可能性を秘めています。
注目すべきポイントは、α世代が持つ「デジタルファースト」の思考と「社会貢献意識」の高さです。これらの特徴は、企業の商品開発やマーケティング戦略に根本的な変化を要求するでしょう。従来の「商品を売る」発想から「価値を共創する」発想への転換が必要になります。
また、α世代の消費行動は、AIやメタバース技術の発展と密接に関連しています。彼らが成人する頃には、現在では想像できないほど高度なデジタル体験が日常となっているでしょう。企業は長期的視点で技術投資を行い、α世代の期待に応えられる準備を進める必要があります。
まとめ|α世代の消費行動理解が成功の鍵

α世代の消費行動は、従来の世代とは根本的に異なる特徴を持っています。代理消費の構造、デジタル体験への期待、ゲーミフィケーションへの親和性、環境・社会問題への関心など、これらの特徴を理解することがマーケティング成功の出発点となります。
Webマーケターが心がけるべきは、α世代への直接アプローチだけでなく、購買決定権を持つ親世代への配慮も忘れないことです。子どもの興味と親の価値観の両方を満たすマーケティング戦略こそが、真の成功をもたらすでしょう。今から準備を始めることで、α世代が本格的な消費者となる時代に向けた競争優位を築くことができます。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
