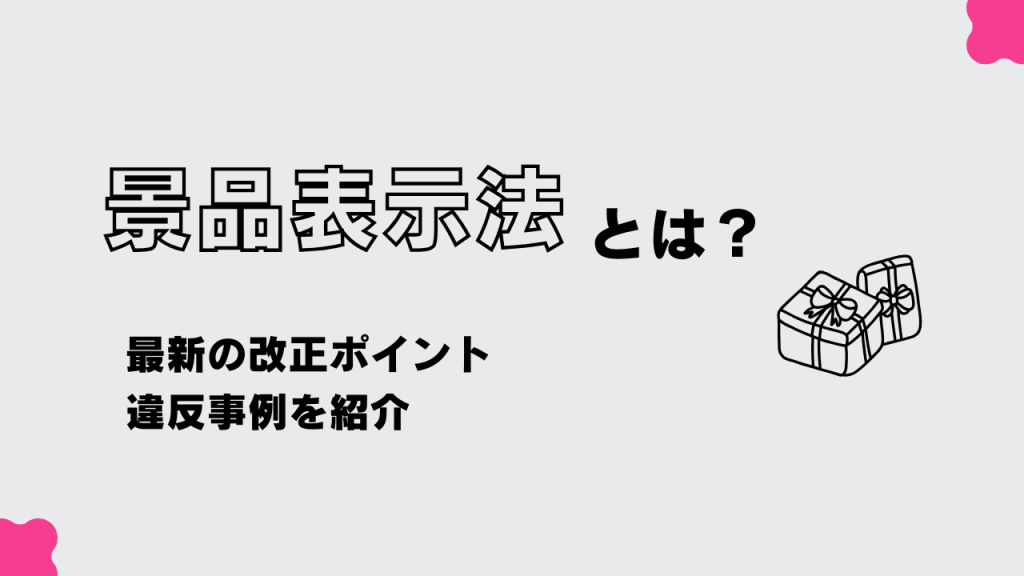
景品表示法とは?違反事例・罰則・プレゼント上限までわかりやすく解説
「この広告表現が法律違反にならないか不安だ」「キャンペーンのプレゼント上限はいくらまでOK?」「最新の法改正で何が変わった?」
こうした疑問をお持ちの、ECサイト運営者、広告担当者、インフルエンサーの方は多いのではないでしょうか。
この記事では、景品表示法の基本から最新の改正ポイント、具体的な違反事例、罰則まで丁寧に解説します。
目次
景品表示法とは

「景品表示法(けいひんひょうじほう)」とは、正式には 「不当景品類及び不当表示防止法」 と呼ばれる日本の法律です。消費者庁が所管しています(2009年9月までは公正取引委員会が所管)
この法律は、消費者を誤解させるような広告や、過大な景品(プレゼント・特典など)を提供することを防ぐために制定されています。
消費者が商品やサービスを選ぶときに、正確な情報に基づいて公正に判断できるようにすることを目的としています。
景品表示法は、企業だけでなく、個人事業主・インフルエンサー・ECショップ運営者など、消費者向けに商品やサービスを宣伝・販売するすべての人に関係します。
SNS投稿・ランディングページ(LP)・広告バナーなども対象です。
景品表示法違反となるケース

この章では、景品表示法における「違反」とは何か、どんなケースが該当するのかを解説します。
景品表示法では、大きく分けて以下の2つが禁止されています。
- 不当表示(消費者を誤解させる広告表示)
- 景品類の提供(課題なプレゼントや特典)
①不当表示(優良誤認・有利誤認など)
不当表示は、消費者に「実際よりもすごく良い商品・サービスだ」と誤解させる表示のことです。
優良誤認表示
自社の商品やサービスの品質・内容などを、実際よりも優れていると誤認させる表示のことです。
【例】
- 実際は国産ではないのに「国産牛」と表示
- 通常の米なのに「特Aランク」と表記
- ダイエットサプリについて効果が実証されていないのに「1週間で5kg減」と表示
根拠データをもとに客観的に説明できる表現にすることが重要です。
有利誤認表示
有利誤認表示とは、価格や取引条件(特典・サービス内容など)について、実際よりもお得・有利であると誤認させる表示のことです。
【例】
- 常時セール価格を「期間限定50%」と表示
- 定価で一度も販売していないのに「通常価格5000円→今だけ2500円」などと表記
- 送料込みを「送料無料キャンペーン中」と表示‗
その他誤認されるおそれのある表示(二重価格表示・おとり広告など)
不当表示には、優良誤認・有利誤認以外にも以下のようなものが含まれます。
| 表示の種類 | 概要 | 具体例 | リスク |
|---|---|---|---|
| 二重価格表示 | 実際よりも値引き幅が大きく見える価格表示 | 「通常価格10,000円 → 今だけ4,980円」と表示し、通常価格での販売実績がない | 有利誤認(措置命令・課徴金) |
| おとり広告 | 実際には販売する意思のない商品で客を誘引 | 「限定10台・半額セール」と広告し、実際には在庫がない | 不当表示(措置命令) |
| 比較広告 | 他社と比較して根拠のない優位性を示す表示 | 「他社製品より2倍効果」と広告するが、裏付けデータが存在しない | 優良誤認(措置命令) |
②上限を超えた景品類(プレゼント・懸賞)の提供
キャンペーンやプレゼント企画も、景品表示法の規制対象です。 事業者が過大な景品を提供すると、消費者は景品に惑わされて、本来の価値が低い商品や割高な商品を購入してしまう可能性があります。
また、過大景品の競争が激化すると、事業者は商品そのものの質向上に力を入れなくなり、消費者にさらなる不利益が及ぶ悪循環が生まれます。
なお、景品の種類によって上限額は異なります。
| 景品の種類 | 概要 | 取引価額 | 景品の上限額 | 景品総額の上限 |
|---|---|---|---|---|
| 一般懸賞 (抽選・くじ) | フォロー&リツイート抽選、購入者限定抽選など | 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | |||
| 共同懸賞 (複数企業合同) | 商店街やイベントでの合同キャンペーンなど | (取引価額によらず) | 30万円 | 売上予定総額の3% |
| 総付景品(ベタ付け) (全員に配布) | ノベルティ、購入特典、来店プレゼントなど | 1,000円未満 | 200円 | 制限なし |
| 1,000円以上 | 取引価額の20% |
たとえば、5,000円の商品を購入した人に抽選で景品を贈る場合、上限は10万円です。もし全員に贈る場合は、上限は取引価額の20%(5,000円 × 20% = 1,000円)となります。
SNSキャンペーンやECサイトの購入特典なども対象になるため、景品提供の方法と金額の上限を必ず確認しましょう。
アンケート謝礼やキャッシュバックも対象
「景品」と聞くとモノを想像しがちですが、金銭・ポイント・電子マネーなどの金銭的価値を持つものもすべて規制の対象となります。
- アンケート回答でギフトカードを配布
- 商品購入後にキャッシュバックを行う
- SNS投稿でギフト券を進呈する
特にキャッシュバックやポイント付与は「景品ではなく値引き」と誤認されやすいため、提供条件・上限金額・期間を明確に表示しておくことが重要です。
令和5年改正 景品表示法のポイント

景品表示法は令和5年に改正され、令和6年(2024年)10月1日に施行されました。
この改正は、事業者の自主的な改善を促しつつ、違反行為に対する抑止力を強化することを目的としており、
- 事業者の自主的な改善努力を促す制度創設
- 違反への抑止力強化
- 法執行体制の充実
の3つを柱としています。
①事業者の自主的な改善努力を促す制度の創設
一つ目の柱は、自主改善の促進です。改正内容は次の通りです。
是正措置計画制度(第26~33条)
疑わしい表示(優良誤認表示など)を行った事業者が是正計画を策定して申請し、内閣総理大臣の認定を受けると、措置命令や課徴金納付命令の適用を受けずに問題を迅速に改善できます。(通称「確約手続き」)。
返金方法の柔軟化(第10条)
従来は現金での返金が原則でしたが、改正により電子マネー等の支払い手段も認められるようになりました。
②違反行為への抑止力強化
二つ目の柱は、違反行為への抑止力強化です。
課徴金算定の推計制度(第8条第4項)
売上額を正確に把握できない場合でも、推計による課徴金の算定ができるようになりました。
直罰の導入(第48条)
優良誤認表示・有利誤認表示について、100万円以下の罰金を直接課すことが可能になりました。従来は行政命令(措置命令)を経ないと罰則が科されませんでしたが、違反行為そのものが直接の罰金対象となりました。
③法執行体制の充実・透明性の向上
3つ目の柱は、法執行体制の充実・透明性の向上です。
国際対応(第41~44条)
越境ECや海外広告に関する違反行為にも対応できるよう、海外事業者への送達や、外国当局への情報提供が可能になりました。
適格消費者団体による資料開示要請(第35条)
適格消費者団体が事業者に対して「表示内容を裏付ける資料」を開示するよう要請できるようになりました。
事業者が取るべき対応
令和5年の改正を受け、事業者はこれまで以上に自社の広告や商品表示に対するコンプライアンス体制を強化する必要があります。
表示内容を支える合理的な根拠を明確にし、関連資料を適切に準備・管理することが不可欠です。
広告・マーケティングにおける景品表示法の注意点

この章では、実際の広告運用やマーケティング活動で特に注意すべき点を解説します。
ステマ(ステルスマーケティング)は景品表示法違反
2023年10月から、広告であることを隠す「ステルスマーケティング(ステマ)」は景品表示法違反(不当表示)となりました。
報酬や商品提供を受けて投稿する場合は、広告・PRであることを明記することが必須です。
【違反例】
- インフルエンサーが「自腹で購入」と装って商品紹介(実際は企業から無償提供)
- モニター投稿なのに「PR」の表記がない
- クチコミサイトで企業が自社商品の高評価レビューを投稿
これらはすべて、消費者を欺く表示として措置命令の対象になる可能性があります。「PR」「広告」「提供:●●社」など、消費者が広告だと明確にわかる表示が必要です。
広告文・チラシ・Web表記でのNG表現とOK表現
広告やランディングページの表現でも、消費者に誤解を招くコピーは避けなければなりません。
<H4>根拠のない「No.1」「日本初」などの最上級表現
「No.1」「日本初」「世界一」「業界トップ」といった最上級表現は、景品表示法上、非常に厳しくチェックされます。
使用する場合は調査データによる合理的な根拠が必須です。
【NG例】
- 「顧客満足度No.1!」(※根拠データの記載がない、または「※自社調べ」となっている)
【OK例】
- 〇〇部門 顧客満足度No.1(※株式会社〇〇リサーチ 2024年度〇〇業界調査)
※「いつ」「どの範囲で」「何の」No.1なのかを、第三者機関による客観的な調査データとともに、表示のすぐ近くに明記する必要があります。
「絶対」「必ず」などの断定表現
「絶対」「必ず」「100%」「完璧」といった表現は、実際には効果や結果を保証できないため、優良誤認に当たる可能性が高い表現です。
【NG例】
- 「飲むだけで絶対にやせるサプリ」
【OK例】
- スリムな体を目指す方をサポートするサプリ
※効果や結果を保証する表現は避け「サポートする」「目指す」といった表現にとどめるか、「※効果を保証するものではありません」といった打消し表示を適切に行う必要があります。
医薬品的な効能・効果の表現(主に健康食品・化粧品)
健康食品や化粧品は医薬品ではないため、「病気が治る」「症状が改善する」「若返る」といった表現はできません(薬機法違反にもあたります)。
【NG例(健康食品)】
- 「飲むだけで高血圧が治る」
- 「アトピーが改善する水」
【OK例(健康食品)】
- 「高めの血圧が気になる方をサポート」
- 「毎日の健康維持を応援します」
【NG例(化粧品)】「塗るだけでシミが消える美容液」「アンチエイジング(老化防止)」
【OK例(化粧品)】「(メラニンの生成を抑え)シミ・そばかすを防ぐ」「(年齢に応じた)エイジングケア」
わかりにくい「打消し表示」
「※個人の感想です」「※効果には個人差があります」といった注釈(打消し表示)も規制対象です。 メリットを強調する表示に対し、注釈が極端に小さい、離れすぎている場合、不当表示とみなされます。
【NG例】
「1か月で-10kg」と大きく記載し、ページ最下部に小さなグレー文字で「※適切な運動と食事制限を併用したAさんの例です」と記載する。
【OK例】
「1ヶ月で-10kg!(※Aさんの例。適切な運動と食事制限を併用した場合)」
※打消し表示はメリット表示と一体として認識できるよう、明瞭な大きさ・場所で記載する必要があります。
割引・値引き・二重価格表現
値引きやセールの表現も違反が生じやすい領域です。
【NG例】
- 「通常価格10,000円 → 今だけ4,980円」と表示し、実際には「通常価格」での販売実績がない。
- ずっと同じ価格なのに「今だけ●●円引き」と表記する。
比較価格(通常価格など)には、実際に販売実績がある価格を使用し、セールは期間・条件を明示する必要があります。
景品表示法の違反事例集

この章では、消費者庁が公表している景品表示法の違反事例集をまとめました。
「国民生活センターのお墨付き」と誤認させた粉末飲料
国民生活センターによる試験で「ポリフェノール含有量日本一」と認められたかのように表示した粉末飲料が、根拠のない優良誤認表示として措置命令を受けました(平成25年12月10日)。
実際には、国民生活センターが当該商品の試験を行った事実はなく、パンフレット上で「第三者機関による評価」を装っていた点が問題視されました。
この事例は、存在しない試験結果や認定を根拠に「No.1」「認められた」と訴求する行為が、優良誤認に該当する典型例です。
信頼性を演出するための過剰な表現は、たとえ意図的でなくとも処分の対象となるリスクがあります。
根拠のない「抗シワ効果」をうたった化粧品
「使用すると直ちにシワが改善する」といった表示を行った化粧品が、合理的な根拠を欠く優良誤認表示として措置命令を受けました(平成24年7月19日)。
事業者はチラシ上で抗シワ効果を強調していましたが、消費者庁が求めた裏付け資料を提出したものの、提示内容はいずれも表示の根拠として合理的と認められないものでした。
本件は、科学的・客観的な根拠がないまま効果を断定的に訴求した典型例です。効果・効能を示す場合には合理的な根拠を明示できることが必須です。
常態化した「期間限定割引」を装った通信講座
「今だけ1万円割引」と期間限定を装った通信講座の広告が、実際には常時割引を行っていた虚偽の価格表示として措置命令を受けました(平成27年3月20日)。
ウェブサイト上では、特定期間内の申し込みに限り「正規受講料から1万円引き」と表示していましたが、実際には平成22年から26年にかけてほとんどの期間で同様の割引を継続していました。
このように、恒常的に実施している値引きを「期間限定」「今だけお得」と示す行為は、景品表示法の有利誤認表示に該当します。
消費者に「今申し込まなければ損をする」と誤認させる表示は、価格訴求を用いた典型的な違反事例です。
景品表示法違反時の罰則・措置
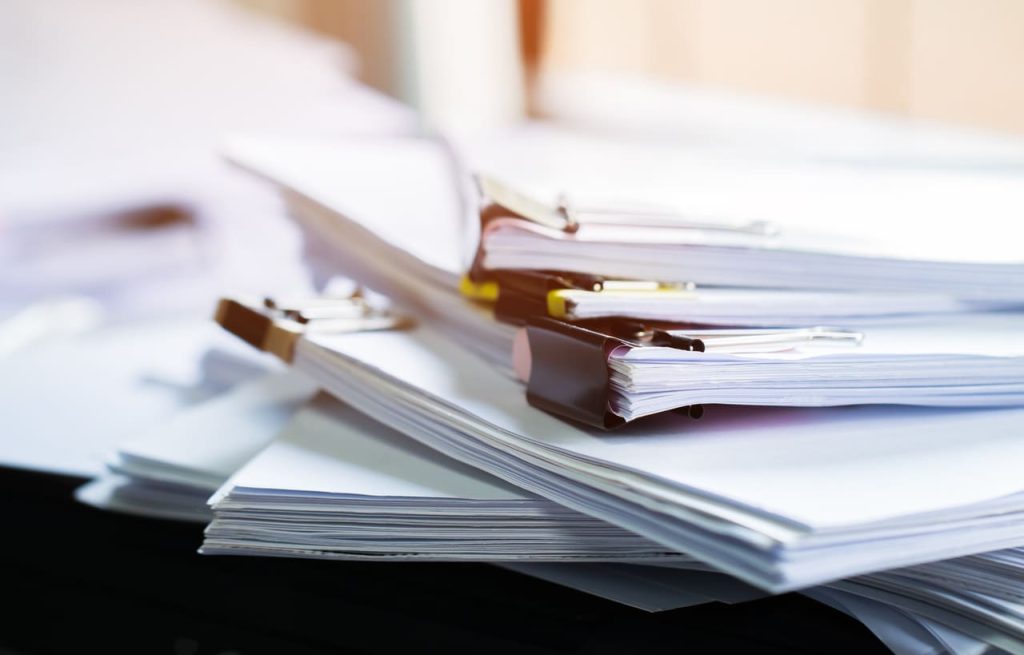
この章では、景品表示法に違反した場合に、どのような罰則や行政措置が取られるのかを解説します。
違反時の措置
景品表示法に違反した場合、消費者庁は主に以下の措置を行うことができます。
①措置命令(再発防止命令)
違反表示を行った事業者に対して、
- 不当表示の停止・修正
- 再発防止のための体制整備
- 消費者への周知・公表
などを命じるのが措置命令です。
この命令は行政処分にあたり、違反内容や企業名が公開されます。一度公表されるとネット上に情報が残り続けるため、ブランドイメージへの影響が非常に大きい点が特徴です。
②課徴金(不当表示で得た売上の3%)
不当表示によって売上を得た場合、その売上額の3%を課徴金として納付することが義務付けられています(2016年以降)。
課徴金は罰金ではなく行政上の措置ですが、高額になるケースが多く、企業にとっては大きなダメージとなります。
通報・相談窓口(消費者庁への問い合わせ方法)
景品表示法に関する通報や相談は、消費者庁または各地域の消費生活センターで受け付けています。
明らかな誇大広告など不当表示が疑われる場合は、誰でも通報が可能です。
①消費者庁表示対策課への通報
②消費者生活センターへの通報
共通ダイヤル:188
共通ダイヤルに電話をかけると、各地域の消費者生活センターにつながります。
景品表示法関連のガイドライン一覧
景品表示法関連の詳細なガイドラインは、消費者庁のウェブサイトで確認できます。
まとめ:景品表示法を正しく理解して公正な広告・販促を

景品表示法は、消費者に誤認させる表現や景品提供を防ぐために定められた法律です。特にプレゼント企画・キャンペーン・値引き広告など、日常的に行われる販促活動にも深く関係しています。
違反するとブランドの信頼を損なうだけでなく、行政処分や課徴金の対象となるリスクもあります。
まずは、自社の広告(LP、SNS投稿、バナー)や、実施中のキャンペーンが、この記事で解説した「不当表示」や「景品規制」に抵触していないか、改めて見直してみることをおすすめします。
法令に沿った公正な表現で、消費者から信頼されるブランドづくりを目指しましょう。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
