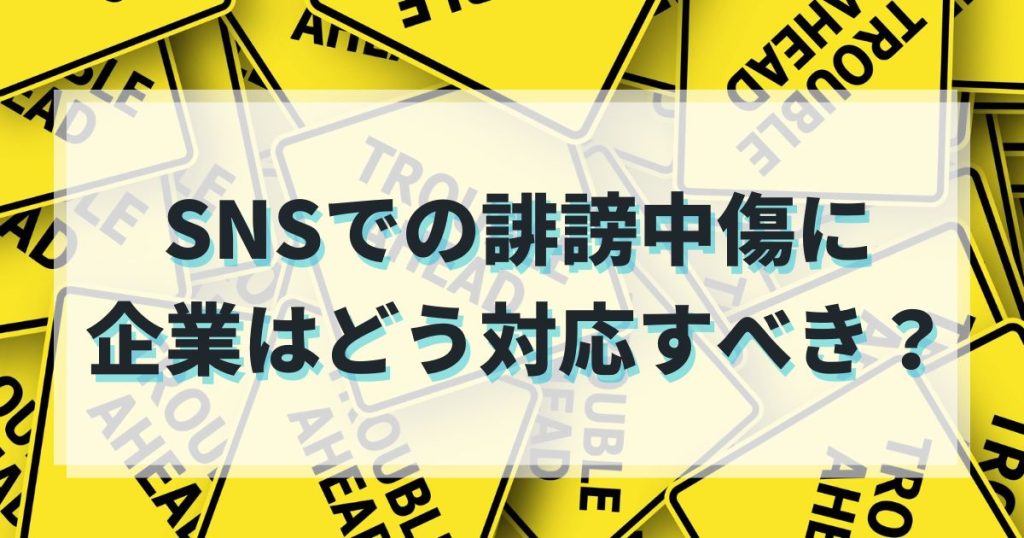
SNSでの誹謗中傷に企業はどう対応すべき?社内教育の進め方やコツを解説
SNSの普及により、企業が誹謗中傷の被害に遭うケースが急増しています。誹謗中傷とは、根拠のない悪口や中傷によって相手の名誉や信用を傷つける行為のことです。企業にとってSNS上での誹謗中傷は、ブランドイメージの悪化や売上減少など、深刻な経営リスクをもたらします。
注意すべきは、従業員の不適切な投稿が企業全体への誹謗中傷に発展するケースです。新人教育の段階で適切な知識を身につけることで、このようなリスクを大幅に軽減できます。
本記事では、企業が関わるSNSの誹謗中傷についてわかりやすく解説しています。SNSの誹謗中傷の影響や、企業が行うべき対策、SNSに関する社内教育に関しても紹介しています。企業の信頼を守るためにも、ぜひ参考にしてください。
目次
SNSの誹謗中傷とは?定義と企業への影響

SNSでの誹謗中傷は、Twitter(X)、Instagram、Facebook、TikTokなどのソーシャルメディア上で行われる誹謗中傷行為を指します。単なる批判や意見とは異なり、事実に基づかない悪意ある内容で相手を貶める行為が該当するのです。企業に対する誹謗中傷は、会社そのもの、経営陣、従業員、商品・サービスなど多岐にわたります。
企業がSNS誹謗中傷を受けると、風評被害による売上減少、採用活動への悪影響、株価下落、取引先との関係悪化など、多方面にわたって深刻な損害を被る可能性があります。とくに中小企業では、一度の炎上が企業存続に関わる問題となることも少なくありません。迅速で適切な対応が企業の命運を左右すると言っても過言ではないはずです。
どこからが誹謗中傷?線引きの判断基準
SNS上での発言がどこから誹謗中傷に該当するかの判断は、法的観点と社会通念の両面から考える必要があります。
法的には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に名誉毀損罪が成立し、「公然と人を侮辱した」場合に侮辱罪が成立します。ただし、正当な批判や事実に基づく意見表明は、誹謗中傷には該当しません。
具体的な判断基準として、投稿内容が事実かどうか、公益性があるかどうか、表現方法が適切かどうかが重要なポイントになります。「〇〇会社はブラック企業だ」という表現も、具体的な労働法違反の事実を示す場合と単なる感情的な批判では法的評価が異なるのです。企業としては、どのような投稿が法的リスクを伴うかを理解し、従業員教育に活かすことが重要となります。
企業がSNS誹謗中傷で受ける具体的被害
企業がSNS誹謗中傷を受けた場合の被害は、短期的なものと長期的なものに分かれます。短期的な被害としては、炎上による一時的な売上減少、問い合わせ対応業務の増加、従業員のモチベーション低下などが挙げられます。これらの被害は適切な対応により比較的早期に回復可能です。
長期的な被害はより深刻で、ブランドイメージの失墜、優秀な人材の離職、新規採用の困難、取引先との信頼関係悪化、金融機関からの評価低下などが考えられます。とくにBtoC企業では、消費者の信頼回復に数年を要するケースも珍しくありません。予防と早期対応の重要性を全従業員が理解することで、このような深刻な被害を回避できるのです。
SNS誹謗中傷に関する法律と罰則の最新情報

SNS誹謗中傷に関する法整備は近年大きく進展しており、企業担当者は最新の法的動向を把握しておく必要があります。2022年7月に侮辱罪の法定刑が引き上げられ、より厳しい処罰が可能になりました。また、プロバイダ責任制限法の改正により、発信者情報の開示手続きも簡素化されています。
これらの法改正は、誹謗中傷の被害者保護を強化する一方で、企業や従業員が加害者となった場合のリスクも高めています。適切な知識を持たずにSNSを利用することで、思わぬ法的責任を負う可能性があるのです。企業としては、最新の法的動向を踏まえた教育体制の構築が急務と言えるます。
名誉毀損罪・侮辱罪の改正内容と処罰
名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」に対して3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される犯罪です。企業に対する名誉毀損も個人と同様に処罰対象となります。重要なのは、摘示した事実が真実であっても名誉毀損罪は成立するという点です。
2022年7月の法改正により、侮辱罪の法定刑が「拘留または科料」から「1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」に引き上げられました。これにより、SNS上での悪質な侮辱行為に対してより厳格な処罰が可能になったのです。企業の従業員が軽い気持ちで行った投稿が刑事責任を問われる可能性があることを、教育の際に強調する必要があります。
プロバイダ責任制限法の改正ポイント
プロバイダ責任制限法の改正により、2022年10月から発信者情報開示の手続きが大幅に簡素化されました。従来は裁判所への仮処分申立てと訴訟の2段階の手続きが必要でしたが、新しい制度では1回の手続きで開示が可能になっています。これにより、誹謗中傷の加害者特定にかかる時間と費用が大幅に削減されました。
改正法では、新たに「発信者情報開示命令」という制度が導入されています。この制度により、被害者は比較的短期間で加害者を特定し、適切な法的措置を講じることが可能になったのです。企業にとっては被害回復の選択肢が増えた一方で、従業員が加害者となった場合の発覚リスクも高まっています。予防教育の重要性がより一層高まったと言えるでしょう。
企業が加害者になった場合のリスク
企業の公式アカウントや従業員の投稿が誹謗中傷と判断された場合、企業は民事・刑事の両面で重大なリスクを負います。民事面では損害賠償責任が発生し、慰謝料だけでなく逸失利益の賠償も求められる可能性があるのです。金額は数十万円から数百万円、場合によっては数千万円規模になることもあります。
企業が加害者になった場合のリスク
2025年の法改正を受けて、企業や従業員が誹謗中傷の加害者となった場合のリスクは大幅に増大しています。
民事面では損害賠償責任の算定基準が厳格化し、慰謝料に加えて逸失利益や風評被害の賠償額が高額化する傾向にあるのです。とくに情報流通プラットフォーム対処法の施行により証拠保全が容易になったことで、損害立証の精度が向上し、賠償額の増額が見込まれます。
刑事面では、侮辱罪の厳罰化(2022年施行)の効果が2025年現在で明確に現れており、実際の起訴事例が増加しています。企業の担当者個人が名誉毀損罪や侮辱罪で処罰を受けるリスクが現実的なものとなったのです。
さらに深刻なのは、新法による透明性レポートの公開義務により、企業の不適切投稿が長期間記録として残る可能性が高まったことでしょう。これらの複合的なリスクを回避するためには、2025年の法的環境に対応した継続的な従業員教育が不可欠です。
企業のSNS誹謗中傷対策|予防から対処まで
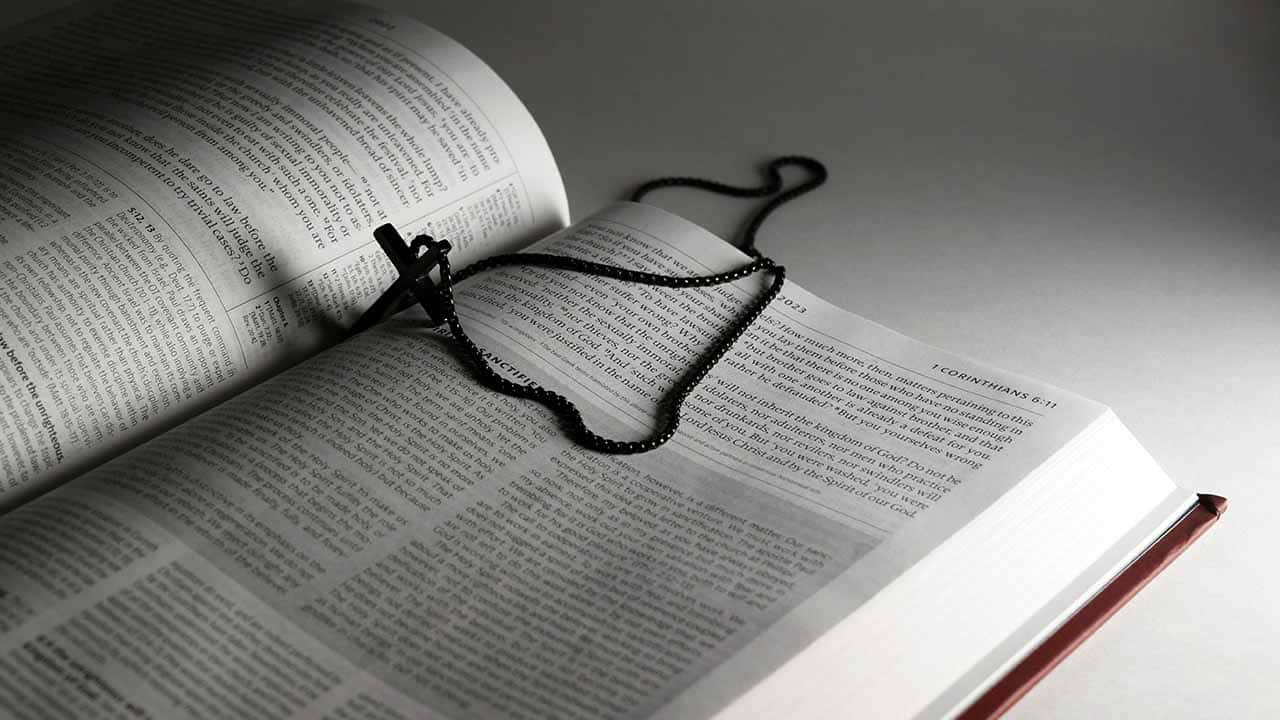
企業のSNS誹謗中傷対策は、予防策と事後対応策の両輪で進める必要があります。予防策としては、社内ルールの整備、従業員教育の徹底、監視体制の構築が重要です。事後対応策では、迅速な初動対応、適切な削除要請、必要に応じた法的措置が求められます。
新人教育においては、SNSの正しい使い方と誹謗中傷のリスクについて、具体例を交えて分かりやすく説明することが重要です。理論だけでなく、実際の事例を通じて学ぶことで、従業員の理解度と意識向上を図ることができます。継続的な教育と定期的な見直しにより、企業全体のリスク管理体制を強化していくことが大切です。
SNS運用前に整備すべき社内ルール
企業がSNSを安全に運用するためには、明確な社内ルールの策定が不可欠です。ソーシャルメディアポリシーとして、投稿内容のガイドライン、承認プロセス、禁止事項、違反時の処分などを明文化する必要があります。とくに、競合他社への批判、顧客情報の漏洩、政治的・宗教的発言、差別的表現などは厳格に禁止したほうが良いです。
社内ルールには、個人アカウントでの投稿についても言及することが重要です。従業員が個人のアカウントで会社に関する投稿を行う際の注意事項、会社名や所属部署の記載ルール、業務時間中のSNS利用制限などを明確に定めます。ルールの策定後は、全従業員への周知徹底と定期的な見直しを行い、時代の変化に合わせてアップデートすることが大切です。
誹謗中傷を受けた際の初動対応手順
企業がSNS誹謗中傷を発見した際の初動対応は、被害の拡大を防ぐ上で極めて重要です。まず、該当する投稿のスクリーンショット保存と魚拓取得を行い、証拠を確実に残す必要があります。同時に、投稿の拡散状況を調査し、関連する投稿やリツイート、コメントなどもすべて記録しましょう。
次に、投稿内容の真偽を確認し、事実誤認がある場合は正確な情報の発信を検討します。ただし、炎上を拡大させる可能性もあるため、対応方法については慎重に判断することが必要です。
24時間以内に社内の対応チームを招集し、削除要請、法的措置、広報対応などの方針を決定します。迅速かつ冷静な判断が、被害を最小限に抑える鍵となるのです。
削除請求と発信者情報開示の実践方法
誹謗中傷投稿の削除請求は、まずプラットフォーム運営者への直接申請から始めます。Twitter(X)、Instagram、Facebook、TikTokなどの主要SNSには、それぞれ専用の報告フォームが用意されています。申請時には、誹謗中傷に該当する理由を明確に記載し、証拠となる資料を添付することが重要です。
運営者による削除が行われない場合は、裁判所への仮処分申立てを検討します。仮処分では、名誉毀損やプライバシー侵害の成立要件を満たすことを立証する必要があるでしょう。
発信者情報開示請求については、改正プロバイダ責任制限法に基づく新しい手続きを利用することで、従来よりも迅速な解決が期待できます。ただし、法的手続きには専門知識が必要なため、弁護士との連携が不可欠です。
法的措置にかかる費用と期間の目安
SNS誹謗中傷に対する法的措置には、一定の費用と時間がかかることを理解しておく必要があります。削除請求の仮処分申立てでは、申立費用として数万円、弁護士費用として30~50万円程度が一般的です。手続きにかかる期間は1~2ヶ月程度となります。
発信者情報開示請求では、新制度により費用と期間が短縮されたものの、弁護士費用として50~100万円程度かかります。期間は3~6ヶ月程度を見込んでおくべきです。
損害賠償請求まで進める場合は、さらに50~100万円の追加費用と6ヶ月~1年の期間が必要になります。これらの費用対効果を慎重に検討し、企業の状況に応じて最適な対応策を選択することが重要です。
新人向けSNS誹謗中傷教育の進め方

新入社員へのSNS誹謗中傷教育は、企業リスク管理の要となる重要な取り組みです。単なる知識の詰め込みではなく、実際の業務や日常生活で活用できる実践的な教育プログラムを構築することが求められます。理論と実例のバランスを取りながら、段階的に理解を深めていくアプローチが効果的でしょう。
教育の成功には、継続性と参加型の学習環境が重要です。一度の研修で終わらせるのではなく、定期的なフォローアップ研修や事例検討会を実施し、知識の定着と意識の向上を図ります。また、受講者が積極的に参加できるワークショップ形式を取り入れることで、より深い理解と実践力の向上を目指すことができるのです。
企業が新人に教えるべき5つのポイント
新人教育で最も重要なのは、SNS誹謗中傷の基本概念と法的リスクの理解です。どのような行為が誹謗中傷に該当し、どのような法的責任を負う可能性があるかを具体例とともに説明します。名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪などの基本的な法律知識と、実際の処罰事例を紹介することで、リスクの深刻さを認識してもらいましょう。
- SNS誹謗中傷の定義と法的リスクの理解
- 投稿前のチェックポイントの習慣化
- 炎上時の対処法と社内報告ルールの徹底
- 個人情報保護とプライバシー配慮の重要性
- 企業アカウント運用時の特別な注意事項
最も重要なのは、投稿前のチェック習慣の確立です。「この投稿は誰かを傷つけないか」「会社の信用を損なわないか」「法的問題はないか」という3つの観点から、投稿内容を必ず確認する習慣を身につけてもらいます。また、炎上した場合の対処法、社内報告の重要性、個人情報保護の注意点についても併せて教育することが必要です。
実際の誹謗中傷事例を使った研修方法
効果的な教育には、実際の誹謗中傷事例を活用したケーススタディが不可欠です。過去に発生した企業の炎上事例や法的措置に至った事案を教材として使用し、なぜ問題となったのか、どのような対応が適切だったかを参加者同士で議論してもらいます。匿名化した実例を使用することで、リアリティのある学習環境を提供できるでしょう。
ロールプレイング形式の研修も効果的です。参加者を加害者役、被害者役、第三者役に分け、実際の誹謗中傷シナリオを演じてもらうことで、それぞれの立場での感情や影響を体験できます。
また、グループワークとして「この投稿は誹謗中傷に該当するか」を議論する時間を設け、判断基準の理解を深めることも重要です。研修後にはレポート提出を求め、学習内容の定着を図ります。
チェックリストで確認する投稿前の注意点
SNS投稿前のチェックリストは、誹謗中傷を未然に防ぐ最も実践的なツールです。「内容に事実誤認はないか」「感情的な表現になっていないか」「特定の個人や企業を攻撃していないか」など、具体的なチェック項目を設定します。新人でも迷わず使用できるよう、判断に困った場合の対応フローも併せて提供することが大切です。
チェックリストには、投稿時間や頻度に関する項目も含めるべきです。深夜の投稿や連続投稿は感情的になりがちで、冷静な判断ができない可能性があります。
また、他社や競合に関する投稿、政治的・宗教的な内容、プライベートな情報の扱いについても明確な基準を設けます。定期的にチェックリストの有効性を検証し、新たな事例や法改正に応じてアップデートすることで、常に最新の状況に対応できる体制を維持するのです。
SNS誹謗中傷の事例から学ぶ教訓

実際のSNS誹謗中傷事例を分析することで、リスクの深刻さと対策の重要性を具体的に理解できます。近年、企業が直接的または間接的に誹謗中傷の被害を受けるケースが急増しており、その影響は業界や企業規模を問わず広範囲に及んでいるのです。事例研究を通じて、自社で同様の問題が発生した際の適切な対応策を事前に検討しておくことが重要でしょう。
成功事例と失敗事例の両方を学ぶことで、より実践的な知識を得ることができます。迅速で適切な対応により被害を最小限に抑えた企業もあれば、対応の遅れや不適切な判断により深刻な被害を被った企業もあるのです。これらの事例から得られる教訓を新人教育に活かし、企業全体のリスク管理能力向上につなげていくことが求められます。
企業が実際に受けた誹謗中傷の事例
飲食業界では、商品への異物混入を偽装したSNS投稿により企業が甚大な被害を受けた事例があります。
投稿者は集客目的で虚偽の情報を発信しましたが、SNSで急速に拡散され、該当店舗の売上が一時的に大幅減少しました。企業は迅速に事実調査を行い、警察への被害届提出と投稿者の特定を進めることで、最終的に名誉回復を図ったのです。
IT企業においては、元従業員による労働環境に関する誹謗中傷投稿が問題となった事例もあります。「ブラック企業」「パワハラが日常的」といった根拠のない投稿が行われ、採用活動に深刻な影響を与えました。企業は法的措置を検討する一方で、労働環境の改善と透明性の向上に取り組み、信頼回復に努めています。これらの事例は、誹謗中傷対策の重要性と継続的な企業努力の必要性を示しているでしょう。
従業員の不適切投稿による企業への影響
従業員の個人アカウントでの不適切投稿が企業に大きな影響を与える事例も増加しています。
ある小売業では、従業員が競合他社を批判する投稿を行ったところ、所属企業も同様の考えを持っていると誤解され、ブランドイメージが大きく損なわれました。企業は当該従業員への処分と公式謝罪を行いましたが、顧客離れを食い止めることはできなかったのです。
製造業では、従業員が工場内の写真とともに「こんな会社で作られた商品を買う人の気が知れない」という投稿を行い、商品の安全性に対する消費者の不信を招いた事例があります。企業は即座に該当従業員を処分し、製造工程の透明性向上に努めましたが、売上回復には長期間を要しました。これらの事例は、従業員教育の徹底と継続的な啓発活動の重要性を物語っています。
成功した対処事例とその教訓
ある化粧品メーカーは、商品の副作用に関する根拠のない誹謗中傷を受けた際、24時間以内に科学的根拠に基づく反証資料を公開し、透明性の高い対応で信頼を維持しました。同社は平素から危機管理マニュアルを整備し、迅速な情報収集と対応体制を構築していたため、被害を最小限に抑えることができたのです。
金融機関では、システム障害に関する憶測投稿が拡散した際、リアルタイムでの情報発信とカスタマーサポートの強化により、顧客の不安を解消することに成功しています。同機関は日頃からSNSでの積極的な情報発信を行っており、フォロワーとの信頼関係が構築されていたことが功を奏しました。これらの成功事例から学べるのは、平時からの準備と誠実な対応の重要性でしょう。
企業のSNS誹謗中傷教育を成功させるコツ

効果的なSNS誹謗中傷教育を実現するためには、単発的な研修ではなく体系的で継続的な取り組みが必要です。
教育プログラムの設計段階から、受講者の理解度測定、フォローアップ、効果検証までを一連の流れとして捉え、PDCAサイクルを回していくことが重要でしょう。また、教育内容は法改正や社会情勢の変化に応じて定期的にアップデートし、常に最新の情報を提供することが求められます。
成功の鍵となるのは、経営層のコミットメントと現場担当者の熱意です。トップダウンでの方針明確化と、ボトムアップでの実践的な改善提案が組み合わさることで、より実効性の高い教育体制を構築できるのです。受講者が主体的に学べる環境を整備し、知識の習得だけでなく意識変革まで促すことが、真の教育成果につながります。
継続的な教育体制の構築方法
継続的な教育体制の基盤となるのは、年間教育計画の策定です。新入社員向けの基礎研修、中堅社員向けの応用研修、管理職向けの危機管理研修など、階層別のプログラムを体系的に組み立てます。また、四半期ごとの事例検討会や月次の情報共有会を定期開催し、最新の動向や社内外の事例を共有する場を設けることが重要でしょう。
教育効果を持続させるためには、eラーニングシステムの活用も有効です。いつでもどこでも学習できる環境を整備し、受講履歴や理解度テストの結果を管理することで、個人別の学習進捗を把握できます。
さらに、社内SNSや掲示板を活用した情報発信、ケーススタディの共有、質問・相談窓口の設置により、日常的な学習と意識向上を促進することができるのです。
新人教育に活用できるツールと資料
効果的な新人教育には、視覚的で理解しやすい教材の準備が不可欠です。実際の誹謗中傷事例を匿名化した動画教材、判断に迷いやすいケースをまとめたケースブック、投稿前チェックリスト、緊急時対応フローチャートなど、実務で即座に活用できるツールを整備します。これらの資料は定期的に更新し、常に最新の情報を反映させることが重要です。
デジタルツールの活用も教育効果を高めます。SNS投稿のシミュレーションゲーム、誹謗中傷判定クイズアプリ、リスク診断ツールなど、ゲーム感覚で学べるコンテンツはとくに若手社員の関心を引きやすいものです。
また、社外の専門機関が提供する教育プログラムや資格制度の活用も検討すべきでしょう。多様な学習機会を提供することで、受講者の理解度と実践力を総合的に向上させることができます。
社内コンプライアンス強化のポイント
SNS誹謗中傷対策を含む包括的なコンプライアンス体制の構築には、明確なルールと実効性のある運用が必要です。
ソーシャルメディアポリシーの策定だけでなく、違反時の処分基準、報告体制、相談窓口の設置など、実際に問題が発生した際の対応フローを明文化します。また、定期的なコンプライアンス研修と意識調査により、組織全体の理解度と課題を把握することが重要です。
内部通報制度の整備も効果的な予防策となります。従業員が誹謗中傷に関わる問題を発見した際に、安心して報告できる環境を構築することで、早期発見と迅速な対応が可能になるのです。通報者の匿名性を保護し、報復を禁止する仕組みを明確にすることで、制度の実効性を高めることができます。
コンプライアンス強化には、経営層から現場まで一体となった取り組みが不可欠です。定期的な役員会での検討、部門長による現場への浸透活動、従業員代表による改善提案など、多層的なアプローチにより組織文化として根付かせていくことが重要となります。他社の事例研究や業界団体との情報交換を通じて、常にベストプラクティスを取り入れる姿勢を維持することも大切です。
まとめ|SNS誹謗中傷教育で企業と従業員を守ろう

SNS誹謗中傷は現代企業が直面する重要なリスクの一つであり、適切な教育と対策により被害を大幅に軽減することができます。本記事で解説した基本知識、法的動向、対処方法、教育手法を参考に、自社の状況に応じた包括的な対策を構築することが重要です。とくに新人教育においては、理論と実践のバランスを取りながら、継続的な学習環境を整備することで、真の効果を得ることができるはずです。
企業の信頼とブランド価値を守るためには、全従業員がSNS誹謗中傷のリスクを正しく理解し、適切な行動を取れるようになることが不可欠です。今回紹介した教育方法やツールを活用し、組織全体のリテラシー向上に取り組んでください。継続的な教育と意識向上により、SNSを安全かつ効果的に活用できる企業文化を構築していきましょう。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
-
NEW ARTICLE
2026/02/05
SEOとリスティング広告の違いは?使い分けや併用による相乗効果についてを解説
広告
- リスティング広告
-
NEW ARTICLE
2026/02/04( 更新)
リスティング広告運用代行会社の選び方!確認すべきポイントや代行費用相場を解説
広告広告運用
- リスティング広告
-
NEW ARTICLE
2026/02/03( 更新)
リスティング広告の費用相場はいくら?予算の決め方や費用を抑える方法を解説
広告広告運用
- リスティング広告
-
ARTICLE
2025/04/08( 更新)
リスティング広告の改善方法を解説!課題・指標別の分析方法と成果を出す施策を紹介
広告広告運用
- リスティング広告
