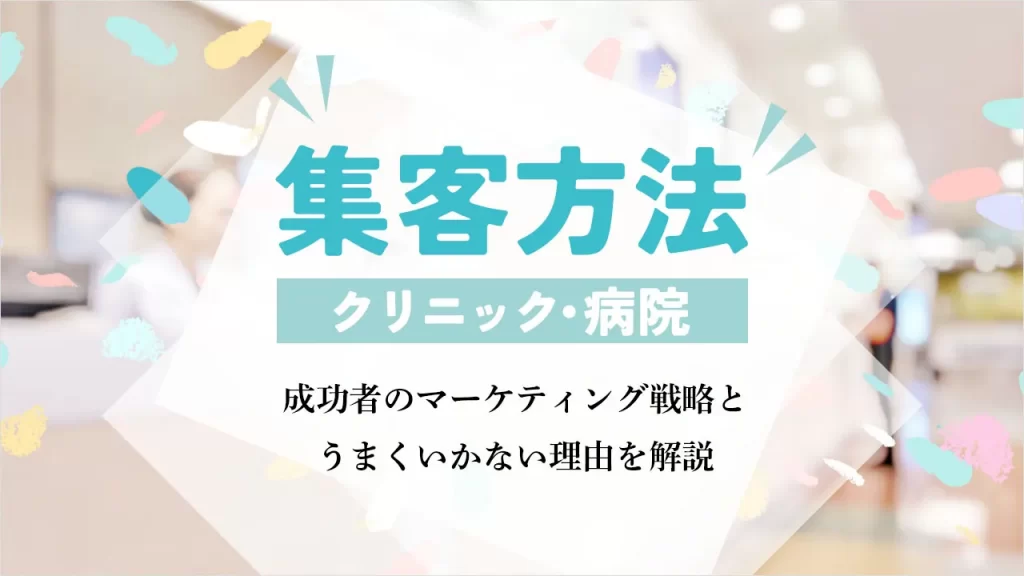
クリニック集客の秘訣|患者が病院を選ぶ基準や初診を増やすマーケティング戦略
「開業したのに患者が増えない」
「再来院が少ない気がする」
「自院に合っている集客方法がわからない」
といった悩みを持つクリニック・病院は多いです。
設備を整え診療体制も万全なのに、なかなか患者数が伸びないのには必ず理由があります。近年は患者がインターネットで医療機関を探すことが当たり前になり、口コミや評判を重視する傾向が強まっています。そのため、従来のように「開業すれば患者が来る」という時代ではなくなりました。
本記事では、クリニック・病院の集客がうまくいかない理由から、患者がクリニックを選ぶ基準、おすすめの集客方法8選、初診患者・リピーター・訪問診療それぞれに向いている施策まで、網羅的に解説します。患者に選ばれ続けるクリニックを目指すために、ぜひ参考にしてください。
目次
クリニック・病院の集客がうまくいかない5つの理由

クリニックや病院を開業したものの、なかなか患者が増えないと悩んでいる経営者は少なくありません。設備を整え、診療体制も万全なのに集客がうまくいかないのには、必ず理由があります。
闇雲に広告を出したり、ホームページを作るだけでは効果は出にくいでしょう。まずは集客がうまくいかない原因を把握し、適切な対策を講じることが大切です。ここでは、クリニックの集客が失敗する代表的な5つの理由を解説します。
認知度が低く患者の選択肢に入っていない
開業したばかりのクリニックや、Web上に情報がほとんどないクリニックは、そもそも患者に認知されていない可能性があります。どれだけ良い診療を提供していても、存在を知られていなければ通院の選択肢にすら入りません。
近隣住民だけでなく、Web検索やGoogleマップで探している患者にも見つけてもらえる状態を作る必要があります。ホームページの開設やGoogleビジネスプロフィールへの登録など、情報をオープンにする取り組みが重要です。
他院との差別化ができていない
患者は複数のクリニックを比較検討した上で、通院先を決めています。他院にはない特徴や強みが明確でないと、「ここでなければいけない理由」が見つからず選ばれにくくなります。
たとえば「夜間診療対応」「女性医師在籍」「キッズスペース完備」など、自院ならではの価値を打ち出すことが大切です。患者が求めているものと、自院が提供できる価値を照らし合わせて差別化ポイントを見つけてみてください。
オンライン予約システムが未整備
電話予約のみの対応だと、診療時間外に予約できない不便さや、待ち時間が読めない不安から敬遠される可能性があります。近年は24時間いつでも予約できるオンラインシステムを求める患者が増えています。
オンライン予約があれば、患者は自分の都合に合わせて予約でき、待ち時間も短縮できます。院内感染リスクを避けたい患者にとっても、予約システムの有無は重要な選択基準です。
患者との定期的な接点がない
一度来院してもらえても、その後つながりが途切れてしまうと再来院にはつながりません。患者がクリニックのことを忘れてしまえば、次に症状が出たときに別のクリニックを選ぶ可能性が高まります。
LINE公式アカウントやメールマガジン、SNSなどを活用し、定期的に情報を発信することで患者との接点を維持できます。予防接種のお知らせや健康情報の提供など、有益な情報を届ける仕組みを作りましょう。
分析と改善のサイクルが回っていない
集客施策を実施しても、その効果を測定・分析していなければ、何が良くて何が悪かったのかわかりません。効果のない方法に費用と時間をかけ続けてしまうリスクがあります。
ホームページへのアクセス数、予約の経路、患者の年齢層など、データを定期的にチェックし改善につなげることが重要です。PDCAサイクルを回すことで、自院に最適な集客方法が見えてきます。
患者がクリニックを選ぶ基準と心理
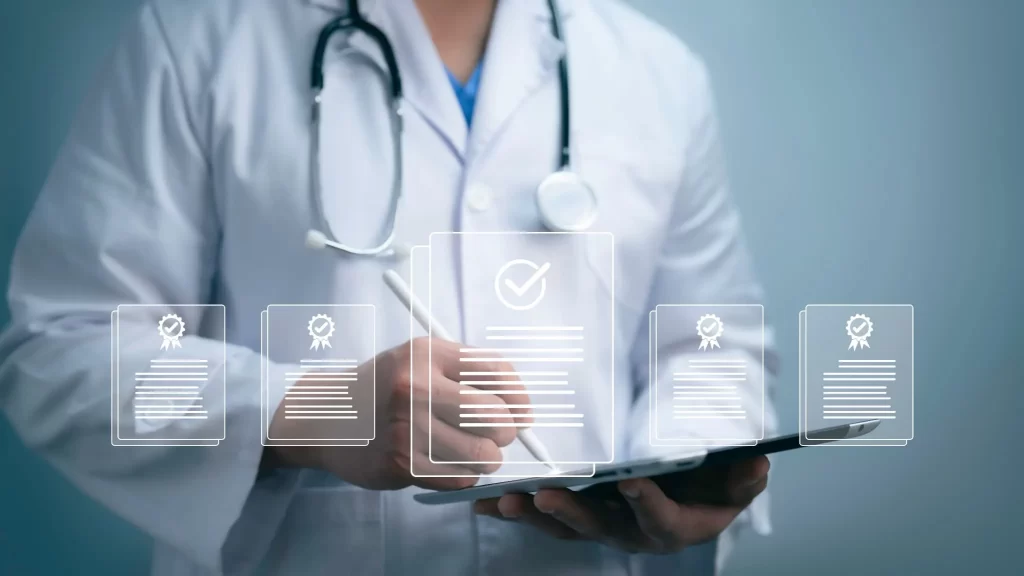
集客を成功させるには、患者がどのような基準でクリニックを選んでいるのかを理解することが欠かせません。患者の心理や行動パターンを知ることで、どのような情報を発信すべきか、どんな強みをアピールすべきかが明確になります。
厚生労働省の「令和5年受療行動調査」によると、患者の約8割が医療機関を選ぶ際に何らかの情報を参考にしていることがわかっています。ここでは、患者がクリニックを選ぶ際に重視する4つの基準を解説します。
口コミ・評判を最も重視する傾向
同調査によれば、患者の6割以上が「家族・友人・知人の口コミ」を参考にしています。実際に通院した人の生の声は、ホームページの情報よりも信頼性が高いと感じる患者が多いためです。
加えて、外来患者の約3割が「医療機関が発信するインターネット情報」も参考にしています。GoogleビジネスプロフィールやSNSでの口コミ、ポータルサイトのレビューなど、Web上の評判も重要な判断材料になっています。
アクセスのしやすさと診療時間
自宅や職場から通いやすい立地にあるかどうかは、患者にとって最も基本的な選択基準です。駅から近い、駐車場がある、バス停が近いなど、アクセスの良さは大きなアドバンテージになります。
診療時間も重要な要素です。平日の夕方まで、土曜日や日曜日も診療しているクリニックは、仕事や学校のある患者にとって通いやすく選ばれやすい傾向があります。
院内の雰囲気と清潔感
初めて訪れたクリニックの第一印象は、再来院の可否を大きく左右します。待合室が清潔で明るい、設備が整っている、プライバシーに配慮されているなど、院内環境への配慮が患者の安心感につながります。
子連れの患者が多い小児科や内科であれば、キッズスペースの有無も選択基準になります。美容クリニックであれば、パウダールームの充実度なども評価のポイントです。
医師やスタッフの対応への期待
いくら設備が整っていても、医師やスタッフの対応が悪ければ患者は離れてしまいます。丁寧な説明、親身な対応、笑顔での接遇など、人としての温かさが信頼関係を築きます。
口コミサイトやSNSでは、医師の説明のわかりやすさや、受付スタッフの態度について言及されることが多くあります。スタッフ教育を徹底し、患者満足度を高めることが集客にもつながります。
▶参考:令和5(2023)年受療行動調査(概数)の概況|厚生労働省
集客を始める前に確認すべき5つのチェックリスト

集客施策を始める前に、まずクリニック自体の受け入れ態勢を整えておくことが重要です。せっかく集客に成功しても、患者満足度が低ければリピーターにはつながりません。
ここでは、集客を始める前にチェックしておくべき5つの項目を紹介します。これらをクリアしてから集客施策に取り組むことで、より高い効果が期待できます。
患者満足度を高める診療体制の整備
診療内容そのものが患者満足度の基盤です。特に意識したいのが「インフォームドコンセント」の徹底です。インフォームドコンセントとは、医療者が患者に十分な説明を行い、患者が納得した上で治療方針を決めることを指します。
一方的に治療を進めるのではなく、患者の不安や疑問に寄り添い、理解を得ながら診療を進める姿勢が大切です。説明が丁寧で信頼できると感じてもらえれば、口コミでの評価も高まります。
院内の内装・設備の見直し
待合室の椅子が古い、掲示物が色褪せている、トイレが清潔でないといった細かな点も、患者は意外と見ています。院内環境が整っていないと、どれだけ良い診療をしても「また来たい」と思ってもらえない可能性があります。
バリアフリー対応、キッズスペース、授乳室、パウダールームなど、ターゲット患者層に合わせた設備を整えることも効果的です。清潔感と快適さを保つことで、患者の居心地が良くなります。
スタッフ教育と接遇マナーの徹底
受付スタッフや看護師の対応は、患者の印象を大きく左右します。言葉遣いが荒い、笑顔がない、説明が不十分といった対応は、低評価の口コミにつながる原因です。
定期的な接遇研修を実施し、患者目線での対応を徹底しましょう。口コミサイトで過去の評価をチェックし、改善点を洗い出すことも有効です。
次回来院を促す仕組みづくり
継続的な治療が必要な患者に対して、次回の受診日をしっかり伝える仕組みが必要です。診察券の裏に次回予約日を記入したり、メモを渡したりするなど、忘れない工夫が大切です。
予約システムと連携して、受診日前日にリマインドメールやLINEメッセージを送る仕組みを導入しているクリニックもあります。患者が通院を忘れないサポートをすることで、再来院率が高まります。
患者とつながるツールの準備
集客施策を行う上で、患者と継続的にコミュニケーションを取れるツールを用意しておくことが大切です。LINE公式アカウント、メールマガジン、SNSアカウントなどがあります。
これらのツールを使えば、予防接種のお知らせや休診日の案内、健康に関する情報など、患者にとって有益な情報を定期的に届けられます。クリニックのことを忘れずにいてもらうための接点は必須といえます。
クリニックの集客・マーケティング成功事例に学ぶ

集客に成功しているクリニックには、共通するマーケティングプロセスがあります。場当たり的に施策を打つのではなく、戦略的に計画を立て、実行し、改善を繰り返しているのが特徴です。
ここでは、成功しているクリニックが実践している6つのマーケティングプロセスを紹介します。これらのステップを踏むことで、集客の成功率を高められます。
環境分析で自院の強みを明確化
集客を始める前に、まず自院がどのような環境に置かれているのかを分析することが重要です。自院の強み・弱み、市場の機会・脅威を整理する「SWOT分析」が有効です。
たとえば「夜間診療ができる(強み)」「駅から遠い(弱み)」「周辺に高齢者が多い(機会)」「近隣に大型病院がある(脅威)」といった形で洗い出します。これにより、どこで勝負すべきかが見えてきます。
ターゲット患者層の絞り込み
すべての患者に対応しようとすると、メッセージが曖昧になり誰にも響かなくなります。成功しているクリニックは、メインターゲットとなる患者層を明確にしています。
たとえば「30代の子育て世代の主婦」「オフィス街で働く会社員」など、ターゲットを具体的にイメージすることで、どのような情報を発信すべきか、どんなサービスを提供すべきかが明確になります。
自院のポジショニング戦略
競合クリニックと差別化するために、自院の立ち位置を明確にする必要があります。「矯正歯科に特化」「在宅診療に強い」「美容施術メニューが豊富」など、自院だけの強みを打ち出すことが大切です。
ポジショニングが曖昧だと、患者から見て他院との違いがわからず選ばれにくくなります。市場での自院の位置づけをはっきりさせることで、ブレない集客戦略が立てられます。
複数の施策を組み合わせて実施
一つの集客方法だけに頼るのではなく、複数の施策を組み合わせる「マーケティングミックス」が効果的です。たとえばホームページとMEO対策、SNSとLINE公式アカウントなど、相乗効果を狙います。
ホームページで詳細情報を提供し、SNSで認知度を高め、LINE公式アカウントでリピーターを増やすといった形で、それぞれの役割を分担させることで集客力が高まります。
データ分析と改善の継続
集客施策を実施したら、必ず効果測定を行ってください。ホームページへのアクセス数、予約経路、患者の年齢層や来院理由などのデータを収集し、分析します。
効果が出ていない施策は早めに見直し、効果のある方法はさらに強化するといったPDCAサイクルを回すことが重要です。データに基づいた改善を積み重ねることで、自院に最適な集客方法が見つかります。
リピーター・再初診患者の獲得重視
新規患者の獲得だけでなく、一度来院した患者に再び選んでもらう施策も重要です。リピーター患者や再初診患者(1〜3ヶ月以上経過して再来院する患者)を増やすことで、安定した経営につながります。
LINE公式アカウントやSNSで定期的に情報を発信し、患者との接点を維持することが大切です。クリニックのことを忘れずにいてもらえれば、次に症状が出たときに選んでもらいやすくなります。
クリニック・病院のおすすめ集客方法8選

クリニックの集客方法には、オンライン施策からオフライン施策まで様々な選択肢があります。それぞれの手法には特徴があり、目的や予算、ターゲット層に応じて使い分けることが大切です。
ここでは、クリニックにおすすめの集客方法を8つ紹介します。各手法の特徴と効果を理解し、自院に合った方法を選びましょう。
ホームページは信頼性・認知度向上に必須
クリニックのホームページは、患者が最も詳しい情報を得られる場所です。診療科目、診療時間、医師のプロフィール、院内写真、アクセス情報など、患者が知りたい情報を網羅的に掲載できます。
ホームページがないと、Web検索で見つけてもらえず、信頼性にも欠けると判断される可能性があります。無料で作成できるサービスもありますが、SEO対策や予約システムの導入を考えると、ある程度の投資をして専門業者に依頼するのがおすすめです。
MEO対策は認知度と口コミ獲得に効果的
MEO対策とは、Googleマップで検索された際に自院の情報を上位表示させる施策です。「内科 新宿」「歯科 渋谷駅」など地域名で検索する患者に対して、効果的にアプローチできます。
Googleビジネスプロフィールに登録し、診療時間や電話番号、写真、最新情報を充実させることが重要です。患者からの口コミも集まりやすく、口コミへの丁寧な返信が信頼感につながります。
新規患者獲得ならSEO対策がおすすめ
SEO対策とは、Googleなどの検索エンジンで上位表示されるようにホームページを最適化する施策です。「腰痛 クリニック 大阪」「小児科 夜間診療 横浜」など、患者が検索しそうなキーワードで上位表示されれば、新規患者の獲得につながります。
ブログやコラム記事を定期的に更新し、患者の悩みに答えるコンテンツを増やすことがSEO対策として有効です。ただし効果が出るまでに数ヶ月かかるため、長期的な視点で取り組む必要があります。
短期間で効果を出したいならWeb広告
リスティング広告やディスプレイ広告などのWeb広告は、即効性が高いのが特徴です。検索結果の上部に広告として表示されるため、すぐに患者の目に触れる機会が増えます。
クリック課金制なので、広告を見ただけでは費用が発生せず、興味を持った人がクリックした時だけ料金が発生します。予算に応じて広告を出稿できるため、開業直後など早く認知度を高めたい時期におすすめです。
SNS運用で認知度アップと拡散力を活用
X(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSは、不特定多数の人に情報を届けられます。診療事例や健康情報、クリニックの雰囲気を写真や動画で発信することで、親近感を持ってもらいやすくなります。
SNSの強みは拡散力です。有益な情報や共感を呼ぶ投稿は、フォロワー以外にも広く届く可能性があります。ただし定期的な投稿が必要なため、運用の手間がかかる点は考慮する必要があります。
ポータルサイトは比較検討層の取り込みに有効
医療機関のポータルサイトとは、全国の病院やクリニックの情報を検索できるWebサイトです。エキテンやEPARKなどが代表的で、地域や診療科目で絞り込んで検索する患者が利用しています。
複数のクリニックを比較検討している患者層にアプローチできるのが特徴です。掲載料がかかる場合もありますが、オンライン予約システムなどの機能を利用できるサイトもあり、導入の手間を省けるメリットがあります。
リピーター獲得ならLINE公式アカウント
LINE公式アカウントは、患者と直接つながり、定期的に情報を届けられるツールです。予防接種のお知らせ、休診日の案内、健康に関するコラムなど、メールマガジンのように活用できます。
LINEは開封率が高く、患者との接点を維持しやすいのが特徴です。予約機能や問診票の事前記入機能と連携させれば、患者の利便性も向上します。リピーター育成に最適な施策です。
地域密着型ならチラシ・看板が有効
チラシのポスティングや看板設置などのオフライン施策は、地域に密着したクリニックに有効です。Web検索に慣れていない高齢者層や、近隣住民に直接アプローチできます。
新聞の折り込みチラシや地域の広報誌への掲載、大通り沿いの看板設置など、ターゲット層に合わせて手法を選びましょう。費用はかかりますが、地域での認知度向上に即効性があります。
初診患者を増やすための集客施策

新規の初診患者を獲得することは、クリニックの成長に欠かせません。初診患者は、まだクリニックのことをよく知らない状態で訪れるため、不安や疑問を解消し、安心して来院してもらう工夫が必要です。
ここでは、初診患者を増やすために効果的な3つの施策を紹介します。患者の心理的なハードルを下げることがポイントです。
新規患者が求める情報を発信する
初診患者が最も知りたいのは、「このクリニックは自分の悩みを解決してくれるのか」という点です。ホームページやSNSで、対応できる症状、診療内容、治療方針などを具体的に発信してください。
医師のプロフィールや経歴、院内の雰囲気がわかる写真も重要です。顔が見える情報があると、初めての患者でも安心感を持って来院できます。「よくある質問」のページを設けるのも効果的です。
予約のハードルを下げる工夫
初診患者にとって、電話予約は意外とハードルが高いものです。何を聞かれるかわからない不安や、電話する時間がないといった理由で、予約を躊躇してしまうことがあります。
24時間対応のオンライン予約システムを導入すれば、患者は自分の都合の良いタイミングで予約できます。予約フォームは入力項目を最小限にし、スマートフォンでも操作しやすいデザインにすることが大切です。
初診限定の特典や安心感の提供
初診患者向けの特典を用意することで、来院のきっかけを作れます。たとえば「初診料割引」「初回カウンセリング無料」「待ち時間優先案内」などが考えられます。
医療広告ガイドラインに抵触しない範囲で、患者が来院しやすくなる工夫を取り入れましょう。ホームページに「初めての方へ」のページを作り、来院の流れを丁寧に説明するのも安心感につながります。
再来院・リピーターを増やす集客施策
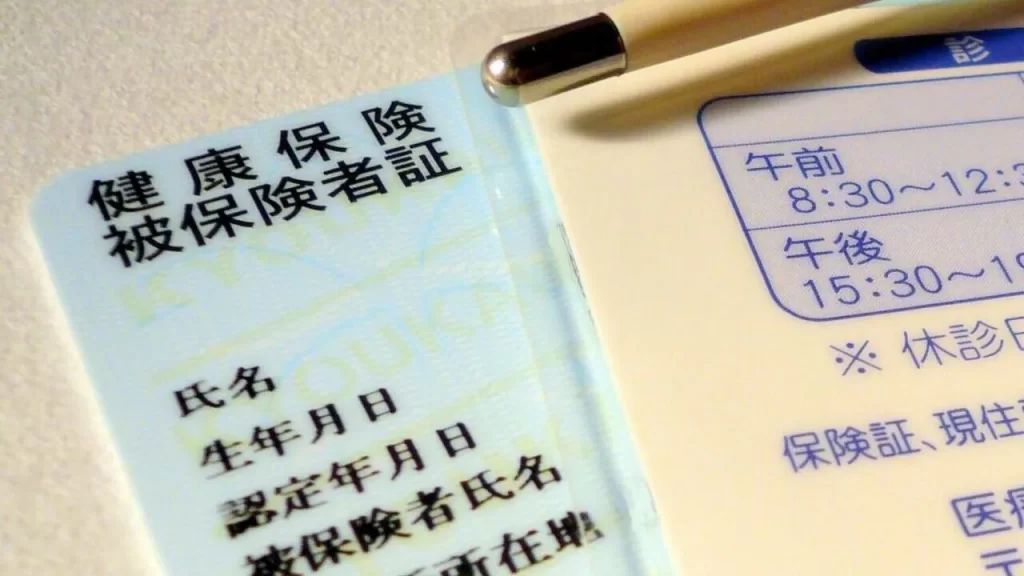
新規患者の獲得と同じくらい重要なのが、一度来院した患者にリピーターになってもらうことです。リピーターが増えれば、安定した経営基盤ができ、新規集客にかかるコストも削減できます。
ここでは、再来院やリピーターを増やすために効果的な3つの施策を紹介します。患者との関係性を維持し続けることがポイントです。
定期的な情報発信で接点を維持
患者がクリニックのことを忘れてしまうと、次に症状が出たときに別のクリニックを選ぶ可能性があります。LINE公式アカウントやメールマガジン、SNSを活用し、定期的に有益な情報を届けることが大切です。
予防接種のお知らせ、季節ごとの健康情報、新しい診療メニューの案内など、患者にとって役立つ内容を発信することが大切です。押し付けがましくならない程度の頻度で、つながりを保ち続けます。
次回予約を促す院内フロー整備
継続的な治療が必要な患者に対しては、診察時に次回の予約を取ってもらう仕組みを作ることが重要です。受付で次回予約日を案内し、その場で予約を取ってもらえれば、患者が忘れるリスクを減らせます。
診察券の裏に次回予約日を記入したり、予約日が近づいたらリマインドメールやLINEメッセージを送ったりする工夫も効果的です。患者が通院を継続しやすい環境を整えましょう。
診察券・リマインド機能の活用
診察券にポイント制度を導入したり、次回来院時の特典を設けたりすることで、再来院のきっかけを作れます。ただし、医療広告ガイドラインに抵触しないよう注意が必要です。
予約システムと連携したリマインド機能を活用すれば、予約日の前日や当日にお知らせを自動送信できます。患者が予約を忘れることを防ぎ、無断キャンセルの削減にもつながります。
訪問診療で集客するための施策

高齢化が進む中、在宅医療や訪問診療のニーズは年々高まっています。通院が困難な患者や、自宅での療養を希望する患者に対して訪問診療を提供することで、新たな患者層を獲得できます。
ここでは、訪問診療で集客するために効果的な3つの施策を紹介します。地域との連携と情報発信がポイントです。
地域の介護施設・ケアマネとの連携
訪問診療を必要とする患者の多くは、介護施設やケアマネージャーを通じて医療機関を探しています。地域の介護施設や居宅介護支援事業所と連携し、顔の見える関係を築くことが重要です。
定期的に施設を訪問して挨拶したり、事例報告会や勉強会に参加したりすることで、信頼関係が生まれます。ケアマネージャーから患者を紹介してもらえる体制を作っておくと良いです。
在宅医療の情報を積極的に発信
訪問診療を行っていることを、ホームページやSNS、ポータルサイトで積極的に発信しましょう。対応できる疾患、訪問の頻度、緊急時の対応など、具体的な情報を掲載することが大切です。
在宅医療に関する不安や疑問に答えるコンテンツを用意することで、患者や家族が安心して相談できます。「訪問診療について」の専用ページを作り、わかりやすく説明してください。
往診対応エリアの明確化
訪問診療を検討している患者や家族にとって、自宅が対応エリアに含まれているかどうかは最も重要な情報です。ホームページやGoogleビジネスプロフィールに、対応可能なエリアを正確に明記してください。
地図上で対応エリアを視覚的に示したり、「〇〇区全域」「〇〇駅から半径5km以内」など具体的に記載することで、患者が判断しやすくなります。エリア外でも相談可能な場合はその旨も記載しておくと親切です。
クリニック集客を成功させる3つのポイント

集客施策を実施する際には、やみくもに手を広げるのではなく、成功のポイントを押さえて取り組むことが重要です。限られた予算と時間の中で、効果的に集客を行うためのコツがあります。
ここでは、クリニックの集客を成功させるために押さえておくべき3つのポイントを解説します。これらを意識することで、集客の成功率が高まります。
患者ニーズを正確に捉える
集客施策を考える前に、ターゲットとなる患者が何を求めているのかを把握することが不可欠です。会社帰りに通いやすい時間帯を求めているのか、子連れで通いやすい環境を求めているのか、ニーズは患者層によって異なります。
患者のニーズに合わせた情報発信やサービス提供ができれば、自然と選ばれるクリニックになります。口コミやアンケートを活用して、患者の声を集めることから始めましょう。
継続的な情報発信と改善
ホームページを作成したり、SNSアカウントを開設したりしても、更新が止まってしまっては効果が薄れてしまいます。定期的に情報を発信し続けることで、患者との接点を維持できます。
また、発信する内容も患者の反応を見ながら改善していくことが大切です。どのような投稿に反応が良いのか、どのページがよく見られているのかを分析し、より効果的な情報発信につなげましょう。
施策の効果測定と最適化
集客施策を実施したら、必ず効果測定をしてください。ホームページへのアクセス数、予約の経路、問い合わせの件数など、数値で把握できるデータを定期的にチェックします。
効果が出ていない施策は見直し、効果のある施策はさらに強化するというPDCAサイクルを回すことが重要です。データに基づいた改善を積み重ねることで、自院に最適な集客方法が見つかります。
クリニック・病院の広告で守るべき医療広告ガイドライン
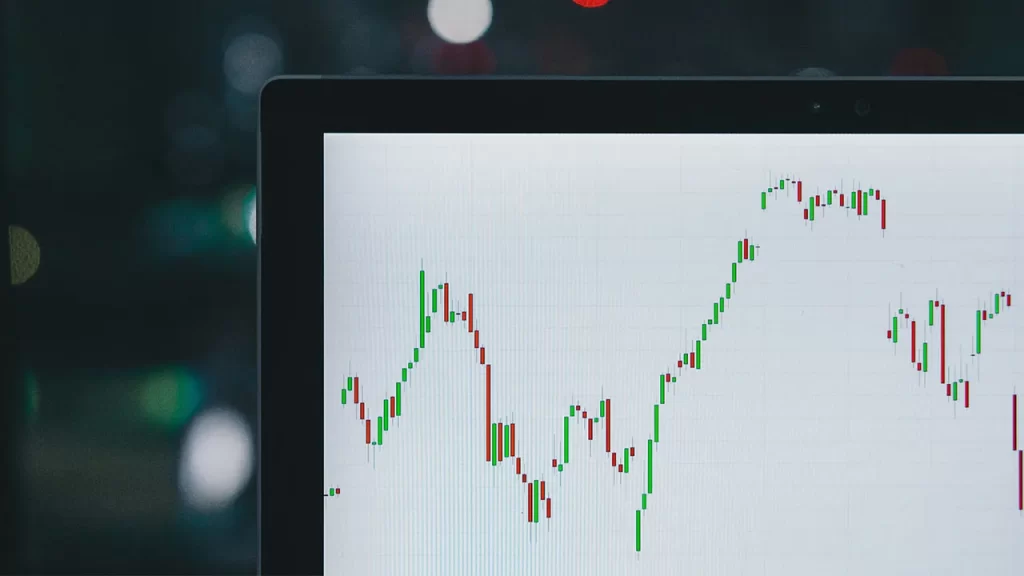
クリニックが広告を出す際には、厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」を遵守する必要があります。医療は人の健康や命に関わる分野であるため、誇大広告や虚偽の情報で患者を誤解させることは厳しく規制されています。
違反すると罰則が科されるだけでなく、クリニックの信頼を大きく損なうリスクがあります。ここでは、医療広告ガイドラインの基本と注意すべきポイントを解説します。
医療広告ガイドラインとは
医療広告ガイドラインとは、医療機関が行う広告活動について定められた規制のことです。正式には「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」と呼ばれ、患者が正確な情報に基づいて医療機関を選べるよう設けられています。
広告の対象には、ホームページ、SNS、チラシ、看板、メールマガジンなど、患者に情報を発信するすべての媒体が含まれます。ガイドラインを正しく理解し、適切な広告活動を行うことが重要です。
禁止されている広告表現
医療広告ガイドラインでは、以下のような表現が禁止されています。
| 禁止事項 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 虚偽広告 | 事実と異なる内容や実現不可能な表現 | 「どんな病気も必ず治る」「絶対安全」など |
| 誇大広告 | 著しく誤認を与える優秀性の表現 | 「最高の」「日本一」「〇〇し放題」など |
| 比較優良広告 | 他院と比較して優れていると示す表現 | 「都内No.1」「〇〇病院より優れている」など |
| 体験談 | 患者の主観的な体験や感想 | ホームページへの口コミ掲載、患者インタビューなど |
| ビフォーアフター | 詳細な説明やリスクの記載がない治療前後の写真 | 費用、期間、副作用の記載がない症例写真 |
これらの表現は、患者に誤った期待を抱かせる可能性があるため禁止されています。広告を作成する際は、事実に基づいた正確な情報のみを記載することが大切です。
違反した場合のペナルティ
医療広告ガイドラインに違反した場合、保健所による調査や中止命令が行われます。改善が見られない場合や、悪質な虚偽広告と判断された場合には、最長6ヶ月の懲役または最大30万円の罰金が科されることがあります。
罰則だけでなく、患者からの信頼を失い、クリニックの評判が大きく損なわれるリスクもあります。広告を作成する際は、必ずガイドラインを確認し、不安な点があれば専門家に相談することをおすすめします。
まとめ|クリニック集客は患者視点と継続的な改善が鍵

クリニックの集客を成功させるためには、患者がどのような基準で医療機関を選んでいるのかを理解し、患者視点に立った施策を実施することが重要です。口コミや評判、アクセスのしやすさ、院内の雰囲気など、患者が重視するポイントを押さえた情報発信を心がけましょう。
ホームページやMEO対策、SNS運用など、複数の集客方法を組み合わせることで相乗効果が生まれます。初診患者の獲得だけでなく、リピーターや再初診患者を増やす施策にも力を入れることで、安定した経営基盤が築けます。訪問診療を提供する場合は、地域の介護施設やケアマネージャーとの連携も欠かせません。
集客施策を実施したら、必ず効果測定と改善を繰り返すことが成功の鍵です。データに基づいてPDCAサイクルを回し、自院に最適な方法を見つけてみてください。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT

