
オウンドメディアの集客方法とは?アクセスを増やすコンテンツ作成のコツも解説
オウンドメディアの集客には押さえるべきポイントがあります。本記事では、オウンドメディアの意義から集客に強いオウンドメディアの始め方、運用時やコンテンツ作成時のポイント、具体的な集客方法、成功事例に至るまで徹底解説。
- オウンドメディアの流入数が増えない
- 効果的なオウンドメディアの運用方法が分からない
- 商品やサービスのファンを増やすコンテンツを作成したい
など、オウンドメディアの集客に関わる悩みを抱えた経営者やマーケターは必見です。
ー集客にお困りの方へー

集客にはインターネット活用が必須!
ネット集客をはじめるにあたって、把握しておきたいことを、分かりやすくまとめました!ネット集客の理解のために、まずはこの資料をご覧ください。
目次
オウンドメディアとは
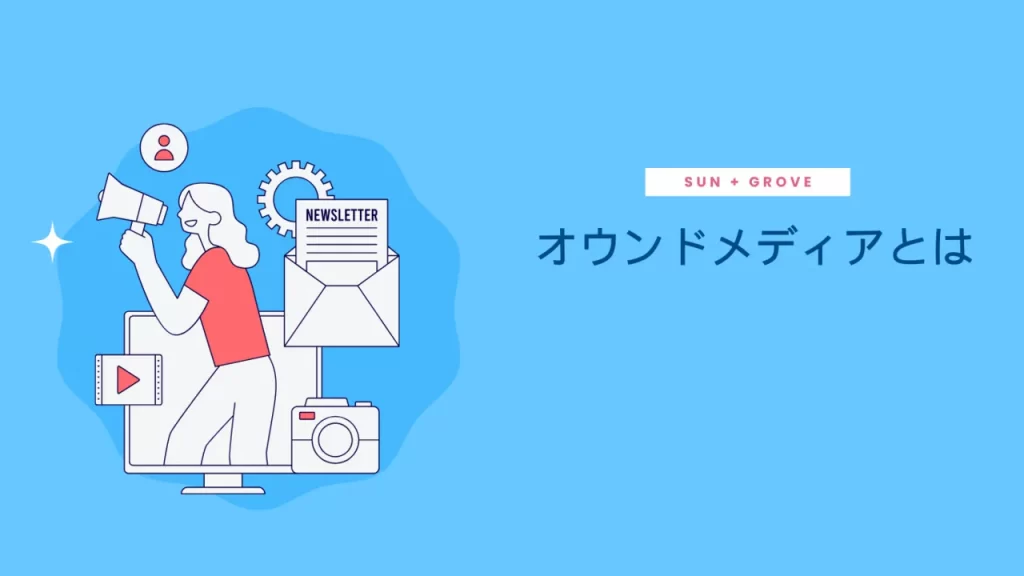
オウンドメディア(Owned Media)とは、企業が所有するメディアのことです。広義ではパンフレットや広報誌などもオウンドメディアに分類されますが、近年ではWebサイトや自社ブログなどを対象に用いられるのが一般的です。本記事においても、オウンドメディア=企業が所有するWebサイト・ブログという観点からお伝えしていきます。
オウンドメディアとトリプルメディア
企業の集客やマーケティング活動の核となる3つのメディアとして「オウンドメディア」「ペイドメディア」「アーンドメディア」が挙げられます。これらメディアの総称を「トリプルメディア」といい、それぞれがコンテンツの発信・仲介・拡散という役割をになっています。
| トリプルメディアの種類 | 意味 | 役割 | 例 |
|---|---|---|---|
| オウンドメディア | 企業が所有するメディア | コンテンツの発信 | Webサイト、自社ブログ |
| ペイドメディア | 企業が費用を払って広告を掲載するメディア | コンテンツの仲介(広告からオウンドメディアへ誘導) | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌のマス4媒体、Web広告 |
| アーンドメディア | ユーザーや消費者自身が情報を発信するメディア | コンテンツの拡散 | 口コミサイト、SNS、掲示板やQAサイト |
これらは、組み合わせて活用することで集客力のアップやマーケティング活動の円滑化につながります。オウンドメディアの集客に入る前に、このトリプルメディアの関係性は押さえておきましょう。
▼合わせて読みたい記事
コンテンツとは?意味と種類と制作ポイントを再確認
ペイドメディアとは?特徴や運用するメリットと効果、注意点を解説
アーンドメディアとは?その意味とオウンドメディアとの違いや運用する方法を解説
トリプルメディアとは?メリット・デメリットや戦略のポイントを事例から解説
オウンドメディアのメリット
オウンドメディアを活用する最大のメリットは「独自の声を届けられる」ところにあります。ペイドメディアやアーンドメディアはその性質上、企業が発信内容を完全にはコントロールできないため、オウンドメディアを活用することが競合他社との差別化につながりやすいのです。また、その自由度の高さを活かし「商品やサービスを知らない人」から「知っているけど買う動機がない人(迷っている人)」に至るまで、各ユーザーに最適化されたコンテンツを発信できるのも魅力です。
その他にもオウンドメディアには以下のようなメリットも存在します。
- 中長期的な集客が可能になる
- コンテンツは資産になる
検索エンジン上からオウンドメディアへの自然流入があれば、広告費をかけずとも無料で集客できます。広告と比べると即効性には劣りますが、中長期的に見たらコストパフォーマンスの優れた集客方法といえます。
くわえて、ブログ記事などユーザーの問題を解決するコンテンツはオウンドメディアに蓄積されていきます。Web上に残り続けるノウハウや情報は価値ある資産です。
オウンドメディアのデメリット
集客やマーケティングにおいて優秀なオウンドメディアですが、デメリットも確かに存在します。オウンドメディアのデメリットは主に以下の通りです。
- 速効性は期待できない
- 定期的な情報発信が欠かせない
- 立ち上げるまでに初期費用・工数がかかる
オウンドメディアを活用した集客はコンテンツマーケティングとよばれ、メディアの立ち上げ→コンテンツの作成・発信→メディアの成長→ファンの醸成→問い合わせや資料請求→商談という流れをとるため、広告に比べると即効性を期待できません。また、その過程では初期費用や人材の確保など、ある程度のコスト・工数をかける必要があります。
集客に強いオウンドメディアの始め方

集客に強いオウンドメディアを立ち上げるなら、以下の5つのステップを踏んでおくと安心です。
- コンセプトを策定する
- スタッフを確保する
- 配信基盤を確保する
- 必要なコンテンツの洗い出す
- コンテンツ制作体制を整える
では、それぞれの工程とそのポイントについて解説していきます。
コンセプトを策定する
集客に強いオウンドメディアを望むのなら、運営する目的や目標を明確にし、ターゲットとするユーザーのニーズや関心を把握することから始めましょう。
また、オウンドメディアのテーマや方向性、差別化要素などもこの時点で決めます。コンセプトは、オウンドメディアの基盤となるものなので、時間をかけてでもしっかりと考えるべきポイントです。
スタッフを確保する
オウンドメディアの運営には、コンテンツの企画・制作・編集・公開・分析など、さまざまな業務が発生します。円滑に運営し、集客力を高めていくのであれば、これらの業務を担当するスタッフをしっかりと確保することが重要です。
スタッフは、社内の人員を割り振るか、外部の専門業者に委託するか、あるいは両方を組み合わせるか、という選択肢があります。予算や人材の状況に応じて、最適な運営体制を構築しましょう。
配信基盤を確保する
オウンドメディアの配信基盤とは、コンテンツを公開するためのプラットフォームやツールのことです。Webサイトやブログを作る場合は、ドメインやサーバー、CMSなどを選びます。SNSを使う場合は、専用のアカウントやページを作成します。
配信基盤は、オウンドメディアの品質や効果に大きく影響する部分です。特にWebサイトの場合、通信が安定しないサーバーや扱いづらいCMSだと、のちのち公開することがほとんどです。以下の記事も参考にしつつ、慎重に選びましょう。
必要なコンテンツの洗い出す
オウンドメディアのコンテンツとは、ユーザーに提供する情報や価値のことです。コンテンツは、テキストや画像や動画など、さまざまな形式で表現できます。
コンテンツを洗い出す際には、ターゲットの検索ニーズや関心に合わせたキーワードを選び、それに応える内容を考えましょう。また、集客に強いオウンドメディアを目指すなら、競合のコンテンツや市場の動向も調査し、自社の強みや特色を生かしたコンテンツを作ることが重要です。
コンテンツ制作体制を整える
オウンドメディアのコンテンツを作るには、制作の流れやルール、スケジュールなどを決めておく必要があります。たとえば、以下のような点について事前に設定しておくのがおすすめです。
- 企画書や原稿のテンプレート
- 画像や動画の規格
- SEO対策や校正・添削の方法
このようにコンテンツ制作体制を整えることで、品質の高いコンテンツを効率的に作ることができます。そして、高品質なコンテンツはオウンドメディア集客の強い武器になるのです。
集客に強いオウンドメディア運営のポイント

集客に強いオウンドメディア運営を実現するためには、以下のような4つのポイントを押さえる必要があります。
- 定期的にコンテンツを発信する
- ゴールに近いところからコンテンツを作る
- コンテンツの一貫性を保つ
- PDCAを回す
では、それぞれについて解説していきます。
定期的にコンテンツを発信する
オウンドメディアの集客力を高めるのなら、定期的なコンテンツの更新はマストです。継続性こそがオウンドメディアを成長させます。とはいえ、とにかく大量のコンテンツを発信すれば良いというわけではありません。
ユーザーのニーズや関心に応じたキーワードやテーマを選び、価値ある情報を提供する必要があります。定期的に高い品質のコンテンツを発信することで、ユーザーの期待に応えるとともに、検索エンジンからの流入やSNSでの拡散も見込めるようになるのです。
ゴールに近いところからコンテンツを作る
オウンドメディアの目的は、集客・マーケティングであることを忘れてはいけません。オウンドメディアのコンテンツは、ユーザーの購買プロセスに沿って作る必要があります。
そのなかでも、最も重要なのは、ゴール(商談)に近いところにあるコンテンツです。たとえば、商材の導入事例やユースケース、FAQ、プライスリストなどです。これらのコンテンツは、ユーザーの購入意欲を高めるとともに、問い合わせや資料請求などのアクションに誘導する役割を果たすため、制作優先度が高いと考えておきましょう。
コンテンツの一貫性を保つ
オウンドメディアのコンテンツは、形はどうであれ、最終的には自社のブランドや商品・サービスの価値を知ってもらうためのものです。それを実現するためには、コンテンツの一貫性を保つことが重要といえます。
コンテンツの一貫性では、言い回しや表記、デザインやトーン&マナーなど、コンテンツの表現ももちろん大切ですが、”すべての掲載コンテンツが「商談創出」に向かっている”という共通認識をもって、制作に向き合うことも重要です。
PDCAを回す
オウンドメディアの運営は、一度構築したら終わりではありません。継続的に運営して改善していくことが集客力のアップにつながります。そのためには、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回すことが重要です。
PDCAサイクルとは、計画(Plan)を立てて実行(Do)し、効果を測定(Check)して改善(Act)するというサイクルのことです。オウンドメディアの運営では、コンテンツの効果測定や分析を行い、改善のための施策を実施することで、コンテンツの質や集客力を高めることができます。
▼合わせて読みたい記事
PDCAサイクルとは?古いといわれる理由・代わるものまで紹介
オウンドメディアの集客方法3選

オウンドメディアの集客方法として代表的なものは以下の3つです。
- SEO
- SNS
- Web広告
では、一つずつそのポイントや注意点を紹介します。
SEO
SEOとは「Search Engine Optimization」の略称で、検索エンジン最適化のことです。これに取り組むことで、自社のオウンドメディアが検索結果で上位に表示されるようにできます。検索結果の上位=検索ユーザーがクリックしやすいページとなるため、検索ボリューム(検索件数)の多いキーワードでSEOに取り組めば、それだけ集客力を高めることが可能です。
オウンドメディアの集客方法としてSEOに取り組む際のポイントは以下の通りです。
- ユーザーの検索ニーズに合わせたキーワードを選ぶ
- キーワードに応える質の高いコンテンツを作成する
- コンテンツのタイトルや見出し、URLなどを最適化する
- 内部リンクや外部リンクを効果的に活用する
- ページの表示速度やモバイル対応などを改善する
SEOで集客を成功させるためには、読者にとって有益なコンテンツの制作と、いかに検索エンジンにそのコンテンツの有益性を伝えるのかがカギになってきます。初心者でも取り組めるため、以下の動画や記事も参考にしながらSEOに挑戦してみましょう。
SEOからの集客の注意点
オウンドメディアの集客方法として、SEOに取り組むのであれば以下の3つの注意点も押さえておく必要があります。
- SEOは短期的に効果が出るものではない
- SEOのルールやトレンドは変化する
- YMYL領域は上位表示が難しい
Web上には膨大な量の記事やWebサイトが存在します。そんななかSEOは検索エンジンからの評価によって順位が決定するのです。そのため、膨大なページの中からあなたのオウンドメディア(もしくはその記事)を見つけ出し、他のページと比較し評価を下すまで一定の時間を要します。立ち上げたばかりのオウンドメディアならなおさらです。
また、SEOのルールやトレンドは日々変化します。特にコアアップデートと呼ばれる検索アルゴリズムの大きな変更で順位も大きく変動する可能性があります。高い順位を維持していたのにコアアップデートを機に圏外に飛ばされてしまうなんてことも少なくありません。
そして、YMYL領域(健康・医療分野や金融など、お金や人生に影響を与える分野)に関わるコンテンツは、その分野の専門家の監修を受けることを大前提とし、権威性・専門性が担保されて初めて上位表示の可能性が出てきます。ただでさえ奥が深く、答えのないSEOですが、YMYL領域に関しては特に高い権威性・専門性が求められるため注意が必要です。
▼合わせて読みたい記事
YMYLとは?対象の領域とSEOで必ず取り組みたい7つの対策ポイントを解説!
SNS
SNSは、ユーザーとのコミュニケーションや情報拡散に有効なツールです。オウンドメディアに紐付いたアカウントを作成・運用しフォロワーを獲得、ブログ記事などを発信すれば、オウンドメディアへの集客を増やすことができます。無料で始められ、魅力的な投稿の場合、拡散されることもあるため、オウンドメディアの集客力を高めるならまず試したい方法です。
オウンドメディアの集客にSNSを活用する際のポイントは以下の通りです。
- ターゲットユーザーが利用するSNSを選ぶ
- コンテンツの質と量を両立させる
- ユーザーとの双方向のコミュニケーションをとる
SNSには、FacebookやX(旧Twitter)、Instagramなどさまざまな種類がありますが、それぞれに特徴やユーザー層が異なります。自社のターゲットユーザーが利用するSNSを選ぶことで、効果的にアプローチすることができるのです。たとえば、若い女性に人気のあるInstagramは、ファッションやコスメなどのビジュアル重視の商品やサービスを紹介するのに適しています。また、YouTubeやTikTokといった動画サイトは若年層の利用率が高いという特徴があります。ターゲットユーザーが利用するSNSを選ぶことがオウンドメディア集客の第一歩といえるでしょう。
次に、SNSではコンテンツの質と量を両立させることが重要です。コンテンツの質とは、ユーザーにとって魅力的で有益な情報を提供することです。コンテンツの量とは、定期的に投稿することで、ユーザーの目に留まりやすくすることです。コンテンツの質と量を両立させることで、ユーザーのファン化や拡散効果を高めることができます。
そして、SNSの特徴の一つとして、”ユーザーとの双方向のコミュニケーション”がとれることが挙げられます。ユーザーからのコメントや質問に返信したり、ユーザーの投稿にいいねやシェアをしたりすることで、信頼関係を構築しやすくなるのです。また、ユーザーのニーズや意見をヒアリングすることもできるため、コンテンツ制作や商品・サービスの改善に活かせるのも魅力的です。
SNSからの集客の注意点
SNSを活用してオウンドメディアの集客力を高めるのなら、以下の2点のポイントは注意しておきましょう。
- SNSの特徴やトレンドに合わせる
- SNSの運用体制や効果測定をしっかりする
SNSは、常に変化しているものです。SNSの特徴やトレンドに合わせて、コンテンツの形式や内容を工夫し適応することが必要です。たとえば、動画やストーリーなどのコンテンツが人気になっている場合は、それらを取り入れることで、ユーザーの興味を引きやすくなります。また、時事ネタや季節ネタなどの話題にも敏感になることで、ユーザーとの共感を生みやすくなるでしょう。常に様々な情報にアンテナを張っておくことが大切です。
また、SNSの運用には、人的リソースや時間がかかります。コンテンツの制作やチェック、投稿や返信、トラブル対応など、やるべき業務は意外と少なくありません。そのため、SNSの運用体制をしっかりと整えることが大切です。また、SNSの運用を成果につなげるためには、効果測定が不可欠です。フォロワー数やいいね数、シェア数、クリック数などの指標をモニタリングし、改善点を見つけ出すことが欠かせません。無料で始められる施策として魅力的ではありますが、一定のリソースを割いて根気強く運用していく必要があることは念頭に置いておきましょう。
Web広告
Web広告とは、インターネット上のメディアに掲載する広告のことです。検索エンジンやWebサイト、SNS、動画サイトなどに表示されます。Web広告は、年齢や性別、趣味嗜好に合わせたターゲティングも可能なため、オウンドメディアへの集客を増やすことができます。
オウンドメディアの集客にWeb広告を活用する際のポイントは以下の通りです。
- オウンドメディアの目的に合わせて広告の種類を選ぶ
- ターゲットユーザーに合わせて広告の内容を工夫する
- 広告の効果測定と改善を継続する
Web広告には、検索エンジンに表示されるリスティング広告や、SNSに表示されるSNS広告、外部サイトに表示されるディスプレイ広告など、さまざまな種類があります。それぞれに特徴や効果が異なるので、オウンドメディアの目的に合わせて広告の種類を選ぶことが重要です。たとえば、認知度を高めたい場合は、画像や動画でインパクトのあるディスプレイ広告がおすすめです。一方、購入や申し込みにつなげたい場合は、ニーズの高いユーザーに届くリスティング広告が効果的といえます。
また、Web広告の内容は、ターゲットユーザーに合わせて工夫することが大切です。ターゲットユーザーの年齢や性別、興味や関心、課題やニーズなどを分析し、それに応えるようなメッセージやキャッチコピー、画像や動画を作成しましょう。広告からオウンドメディアに誘導するためには、クリックしたくなるような特典やキャンペーン、CTA(コール・トゥ・アクション)を設定するのも大切です。
そして、Web広告の運用に欠かせないのが、効果測定と改善を継続することです。広告の効果測定には、広告の表示回数やクリック率、コンバージョン率などの指標をモニタリングすることが求められます。これらの指標をもとに、広告の内容や配信条件を改善することで、より効果的な広告にすることができるのです。
▼合わせて読みたい記事
Web広告の種類とは?運用することで期待できる効果・メリットについても解説
Google広告とは?料金や配信の種類・設定方法などを紹介!運用のポイントもあわせて解説
Web広告からの集客の注意点
オウンドメディアの集客にWeb広告を活用する際は、以下の点について注意する必要があります。
- 広告の予算や期間を適切に設定する
- 広告の内容や配信条件に法令や規約に違反しない
まず、Web広告を運用するには、広告の予算や期間を適切に設定することが大切です。予算や期間を設定する際には、オウンドメディアの目的やターゲットユーザー、広告の種類や効果などを考慮する必要があります。基本的にWeb広告は、掲載期間が長くなるほど費用が高くなり費用対効果も低くなっていく傾向にあるため、予算や期間を過剰に設定したり、見積もりが甘かったりすると、「費用をかけたのに集客ができない」というリスクがあるのです。そのため、広告の効果測定を行いながら、予算や期間を最適化することも大切といえるでしょう。
そして、Web広告の内容や配信条件には、法令や規約に違反しないことが求められます。法令や規約に違反すると、広告が停止されたり、罰金や損害賠償を請求されたりする可能性もあるのです。たとえば、虚偽や誇大な表現、差別的な表現、他社の商標や著作物の無断使用などは避ける必要があります。くわえて、広告の種類や配信先によっても、異なる法令や規約が適用される場合があります。広告を運用する前に、必ず法令や規約を確認しておきましょう。
集客に強いオウンドメディアコンテンツの作成方法

オウンドメディアで集客に強いコンテンツを作成するなら、以下の4つのポイントは押さえておきたいところです。
- ペルソナを設定する
- ペルソナの悩みを明らかにする
- 悩みを解決するコンテンツを考える
- コンテンツSEOに取り組む
では、一つずつ解説していきます。
ペルソナを設定する
ペルソナとは、自社のターゲットユーザーを”仮想の人物像として具体化”したものです。ペルソナを設定することで、ユーザーのニーズや課題、検索意図などを把握しやすくなります。ペルソナに合わせたコンテンツを作成すれば、ユーザーの関心を引き、信頼関係を築くことができます。具体例としては、以下のようなペルソナが考えられます。
- ペルソナA:30代男性、会社員、結婚して子供が2人、趣味はゴルフ、家族との時間を大切にする、車に興味があるが購入には慎重、車の情報はインターネットや雑誌で収集する
- ペルソナB:20代女性、大学生、ショッピングや旅行が好き、SNSで情報発信や交流を楽しむ、美容や健康に関心が高い、コスメやサプリメントの購入は口コミやレビューを参考にする
上記のようにペルソナの設定には、年齢や性別、職業や趣味、価値観やライフスタイルなどの基本情報や、ユーザーが抱える問題や目標、解決策や情報源などの詳細情報を考慮する必要があります。たとえば、ペルソナAであれば「なるべく費用をかけず納得のいく車を購入したい」という潜在的なニーズが考えられるため、「費用をかけずに車を購入する方法」を解説した記事などが刺さりやすいと考えられます。一方、ペルソナBであれば、「口コミやレビューの良いコスメが欲しい」という潜在的なニーズがあるため、「肌質別の人気コスメの口コミまとめ」のようなコンテンツに興味を示すでしょう。
▼合わせて読みたい記事
ペルソナとは?マーケティングに欠かせない理由と具体的な作り方を紹介!
ペルソナの悩みを明らかにする
ペルソナから得られるニーズに対して、悩みを解決するコンテンツを作成することで、ユーザーの疑問や不安を解消し、最終的に購買意欲の向上につなげることができます。ペルソナの悩みを明確にするには、以下のような方法があります。
- ユーザーインタビューを行う
- キーワードリサーチを行う
- 競合サイトを分析する
まず、直接ユーザーに話を聞くことで、ユーザーの悩みやニーズを深く理解することができるでしょう。ユーザーインタビューでは、オープンエンドの質問(回答に制約を設けないタイプの質問)を多く使い、ユーザーの本音を引き出すことがポイントです。
次に、ユーザーが検索エンジンで入力するキーワードを調べることで、ユーザーの悩みや関心事を把握するという手があります。キーワードリサーチでは、長いキーワードや質問形式のキーワードに注目すると、ユーザーの悩みが具体的に分かりやすくなる傾向にあるため、意識してみましょう。
そして、同じ商品やサービスを提供する競合サイトのコンテンツを分析することも大切です。そうした競合分析からユーザーの悩みやニーズを推測することができます。競合サイトの分析では、タイトルや見出し、本文の内容や構成、画像や動画などのメディア、CTA(コール・トゥ・アクション)などに注目すると、コンテンツの特徴や工夫が分かりやすくなります。もちろん、まるパクリはご法度ですが、コンテンツ作成のヒントを得るにはもってこいの方法です。
悩みを解決するコンテンツを考える
ペルソナの悩みを明確にしたら、次にその悩みを解決するコンテンツを考える企画段階です。悩みを解決するコンテンツを企画する際には、以下のような点がポイントになります。
- ベネフィットを伝える
- プルーフを示す
- ストーリーを語る
まずは、ユーザーにとってのメリットや価値を具体的に伝えることで、ユーザーの関心を引くことが重要です。ベネフィットを伝えるには、自社の商品やサービスの特徴や機能を単に示すだけでなく、そのコンテンツがユーザーの悩みをどのように解決するかを明確にし、「悩みが解決した未来」を想像させることがポイントです。
そのなかで、ユーザーにとっての信頼性や安心感を高めるために、プルーフ(証拠)を示すことが効果的といえます。プルーフを示す際は、数字やデータ、事実や根拠、第三者の評価や口コミなどを用いるのが王道といえるでしょう。
そして、ユーザーにとっての感情や共感を呼び起こすために、ストーリー(物語)を語ることも効果的です。ストーリーを語る際は、商品やサービスを使った成功事例や体験談、ユーザーのビフォーアフター、コンテンツを読んだことでどのような変化があったかなどを示せると良いでしょう。
▼合わせて読みたい記事
ストーリーテリングとは?意味、やり方、事例紹介など交えて解説
コンテンツSEOに取り組む
コンテンツSEOとは、検索エンジンに優しく、ユーザーにとって有益なコンテンツを作成することです。コンテンツSEOに取り組むことで、検索結果の上位にコンテンツが表示されやすくなり、検索からの集客を増やすことができます。コンテンツSEOに取り組む際は、以下のようなポイントを押さえておく必要があります。
- キーワードを選定する
- コンテンツの構成を考える
- キーワードを適切に配置する
- ユーザーファーストなコンテンツを目指す
コンテンツSEOにおいて、キーワードは非常に重要な要素です。キーワードとは、ユーザーが検索エンジンに入力する単語やフレーズのことであり、これを選定することで、ユーザーの検索意図やニーズを把握することができます。キーワードを選定する際には、ペルソナに合わせる、ロングテールにする、競合を分析するといったポイントに注意しましょう。
次に、コンテンツの構成を考えます。コンテンツのタイトルや見出し、本文の内容や順序、画像や動画などのメディアの配置などを決めていく段階です。コンテンツの構成を考えることで、コンテンツの品質やわかりやすさを高めることができます。コンテンツの構成を考える際には、タイトルを工夫する、見出しを設定する、本文を充実させる、画像や動画、グラフや表を活用することなどが大切になってきます。
また、ユーザーが検索するキーワードをコンテンツに適切に配置するのも肝心です。適切なキーワード配置ができれば、検索エンジンにコンテンツの内容をしっかりと理解させることができます。キーワードを配置するには、タイトルや見出し、本文の冒頭や結び、URLやメタデータなどに注目することがポイントです。
そして、コンテンツSEOでは、ユーザーファーストなコンテンツを目指す必要があります。構成に沿って文章を書くことももちろん大事ですが、コンテンツの執筆をする際には、読みやすさ・分かりやすさが最も注力すべき点といえます。たとえば、専門用語や難解な言葉を使う場合は、必ず定義や説明を加えることや、文章の構成や段落の区切りを工夫することが大切です。ユーザーの理解度や興味度を高めることは、検索エンジンからの高評価につながるのです。
▼合わせて読みたい資料
集客に困らなくなる!コンテンツSEO戦略
オウンドメディアの集客成功事例

オウンドメディアには、独立型と公式サイト一体型があります。独立型のオウンドメディアは、コーポレートサイトなどの公式サイトとは別に作られ、製品やサービスの周辺情報・広報やブランディングに特化したWebサイトです。一方、公式サイト一体型のオウンドメディアは、コーポレートサイトやサービスサイトなどの公式サイトの中でブログ記事を運用している形が典型的です。
では、具体的にどのようにオウンドメディアの集客を成功させているのか、実際に運用されている事例を見てみましょう。
▼合わせて読みたい記事
コーポレートサイトとは? 制作する目的やポイント・成功しているサイトの例を紹介!
サービスサイトとは?コーポレートサイトとの違い、作成の目的を解説!
サイボウズ式(サイボウズ株式会社)

サイボウズ式は、サイボウズ株式会社が運営する独立型のオウンドメディアです。「新しい価値を生み出すチームのメディア」として、企業の認知度向上とブランディングを目的に運営されており、”製品のPRにつなげない”ことを徹底しています。
サイボウズ式の主なコンテンツのカテゴリは、以下の通りです。
- カイシャ・組織
- 働き方・生き方
- 家族と仕事
- サイボウズ
運営企業と直接関係のあるコンテンツは「サイボウズ」のカテゴリのみ。その他は、チームワーク、マネジメント、キャリア、働き方など、仕事に関するコンテンツ内容を多く発信しています。ワークスタイルや仕事の意義について関心のある読者がターゲットとして設定されていることが分かります。
ferret(株式会社ベーシック)
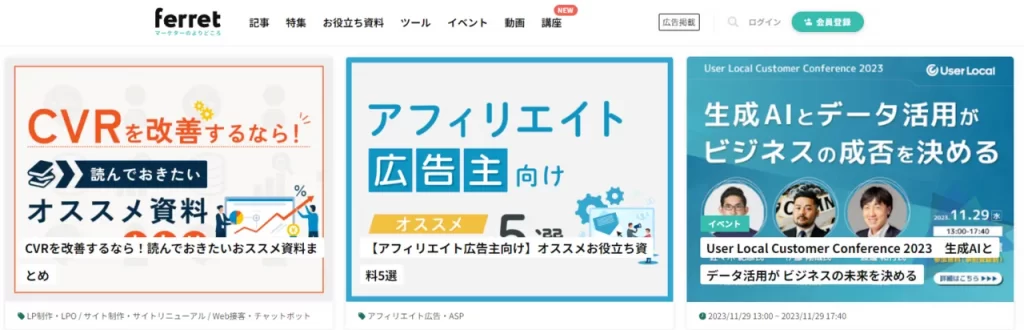
ferretは、株式会社ベーシックが運営する独立型のオウンドメディアです。「マーケターのよりどころ」をコンセプトに、SEO(検索エンジン最適化)やSNSマーケティングなどのWebマーケティングを体系的に学べる全300の講座、施策に利用できるツールの紹介まで、幅広いコンテンツが用意されています。
オウンドメディアと連動させる形で、セミナーの開催やメルマガの配信も行っており、コンテンツマーケティングへ精力的に取り組んでいることが分かります。駆け出しのマーケターやWebの知識をつけたい社会人をターゲットに、有益な情報を提供してくれるメディアです。
ドリップしよう。- Shall we drip? – (キーコーヒー株式会社)

「ドリップしよう。- Shall we drip? – 」は、キーコーヒー株式会社が運営する独立型のオウンドメディアです。コーヒーを美味しく嗜むための知識を中心に、気分転換や集中力を高めるためのノウハウについてのコンテンツも発信しています。
キーコーヒー株式会社の公式Instagramアカウントとも連携しており、”#キーコーヒー”をつけてコーヒーシーンを投稿してもらうという取り組みもしています。アーンドメディアとの相乗効果で、コーヒー好きの方への広いアプローチを実現しているオウンドメディアです。
壁紙マッチング®️(有限会社イガラシ)

壁紙マッチング®️は、有限会社イガラシが運営する公式サイト一体型のオウンドメディアです。壁紙や床材の張り替えなどのサービスの料金・流れも説明しており、サービスサイトとしての運用も想定された作りになっています。
ブログ・施工事例では、実際の施工過程をビフォーからアフターまで細かく写真付きで紹介しています。住まいの壁紙やフローリングの張り替えを検討中のターゲットに対し、安心して仕事を頼んでもらうためのコンテンツが充実したオウンドメディアです。
▼合わせて読みたいインタビュー記事
有限会社イガラシ 様インタビュー「ホームページからの集客が軌道に乗り、顧客獲得コストの15%削減に成功!お客様によりよいサービスを提供できるように。」(サングローブ株式会社)
松濤明武会(松濤明武会 空手教室)

空手教室を運営する松濤明武会の公式サイト一体型のオウンドメディアです。ブログでは、入会キャンペーンのお知らせだけではなく、実践的な受けや突きの上達方法などの空手に関するコンテンツを発信しています。
実際に記事で使用されている画像やYouTube動画の多くが、生徒(子ども)であることからも分かるように、空手教室に関心のある保護者をターゲットに置いているオウンドメディアといえます。
▼合わせて読みたいインタビュー記事
松濤明武会 様インタビュー「月間平均13,000PV!運用3年で成長率300%超えを実現!
ホームページだけで毎月約100件の問い合わせを獲得できています。」(サングローブ株式会社)
オウンドメディアの集客は企業を成長させる

オウンドメディアは、企業が自らの知識やノウハウ、価値を自由に提供し、コンテンツの発信という名のコミュニケーションを通じて、ターゲットとなる人々との絆を深めるための強力なツールです。その集客力の向上は単なるマーケティング手法以上に、企業文化やビジョンを具現化し、組織全体を成熟させることにつながります。
ぜひ、本記事を参考に、あなたの企業もオウンドメディアの集客力を高める取り組みに注力してみてはどうでしょうか。その先にあるのは、自社ファンの獲得であり、企業の飛躍的な成長であるはずです。
ー集客にお困りの方へー

集客にはインターネット活用が必須!
ネット集客をはじめるにあたって、把握しておきたいことを、分かりやすくまとめました!ネット集客の理解のために、まずはこの資料をご覧ください。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
