
ページ表示速度はSEOで重要!ページスピードの測定方法や改善ポイントを解説
GoogleやYahooで調べものをする時、サイト表示が遅いとイライラしてしまうことがあるはずです。なかなか表示されない場合は、別のサイトに移動するケースも多いです。
このように、ページ表示速度は、サイトを訪れるユーザーの満足度に大きく影響します。たった1秒遅くなったとしても、ユーザーにとっては不満に繋がるので離脱されます。
本記事では、そんなページ表示速度を確認する方法や、改善ポイントを解説していきます。計測におすすめのツールやページ表示速度が遅くなる原因も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそもページ表示速度とは?

ページ表示速度とは、名前の通りにWebサイトのページが表示される速度を指します。ページ表示速度の目安は3秒未満が良いと言われています。早い分には問題ありません。むしろ1秒であれば、ユーザーはストレスなくWebサイトを閲覧できるので訪問数が伸び、CVRが上がりやすくなります。
ページ表示速度がSEOに重要と言われる理由
ページ表示速度がSEOに重要と言われる理由は、Googleの検索順位アルゴリズムの指標として「Speed Update」が入っているからです。
つまりは、ページ表示速度がGoogleからの評価に関わってきます。遅いページほど評価が悪くなるので、検索順位の低下に繋がります。
ページ表示速度はユーザーの離脱率にも関係する
ページ表示速度は、Webサイトの離脱率にも関係します。Googleによると、表示速度が3秒だと直帰率は32%増加、5秒だと90%増加すると言われています。
たった5秒と思われがちですが、ユーザーにとっては見たい情報をすぐ見れないのはストレスに繋がります。ユーザーの直帰率が高いと感じたときは、ページ表示速度が遅くなっていないか確認したほうが良いです。
ページ表示速度を測定する方法

ページ表示速度が遅くなってないか測定する方法は、専用ツールを利用することです。
利用するなら、Googleが無料で提供するページ表示速度測定ツール「PageSpeed Insights」がおすすめです。URLを入れるだけで、スマートフォンとパソコンでのページ表示速度を無料で測定できます。
ウェブに関する主な指標の評価も「合格」「不合格」か教えてくれるので、サイト改善をすべきかどうか判断しやすいです。また、パフォーマンス・ユーザー補助・おすすめ方法・SEOの項目でも、問題がないか表示されます。
なお、同じくGoogleが提供する「Test My Site」という測定ツールもありましたが、2022年9月にサービス終了しています。
ページ表示速度が遅くなる主な原因
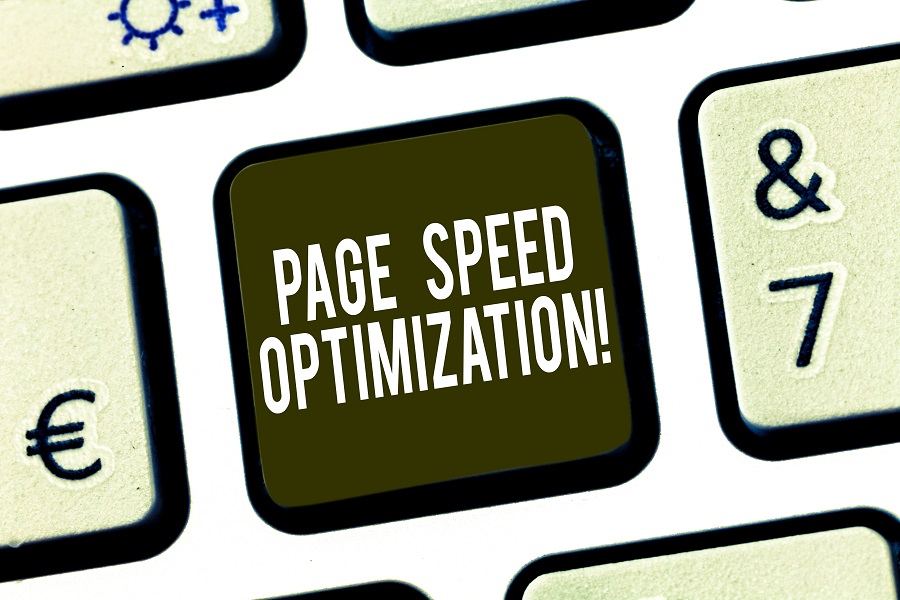
ページ表示速度が遅くなる主な原因は以下の6つです。
- 画像が重い・多い
- コンテンツの量が多い
- キャッシュが残りすぎている
- HTMLやCSSに無駄が多い
- JavaScriptが多い
- ページにアクセスが集中している
それぞれの原因について、簡単に解説していきます。
画像が重い・多い
画像は、ページ表示速度が遅くなる1番の原因でもあります。画像の量はもちろんですが、サイズや容量が重いとすぐにページ表示速度が遅くなります。よくネットサーフィンをする人であれば、画像だけ読み込みができない現象を目にしたことがあるはずです。
コンテンツの量が多い
コンテンツは、文章だけではなく画像や動画など様々な要素で構成されています。単純に、コンテンツの量が多いと、その分サイト自体の容量が重くなります。単純に、すべてのコンテンツを表示するまで、時間がかかることがページ表示速度の低下に繋がります。
HTMLやCSSに無駄が多い
WEBページを作る際は、HTMLやCSSなどのプログラミング言語が用いられます。複数の階層で複雑に設置されるため、直接ページに現れない無駄なプログラムが生まれることもあります。これがまさにページ速度が遅くなる原因です。ページ読み込みの際、余計に時間がかかってしまいます。
JavaScriptが多い
JavaScriptはWEBサイトの動作にバリエーションを持たすことができる便利なプログラミング言語です。JavaScriptを使用することで、WEB上でさまざまなアクションが可能になります。一方、メリットして扱える分、多用すれば負荷もかかります。データが蓄積されると重くなり、表示に遅延が生じるため注意が必要です。
ページにアクセスが集中している
ページにアクセスが集中している場合は、アクセス数に対しサーバーのスペックが釣り合っていません。アクセスが集中した際、サーバーが通信を捌ききれないと、重みに耐えきれず不安定のままページの読み込みに支障をきたします。あるいはサーバーダウンで閲覧不可能になるため、事前に対策しておくべきです。
ページ表示速度を改善するポイント

先に説明したページの表示速度が遅くなる原因を踏まえて、改善に有効な方法をご紹介します。
- 画像や動画の容量を軽くする
- コンテンツの整理を行う
- HTML・CSS・JavaScriptを見直す
- ブラウザキャッシュを用いる
- HTTP/2に対応したレンタルサーバを利用する
- サーバー自体のスペックを上げる
- AMPでページスピード高速化
- PWAの導入でUX向上
上記8つの改善を行えば、ページ表示速度が速くなることは間違いありません。遅いと感じたときは、ぜひ紹介している改善方法を試してみてください。
画像や動画の容量を軽くする
画像や動画は、ページ表示速度が重くなる1番の原因です。画質を良くするために、サイズを大きくしたり解像度を上げてしまうとどうしても重くなります。そのため、適切なサイズまで縮小、解像度の軽量化はしておいたほうが良いです。
また、「JPEG」「GIF」「PNG」などの画像ファイル形式も容量に関わってきます。JPEGは写真をはじめ、多くの色数が必要な画像に適した形式です。逆に色数の少ないイラストなどを保存すると、サイズが大きくなる傾向にあります。この場合はGIFがおすすめです。
コンテンツの整理を行う
コンテンツの量が多い場合は、不要なものはないか、内容を軽くできるものはないかなど確認して整理しましょう。PV数やCVRなどの数字をもとに精査すると良いです。
ユーザーにとってできる限り有益なページを作りたいと考えること自体は大賛成です。しかし、ページスピードの遅さゆえ、ユーザーに不満を感じさせ、あまつさえ離脱されるようなことになれば、本末転倒。せっかく用意した力作コンテンツも全て無駄になってしまいます。ページ表示速度改善のタイミングで、今一度見直してみてください。
HTML・CSS・JavaScriptを見直す
ページを構築するHTML・CSS・JavaScriptの見直しは必須です。無駄をなくすことで道(とページ)は開けます。意味のない改行やスペース、インデントなども表示速度を遅くさせる要因です。一つひとつは些細なことかもしれませんが、積み重なれば大きな影響を及ぼします。
なお、CSSやJavaScriptのファイルが複数ある場合、できる限りまとめることで、省エネとスピードアップが期待できます。軽量化されると同時にフォルダ管理のしやすさに寄与し、更新面でのメリットも生まれるでしょう。
ブラウザキャッシュを用いる
Web上には、ブラウザなどが表示したページのデータを一時的に保存する「キャッシュ」という機能があります。これがたくさん残ると、容量が重くなるためページ表示速度が遅くなります。定期的にブラウザキャッシュを消すようにしましょう。方法としては、「.htaccess」というファイルに指定のコードを入力するだけです。
HTTP/2に対応したレンタルサーバを利用する
HTTP/2に対応したレンタルサーバを利用すれば、クライアントとサーバの間の通信が効率化します。HTTP/2は、従来の「HTTP/1.1」からバージョンアップしたものです。
Webサイトの読み込みあたって必要なリソースを効率的に処理できる仕組みになっているので、コンテンツ自体の伝送速度アップにも寄与します。なお、前提としてサイトがSSL化対応していなければなりません。
サーバー自体のスペックを上げる
サーバー自体のスペックを上げれば、処理速度が速くなります。アクセスが集中した場合でもページ表示速度が遅くなりにくいです。サーバーが落ちる懸念もなくなるので、予算があるのであればサーバー強化しておいたほうが良いです。
AMPでページスピード高速化
AMP(Accelerated Mobile Pages)と呼ばれる、モバイルページを高速に表示させるフレームワークを用いりましょう。JavaScriptの制限やWebサイトをいちいち読み込ませることなく保存上のキャッシュだけでコンテンツを返す(表示させる)など極力負荷を軽減する仕様となっています。
サイトの構造が複雑になりすぎるとうまく機能しないケースもありますが、食べログやマイナビニュースなどアクセス数が多いサイトで利用されているほどです。有名なサイトの実績があるので、ページ表示速度に悩んでいるなら導入するのもアリです。
PWAの導入でUX向上
PWA(Progressive Web Apps)とは、アプリさながらのページスピードを可能とするWebサイトの機能です。仕組み上(実装されるのは’/service-worker.js’)、キャッシュによって高速化を実現しています。
オフラインでもサイトを利用できるため、データサイズやインターネット環境に悩まされることなく、スムーズな閲覧に寄与します。UX向上にも繋がるといってもいいでしょう。
ページ表示速度を改善してユーザーの離脱を防ごう!

今以上にもっと多くのユーザーにページを閲覧してもらうためには、表示速度の測定と改善が重要です。1秒遅くなるだけで、かなりのユーザーが離脱している可能性があるからです。
逆に考えると、改善によって1秒でも早くページが表示されれば、今以上にもっと訪問者が増えます。PV数だけでなくCVRにも繋がりやすくなるので、会社の売り上げに貢献できるはずです。本記事を参考に、ページ表示速度の見直しを図ってみてください。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
-
ARTICLE
2024/05/15( 更新)
Pinterest(ピンタレスト)のアカウントが停止されるケースを解説!再開方法とは?
情報管理・収集Pinterest
-
ARTICLE
2023/02/17( 更新)
インバウンドマーケティングとは?アウトバウンドマーケティングとの違いについても解説
企業経営事業戦略
- 用語
-
ARTICLE
2023/02/14( 更新)
製造業のマーケティングはニッチさを活かす!基本からWeb戦略まで徹底解説
企業経営業種別
- 集客
-
ARTICLE
2018/07/30( 更新)
【初心者向け】コンテンツマーケティングとは?始め方やよくある落とし穴を解説
企業経営事業戦略
- 用語
