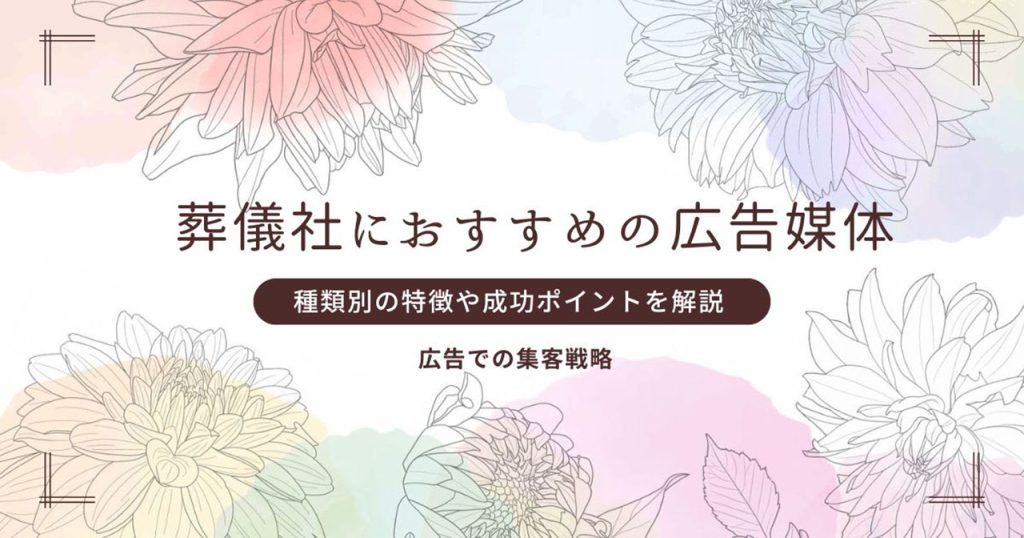
葬儀社の広告はどの媒体がおすすめ?種類別の特徴と成功のポイントを解説
「広告を出してみたいけれど、何から始めればいいのかわからない」「Web広告とチラシ、どちらが効果的なのか」と悩んでいる葬儀社の担当者の方は多いのではないでしょうか。
葬儀業界では、利用者がインターネットで情報を集め、複数の葬儀社を比較検討する時代になりました。待っているだけでは選ばれない環境の中で、広告を活用した集客は避けて通れない課題です。
本記事では、葬儀社におすすめの広告の種類から、費用目安、効果的な運用方法、注意点まで、初心者でもわかりやすく解説します。リスティング広告やGoogleローカル広告といったWeb広告から、チラシや新聞折込といったオフライン広告まで、それぞれの特徴と始め方を具体的に紹介しています。広告で成果を出したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
葬儀社が広告を始めるべき3つの理由

かつての葬儀業界では、地域のつながりや口コミだけで十分な集客ができていました。菩提寺との関係や地域コミュニティの紹介で、自然と依頼が舞い込んできた時代です。
しかし現在は、インターネットの普及や価値観の多様化により、利用者自らが複数の葬儀社を比較検討して選ぶ時代に変わりました。待っているだけでは選ばれない環境になっているのです。
広告を活用することで、自社の存在を知ってもらい、他社との違いを明確に伝えられます。ここでは、葬儀社が広告を始めるべき3つの理由を解説していきます。
葬儀業界の集客環境が大きく変化している
少子高齢化が進む一方で、葬儀業界への新規参入が相次いでいます。大手企業や異業種からの参入により、競争が激化し、価格競争も厳しくなりました。地域に根差した中小葬儀社であっても、何もしなければ大手に顧客を奪われてしまうリスクが高まっています。
家族葬や直葬といった小規模な葬儀形式が主流になり、利用者のニーズも多様化しました。「費用を抑えたい」「家族だけで静かに見送りたい」「宗教色のない式にしたい」など、求められるサービスは人それぞれです。このような環境では、自社がどんな強みを持ち、どんな顧客に選ばれるべきかを明確に発信する必要があります。広告は、その発信手段として欠かせないツールなのです。
事前相談・比較検討する利用者が増加中
「終活」という言葉が定着し、元気なうちから自分の葬儀について考える人が増えています。かつては急な逝去に慌てて葬儀社を探すケースが大半でしたが、今は生前に複数の葬儀社を比較し、事前相談や見積もりを取る利用者が増加中です。
この変化は葬儀社にとって大きなチャンスです。いざという時ではなく、平時の段階で接点を持てれば、信頼関係を築きやすくなります。事前相談会の案内や資料請求を促す広告を展開することで、将来的に自社を選んでもらえる可能性が高まります。比較検討の段階で選択肢に入るためには、積極的な情報発信が不可欠です。
広告を活用すれば新規顧客を安定的に獲得できる
口コミや紹介だけに頼る集客方法は、安定性に欠けます。良い評判が広がるまでには時間がかかりますし、悪い評判が立つと挽回が困難です。広告を活用すれば、自社でコントロールできる集客の仕組みを作れます。
Web広告なら「〇〇市 葬儀社」と検索した人に即座にアプローチでき、チラシなら地域の高齢者層に確実に情報を届けられます。広告費をかけた分だけ、問い合わせや相談の件数を増やせる可能性が高まるのです。もちろん闇雲に広告を出しても効果は出ません。ターゲットや広告媒体を正しく選び、戦略的に運用することで、安定した新規顧客の獲得が実現できます。
葬儀社向けの広告は「Web」と「オフライン」の2種類

広告にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や向き不向きがあります。葬儀社の場合、ターゲット層や商圏エリア、予算によって最適な広告媒体は異なります。闇雲にすべての広告に手を出すのではなく、自社に合った方法を選ぶことが成功の第一歩です。
葬儀社向けの広告は大きく分けて「Web広告」と「オフライン広告」の2種類に分類できます。それぞれの特性を理解し、組み合わせて活用することで、より効果的な集客が可能になります。
ここでは、葬儀社が知っておくべき広告の基本的な分類と、その違いについて解説します。
Web広告とオフライン広告の違いを理解しよう
Web広告とは、インターネット上で展開する広告のことです。GoogleやYahoo!の検索結果に表示されるリスティング広告、SNSで表示されるSNS広告、Googleマップに表示されるローカル広告などが代表例です。スマートフォンやパソコンを使う層に効果的で、効果測定がしやすく、予算を柔軟に調整できるメリットがあります。
一方、オフライン広告は、チラシや新聞折込、看板など、インターネットを介さない従来型の広告です。高齢者層や、Web検索をあまり利用しない層にもリーチできる点が強みです。紙として手元に残るため、保管されやすく「いざという時」に思い出してもらえる可能性があります。
葬儀社の場合、どちらか一方に偏るのではなく、Web広告で若年層や事前相談層を狙い、オフライン広告で地域の高齢者層にアプローチするといった使い分けが効果的です。
【Web広告】葬儀社向けおすすめ広告4選

インターネットの普及により、葬儀社を探す際にまずWeb検索を行う利用者が増えています。「〇〇市 葬儀社」「家族葬 費用」といったキーワードで検索し、複数の葬儀社を比較検討するのが一般的です。Web広告は、こうした検索行動を起こしている顕在層に直接アプローチできる強力な手段です。
ここでは、葬儀社が活用すべきWeb広告を4つ紹介します。
- リスティング広告
- ローカル広告
- SNS広告
- ポータルサイト掲載
それぞれの特徴や費用目安、始め方を具体的に解説しますので、自社に合った方法を見つけてください。
リスティング広告|検索した人に直接アプローチ
リスティング広告とは、GoogleやYahoo!の検索結果ページの上部に表示される広告です。「広告」と小さく表示されますが、検索結果と同じように見えるため、クリックされやすい特徴があります。葬儀社を探している人が検索した瞬間に、自社の情報を届けられる即効性の高い広告手法です。
最大の強みは、ニーズが明確な顕在層にピンポイントでアプローチできる点です。「〇〇市 葬儀 急ぎ」と検索している人は、まさに今すぐ葬儀社を探している緊急性の高い顧客です。こうしたキーワードで広告を出せば、高い確率で問い合わせにつながります。費用はクリックされた回数分だけ発生する仕組みなので、無駄な広告費を抑えられるのもメリットです。
リスティング広告の特徴と費用目安
リスティング広告は、キーワード単位で広告を出稿できるため、ターゲットを細かく設定できます。たとえば「家族葬」「一日葬」「直葬」といった葬儀形式ごとに広告を分け、それぞれに適した訴求文を表示させることが可能です。地域名を組み合わせれば、商圏エリア内の利用者だけに広告を届けられます。
費用はキーワードの競合度によって変動します。葬儀業界の場合、1クリックあたり200円〜1,000円程度が相場です。月額予算は5万円〜30万円程度から始められます。競合が多い都市部ではクリック単価が高くなりやすいため、予算に応じてキーワードを絞り込む工夫が必要です。問い合わせ1件あたりの獲得コスト(CPA)は、1万円〜5万円程度を目安にすると良いでしょう。
葬儀社がリスティング広告を始める方法
リスティング広告を始めるには、Google広告やYahoo!広告のアカウントを作成します。初めての場合は、Google広告から始めるのがおすすめです。管理画面で広告文を作成し、予算とキーワードを設定すれば、すぐに配信を開始できます。
ただし、効果を出すには広告文の工夫やキーワード選定、ランディングページ(広告のリンク先)の最適化が欠かせません。初心者の場合、最初は少額予算でテスト運用し、反応を見ながら改善していくのが失敗しないコツです。専門的な知識が必要なため、不安な場合は運用代行業者に相談するのも一つの方法です。
ローカル広告|地図検索で上位表示できる
ローカル広告とは、Googleマップやローカル検索結果に表示される広告です。「〇〇市 葬儀社」と検索した際、地図上に「広告」と表示される店舗情報がこれに該当します。通常の検索結果よりも目立つ位置に表示されるため、地域で葬儀社を探している顕在層に強くアプローチできます。
葬儀社のような地域密着型ビジネスにとって、ローカル広告は非常に効果的です。地図上で視覚的に位置関係がわかるため、「近くの葬儀社を探したい」というニーズに直接応えられます。
クリックすると電話番号やルート案内が表示されるため、問い合わせまでの導線がスムーズです。リスティング広告と組み合わせることで、検索結果ページを広く占有でき、より高い集客効果が期待できます。
ローカル広告の特徴と費用目安
ローカル広告の最大の特徴は、地図上で視認性が高いことです。検索結果ページの上部に地図と店舗情報が大きく表示されるため、ユーザーの目に留まりやすくなります。スマートフォンで検索した場合は画面の大半を占めるため、とくに効果的です。
費用はリスティング広告と同様、クリック課金制です。1クリックあたり100円〜500円程度が相場で、月額予算は3万円〜20万円程度から始められます。競合の多い都市部ではクリック単価が高くなる傾向にありますが、地域を限定して配信できるため、無駄な広告費を抑えられます。Googleビジネスプロフィールに登録していることが前提となるため、まだ登録していない場合は、まず無料登録を済ませておきましょう。
葬儀社がローカル広告を始める方法
ローカル広告を始めるには、まずGoogleビジネスプロフィールに店舗情報を登録する必要があります。住所、電話番号、営業時間、サービス内容、写真などを充実させておくことで、広告の効果が高まります。口コミや評価も表示されるため、日頃から良いサービスを提供し、高評価を集めておくことも重要です。
登録後は、Google広告の管理画面から「ローカルキャンペーン」を選択し、配信設定を行います。配信エリアは商圏に合わせて細かく設定でき、「〇〇市内のみ」「半径10km以内」といった指定が可能です。広告文はGoogleビジネスプロフィールの情報が自動的に使用されるため、魅力的な店舗情報を事前に整えておくことがポイントです。リスティング広告と同時に運用することで、検索結果ページでの露出を最大化できます。
SNS広告|潜在層へのアプローチに有効
SNS広告とは、FacebookやInstagram、LINE、X(旧Twitter)などのSNS上で配信する広告です。年齢や性別、地域、興味関心などで細かくターゲティングできるため、「終活に興味がある50代」「親の介護をしている40代」といった潜在層にアプローチできます。
リスティング広告が「今すぐ顧客」に強いのに対し、SNS広告は「将来の顧客」を育てる広告です。事前相談会の案内や、終活に関するお役立ち情報を発信することで、いざという時に思い出してもらえる関係性を築けます。画像や動画を使った視覚的な訴求ができるため、斎場の雰囲気やスタッフの人柄を伝えやすいのも特徴です。
SNS広告の特徴と費用目安
SNS広告の強みは、細かいターゲティングができる点です。たとえばFacebook広告では、「50歳以上」「〇〇市在住」「終活に興味がある」といった条件で広告を配信できます。Instagram広告は視覚的な訴求に優れており、清潔感のある斎場の写真や、スタッフの温かい対応を伝える投稿が効果的です。
費用は月額5万円〜20万円程度から始められます。クリック単価は50円〜300円程度と、リスティング広告よりも安い傾向にあります。ただし、SNS広告は即効性が低く、認知度向上やブランディングを目的とした中長期的な施策と考えた方が良いでしょう。問い合わせに直結するというよりも、将来的な顧客との接点を作る広告です。
葬儀社がSNS広告を始める方法
まずは自社に合ったSNSを選びましょう。50代以上の終活層にアプローチしたいならFacebookやLINE、若い世代(親の葬儀を検討する子ども世代)にアプローチしたいならInstagramが適しています。各SNSの広告管理画面からアカウントを作成し、広告画像と文章を用意すれば配信を開始できます。
SNS広告で成果を出すには、「売り込み感」を出さないことが重要です。「事前相談で不安を解消しませんか?」「終活セミナー開催のお知らせ」といった、役立つ情報を提供する姿勢が求められます。広告からLINE公式アカウントへ誘導し、継続的にコミュニケーションを取る仕組みを作るのも効果的です。
ポータルサイト掲載|即効性は高いが注意も必要
葬儀専門のポータルサイトとは、複数の葬儀社を比較検討できるWebサイトのことです。「いい葬儀」や「小さなお葬式」といった大手サイトが代表例です。これらのサイトに自社情報を掲載することで、葬儀社を探している利用者にアプローチできます。
ポータルサイトのメリットは、すでに集客力のあるプラットフォームを活用できる点です。SEO対策やWeb広告を自社で行う必要がなく、サイト側が集めた顧客に自社をアピールできます。口コミや評価が掲載されるため、良い評判があれば新規顧客の信頼を得やすくなります。ただし、費用面や競合との比較に注意が必要な広告手法でもあります。
ポータルサイト掲載の特徴と費用目安
ポータルサイトの掲載には、大きく分けて「掲載料型」と「成果報酬型」の2種類があります。掲載料型は、月額固定費を支払って自社情報を掲載する形式です。費用は月額3万円〜15万円程度で、サイトや掲載プランによって異なります。
成果報酬型は、ポータルサイト経由で問い合わせや成約があった場合に手数料を支払う形式です。相場は成約金額の20%〜30%、または1件あたり7万円〜10万円程度です。初期費用がかからないメリットがありますが、手数料が高額になりやすく、利益率が下がるリスクがあります。とくに低価格の家族葬や直葬の場合、手数料の割合が大きくなり、採算が合わないケースもあります。
ポータルサイトを利用する際の注意点
ポータルサイトの最大の注意点は、価格競争に巻き込まれやすいことです。サイト内では多数の葬儀社が横並びで比較されるため、価格の安さで選ばれがちです。自社の強みやサービスの質を十分にアピールできないまま、価格だけで判断されてしまうリスクがあります。
また、ポータルサイト経由の顧客は「とりあえず見積もりを取っている」段階の人も多く、成約率が低い傾向にあります。複数の葬儀社に同時に見積もり依頼をしているため、対応に時間がかかる割に成約に至らないケースも少なくありません。ポータルサイトは即効性がある一方で、依存しすぎると利益率が下がり、経営を圧迫する可能性があります。自社のWeb広告やMEO対策と並行して活用し、バランスを取ることが大切です。
【オフライン広告】地域密着型におすすめの広告3選

Web広告が主流になりつつありますが、オフライン広告もまだまだ有効な集客手段です。とくに葬儀業界の主要顧客である高齢者層は、インターネットをあまり利用しない方も多く、チラシや新聞折込といった従来型の広告が効果を発揮します。
ここでは、葬儀社におすすめのオフライン広告を3つ紹介します。
- チラシ・ポスティング
- 新聞折込広告
- 看板・交通広告
オフライン広告の強みは、物理的に手元に残る点です。Webサイトは見たらすぐに忘れられてしまうことも多いですが、紙のチラシは「いざという時のために」と保管されるケースがあります。
チラシ・ポスティング|高齢者層に確実に届く
チラシ・ポスティングは、地域の各家庭に直接チラシを配布する広告手法です。Web広告と違い、インターネットを使わない高齢者層にも確実に情報を届けられます。配布エリアを自社の商圏に絞り込めるため、無駄なく効率的にアプローチできるのが特徴です。
チラシの最大の強みは、保存性の高さです。葬儀は「いつ必要になるかわからない」サービスのため、チラシを見た瞬間に問い合わせることは少ないです。しかし、冷蔵庫や引き出しに保管しておき、いざという時に取り出して連絡してもらえる可能性があります。紙という媒体だからこそ、「とりあえず取っておこう」と思わせる安心感があるのです。
チラシ・ポスティングの特徴と費用目安
チラシ配布にかかる費用は、印刷費とポスティング代の2つです。印刷費はA4サイズで1枚あたり3円〜10円程度、ポスティング代は1枚あたり3円〜7円程度が相場です。たとえば1万枚配布する場合、合計で6万円〜17万円程度の費用がかかります。
反響率(チラシを見て問い合わせをする割合)は0.01%〜0.1%程度と言われています。1万枚配布して1件〜10件程度の反響があれば成功と言えます。即効性は低いですが、長期的に保管されることで「いざという時」に思い出してもらえる可能性があります。配布エリアや配布時期、チラシのデザインによって反響率は大きく変わるため、テストを繰り返しながら改善していくことが大切です。
効果的なチラシを作る3つのポイント
チラシで成果を出すには、デザインと内容が重要です。まず1つ目のポイントは、「安心感」を伝えることです。料金の明確な表示、24時間対応、創業年数や実績など、利用者が不安に感じるポイントを先回りして解消する情報を掲載すると良いです。
2つ目は、「保管したくなる情報」を載せることです。単なる広告だけでなく、葬儀の流れやマナー、連絡先リストなど、役立つ情報を盛り込むと保管されやすくなります。3つ目は、「顔が見える安心感」を出すことです。代表者やスタッフの顔写真、コメントを掲載することで、「どんな人が対応してくれるのか」がわかり、信頼感が高まります。冷たい印象の広告ではなく、温かみのあるデザインを心がけましょう。
新聞折込広告|信頼性が高く保管されやすい
新聞折込広告とは、新聞に挟んで配布されるチラシのことです。ポスティングとの違いは、新聞を購読している家庭にのみ届けられる点です。新聞購読者は比較的高齢で、収入が安定している層が多いため、葬儀社のターゲットと合致しやすい特徴があります。
新聞折込の最大のメリットは、信頼性の高さです。新聞という信頼されるメディアに掲載されることで、チラシ自体の信頼度も高まります。ポスティングと違い、「新聞に入っていた広告だから」という理由で保管されやすく、いざという時に見返してもらえる可能性があります。
新聞折込広告の特徴と費用目安
新聞折込の費用は、新聞社への折込料金と印刷費です。折込料金は1枚あたり3円〜5円程度で、印刷費を含めると1枚あたり6円〜15円程度が相場です。1万部配布する場合、合計で6万円〜15万円程度の費用がかかります。ポスティングよりもやや高めの費用設定ですが、ターゲット層に的確に届けられるメリットがあります。
ただし、新聞購読率は年々低下しており、とくに若年層ではほとんど購読されていません。配布対象が限られるため、広いエリアに情報を届けたい場合はポスティングの方が適しています。逆に、高齢者層が多い地域や、新聞購読率が高い地方都市では、新聞折込が効果的です。地域の新聞購読率を事前に調べてから判断すると良いでしょう。
看板・交通広告|認知度向上に効果的
看板や交通広告は、斎場の外観や駅、バス停などに掲示する広告です。直接的な問い合わせにはつながりにくいですが、地域での認知度を高める効果があります。「この辺りに葬儀社があったな」と記憶してもらうことで、いざという時に思い出してもらえる可能性が高まります。
看板は一度設置すれば長期間掲示できるため、ランニングコストが低い点が魅力です。通行人の目に何度も触れることで、自然と認知度が上がります。とくに斎場が幹線道路沿いにある場合は、看板の設置が効果的です。
看板・交通広告の特徴と費用目安
看板の費用は、サイズや素材、設置場所によって大きく異なります。小型の自立看板であれば10万円〜30万円程度、大型の屋外看板は50万円〜200万円程度かかります。一度設置すれば数年間は使い続けられるため、長期的に見ればコストパフォーマンスは高いと言えます。
交通広告(駅やバスの広告)は、月額3万円〜20万円程度が相場です。掲示期間は通常1ヶ月単位で、更新ごとに費用がかかります。即効性は低いですが、地域住民の目に触れ続けることで、ブランド認知度が高まります。看板や交通広告は、Web広告やチラシと組み合わせて活用することで、より効果を発揮します。
葬儀社の広告運用で成功する5つのポイント

広告の種類を理解し、予算を確保しても、やみくもに広告を出すだけでは成果は出ません。葬儀社の広告運用で成功するには、押さえるべきポイントがあります。ここでは、初めて広告に取り組む葬儀社が意識すべき5つのポイントを紹介します。
- ターゲットを明確に設定する
- 自社の強みを具体的に訴求する
- 料金の透明性を打ち出す
- 安心感・信頼感を最優先にする
- 小さく始めて改善を繰り返す
これらのポイントを実践することで、限られた予算でも効果的に集客できる可能性が高まります。1つずつ確認し、自社の広告戦略に取り入れてみてください。
ターゲットを明確に設定する
広告を成功させるには、「誰に届けたいのか」を明確にすることが最重要です。「とにかく多くの人に見てもらいたい」という考えでは、広告費を無駄にしてしまいます。葬儀社の場合、ターゲットは大きく分けて「今すぐ顧客」と「将来顧客」の2種類に分けられます。
「今すぐ顧客」は、身内の逝去により急いで葬儀社を探している人です。この層にはリスティング広告やローカル広告が有効です。一方「将来顧客」は、終活に興味がある人や、親の介護をしている人など、まだ具体的なニーズはないものの将来的に葬儀社を利用する可能性がある層です。この層にはSNS広告やチラシが適しています。
さらに細かく設定するなら、「家族葬を希望する50代」「費用を抑えたい30代の子ども世代」「宗教色のない葬儀を望む60代」といった具体的なペルソナを作ると良いでしょう。ターゲットが明確になれば、広告の訴求ポイントや使うべき媒体も自然と絞り込めます。
自社の強みを具体的に訴求する
葬儀社の広告でよく見かけるのが、「安心」「丁寧」「真心」といった抽象的な言葉です。これらの言葉は間違いではありませんが、競合他社も同じことを言っているため、差別化にはつながりません。利用者は「何がどう安心なのか」「どう丁寧なのか」を具体的に知りたいのです。
自社の強みを明確にするには、「他社にはない特徴」を洗い出すことが大切です。たとえば、「創業50年の地域密着」「葬祭ディレクター1級保有者が全員対応」「追加料金一切なしの明瞭会計」「駅から徒歩3分の好立地」「24時間365日、30分以内に駆けつけます」といった具体的な情報です。数字や資格、地理的な条件など、客観的に伝えられる要素を盛り込むことで、信頼感が高まります。
料金の透明性を打ち出す
葬儀費用に対する不安は、利用者が最も気にするポイントの1つです。「いくらかかるのかわからない」「追加料金が発生するのでは」という不信感を持たれてしまうと、問い合わせにはつながりません。広告では、料金の透明性を明確に打ち出すことが重要です。
具体的には、「家族葬プラン30万円(税込・追加料金なし)」「見積もり後の追加請求は一切ありません」といった表現が効果的です。何が含まれていて、何が含まれていないのかを明記することで、利用者は安心して問い合わせできます。
ただし、景品表示法に違反しないよう、誤解を招く表現は避けなければなりません。詳しくは後述の「注意点」の章で解説します。
安心感・信頼感を最優先にする
葬儀は人生で何度も経験するものではなく、多くの人にとって初めての経験です。大切な人を亡くした直後の精神的に不安定な状態で、葬儀社を選ばなければなりません。そのため、利用者が最も重視するのは「この葬儀社に任せて大丈夫だろうか」という安心感です。
安心感を伝えるには、スタッフの顔写真や経歴、代表者のメッセージを掲載することが有効です。「どんな人が対応してくれるのか」が見えることで、利用者は安心して問い合わせできます。
また、実際に利用した人の声や口コミ、施行実績の数字を掲載することで、第三者からの客観的な信頼性も伝えられます。価格の安さよりも、まずは安心感を最優先にした広告作りを心がけましょう。
小さく始めて改善を繰り返す
広告運用で失敗しがちなのが、最初から大きな予算をかけてしまうことです。どの広告が効果的かは、実際に運用してみないとわかりません。いきなり高額な広告費を投入するのではなく、まずは小さく始めて反応を見ることが大切です。
たとえば、リスティング広告なら月5万円、チラシなら1,000枚といった少額から始めてみましょう。問い合わせが何件あったか、どのキーワードで広告がクリックされたか、どのエリアで反響があったかを記録し、データを蓄積します。
効果が出た広告には予算を増やし、効果が出なかった広告は改善するか停止する。このPDCAサイクルを回すことで、無駄な広告費を抑えながら成果を最大化できます。
葬儀社の広告で押さえるべき効果測定の方法

広告を出しただけで満足してはいけません。「どの広告から何件問い合わせがあったのか」「広告費に対してどれだけの売上があったのか」を測定することで、次の広告戦略が見えてきます。効果測定をしないまま広告を続けると、無駄な費用を垂れ流すことになりかねません。
ここでは、葬儀社が押さえるべき効果測定の基本を3つ紹介します。
- 広告ごとに問い合わせ経路を分ける工夫
- 費用対効果(ROI)の計算方法を知っておく
- 短期と長期の両方の視点で効果を見る
難しい専門知識は不要ですので、今日から実践してみてください。
広告ごとに問い合わせ経路を分ける工夫
効果測定の第一歩は、「どの広告から問い合わせがあったのか」を把握することです。リスティング広告、チラシ、ポータルサイトなど、複数の広告を同時に運用している場合、どれが効果的なのかを判断する必要があります。
最も簡単な方法は、広告ごとに電話番号を変えることです。たとえば、チラシ用の電話番号とWeb広告用の電話番号を分けることで、どちらから問い合わせがあったかが一目でわかります。
電話番号を増やせない場合は、問い合わせ時に「どこで当社を知りましたか?」と口頭で確認する方法もあります。Web広告の場合は、Google広告の管理画面で「コンバージョン数(問い合わせ件数)」を確認できるため、必ず設定しておきましょう。
費用対効果(ROI)の計算方法を知っておく
広告の効果を正しく測るには、費用対効果(ROI:Return On Investment)を計算する必要があります。ROIとは、「広告費に対してどれだけの利益が得られたか」を示す指標です。計算式は以下の通りです。
- ROI(%)=(広告経由の売上 − 広告費)÷ 広告費 × 100
たとえば、月10万円の広告費をかけて、広告経由で3件の成約があり、売上が150万円だった場合、ROIは1,400%となります。この数字が高いほど、広告の費用対効果が良いことを意味します。逆にROIがマイナスの場合は、広告費が売上を上回っているため、改善が必要です。すべての広告でROIを計算し、効果の高い広告に予算を集中させることで、効率的な運用が可能になります。
短期と長期の両方の視点で効果を見る
広告の効果は、短期的な視点だけで判断してはいけません。リスティング広告やポータルサイトのように、すぐに問い合わせにつながる広告もあれば、チラシやSNS広告のように、効果が出るまで時間がかかる広告もあります。
たとえば、チラシを配布した直後は反応が少なくても、数ヶ月後に「以前もらったチラシを見て」と問い合わせが来ることもあります。SNS広告も、認知度を高めることで、将来的に指名検索が増える可能性も捨てきれません。
短期的に成果が出ないからといってすぐにやめるのではなく、3ヶ月〜6ヶ月程度の中長期的な視点で効果を測定しましょう。即効性のある広告と、じっくり育てる広告をバランスよく組み合わせることが、安定した集客につながります。
葬儀社の広告で絶対に避けるべき注意点

葬儀社の広告は、一般的な商品やサービスの広告とは異なる配慮が必要です。大切な人を亡くした直後の遺族に対して、不適切な表現や誤解を招く広告を出してしまうと、企業の信頼を大きく損なうことになります。
ここでは、葬儀社が広告を出す際に絶対に避けるべき注意点を3つ解説します。
- 景品表示法違反にならない表現を心がける
- 価格訴求だけに頼らない広告設計にする
- ネガティブな言葉選びを避ける配慮を
法律違反やトラブルを避けるためにも、必ず確認してください。
景品表示法違反にならない表現を心がける
景品表示法とは、消費者に誤解を与える広告表示を禁止する法律です。葬儀業界でも、過去に大手企業が景品表示法違反で措置命令を受けた事例があります。「追加料金一切なし」と広告に記載していたにもかかわらず、実際には例外的に追加料金が発生するケースがあり、消費者に誤認を与えたことが問題となりました。
広告で料金を表示する際は、「何が含まれているのか」「どんな場合に追加料金が発生するのか」を明確に記載する必要があります。たとえば「基本プラン50万円」と表示する場合、その金額に含まれるサービス内容(棺、祭壇、搬送費など)を具体的に記載しましょう。含まれないもの(飲食費、返礼品など)も明記することで、誤解を防げます。曖昧な表現や誇大広告は、企業の信頼を損なうだけでなく、法的なリスクも伴うため、慎重に確認してください。
価格訴求だけに頼らない広告設計にする
「最安値」「業界最低価格」といった価格の安さだけを前面に出した広告は、短期的には問い合わせを増やせるかもしれません。しかし、価格だけで選ばれた顧客は、他社がさらに安い価格を提示すれば簡単に離れていきます。価格競争に巻き込まれると、利益率が下がり、サービスの質を維持できなくなる悪循環に陥ります。
葬儀は「安ければ良い」というサービスではありません。遺族は価格よりも、「安心して任せられるか」「丁寧に対応してもらえるか」を重視しています。広告では、価格だけでなく、自社の強みやスタッフの人柄、実績、口コミなど、総合的な価値を伝えることが大切です。適正な価格で、質の高いサービスを提供している姿勢を打ち出すことで、長期的に選ばれる葬儀社になれます。
ネガティブな言葉選びを避ける配慮を
葬儀に関する広告では、言葉選びに細心の注意が必要です。「死亡」「死体」「遺体」といった直接的で冷たい印象を与える言葉は、遺族の感情を逆なでする可能性があります。広告では、故人への敬意と遺族への配慮が感じられる柔らかい表現を心がけましょう。
たとえば、「死亡」ではなく「ご逝去」「お亡くなりになる」、「遺体」ではなく「ご遺体」「故人様」、「火葬する」ではなく「荼毘に付す」「お見送りする」といった言い換えが推奨されます。また、「葬式」よりも「ご葬儀」「お葬式」の方が丁寧な印象を与えます。
些細な言葉の違いですが、こうした配慮が企業の姿勢を表し、信頼感につながります。広告を作成する際は、遺族の立場に立って、不快感を与える表現がないか必ず確認しましょう。
初めての広告運用なら専門業者への相談も検討を

ここまで、葬儀社が活用できる広告の種類や成功のポイント、注意点を解説してきました。しかし、実際に広告を運用するとなると、「どこから手をつければ良いのかわからない」「効果的な広告文が作れない」「効果測定の方法が難しい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
広告運用には専門的な知識とノウハウが必要です。初めて広告に取り組む場合、試行錯誤を繰り返すうちに予算を使い果たしてしまうリスクもあります。そんな時は、プロの力を借りることも選択肢の1つです。
広告運用には専門知識とノウハウが必要
リスティング広告やローカル広告、SNS広告といったWeb広告は、設定やキーワード選定、広告文の作成など、専門的なスキルが求められます。たとえば、リスティング広告では「どのキーワードで広告を出すか」「クリック単価をいくらに設定するか」「広告の表示時間帯をどうするか」など、細かい調整が必要です。
初心者がいきなり運用を始めても、設定ミスで広告費を無駄にしてしまったり、効果が出ないまま予算を消化してしまうケースが少なくありません。チラシやポスティングも、デザインや配布エリアの選定を間違えると、ほとんど反響が得られないこともあります。広告運用は「やってみればわかる」という世界ではなく、データに基づいた戦略的なアプローチが求められるのです。
プロに任せることで効率的に成果を出せる
専門業者に広告運用を依頼すれば、無駄な試行錯誤を省き、最短距離で成果を出せる可能性が高まります。プロは過去の成功事例やデータを持っており、「どの広告が葬儀社に効果的か」「どんな訴求が響くか」を熟知しています。
たとえば、リスティング広告の運用代行を依頼すれば、キーワード選定から広告文の作成、効果測定、改善提案までをまとめて任せられます。MEO対策も、Googleビジネスプロフィールの最適化や口コミ管理、定期的な投稿などを代行してもらえます。自社で試行錯誤する時間とコストを考えれば、プロに依頼した方が結果的に費用対効果が高くなることも多いのです。
無料相談や資料請求から始めてみよう
「広告運用を任せたいけれど、どの業者が良いのかわからない」という方は、まず無料相談や資料請求から始めてみましょう。多くの広告代行会社では、初回の相談を無料で受け付けています。現状の課題をヒアリングし、最適な広告戦略を提案してもらえます。
当社でも、Web広告含めてネット集客で失敗しないためのお役立ち資料を無料配布しております。気になる方は、お気軽にダウンロードしてみてください。
まとめ|葬儀社の広告は戦略的に始めよう

葬儀業界は、地域のつながりだけで集客できる時代ではなくなりました。利用者はインターネットで情報を集め、複数の葬儀社を比較検討するようになっています。こうした環境で選ばれるには、広告を活用して自社の存在を知ってもらい、強みを伝えることが欠かせません。
広告にはWeb広告とオフライン広告があり、それぞれに特徴があります。リスティング広告やローカル広告は「今すぐ顧客」に効果的で、SNS広告やチラシは「将来顧客」を育てるのに適しています。自社のターゲットや予算に合わせて、最適な広告媒体を選んでください。
初めての広告運用で不安がある場合は、専門業者への相談も検討してください。プロのノウハウを活用することで、効率的に成果を出せます。まずは無料相談や資料請求から、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。広告は「やってみないとわからない」部分も多いですが、戦略的に取り組めば、必ず成果につながります。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
-
ARTICLE
2025/12/12( 更新)
【コーチングの集客方法5選】紹介頼みを脱却して選ばれ続けるための仕組みづくり
企業経営業種別
- 集客
-
NEW ARTICLE
2026/02/05
SEOとリスティング広告の違いは?使い分けや併用による相乗効果についてを解説
広告
- リスティング広告
-
NEW ARTICLE
2026/02/04( 更新)
リスティング広告運用代行会社の選び方!確認すべきポイントや代行費用相場を解説
広告広告運用
- リスティング広告
-
NEW ARTICLE
2026/02/03( 更新)
リスティング広告の費用相場はいくら?予算の決め方や費用を抑える方法を解説
広告広告運用
- リスティング広告

