
新規顧客と既存顧客どちらを優先すべき?獲得コスト比較や効果的な手法を解説
「売上を伸ばすために新規顧客を獲得すべきか、既存顧客を大切にすべきか」
この悩みを抱える営業責任者やマーケティング担当者は多いのではないでしょうか。限られた予算と人員の中で、どちらに優先的にリソースを投入すべきかは、企業の成長を左右する重要な判断となります。
本記事では、新規顧客と既存顧客どちらを優先するか判断する3つの指標や、獲得コスト比較、優先すべき企業の特徴を解説しています。新規顧客・既存顧客に効果的なマーケティング手法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
新規顧客と既存顧客の獲得はどちらを優先すべき?

結論として、多くの企業は既存顧客の維持・拡大を優先すべきです。新規顧客の獲得コストは既存顧客の5倍かかるとされており、限られた予算で最大の効果を求めるなら既存顧客への投資が合理的でしょう。
ただし、どちらを優先すべきかは企業の状況によって異なります。既存顧客のリピート率が低い、市場が拡大している、競合に顧客を奪われているといった場合は新規顧客獲得を優先する必要があります。重要なのは自社の現状を正確に把握し、データに基づいて判断することです。
どちらを優先するか判断する3つの指標
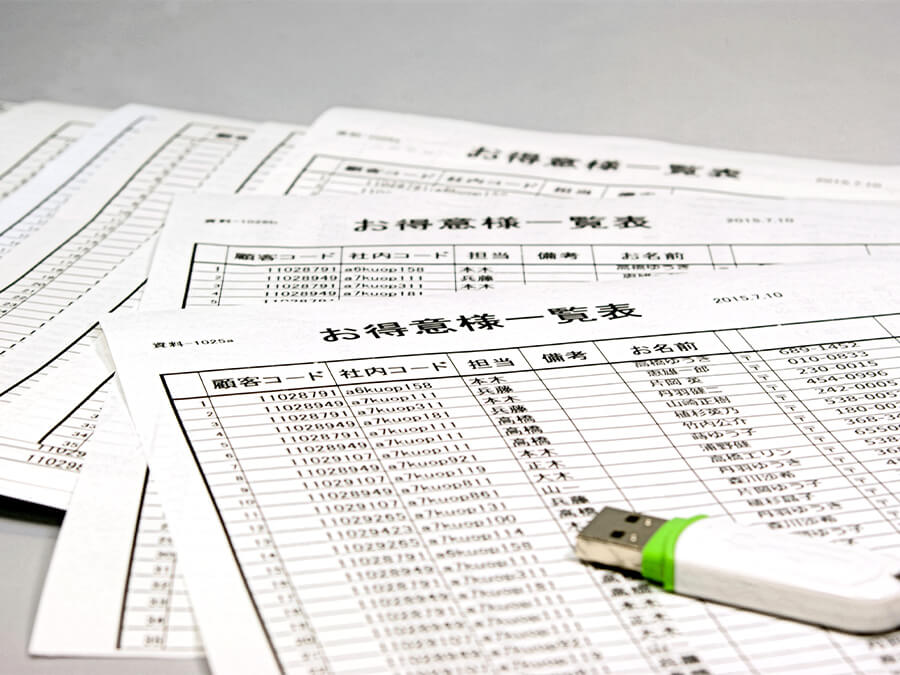
新規顧客と既存顧客のどちらに注力すべきかは、感覚ではなくデータで判断することが重要です。以下の3つの指標を確認することで、自社にとって最適な戦略を選択できます。
- 既存顧客のリピート率から判断
- 新規顧客の獲得単価から判断
- 売上目標と現状のギャップから判断
これらの指標は毎月チェックし、市場環境の変化に応じて戦略を調整していくことが売上拡大のカギとなるでしょう。
既存顧客のリピート率から判断
リピート率が30%以下の場合は、既存顧客の維持を最優先に取り組みましょう。リピート率の計算式は「リピート顧客数 ÷ 全顧客数 × 100」で、この数値が低いということは顧客満足度に問題がある可能性が高いためです。
業界平均と比較することも重要な判断材料になります。例えばECサイトの平均リピート率は25~30%、飲食店では50~60%が目安とされています。自社の数値が業界平均を大きく下回る場合は、商品・サービスの品質向上や顧客対応の見直しが急務です。
新規顧客の獲得単価から判断
新規顧客の獲得単価(CAC:Customer Acquisition Cost)が既存顧客の売上単価を上回っている場合、新規獲得の手法を見直す必要があります。獲得単価は「マーケティング費用 ÷ 新規顧客数」で算出でき、この数値が高すぎると利益を圧迫してしまいます。
一般的に、獲得単価は顧客生涯価値(LTV)の3分の1以下に抑えることが理想とされています。例えば顧客のLTVが30万円なら、獲得単価は10万円以下に設定すべきでしょう。この比率を超える場合は、既存顧客の単価向上や紹介制度の活用を検討することをおすすめします。
売上目標と現状のギャップから判断
売上目標に対して現状が大きく不足している場合は、新規顧客獲得に力を入れる必要があります。既存顧客だけでは達成できない売上目標がある場合、積極的な新規開拓が欠かせません。
逆に売上目標に対して現状が80%以上達成できている場合は、既存顧客の単価向上やリピート率改善に注力することで効率的に目標達成が可能です。目標との乖離が20%以内であれば、コストの安い既存顧客施策で十分に対応できるでしょう。
新規顧客と既存顧客の獲得コストを比較

マーケティング予算を効果的に配分するためには、新規顧客と既存顧客の獲得コストの違いを正確に把握することが重要です。一般的に新規顧客の獲得には既存顧客の5倍のコストがかかるとされていますが、業界や企業規模によって実際の数値は大きく変わります。
正確なコスト把握により、限られた予算でより多くの売上を生み出す戦略を立てることができるでしょう。以下では具体的な数値例を交えながら、獲得コストの実態を詳しく解説します。
1:5の法則から見る獲得コストの違い
1:5の法則とは、既存顧客に販売するコストを1とした場合、新規顧客への販売には5倍のコストがかかるという経験則です。この法則が示すように、新規顧客獲得には広告費、営業人件費、販促費などが積み重なり、コストが膨らみやすくなります。
具体例として、既存顧客への電話営業で成約率が30%の場合、新規顧客への同様のアプローチでは成約率が6%程度になることも珍しくありません。この差が最終的に5倍のコスト差となって現れるため、効率性を重視するなら既存顧客へのアプローチを優先すべきです。
中小企業における実際のコスト事例
中小企業のBtoB業界では、新規顧客1件あたりの獲得コストが3~10万円、既存顧客からの追加受注コストが0.5~2万円程度が一般的です。製造業の場合、新規開拓に月20万円の予算を投じて2件受注できるのに対し、既存顧客フォローでは同じ予算で8~10件の追加受注を獲得できるケースもあります。
サービス業では差がより顕著に現れ、新規顧客獲得に1件あたり5万円かかる一方で、既存顧客への追加提案は1万円程度で済むことが多いでしょう。このコスト差を理解することで、予算配分の最適化が可能になります。
業界別の獲得コスト相場と特徴
業界によって獲得コストの相場は大きく異なります。IT・SaaS業界では新規顧客獲得に10~50万円、金融・保険業界では30~100万円かかることも珍しくありません。一方、小売・EC業界では数千円から数万円と比較的低コストで獲得できる傾向があります。
BtoB企業とBtoC企業でも大きな違いがあり、BtoB企業の方が獲得単価は高くなりがちです。ただし、BtoB企業は顧客生涯価値(LTV)も高い傾向にあるため、一概に非効率とは言えません。自社の業界特性を理解した上で、適切な予算配分を行うことが重要でしょう。
既存顧客を優先すべき企業の特徴

既存顧客への投資を優先すべき企業には共通した特徴があります。これらの特徴に当てはまる場合、新規開拓よりも既存顧客の維持・拡大に注力することで、より効率的に売上を伸ばすことができるでしょう。
自社の現状を以下の特徴と照らし合わせることで、最適な戦略選択の参考にしてください。数値で判断できる項目は定期的にモニタリングし、戦略の見直しに活用することをおすすめします。
リピート率が20%以下の場合
リピート率が20%以下の企業は、顧客満足度に根本的な問題を抱えている可能性が高いです。この状態で新規顧客を獲得しても、同様に離脱してしまう可能性が高く、投資対効果が望めません。
まずは既存顧客がなぜリピートしないのか、アンケートやヒアリングを通じて原因を特定することが重要です。商品・サービスの品質、価格設定、顧客対応、アフターサービスなど、あらゆる側面から改善点を洗い出し、リピート率を30%以上まで引き上げることを目標にしましょう。
顧客単価向上の余地がある場合
既存顧客の購買履歴を分析して、アップセルやクロスセルの機会が豊富にある場合は、既存顧客施策を優先すべきです。例えば、基本プランしか利用していない顧客が多い、関連商品の購入率が低いといった状況が該当します。
顧客単価を20~30%向上させることができれば、新規顧客を同等数獲得するよりもはるかに効率的です。既存顧客は自社への信頼があるため、適切な提案を行えば単価向上の成功率も高くなるでしょう。
営業リソースが限られている場合
営業担当者が少ない中小企業では、限られたリソースを効率的に活用することが重要です。新規開拓は1件の成約に多くの時間と労力を要するため、人員が不足している状況では既存顧客フォローに集中した方が成果を上げやすくなります。
営業担当者1人あたりが対応できる既存顧客は50~100社程度が目安とされています。この範囲内で深い関係を築き、継続的な受注を確保することで、安定した売上基盤を構築できるでしょう。
新規顧客を優先すべき企業の特徴

一方で、新規顧客の獲得を優先すべき企業も存在します。これらの特徴に該当する場合は、積極的な新規開拓に取り組むことで事業成長を加速させることができるでしょう。
ただし、新規顧客獲得を優先する場合でも、既存顧客のフォローを完全に止めてはいけません。バランスを取りながら、戦略的に新規開拓に力を入れることが重要です。
既存顧客の離脱率が高い場合
既存顧客の年間離脱率が30%を超える場合、新規顧客の獲得なしには売上維持が困難になります。とくにサブスクリプション型のビジネスでは、離脱率の高さは事業継続に直結する重要な問題です。
この場合、既存顧客の離脱対策と並行して新規顧客の獲得を強化する必要があります。離脱率の改善には時間がかかるため、短期的には新規獲得で売上を補填しながら、中長期的に離脱率の改善に取り組むという2段構えのアプローチが有効でしょう。
市場拡大のタイミングの場合
業界全体が成長期にある、新しい法規制により需要が高まっている、コロナ禍のようなマクロ環境の変化で市場が拡大しているといった状況では、積極的な新規獲得が重要になります。市場拡大期は競合他社も参入してくるため、早期にシェアを確保することが長期的な競争優位につながります。
市場拡大のタイミングを見極めるには、業界レポートや統計データの定期的なチェックが欠かせません。成長期の波に乗り遅れないよう、市場動向には常にアンテナを張っておくことをおすすめします。
競合他社に顧客を奪われている場合
既存顧客が競合他社に流出している場合、新規顧客の獲得で損失を補う必要があります。とくに価格競争が激しい業界では、既存顧客の流出を完全に防ぐことは困難なため、新規獲得による補填が現実的な対応策となるでしょう。
競合分析を行い、自社の弱点を把握した上で、差別化できるポイントを明確にすることが重要です。競合にない独自の価値を提供できれば、新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客の流出防止にも効果を発揮します。
既存顧客の売上拡大に効果的な5つの手法

既存顧客からの売上を最大化するためには、体系的なアプローチが重要です。単発的な施策ではなく、継続的な関係構築を通じて顧客価値を高めていくことが求められます。
以下で紹介する手法は、業界や企業規模を問わず効果が期待できる実践的なものです。
- 顧客データ分析で離脱要因を特定する
- メール・SNSを活用したリテンション施策
- アップセル・クロスセル提案の仕組み化
- 顧客満足度調査とフィードバック活用
- ロイヤリティプログラムの導入
自社の状況に合わせてカスタマイズし、段階的に導入していくことをおすすめします。
顧客データ分析で離脱要因を特定する
既存顧客の購買履歴、問い合わせ履歴、利用パターンを分析することで、離脱の前兆を早期に発見できます。例えば、購入頻度の低下、問い合わせの増加、利用時間の減少などは離脱のサインとして捉えることができるでしょう。
分析結果に基づいて、離脱リスクの高い顧客に対して個別のフォローを行うことが重要です。CRMシステムやMAツールを活用すれば、顧客の行動変化を自動で検知し、適切なタイミングでアプローチすることも可能になります。
メール・SNSを活用したリテンション施策
定期的なメールマガジンやSNSでの情報発信を通じて、顧客との接点を継続的に維持することが重要です。ただし、一方的な宣伝ではなく、顧客にとって有益な情報を提供することで信頼関係を構築していきましょう。
セグメント別にコンテンツをカスタマイズすることで、より高い効果が期待できます。例えば、購入履歴に基づいて関連商品の情報を配信したり、利用頻度に応じてお得情報のタイミングを調整するといった工夫が有効です。
アップセル・クロスセル提案の仕組み化
既存顧客に対するアップセル・クロスセルの提案を仕組み化することで、効率的に単価向上を図れます。購買履歴や利用状況を分析し、最適なタイミングで最適な商品を提案するプロセスを確立することが重要です。
提案の成功率を高めるためには、顧客の課題や目標を深く理解することが欠かせません。定期的な面談やアンケートを通じて顧客ニーズを把握し、そのニーズに合致した提案を行うことで、Win-Winの関係を築くことができるでしょう。
顧客満足度調査とフィードバック活用
定期的な顧客満足度調査を実施することで、サービス改善の具体的な方向性を把握できます。年2回程度のアンケート調査に加え、解約時のヒアリングを必ず行うことで、離脱要因の根本的な解決につながる貴重な情報を収集できるでしょう。
収集したフィードバックは社内で共有し、商品・サービスの改善に反映させることが重要です。顧客の声を元に改善を行い、その結果を顧客に報告することで、顧客との信頼関係がより強固になり、継続利用率の向上が期待できます。
ロイヤリティプログラムの導入
ポイント制度や会員ランク制度などのロイヤリティプログラムは、既存顧客の継続利用を促進する効果的な施策です。利用頻度や購入金額に応じて特典を提供することで、他社への流出を防ぎながら単価向上も図れます。
プログラム設計時は、特典の魅力度と運用コストのバランスを慎重に検討することが重要です。過度な特典は収益を圧迫する一方、魅力が不足すると効果が期待できません。競合他社の事例を参考にしながら、自社の収益構造に適したプログラムを構築しましょう。
新規顧客を効率的に獲得する5つの手法

新規顧客の獲得においては、効率性と継続性を重視することが重要です。短期的な成果だけでなく、長期的に安定した新規獲得ができる仕組みを構築することが事業成長の鍵となります。
以下で紹介する手法は、比較的低コストで始められるものから順に説明しています。
- ペルソナ設定とターゲティング戦略
- コンテンツマーケティングで集客力向上
- 紹介・口コミマーケティングの活用法
- Web広告を活用した効率的な集客
- 営業代行・パートナー連携の活用
自社のリソースと照らし合わせながら、実現可能なものから順次導入していくことをおすすめします。
ペルソナ設定とターゲティング戦略
効率的な新規獲得のためには、理想的な顧客像(ペルソナ)を明確に定義することが重要です。年齢、性別、職業、課題、価値観などを具体的に設定し、そのペルソナが多く存在する場所や媒体を特定することで、マーケティング効率を大幅に向上させることができます。
ペルソナ設定は既存顧客の分析から始めるのが効果的です。収益性の高い既存顧客の共通点を洗い出し、同様の特徴を持つ見込み客をターゲットにすることで、成約率の向上が期待できるでしょう。
コンテンツマーケティングで集客力向上
ブログ記事、動画、資料ダウンロードなどのコンテンツを活用することで、見込み客との最初の接点を創出できます。SEOを意識したコンテンツ作成により、検索エンジンからの自然流入を増やすことも可能です。
コンテンツマーケティングは即効性は低いものの、継続的に取り組むことで安定した見込み客の獲得源となります。月1~2本のペースでも構わないので、ターゲットが関心を持つテーマで継続的に発信することが重要でしょう。
紹介・口コミマーケティングの活用法
既存顧客からの紹介は、最も成約率が高く、獲得コストも低い新規獲得手法の一つです。紹介制度を設計する際は、紹介する側と紹介される側の両方にメリットがあるような仕組みを構築することが重要です。
口コミを促進するためには、顧客体験の向上が欠かせません。期待を上回るサービスを提供し、自然と人に話したくなるような体験を創出することで、口コミの発生確率を高めることができるでしょう。
Web広告を活用した効率的な集客
Google広告やFacebook広告などのWeb広告は、ターゲットを絞り込んで効率的に見込み客にアプローチできる手法です。とくにリスティング広告は購買意欲の高いユーザーにリーチできるため、BtoB企業では高い効果が期待できます。
広告運用では、CPAやROASなどの指標を定期的にモニタリングし、効果の低いキーワードや配信設定を見直すことが重要です。月10~20万円程度の予算からでも始められるため、中小企業でも取り組みやすい施策と言えるでしょう。
営業代行・パートナー連携の活用
人手不足の中小企業では、営業代行サービスや販売パートナーとの連携により新規開拓を効率化できます。自社の営業リソースを既存顧客フォローに集中させながら、外部パートナーに新規開拓を任せることで、両方の施策を並行して進めることが可能です。
パートナー選定時は、自社の商材への理解度や営業スキル、実績などを総合的に評価することが重要です。成果報酬型の契約にすることで、リスクを抑えながら新規獲得の機会を拡大できるでしょう。
新規・既存の最適な予算配分比率
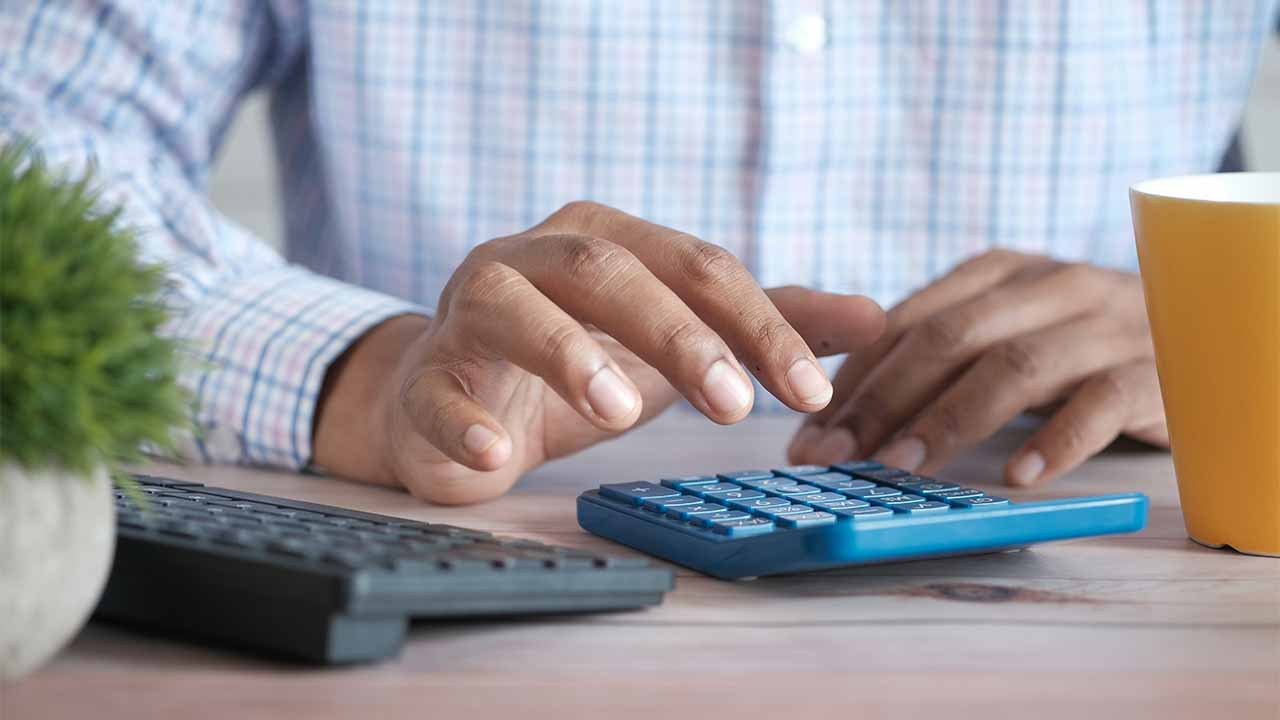
マーケティング予算の配分は、企業の成長段階や業界特性によって大きく異なります。一般的な目安を参考にしながらも、自社の状況に応じて柔軟に調整することが重要です。
予算配分は固定的に考えるのではなく、市場環境の変化や事業の成長に合わせて定期的に見直すことをおすすめします。四半期ごとに効果測定を行い、配分比率の最適化を図ることで、限られた予算で最大の成果を上げることができるでしょう。
成長段階別の予算配分目安
スタートアップ期(設立1~2年)では新規獲得に予算の70~80%を投入し、既存顧客に20~30%を配分するのが一般的です。この段階では顧客基盤の構築が最優先となるため、積極的な新規開拓が求められます。
成長期(設立3~5年)になると、新規獲得60%、既存顧客40%程度の配分が理想的でしょう。成熟期(設立5年以上)では新規獲得40%、既存顧客60%と既存顧客の比重を高めることで、安定した収益基盤を構築できます。
業界別の成功事例から学ぶ配分比率
SaaS業界では新規獲得40%、既存顧客60%の配分で成功している企業が多く見られます。サブスクリプション型のビジネスでは、既存顧客の維持が売上の安定性に直結するためです。
製造業や建設業などのBtoB企業では、新規獲得50%、既存顧客50%の均等配分が効果的とされています。一方、小売業やサービス業などのBtoC企業では、新規獲得65%、既存顧客35%と新規獲得の比重を高めに設定する企業が多い傾向にあります。
兼任業務でも実行できる効率的な進め方
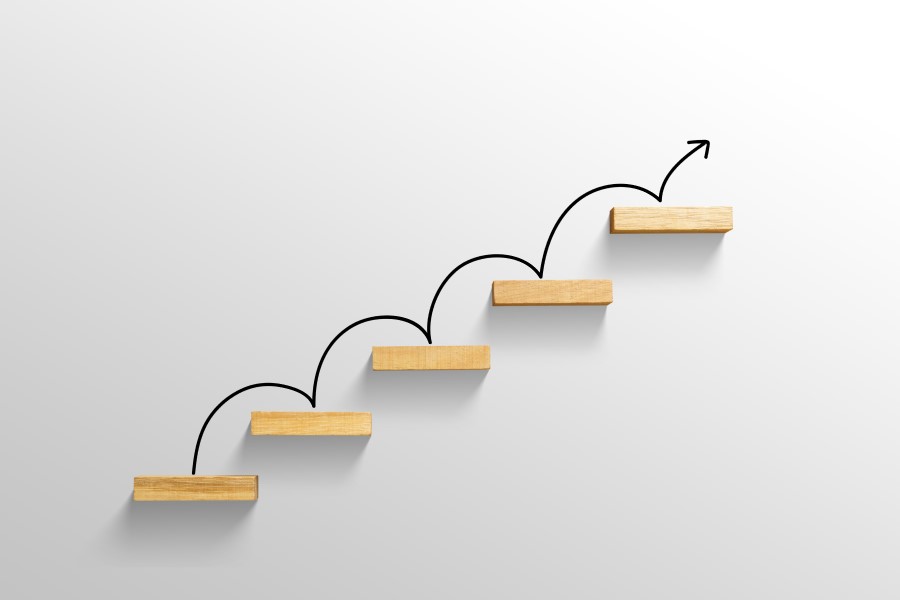
中小企業では営業担当者がマーケティング業務を兼任することが多く、限られた時間で最大の成果を上げる工夫が求められます。重要なのは完璧を目指すのではなく、80%の完成度で素早く実行し、結果を見ながら改善していくアプローチです。
効率化のポイントは、データに基づく意思決定と作業の自動化です。感覚に頼らず、数値で判断することで迷いを減らし、ツールを活用することで作業時間を短縮することができるでしょう。
優先順位を決める簡単チェックリスト
毎月の戦略検討時に活用できるチェックリストを用意することで、効率的に優先順位を決められます。以下の項目を確認し、該当数の多い方を優先することをおすすめします。
- 既存顧客のリピート率が30%以下である
- 新規獲得単価が既存顧客の売上単価を上回っている
- 営業リソースが月20件未満のアプローチしかできない
- 顧客満足度調査で改善の余地が大きいことが判明している
- 競合分析で自社の差別化要素が不明確である
3つ以上該当する場合は既存顧客施策を、2つ以下の場合は新規獲得施策を優先することが効果的です。
月次で見直すべき指標と改善方法
営業とマーケティングなど兼任で業務している場合、複雑な分析は継続が困難なため、最低限の指標に絞って月次でモニタリングすることが重要です。新規獲得数、既存顧客のリピート数、売上単価の3つを基本指標として追跡しましょう。
改善のスピードを上げるためには、PDCAサイクルを短くすることが効果的です。月次で結果を確認し、問題があれば翌月には対策を実行するというスピード感を持つことで、年間を通じて大きな成果の差を生み出すことができるでしょう。
売上を最大化する新規・既存戦略まとめ
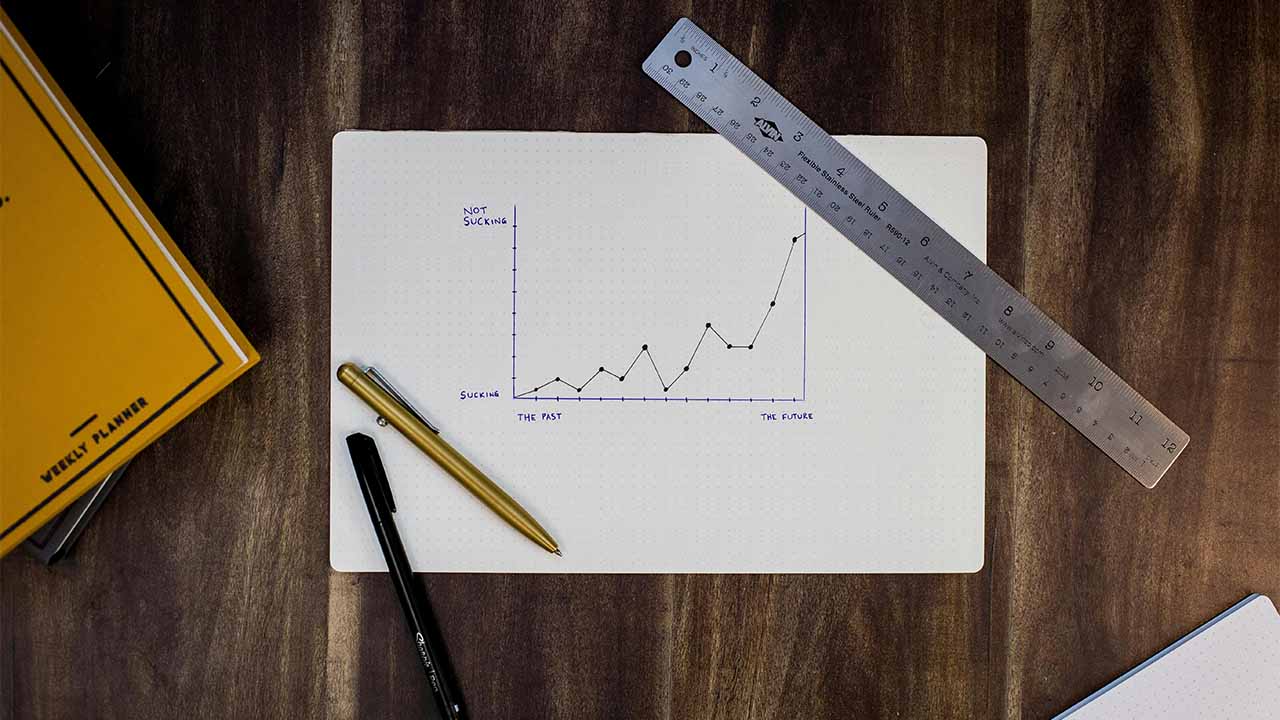
新規顧客と既存顧客のどちらを優先すべきかは、企業の状況によって異なりますが、多くの場合は既存顧客の維持・拡大から始めることが効率的です。1:5の法則が示すように、新規獲得には既存顧客の5倍のコストがかかるため、限られたリソースを最大限に活用するためには既存顧客への投資が合理的でしょう。
ただし、リピート率が20%以下、離脱率が30%以上、市場拡大期などの特殊な状況では新規獲得を優先する必要があります。重要なのは感覚ではなくデータに基づいて判断し、市場環境の変化に応じて戦略を柔軟に調整していくことです。
とくに中小企業の場合は、まず現状の数値把握から始め、自社に最適な戦略を見つけていってください。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
