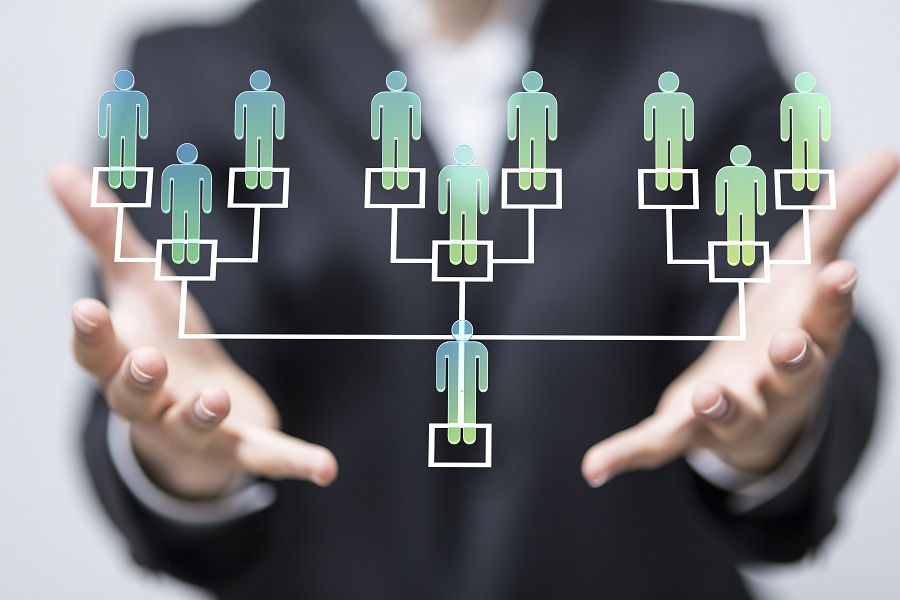
オウンドメディアリクルーティングとは?始め方や成功事例も紹介
オウンドメディアリクルーティング(OMR)とは、自社で保有・運営するメディアを活用して人材採用を行う手法です。スマートフォンが普及し、SNSの利用率が増加した今、オウンドメディアリクルーティングでの採用が主流となりつつあります。
本記事では、そもそもオウンドメディアリクルーティングとは何か、従来の求人サイトとの違いを分かりやすく解説しています。オウンドメディアリクルーティングのメリット・デメリットや始め方はもちろん、成功事例から見る運用のコツまで紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
オウンドメディアリクルーティングとは?

オウンドメディアリクルーティング(OMR)とは、自社で保有・運営するメディアを活用して人材採用を行う手法です。企業が独自に情報発信できるWebサイトやブログ、SNSアカウントなどを通じて、求職者に企業の魅力や価値観を伝えます。従来の求人サイトに頼るだけでなく、自社メディアから直接アプローチすることで、企業文化に共感する人材との出会いを創出できる点が最大の特徴と言えます。
近年、多くの企業がオウンドメディアリクルーティングに注目しています。求人広告だけでは伝えきれない職場の雰囲気や社員の働き方、企業理念の実践例などを、写真や動画を交えて自由に発信できるからです。この手法は大手企業だけでなく、採用予算が限られる中小企業にとっても、長期的に見れば効果的な採用戦略となります。
オウンドメディアリクルーティングの定義
オウンドメディア(Owned Media)は「自社が所有するメディア」を意味します。具体的には、コーポレートサイト内の採用ページ、独立した採用サイト、企業ブログ、公式のInstagramやX(旧Twitter)、YouTube、TikTokなどのSNSアカウントが該当します。これらを採用活動に活用することを「オウンドメディアリクルーティング」と呼ぶのです。
重要なのは、単にメディアを持つだけでなく「継続的に情報発信する」点にあります。求職者が知りたい情報を先回りして提供し、企業への理解を深めてもらうことで、応募意欲の高い人材を惹きつけられます。Indeed Japan株式会社が2018年に「オウンドメディアリクルーティングプロジェクト」を発足させて以降、この採用手法は日本でも急速に広がりました。
求人サイトとの3つの違い
求人サイトとオウンドメディアリクルーティングは、どちらも採用活動に活用されますが、その性質は大きく異なります。最も分かりやすい違いは「情報発信の自由度」です。
求人サイトでは掲載内容のフォーマットが決められており、文字数制限や画像枚数の制約があります。一方、自社メディアなら制限なく、伝えたい情報を好きなだけ発信できるのです。
| 項目 | オウンドメディア | 求人サイト |
|---|---|---|
| 情報量 | 制限なし | 制限あり |
| 掲載期間 | 無期限 | 契約期間のみ |
| ターゲット | 顕在層・潜在層 | 顕在層のみ |
| 即効性 | 低い | 高い |
もう一つの大きな違いは「アプローチできる対象」にあります。求人サイトは転職を考えている顕在層にしか届きませんが、オウンドメディアはSNSなどを通じて「今は転職を考えていないが、良い会社があれば」という潜在層にもリーチできます。ただし即効性では求人サイトに劣るため、両者を組み合わせた採用戦略が効果的です。
オウンドメディアリクルーティングが注目される3つの背景

オウンドメディアリクルーティングが採用手法として注目されるのには、明確な理由があります。採用市場を取り巻く環境が大きく変化し、従来の求人広告だけでは優秀な人材を採用できなくなってきたからです。
求職者の行動変容、労働市場の構造変化、そして企業に求められる情報開示の範囲拡大。これら3つの要因が重なり合い、企業は「待ちの採用」から「攻めの採用」へと戦略転換しています。
求職者の情報収集力が飛躍的に向上
スマートフォンの普及により、求職者は企業情報をいつでもどこでも調べられるようになりました。総務省の調査によると、2023年のスマートフォン保有率は20代で97.6%、30代で96.0%に達しています。求職者は応募前に企業の公式サイトはもちろん、社員の口コミサイト、SNSでの評判まで細かくチェックしている人が多いです。
こうした情報収集リテラシーの向上は、企業側に「見つけてもらう」だけでなく「選んでもらう」ための情報発信を求めています。求人票に書かれた条件だけでは判断材料として不十分で、実際の働き方や職場の雰囲気、社員の人柄まで知りたいというニーズが高まりました。オウンドメディアなら、こうした「求人広告では伝えきれない情報」を豊富に提供できます。
働き方の価値観が多様化している
働く目的や仕事に求める価値は、人それぞれ大きく異なるようになりました。かつては「給与の高さ」や「企業の知名度」が主な判断基準でしたが、今では「ワークライフバランス」「成長機会」「社会貢献」「企業理念への共感」など、より個人的な価値観が重視されています。
リモートワークの普及も、この変化を加速させました。働く場所の自由度が高まったことで、求職者は「どこで働くか」よりも「誰と、どんな価値観で働くか」を重視する傾向が強まっています。画一的な求人広告では、こうした多様なニーズに応えられません。自社の価値観や文化を丁寧に発信し、共感する人材を惹きつけるオウンドメディアリクルーティングの重要性が増しています。
採用市場の売り手市場化が加速
少子高齢化による生産年齢人口の減少で、採用市場は完全な売り手市場です。厚生労働省の発表によると、2024年9月の有効求人倍率は1.24倍と、求職者1人に対して1.24件の求人がある状況が続いています。企業は「選ぶ側」から「選ばれる側」へと立場が変わりました。
売り手市場では、求職者は複数の企業を比較検討する余裕があります。条件面で大差がなければ、企業文化や成長機会、働きがいなど、より深い部分で判断されるようになりました。
こうした状況で他社と差別化するには、自社の独自性や魅力を積極的に発信する必要があります。オウンドメディアリクルーティングは、この「選ばれるための情報発信」を実現する有効な手段といえるでしょう。
▶参照:一般職業紹介状況(令和6年9月分)について|厚生労働省
オウンドメディアリクルーティングの5つのメリット

オウンドメディアリクルーティングには、従来の採用手法にはない多くのメリットがあります。単に「採用コストを削減できる」だけでなく、採用の質を高め、組織全体にポジティブな影響をもたらす可能性を秘めています。
ここでは、企業がオウンドメディアリクルーティングに取り組むべき5つの理由を解説します。
- 企業の魅力を制限なく伝えられる
- 採用ミスマッチを大幅に減らせる
- 求職潜在層にもアプローチ可能
- 中長期的に採用コストを削減できる
- 従業員のエンゲージメント向上にも貢献
中小企業でも実践できる内容ばかりですので、自社の採用戦略に活かせるポイントを見つけてください。
企業の魅力を制限なく伝えられる
求人サイトでは文字数や画像枚数に制限がありますが、自社メディアなら表現の自由度は無限大です。社員インタビューを何本でも掲載できますし、職場の1日を追った動画コンテンツ、プロジェクトの舞台裏、社内イベントの様子など、伝えたい情報をすべて発信できます。
この自由度の高さは、企業のユニークな魅力を伝える上で非常に重要です。たとえば「社員の成長を支援する制度が充実」と求人票に書いても抽象的ですが、実際に制度を利用した社員の体験談を写真付きで紹介すれば、具体的にイメージしてもらえます。求職者が「この会社で働いたらどんな毎日になるか」を想像できるコンテンツこそ、応募を後押しする力になります。
採用ミスマッチを大幅に減らせる
入社前に企業の実態をしっかり理解してもらえれば、「思っていたのと違った」というミスマッチを防げます。オウンドメディアで職場のリアルな姿を発信することで、求職者は自分に合うかどうかを判断した上で応募できるからです。
採用ミスマッチによる早期離職は、企業にとって大きな損失です。採用コスト、教育コスト、そして再び採用活動を行う時間とコストがかかります。厚生労働省の調査では、大卒新入社員の約3割が3年以内に離職しているというデータもあります。オウンドメディアで企業文化や仕事の実情を正直に伝えることは、長期的に見れば最もコストパフォーマンスの高い投資と言えるでしょう。
求職潜在層にもアプローチ可能
求人サイトは「今すぐ転職したい人」にしか届きませんが、オウンドメディアは「いい会社があれば転職を考えたい」という潜在層にもリーチできます。特にSNSでの発信は、転職を考えていない人の目にも留まりやすく、企業への好印象を積み重ねられます。
潜在層へのアプローチは、将来の採用活動を有利にします。日頃から企業の魅力を発信し続けることで、「あの会社で働いてみたい」という憧れを持つ人が増えていきます。実際に転職を考えたとき、真っ先に思い浮かべてもらえる企業になれれば、求人広告を出さなくても応募が集まる状態を作れるはずです。
中長期的に採用コストを削減できる
初期投資は必要ですが、オウンドメディアからの直接応募が増えれば、求人広告費や人材紹介会社への手数料を大幅に削減できます。求人サイトへの掲載は期間限定で費用が継続的にかかりますが、自社メディアのコンテンツは一度作れば資産として残り続けるからです。
人材紹介会社を利用すると、採用が決まった際に年収の30〜35%程度の手数料が発生します。年収500万円の人材なら150万円以上のコストです。オウンドメディア経由で年間数名でも採用できれば、運用コストを差し引いても大きなコスト削減になります。ただし効果が出るまでには時間がかかるため、短期的な採用ニーズには従来の手法と併用する必要があります。
従業員のエンゲージメント向上にも貢献
オウンドメディアの運営は、採用だけでなく既存社員にも良い影響を与えます。社員インタビューや仕事紹介のコンテンツを作る過程で、社員自身が自社の魅力を再認識したり、会社の理念を深く理解したりする機会になるからです。
「自分の会社がメディアで魅力的に紹介されている」ことは、社員にとって誇らしいものです。家族や友人に自社を紹介しやすくなり、リファラル採用(社員紹介による採用)の促進にもつながります。また社員が積極的にSNSでシェアすることで、情報拡散の効果も期待できるはずです。オウンドメディアリクルーティングは、組織全体のエンゲージメントを高める取り組みでもあるのです。
オウンドメディアリクルーティングのデメリットと対策

メリットの多いオウンドメディアリクルーティングですが、当然デメリットも存在します。これらを理解せずに始めると、期待した効果が得られず、途中で挫折してしまうかもしれません。
- 即効性が期待できない
- 運用に人的リソースが必要
- 社内の協力が不可欠
デメリットを正しく把握し、適切な対策を講じることが成功の鍵です。ここでは主な3つのデメリットと、それぞれの具体的な対策方法を解説します。
即効性が期待できない
オウンドメディアリクルーティングの最大のデメリットは、効果が出るまでに時間がかかることです。メディアを立ち上げてコンテンツを発信しても、すぐに応募者が殺到することはありません。検索エンジンからの評価を得るにも、SNSでフォロワーを増やすにも、数ヶ月から1年以上かかるのが一般的です。
コンテンツが蓄積され、企業の認知度が高まってくるまでには相応の時間が必要になります。「来月までに3名採用したい」といった短期的な採用ニーズには向いていません。長期的な採用戦略の一環として、じっくり育てていく覚悟が求められます。
対策:求人サイトとの併用でカバーする
即効性の問題は、従来の採用手法と組み合わせることで解決できます。短期的には求人サイトや人材紹介会社を活用しながら、並行してオウンドメディアを育てていくのです。求人サイトの募集ページから自社の採用サイトへ誘導する導線を作れば、オウンドメディアの露出も増やせます。
段階的にオウンドメディア経由の応募を増やし、徐々に外部サービスへの依存度を下げていく戦略が現実的です。最初の1〜2年は投資期間と割り切り、3年目以降に採用コストが削減されることを目標に設定してみてください。
運用に人的リソースが必要
質の高いコンテンツを継続的に発信するには、企画、取材、執筆、撮影、編集、公開、効果測定と、多くの作業が発生します。採用担当者が片手間でできる業務量ではありません。専任の担当者を置くか、外部の制作会社に依頼するか、いずれにしても相応のリソースが必要です。
多くの企業が「始めたものの更新が止まってしまった」という失敗を経験しています。人手不足でコンテンツ制作が追いつかず、半年以上更新されていないブログやSNSアカウントを放置している企業も少なくありません。更新が止まったメディアは、かえって企業イメージを損ねる可能性があります。
対策:体制整備と外注を組み合わせる
運用体制を整える方法は大きく分けて3つあります。1つ目は専任担当者を配置する方法、2つ目は既存の人事担当者が兼務する方法、3つ目は外部のライターやカメラマンに制作を委託する方法です。理想は専任担当者ですが、中小企業ではリソースを割けない場合があります。
現実的なのは「企画と取材は社内で行い、執筆や編集は外注する」というハイブリッド型です。社員インタビューの取材は社内の人間が行い、その音源や取材メモをもとに外部ライターが記事化する流れなら、社内の負担を抑えながら質の高いコンテンツを作れます。月に数本の記事制作なら、外注費も月5〜10万円程度に抑えられるはずです。
社内の協力が不可欠
オウンドメディアリクルーティングは、人事部門だけで完結できません。社員インタビューへの協力、現場の撮影許可、経営陣のメッセージ発信など、さまざまな部署の協力が必要です。多忙な社員に取材協力を依頼しても断られたり、経営陣の理解が得られず予算が承認されなかったりするケースもあります。
社内の協力が得られないと、コンテンツの質も量も確保できません。「採用は人事の仕事」という意識が強い企業ほど、協力を得るのが難しくなります。全社的な取り組みとして位置づけ、採用活動が会社全体の成長につながることを理解してもらう必要があるでしょう。
対策:目的を共有し巻き込む仕組みを作る
社内の協力を得るには、まずオウンドメディアリクルーティングの目的と意義を経営層に説明し、理解を得ることが重要です。「採用コストの削減」「ミスマッチの防止」「企業ブランディング」といったメリットを数字で示せれば、協力を得やすくなります。
現場社員の協力を得るには、負担を最小限にする工夫が必要です。インタビューは30分程度で終わらせる、事前に質問を共有して準備してもらう、完成した記事を本人に確認してもらうなど、丁寧なプロセスを踏めば協力してもらいやすくなります。また、掲載された記事を社内で共有し、協力への感謝を伝えることも大切です。
オウンドメディアリクルーティングで発信すべき2つのコンテンツ

オウンドメディアで何を発信すればいいか分からない、という声をよく聞きます。闇雲に情報を発信しても、求職者の心には響きません。戦略的にコンテンツを設計する必要があるのです。
発信すべきコンテンツは大きく2つに分類されます。「ジョブディスクリプション」と「シェアードバリューコンテンツ」です。前者は「見つけてもらう」ための情報、後者は「共感してもらう」ための情報と言えます。両方をバランス良く発信することで、自社にマッチした人材を惹きつけられるでしょう。
ジョブディスクリプション(職務記述書)
ジョブディスクリプションとは、募集職種の業務内容や必要なスキルを詳細に記載した職務記述書です。単なる求人票よりも詳しく、「入社したらどんな仕事をするのか」が具体的にイメージできる情報を提供します。業務内容、職務の目的、必要なスキルや経験、責任範囲、評価基準などを明確に記載するのです。
ジョブディスクリプションを充実させる最大のメリットは、検索エンジンで見つけてもらいやすくなることです。「Webデザイナー 東京 リモート可」のような具体的なキーワードを盛り込めば、そのスキルを持つ求職者が検索したときにヒットしやすくなります。また、職種ごとに詳細なページを作ることで、より精度の高いマッチングが実現できます。
シェアードバリューコンテンツ
シェアードバリューコンテンツとは、企業の価値観や文化を伝えるコンテンツです。「この会社で働きたい」という感情を喚起し、企業への共感を生み出すことが目的になります。ジョブディスクリプションが理性に訴えるコンテンツなら、シェアードバリューコンテンツは感情に訴えるコンテンツです。
シェアードバリューコンテンツはさらに「カルチャーコンテンツ」と「パーパスコンテンツ」の2つに分類されます。前者は職場の雰囲気や働き方など「働く環境」を伝え、後者は企業理念や社会貢献など「働く意義」を伝えるものです。両方を組み合わせることで、求職者に多角的に企業の魅力を伝えられます。
カルチャーコンテンツ|企業風土や職場環境
カルチャーコンテンツでは、職場の雰囲気や社員の人柄、働き方の実態など、求人票では伝わりにくい「現場のリアル」を発信します。社員インタビュー、1日の仕事の流れ、オフィスツアー動画、チームでのランチ風景、社内イベントの様子などが代表的です。
「どんな人と一緒に働くのか」は、求職者にとって非常に重要な判断材料です。特に若い世代ほど、給与や福利厚生よりも「人間関係」や「職場の雰囲気」を重視する傾向があります。社員の笑顔が見える写真や、仕事のやりがいを語るインタビュー動画は、求職者の応募を後押しする強力なコンテンツになるでしょう。
パーパスコンテンツ|企業理念と社会貢献
パーパスコンテンツでは、企業の存在意義や理念、社会にどう貢献しているかを伝えます。創業者の想い、企業ビジョン、SDGsへの取り組み、地域貢献活動、社会課題解決への挑戦などがテーマです。
「なぜこの仕事をするのか」という問いに答えるコンテンツは、仕事に意義を求める求職者の心に響きます。とくにミレニアル世代やZ世代は、単に給与を得るためではなく、社会に良い影響を与える仕事をしたいと考える傾向が強いです。企業理念を掲げるだけでなく、それを実践している具体例を示すことで、説得力のあるメッセージになるでしょう。
オウンドメディアリクルーティングの始め方

オウンドメディアリクルーティングを始めたいけれど、何から手をつければいいか分からない。そんな悩みを持つ企業は多いでしょう。闇雲に始めても効果は出ません。戦略的に計画を立て、段階を踏んで進めることが成功への近道です。
ここでは、オウンドメディアリクルーティングを始めるための7つのステップを解説します。
- Step1:目的とゴールを明確にする
- Step2:ターゲット人材を具体化する
- Step3:自社の魅力を棚卸しする
- Step4:運用体制と予算を決定する
- Step5:発信するメディアを選定する
- Step6:コンテンツを制作・発信する
- Step7:効果測定と改善を継続する
中小企業でも実践できる内容ですので、自社の状況に合わせてカスタマイズしながら進めてください。
Step1:目的とゴールを明確にする
まず最初に「なぜオウンドメディアリクルーティングを始めるのか」を明確にしましょう。採用コストの削減、採用ミスマッチの防止、企業ブランディング、特定職種の採用強化など、目的はさまざまです。目的が曖昧なまま始めると、途中で迷走してしまいます。
目的とともに、具体的なゴールも設定してください。「1年後に月間PV数1万を達成」「2年後にオウンドメディア経由での採用を年間3名以上」など、数値目標があると進捗を測りやすくなります。経営層を含めた関係者全員で目的とゴールを共有し、長期的な視点で取り組む覚悟を固めることが、継続的な運用の土台となります。
Step2:ターゲット人材を具体化する
「どんな人材を採用したいのか」を具体的にイメージします。年齢、性別、職歴、スキル、価値観、ライフスタイルなど、ペルソナ(仮想の人物像)を詳細に設定するのです。ターゲットが明確でないと、誰にも刺さらないコンテンツになってしまいます。
たとえば「30代前半、Webマーケティング経験3年以上、ワークライフバランスを重視、リモートワーク希望、成長意欲が高い」といった具体的なペルソナを設定します。ターゲットが明確になれば、どんなメディアで情報収集しているか、どんな情報を求めているかが見えてきます。20代ならInstagramやTikTok、30〜40代ならXやFacebookといった具合に、発信すべきメディアも自ずと決まってくるはずです。
Step3:自社の魅力を棚卸しする
自社にはどんな魅力があるのか、改めて整理します。「特に魅力なんてない」と思う企業も多いですが、外部から見れば魅力的な要素は必ずあります。社員にアンケートを取ったり、インタビューしたりして、「この会社の好きなところ」を聞き出してみてください。
魅力の棚卸しでは、強みだけでなく弱みも正直に把握することが大切です。完璧な企業などありません。弱みを隠すのではなく、「現在改善に取り組んでいる」といった前向きな文脈で伝えることで、かえって誠実さが伝わります。また競合他社の採用サイトも研究し、自社ならではのユニークな魅力は何かを見極める必要があります。
Step4:運用体制と予算を決定する
誰が運用を担当するのか、どこまで社内で対応し、どこから外注するのかを決めます。理想は専任担当者の配置ですが、中小企業では難しいケースも多いでしょう。その場合は、企画とディレクションは社内で行い、制作作業は外部に委託する方法が現実的です。
予算も具体的に算出してください。サイト制作の初期費用、記事やコンテンツ制作費、撮影費、広告費など、項目ごとに見積もります。初年度は初期投資が大きくなりますが、2年目以降は運用費のみになるため、3年間のトータルコストで考えると良いです。予算を確保できないまま始めると、途中で頓挫するリスクが高まります。
Step5:発信するメディアを選定する
ターゲット人材に合わせて、どのメディアで発信するかを決めます。採用サイト、企業ブログ、Instagram、X、YouTube、TikTokなど選択肢は多岐にわたります。すべてを一度に始めるのではなく、優先順位をつけて段階的に拡大していくのが賢明です。
最初は採用サイトと1つのSNSから始めるのがおすすめです。採用サイトは情報のストック場所として、SNSは情報の拡散と入口として機能します。若年層をターゲットにするならInstagramやTikTok、ビジネス層ならXやLinkedInが効果的です。メディアごとに特性が異なるため、それぞれに適したコンテンツを用意する必要があります。
Step6:コンテンツを制作・発信する
いよいよコンテンツ制作に入ります。最初の3ヶ月は、基本的なコンテンツを集中的に作りましょう。企業紹介、代表メッセージ、各部署の紹介、主要な職種のジョブディスクリプション、社員インタビュー数本など、サイトの骨格を作り込むのです。
コンテンツ制作で重要なのは「完璧を目指さない」ことです。最初から100点のコンテンツは作れません。60〜70点のクオリティでも公開し、反応を見ながら改善していく姿勢が大切です。更新頻度も重要で、月に最低2〜4本は新しいコンテンツを追加したいところです。SNSは週に2〜3回の投稿を目標にコンテンツ発信してみてください。
Step7:効果測定と改善を継続する
コンテンツを公開したら終わりではありません。アクセス解析ツールで数値を確認し、効果測定を行います。Webサイトならページビュー数、滞在時間、直帰率、応募ページへの遷移率など、SNSならフォロワー数、エンゲージメント率、投稿のリーチ数などをチェックしてください。
数値を見て「なぜこの記事は読まれたのか」「なぜこの投稿は反応が薄かったのか」を分析し、次のコンテンツ制作に活かします。月に1回は効果測定の時間を設け、PDCAサイクルを回すことが成長の鍵です。効果が出るまでには時間がかかりますが、継続的に改善を重ねることで、確実に成果は積み上がっていきます。
オウンドメディアリクルーティングにかかる費用と期間

オウンドメディアリクルーティングを始める際、最も気になるのは「いくらかかるのか」と「いつ効果が出るのか」ではないでしょうか。予算の目安や効果が出るまでの期間を知らずに始めると、途中で資金が尽きたり、成果が出る前に諦めてしまったりするリスクがあります。
ここでは、オウンドメディアリクルーティングにかかる現実的な費用と期間の目安を解説します。自社の予算や状況に照らし合わせて、実現可能な計画を立ててください。
初期費用の目安は100~300万円
オウンドメディアリクルーティングの初期費用は、採用サイトの制作費が中心になります。
Web制作会社に依頼する場合、シンプルな構成なら100万円前後、オリジナルデザインで機能が充実したサイトなら200〜300万円程度が相場です。既存のコーポレートサイトに採用ページを追加するだけなら、30〜50万円で済むケースもあります。
初期費用を抑えたいなら、WordPressなどのCMSを使って自社で構築する方法もあります。この場合、サーバー代とドメイン代だけなら年間1〜2万円程度で始められます。ただし、デザインやコーディングのスキルが必要なため、制作に時間がかかります。また、初期コンテンツの制作費として、社員インタビュー記事5〜10本分の外注費を見込むと、20〜50万円程度が追加で必要です。
運用費用は月10~50万円が相場
運用フェーズに入ると、継続的にコンテンツを制作・発信するための費用が発生します。月に2〜4本の記事を外部ライターに委託する場合、1本あたり3〜5万円として月10〜20万円程度です。写真撮影や動画制作を含めると、月30〜50万円程度の予算を見ておくと安心です。
社内で内製できれば、外注費を大幅に削減できます。ただし担当者の人件費は別途かかりますし、クオリティの確保も課題です。現実的なのは「社内で企画・取材を行い、執筆や編集は外部に委託する」ハイブリッド型です。この方法なら、月10万円程度の外注費で質の高いコンテンツを継続的に発信できます。
効果が出るまでの期間は6ヶ月~1年
オウンドメディアリクルーティングで成果が見え始めるのは、早くても6ヶ月、一般的には1年程度かかります。検索エンジンからの流入が増えるには、コンテンツが蓄積され、Googleから評価されるまで時間が必要だからです。SNSもフォロワーを増やし、投稿が拡散されるようになるまでには相応の期間がかかります。
「1年後にオウンドメディア経由で年間3〜5名の採用」を目標にするのが現実的です。2年目以降はコンテンツが資産として蓄積され、効果が加速度的に高まっていきます。3年後には求人サイトへの依存度を大幅に下げられる企業も珍しくありません。短期的な効果は期待せず、中長期的な投資として捉えることが重要です。
中小企業がオウンドメディアリクルーティングで成功するコツ

予算や人員が限られる中小企業でも、工夫次第で成果を出せます。ここでは、中小企業が実践すべき3つのコツを解説します。
- 無料ツールを活用して初期費用を抑える
- SNSから始めて段階的に拡大する
- 社員の「リアルな声」を最大の武器にする
大企業の真似をするのではなく、中小企業ならではの強みを活かした戦略が重要です。
無料ツールを活用して初期費用を抑える
予算が限られるなら、まずは無料のツールを活用して小さく始めましょう。WordPressを使えば無料でブログを開設できますし、note、Wantedlyといったプラットフォームを利用すれば、サイト制作費をゼロに抑えられます。デザインにこだわらなければ、十分に採用活動に活用できます。
写真撮影もスマートフォンで十分です。最近のスマホカメラは高性能で、プロのカメラマンに依頼しなくても、社員が撮影した写真で臨場感のあるコンテンツが作れます。動画編集も、スマホアプリで簡単にできる時代です。完璧なクオリティより「リアルさ」「継続性」を重視すれば、低予算でも成果は出せます。
SNSから始めて段階的に拡大する
いきなり本格的な採用サイトを作るのではなく、まずはSNSから始めるのも賢い選択です。InstagramやX、TikTokなら無料で開設でき、すぐに情報発信を始められます。フォロワーが増えてきたら、noteやWantedlyで詳しい情報を発信し、最終的に独自の採用サイトを構築する、という段階的なアプローチが現実的です。
SNSは拡散力があるため、中小企業でも知名度を上げやすいメリットがあります。バズれば一気に認知度が高まりますし、共感を生むコンテンツは企業規模に関係なく評価されます。「完璧な採用サイトを作ってから始める」のではなく、「今できることから始める」姿勢が成功への近道です。
社員の「リアルな声」を最大の武器にする
中小企業の強みは、社長や経営陣と社員の距離が近く、会社の雰囲気が伝わりやすい点にあります。大企業のような洗練されたコンテンツは作れなくても、社員のリアルな声や日常の様子を発信することで、親近感や信頼感を生み出せます。
社員インタビューでも、台本通りの模範解答ではなく、本音で語ってもらうことが大切です。「この会社の好きなところ」だけでなく「入社前に不安だったこと」「大変だった経験」なども正直に語ってもらえば、求職者は「この会社は誠実だ」と感じるはずです。完璧な企業像より、リアルで親しみやすい企業像のほうが、中小企業には適しています。
オウンドメディアリクルーティングの成功事例5選

理論だけでなく、実際に成果を上げている企業の事例を知ることで、自社での実践イメージが湧いてきます。ここでは、オウンドメディアリクルーティングで成功している企業5社の取り組みを紹介します。
業種も規模も異なる企業ですが、共通しているのは「自社らしさ」を大切にしたコンテンツ発信です。完璧を目指すのではなく、できることから始め、継続している点も参考になります。
サイボウズ|働き方改革を体現する発信
グループウェアを開発・販売するサイボウズは、オウンドメディア「サイボウズ式」を運営しています。特徴的なのは、自社製品の宣伝を一切せず、「新しい価値を生み出すチームのメディア」として働き方やチームワークに関する情報を発信している点です。
「多様な働き方」を実践する企業として、社員の働き方インタビューや、育児と仕事の両立、リモートワークの実態など、求職者が知りたいリアルな情報を豊富に提供しています。製品のPRではなく「価値観の発信」に徹することで、サイボウズの企業文化に共感する人材を惹きつけることに成功しているのです。
▶参照:サイボウズ式
メルカリ|「人」にフォーカスしたストーリー
フリマアプリ「メルカリ」を運営するメルカリは、「mercan(メルカン)」というオウンドメディアを展開しています。「メルカリの人を伝える」をコンセプトに、社員一人ひとりの仕事への想いやキャリアストーリーを丁寧に紹介しているのが特徴です。
エンジニア、デザイナー、ビジネス職など、職種ごとの働き方が具体的にイメージできるコンテンツが充実しています。写真も多用し、オフィスの雰囲気や社員の表情が伝わる作りです。「どんな人と働くのか」を重視する求職者にとって、非常に参考になる情報が詰まっています。
▶参照:mercan(メルカン)
大京警備保障|TikTokで若年層の認知拡大
警備サービスを提供する大京警備保障は、TikTokを活用した採用活動で注目を集めました。警備業界は若年層からの応募が少ないという課題がありましたが、TikTokで社員の日常や現場の雰囲気を親しみやすい動画で配信したところ、若い世代からの認知度が大きく向上したのです。
堅いイメージのある警備業界ですが、明るく楽しそうに働く社員の姿を見せることで「こんな職場なら働いてみたい」と思わせることに成功しています。予算をかけずに始められるSNS活用は、中小企業にとって非常に参考になる事例でしょう。
オムロン|BtoB企業の実態を可視化
体温計でおなじみのオムロンは、実はBtoB事業が中心で、一般消費者には事業内容がほとんど知られていませんでした。この認知度の低さが採用活動のネックになっていたため、オウンドメディア「EDGE&LINK」を立ち上げ、企業理念の実践や事業の社会的意義を発信し始めました。
「オムロンがどんな価値を社会に提供しているか」を丁寧に伝えることで、求職者の理解を深めることに成功しています。BtoB企業は一般的に認知度が低く採用に苦労しがちですが、オウンドメディアで情報発信すれば、この課題を克服できることを示した好例です。
▶参照:EDGE&LINK
DeNA|ソーシャルメディアを戦略的に活用
「永久ベンチャー」をモットーに掲げるDeNAは、オウンドメディア「フルスイング」とSNSを組み合わせた戦略的な情報発信で知られています。フルスイングでは「人」と「働き方」にフォーカスし、社員の挑戦や成長のストーリーを発信しています。
特徴的なのは、SNSを入口としてフルスイングへ誘導し、さらに採用サイトへつなげる導線設計が明確な点です。フォロワーへのアンケートなども実施し、求職者が求める情報を把握してコンテンツに反映させています。SNS運用のKPIも段階的に変化させるなど、PDCAを回しながら改善を続ける姿勢も参考になります。
▶参照:フルスイング
まとめ|オウンドメディアリクルーティングで自社に合った人材を獲得しよう

オウンドメディアリクルーティングは、自社メディアを活用して企業の魅力を発信し、価値観に共感する人材を惹きつける採用手法です。求人サイトだけでは伝えきれない企業文化や働き方、社員の人柄などを自由に発信できるため、採用ミスマッチの防止や中長期的なコスト削減につながります。効果が出るまでには6ヶ月から1年という時間がかかりますが、継続的にコンテンツを蓄積することで、求人広告に頼らない採用体制を構築できるのが魅力です。
中小企業でも、無料ツールやSNSを活用すれば低予算で始められます。完璧を目指すのではなく、できることから小さく始め、反応を見ながら改善していく姿勢が成功の鍵です。社員のリアルな声を武器にし、自社らしい情報発信を続けることで、必ず共感してくれる人材との出会いが生まれるはずです。
採用市場が売り手市場である今こそ、オウンドメディアリクルーティングに取り組む好機と言えます。本記事を参考に、自社に合った人材を獲得する第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
