
小売業の「RaaS」とは?注目される理由や活用メリット・導入事例を徹底解説
「店舗を持たずに小売を始めたい」
「リアルな顧客接点がほしいけど、出店はハードルが高い」
そんな悩みを持つ企業が増える中、注目を集めているのが「RaaS(Retail as a Service)」という新しいビジネスモデルです。聞き慣れない言葉かもしれませんが、すでに大手企業からスタートアップまで幅広く活用が進んでいます。
本記事では、小売業の「RaaS」とはどんな意味を持つのか、小売業でRaaSが注目される理由や活用メリット、実際の活用事例などをわかりやすく解説しています。小売やマーケティングの最新トレンドをキャッチアップしたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
小売業の「RaaS」とは?

小売業で使われる「RaaS(ラース)」とは、Retail as a Serviceの頭文字をとった略称で、簡単に言えば「小売の仕組みを他社に貸し出す」ようなビジネスモデルのことです。小売業に関する自社のデータやノウハウなどを、IT技術と組み合わせて外部企業にサービス提供するものです。
- POSなどのITソリューション提供
- 販促や集客のマーケティング支援
- 店舗運営の代行やコンサル
- 決済や在庫の管理
- 店舗スペースの貸出
上記のように、「小売業そのものをサービスとして他社に提供する」という新しい収益モデルがRaaSに当てはまります。実店舗やECの在り方が見直される中、RaaSは小売のDX手段としても注目されています。
RaaSは別の意味を持つ言葉としても使われる
RaaSは、「Robotics as a Service」や「Ransomware as a Service」と言った別の言葉の略称としても使われるケースがあります。
「Robotics as a Service」は、ロボテックサービスのことで製造業で使われる言葉です。「Ransomware as a Service」は、ランサムウェアの攻撃によるサービスのことを指します。
何の業種で「RaaS」という言葉が使われるのか、前後の文章を読み取って把握しましょう。
小売業でRaaSが注目される理由

小売業でRaaSが注目される理由は、主に以下の3つのようなものがあります。
- 購買ルートが多様化
- 消費行動が変化している
- 初期コストを抑えられる
- 小売DXにすぐ対応
それぞれの理由について解説していきます。
購買ルートが多様化
かつての主な購入手段は「実店舗での買い物」でしたが、現在ではECサイトやフリマアプリなど、スマートフォン1台で場所を問わず商品を購入できる時代になりました。
こうした購買ルートの多様化は、自社商品の認知拡大や顧客接点の強化につながる一方、リソースの限られた小売企業にとっては大きな負担です。RaaSは、こうした変化に柔軟に対応する手段として注目されています。すでに実績ある仕組みを活用することで、リスクを抑えながらスムーズに対応を進めることができます。
消費行動が変化している
購買ルートが多様化した今、消費者の購買行動そのものも大きく変化しています。ネットショッピングはもはや当たり前となり、キャッシュレス決済やセルフレジの普及など、ライフスタイル全体が急速に進化しています。
こうした変化に対応するためには、小売業もITテクノロジーを活用し、業務プロセスを見直すことが不可欠です。DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じて効率化を図ることで、低コストかつ高パフォーマンスな運営が可能になります。
小売DXにすぐ対応
人手不足や業務の属人化、紙ベースの管理など、アナログな仕組みに課題を抱える小売企業は少なくありません。しかし、自社で1からDXを進めるには、コストや技術面のハードルが高いのが現実です。
RaaSは、そうした企業に対して、既に整備されたITインフラや店舗運営ノウハウを「サービス」として提供します。そのため、複雑なシステム構築や人材育成にかかる時間を大幅に削減し、スピーディにDX化を実現できます。
初期コストを抑えられる
実店舗の出店や販売システムの構築には、本来多くの初期投資が必要です。物件取得費、内装費、POSレジや在庫管理システムの導入など、まとまった資金がなければスタートラインにも立てないのが現実です。とくに中小企業やD2Cブランドにとって、この初期コストの壁は大きなハードルとなるでしょう。
RaaSは、こうしたコスト面の課題を解消する仕組みとして注目されています。必要な機能や設備を使いたい分だけ借りられるサービスモデルのため、大きな投資をせずにリアル店舗や販売チャネルをすぐに立ち上げることが可能です。小さく始めて反応を見ながら調整できるため、リスクも最小限に抑えられます。
RaaS活用のメリット

RaaSを活用する主なメリットをまとめました。
- 運営の手間が軽くなる
- 売上や販促を効率化
- 事業展開がスピードアップ
RaaSでDX化を進めることで受けられる恩恵ばかりです。それぞれ見ていきましょう。
運営の手間が軽くなる
店舗運営には、シフト管理や在庫確認、売場づくりなど多くの業務が発生します。とくに人手が限られている企業では、一人ひとりの負担が大きくなりやすく、運営が属人的になってしまうリスクもあります。
RaaSでは、そうした業務の一部をあらかじめ仕組み化された形で委託できます。システム面の自動化に加え、店舗レイアウトや運営マニュアルなども標準化されているケースが多く、現場での負担を軽減しながら、効率的な運営が可能となるでしょう。
売上や販促を効率化
RaaSを活用すれば、POSや顧客データ分析ツールなどのITソリューションがセットで提供されるケースが多く、これにより購買データの収集や販促の効果検証が簡単になります。経験や勘に頼らない、データに基づいた販売戦略が立てやすくなります。
また、来店者の属性や購買履歴に応じた提案ができるため、顧客満足度の向上にもつながります。短期的な売上アップだけでなく、継続的な関係構築やLTV(顧客生涯価値)の向上にも効果が期待できます。
事業展開がスピードアップ
自前で出店準備をすると、物件探しから契約、システム導入、人材確保までに多くの時間がかかります。そのため、スピーディな展開が難しく、競合に遅れをとってしまうこともあります。
RaaSは、すでに整ったインフラや運営体制を活用できるため、最小限の準備で新たな店舗展開やサービス展開が可能です。新規市場へのテスト出店や季節限定のポップアップ展開など、スピードが求められる施策でも柔軟に対応できます。
RaaS活用が進んでいる業種やサービス

RaaS活用が進んでいる業種やサービスをまとめました。以下のような業種・業界でRaaSを進めると成功しやすいでしょう。
| 業種・業界 | 活用されている理由・特徴 |
|---|---|
| 家電・ガジェット | b8taのような体験型店舗と相性が良く、試用→購入の導線がつくりやすい |
| アパレル・ファッション | 短期出店やポップアップでブランド体験を提供しやすい。顧客接点の拡張にも効果 |
| 食品・飲料 | D2C系ブランドが実店舗でのテスト販売・サンプリングを行いやすい |
| 美容・コスメ | タッチアップや体験を重視する商材で、店舗スペースの一部利用がしやすい |
| スタートアップ・D2C全般 | 初期投資を抑えて実店舗展開できるため、新規参入に適している |
多くの業種でRaaSが活用されている理由は、それぞれの業界が抱える課題や特性にRaaSの仕組みがマッチしているためです。とくに、短期間での出店や体験重視の販売スタイルを採用している業界では、RaaSの柔軟性やスピード感が大きなメリットとなります。
また、スタートアップやD2Cブランドのように、初期費用を抑えながらもリアルな顧客接点を求める企業にとって、RaaSは実店舗進出の有力な手段です。目的や業種に合わせたRaaS活用が、より成果につながる鍵となります。
RaaSの事例
RaaSはさまざまな業種・企業で導入が進んでいますが、実際にどのように活用されているのかを知ることで、その可能性やメリットがより具体的にイメージしやすくなります。ここでは、ベンチャー企業・EC企業・大手小売業といった異なる立場の3社を取り上げ、それぞれの目的や活用スタイルの違いに注目しながら、代表的なRaaSの事例を紹介します。
b8ta:ベンチャー企業

「b8ta(ベータ)」は、サンフランシスコ発のベンチャー企業です。「売らない小売り」と評されるとおり、b8ta自体は商品を販売しません。店舗内に展示スペースを用意し、メーカーから依頼のあった商品をディスプレイすることで、訪れた消費者に商品を体験してもらうことを目的としています。
日本国内では、新宿・渋谷・有楽町などの一等地に店舗を構え、商品の展示を希望するメーカーは、展示スペースを月額でレンタルします。販売経路を持っていない小売企業にぴったりです。
b8taは展示スペースだけでなく店舗スタッフも用意しています。消費者の購買動向をカメラでチェックし、マーケティングデータとして提供してくれる点もポイントです。
Amazon Go:EC企業

「Amazon Go」は、世界最大のEC企業であるAmazonのRaaSです。最大の特徴は「レジなし」という点。店舗内で商品を手に取ると、設置されたAIカメラがその動きを観測します。消費者が店舗を出る際、専用アプリを通して代金が精算される仕組みです。
また、AmazonはAmazon Goの技術を「Just Walk Out Technology(ジャスト・ウォークアウトテクノロジー)」として外部に提供しています。ニューヨークでは本システムを導入した「Starbuck Pickup with Amazon Go(スターバックス・ピックアップ・ウィズ・アマゾン・ゴー)」が登場するなど、非常に注目度の高いRaaSです。
Kroger:小売業
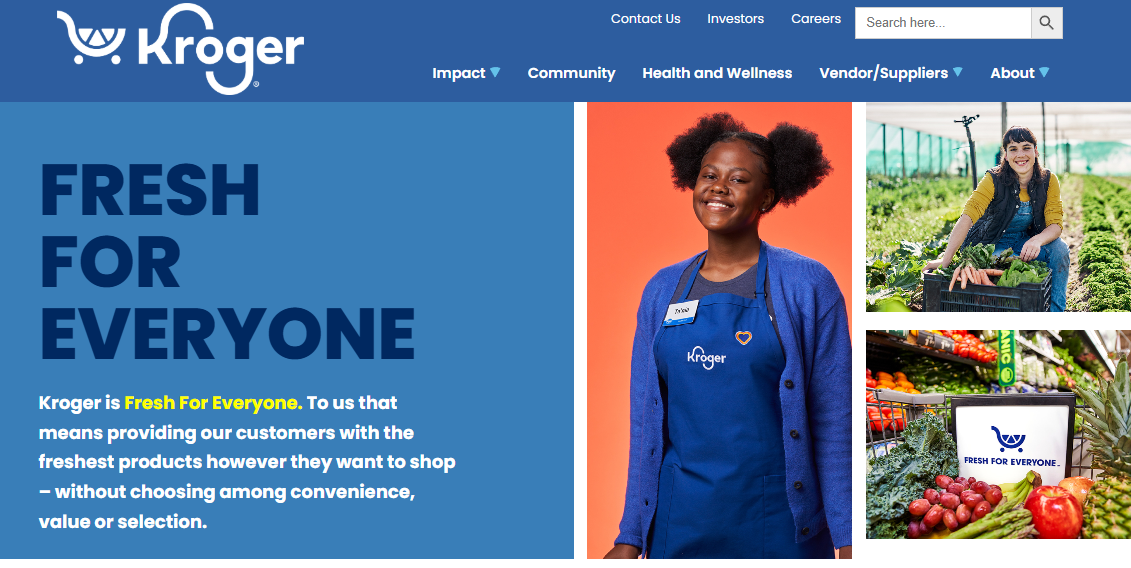
「Kroger(クローガー)」は、アメリカで約2,800のスーパーマーケットを展開している企業です。Microsoftのクラウドコンピューティングサービス「Microsoft Azure」を活用し、「Kroger EDGE Shelf」と呼ばれる電子ディスプレイ棚を開発しました。
消費者が棚の商品をスマホアプリで読み込み、買い物が終了した後、「無人レジ」で決済します。また、店舗に設置されたカメラで消費者の動向をチェックし、AIが分析することで、一人ひとりに最適化されたPOPを表示するといったことも可能です。
もちろん、「Kroger EDGE Shelf」はRaaSとして商品化済みなので、他社も本システムを利用できます。日本国内では、大日本印刷とKrogerが協業し実証実験を進めています。
RaaSと他ビジネスモデルとの違い

RaaSは「Retail as a Service」ですが、他のビジネスモデルとは提供範囲や役割が大きく異なります。以下は、SaaSやフランチャイズ、アウトソーシングなどとの違いをまとめた比較表です。
| モデル名 | 特徴・違いのポイント |
|---|---|
| RaaS | 小売の仕組みごと外部に提供。人・モノ・場も含まれる |
| SaaS | ソフトやツールの機能提供に特化。物理的な運営支援は含まれない |
| フランチャイズ | ブランドや運営権を借りて出店。自由度は低め |
| BPO | 特定の業務だけを外注。小売全体の支援は範囲外 |
| オムニチャネル戦略 | EC・実店舗など複数チャネルを連携。RaaSはその実現を支える側 |
このように、RaaSは単なるツール提供にとどまらず、「人・モノ・場」すべてを一括で支援できる点が大きな特徴です。ソフトウェア提供や業務委託とは異なり、実店舗の運営そのものに深く関わることで、小売業の課題解決により実践的に貢献するでしょう。
RaaSの今後の展望【まとめ】

オンラインとオフラインの境界がますます曖昧になる中、小売業界だけでなくマーケティング全体でも「顧客体験(CX)」が重視される時代に入っています。その影響で、最近ではネット広告だけでなく、実店舗やリアルイベントなど実際に商品やサービスを体験できる場を活用する動きが再び注目されるようになってきました。RaaSは、まさにそうしたリアル接点を支える仕組みとして、企業からの関心が高まっています。
従来のRaaSはPOSや店舗運営支援などが中心でしたが、今後は顧客データとの連携を強化した「マーケティング統合型RaaS」への進化が期待されます。例えば、リアル店舗で得た行動データをもとにWeb広告を出したり、パーソナライズされたリターゲティング施策に活かしたりと、OMO(Online Merges with Offline)の中心的な役割を担うようになるでしょう。
さらに今後は、小売企業に限らず、メーカーやD2Cブランド、さらには地方自治体や観光業など、リアルな接点を持つあらゆる業種でRaaSの活用が進むと考えられます。柔軟な拡張性と実行力を兼ね備えたRaaSは、単なる小売支援にとどまらず、マーケティングプラットフォームの一部として進化していく可能性を秘めています。
RANKING ランキング
- WEEKLY
- MONTHLY
UPDATE 更新情報
- ALL
- ARTICLE
- MOVIE
- FEATURE
- DOCUMENT
-
ARTICLE
2025/06/03( 更新)
生成AIでビジネス業務を効率化。企業が安全・スムーズに導入するための3ステップとプロンプト集
AI文章生成AI
-
ARTICLE
2025/06/17( 更新)
心に響く営業メールのテンプレート25選!業種別例文&ChatGPT(AI)プロンプトを一挙紹介
AI
-
ARTICLE
2020/08/17( 更新)
SNSでコンプライアンス違反が多い理由や企業への影響・対策方法を徹底解説!
企業経営ブランディング
- 用語
- コンプライアンス
-
ARTICLE
2024/04/16( 更新)
OpenAIの動画生成AI「Sora」とは?何ができる?使い方や注意点を解説
AI動画生成AI
